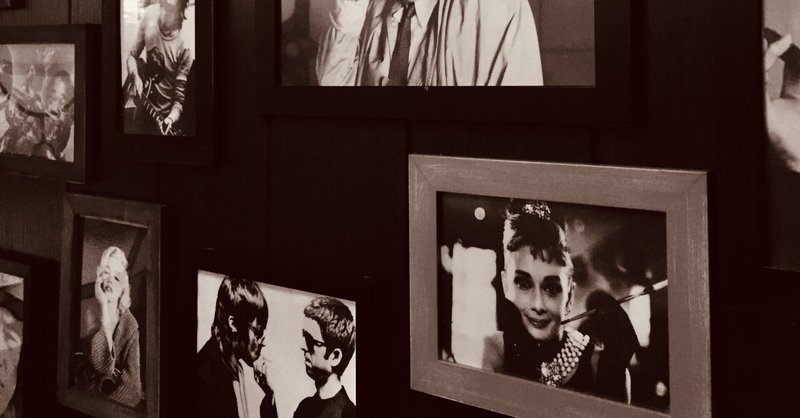- 運営しているクリエイター
2021年5月の記事一覧
「余談的小売文化論」を購読いただいているみなさまへ
体調不良から復帰して約1ヶ月が経ちました。徐々に体力も戻ってきて、noteも安定して更新できるようになりました。いつも読んでくださっているみなさま、本当にありがとうございます。
下記の投稿でもマガジンの更新ができなかった期間分の補填について考えますとお伝えしていたのですが、やはり一斉返金は難しいようなので返金ご希望の方には個別にnote上のサポート機能を使って対応させていただきたいと思います。ご
今週読んだ海外記事(2021.05.28)
最後に海外記事まとめを書いたのがいつだったか思い出せなくてもはや前世の記憶。英語で小説を読み切ったら英語の記事を読むハードルも下がったので以前よりも難なくピックできるようになってきました。ということで今週はしっかり毎日何かしらピックしたのでえらい。
Googleが直営店舗オープンへコロナ禍のアパレル業界を牽引する子供服市場の成長
自分の窓をいかに開けておくか
仲間の結束は強い方がいい。なんの疑いもなく信じられているこの言葉に、私はいつも違和感を覚えてきた。綺麗な言葉の裏側にひっそりと潜む排他性が、その違和感の原因であったように思う。
5月の #あさみのまなび ベストセレクション
しばらくまなびセレクションも投稿できていなかったのですが、復帰とともに消費文化総研内のまなびチャンネルもゆるゆると復活しているので今月のまなびを一部まとめてお届けします。
ちなみに今月から、私のnoteへの感想や質問チャンネルを新しく開設しました(もうすぐ丸三年なのに今さら)!もしかしたらそこでのやりとりの中で私が発したコメントも今後一部このまなびセレクションに掲載していくかもしれません。
4月までに読んだ本一覧
救急車で運ばれてから一文字も本を読めない期間もあったのですが、回復するにつれて徐々に本も読めるようになっていたので4月までに読んだ本をまとめておきたいと思います。ちなみに寝たきり期間にkindle paperwhiteを買ったのでQOR(Quality of Reading)?がかなり向上しました。2021年買ってよかったもののひとつかもしれない…!
もっとみる匿名で書きたい気持ち
ときどきふと、新しいnoteをつくるか別のブログサービスを使うかして今の「最所あさみ」のアカウントとしてではない発信をしたいな、と思うことがある。実名では書けないようなことを書きたいわけではなく、炎上が怖いわけでもない。Twitterやnoteで万単位の方にフォローしていただいている状況でなくとも、同じ気持ちを抱いただろうなと思う。
ブランドの認知拡大は常に善であるか?
ビジネス記事を読んでいると「認知拡大は必ず目指さなければならないものである」と錯覚させられてしまうほど、より多くの人に知られるための手法が次々に紹介されている。
もちろん「知ってもらうこと」はビジネスにおいてとても重要だ。見つけてもらわなければ検討の対象にもならないし、知ってくれる人の範囲が増えればそれだけファンになってくれる人の可能性も広がる。
しかしSNSによって認知拡大のスピードが格段に
コミュニケーションから広がること
祖母とでかけると「この花は何?」と訊ねることが多い。私は植物への関心が特に強いわけではないけれど、祖母に聞くとほぼ確実に植物の名前を教えてくれるのでつい聞いてしまうのだ。教えてもらった次の日にはすっかり忘れてしまうので知識としてはまったく身についていないけれど、祖母といるときは植物への目の向け方が変化することに意味がある気がしている。
植物の名前を知るだけなら、そのうち写真を撮ったら自動的に判別
雑誌と百貨店の決定的違い
私はこれまでずっと雑誌を百貨店のライバルとして捉えてきた。
百貨店に限らず、店舗は「モノを売買する」機能の占有者ではなくなった。いまだに買い物の8割以上は実店舗で発生しているとはいえ、ファッションや生活雑貨などにカテゴリーを絞ればECでの購入比率は格段に上がっているはずだ。
「モノの売買」が実店舗の専売特許ではなくなった今、求められる役割とは何だろうか。その役割の一つが「提案」であり、新しいモ
ユートピアは永遠に訪れない
私はなんでも極論から考える癖がある。あるひとつのテーマに対して「Aを突き詰めるとどうなるか」をイメージする。そして「その真逆であるBを突き詰めるとどうなるか」を考える。もちろん二者択一ではなく選択肢が複数存在する場合もあるのだけど、なんにせよ選択肢を突き詰めた先の世界を想像した上で、どこに「中庸」があるかを測るという思考の仕方をしている。
言い換えれば、極論によって可能性の「行き止まり」を把握し
「私」の開示と憧れの暮らし
久しぶりに花を買って、長らく置物と化していた花瓶に本来の役割を与えた。本棚の上に置かれたその「完成品」を見て、無意識にどう写真に収めるかを考えていた自分に気づく。我に帰るのがあと数秒遅れていたら、写真に添える文言も数通りは考えていたに違いない。
たいしてインスタも使わず、普段からあまり写真を撮らない私ですらもこうなのだ。私たちの中には、隙あらば「私はこんな暮らしをしている」と世間に公開したい欲求