
もっと
先月の15日から、僕は石橋さんとお付き合いすることになった。でも間の悪いことに、それからすぐに運転免許の合宿、および実家への帰省によって、全く会えていないので、恋人どうしらしいことが全然できていない。
毎日のようにLINEで連絡は取り合っているものの、石橋さんの実家は大阪だ。
それはともかくとして、まだ3月の中旬で気温が低いはずなのに、僕は汗まみれになっている。なぜかといえば、今の今まで引っ越し作業を手伝っていたからだ。
免許合宿を終えた3月の頭から、引っ越し業者にて短期バイトをやっている。どうせ春休みに実家にいてもすることがないし、働くついでに体力がつけばいいな、くらいの軽い気持ちだったが、いやはや、なかなかの重労働だ。
僕たちのチームの担当は、企業のお客さんで、オフィス移転のための引っ越しとのこと。大量の机と椅子、それにコピー機や冷蔵庫を運んで、腰がガタガタと震えている。
やっとすべての作業が完了し、新しいオフィスが完成したのを見ると、感慨深くもあるが、しばらく筋肉痛が治らないだろうなという不安もある。

「おつかれさん!」
失われた水分を取り戻すべく、ペットボトルの飲料をガブガブ飲み出す引っ越し会社の僕たちに、企業の社長さんが労いの言葉をかけた。社長さんは高級そうなネクタイをしっかりと締め、高級そうな黒縁のメガネを光らせる。
「いや、ほんと、ご苦労、ご苦労。これ、少なくてすまんが、取っていきなさい」
そう言って社長さんは、ひとりひとりに白い封筒を渡した。やがて、僕の手にもそれが渡された。社員さんが「ありがとうございます!」「滅相もないです!」と口々に叫びながら、こわばった表情で封を開ける。僕も「ありがとうございます!」と大きな声で伝え、社員さんに倣ってゆっくりと封を開けた。
中には、1万札が入っていた。
社員さんたちは改めて、社長さんに深々と頭を下げる。
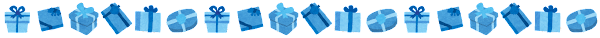
「たまにああやって、御祝儀をくれるお客さんがいるんだよ」
帰りのトラックの車内で、社員さんのひとりが教えてくれた。
「もっとも、大抵は1000円とか2000円とかが普通で、1万円もくれたあの社長はめちゃくちゃ太っ腹だぞ。ラッキーだな、あんた」
「えっ。……すごいいい人だ、社長さん」
「あんた、学生さんだろ?彼女とかいるのか?」
「あ、はい、……でも、付き合ったばかりで、まだなんにも」
「いいねえ、若いってのは。ま、せっかくでかい小遣いもらったんだ。青春を謳歌したまえ」
1万円か。けっこう残業もしたので、バイト代も貯まってきているし、石橋さんと会える状況なら、行きたいところはいくらでもあるんだけどな……。まあ、4月まで待つか。
「あ、そういや、オレ、来週ちょっと有給取るからよ。しばらく違うパートナーになると思うから、まあそこでも頑張れよ」
「あ、はい。しばらく休まれるんですね」
「旅行だよ。半年にいっぺん行くんだ」
旅行か。いいなあ。車窓から対向車線の車たちを見ながら、しばらくぼんやりした。それにしても、車のナンバーっていろんな地域のものがあるな。
もちろん僕の地元の県のものが圧倒的に多いが、名古屋ナンバー、品川ナンバー、中には鹿児島なんて遠方のものもあるし、習志野というどこなのかわからないものもある。仕事、旅行、家庭の事情、それぞれの目的があるのだろう。
なんとなく始めたバイトだが、そこで稼いだお金を、僕はどんな目的に使いたいだろう。やはり、石橋さんの顔ばかりが浮かんだ。今は大阪にいるんだよな。
大阪ってどんな街だろう。一度も行ったことがない。地元の駅からだとどれくらいかかるかな。検索してみるか。いや、待てよ。
大阪に行かないと石橋さんに会えないということは、逆にいえば、僕が大阪に行けばいいんじゃないのか。幸い、この引っ越し業者のバイトは手渡しの日払い制なので、手元にそこそこの軍資金がある。
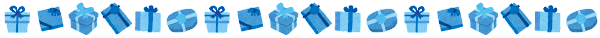
新大阪駅の新幹線改札口を抜けると、軽自動車が置かれているスペースが正面に見えた。大阪駅には新幹線が停まらないし、わかりやすい目印のある新大阪駅で待ち合わせたほうがいいという石橋さんの指示に従った。
「まさか、初デートが大阪とは思わんかったわ」
石橋さんは、嬉しそうに僕の手を引いて、ただっ広い駅の構内を歩いていく。
テレビでよく紹介されるりくろーおじさんの店、名前をよく聞く551の蓬莱、たこ焼き屋に串カツ屋。コンビニの入り口の段ボール箱に大量に積まれたカール。今の僕は本当に、大阪に下り立っているのだ。しかも横にいる石橋さんは、今はもう僕の恋人なのだ。夢じゃないのか。
新大阪駅から地下鉄に乗り換え、なんば駅で下りる。複雑ななんば駅の構内を、石橋さんは迷うことなく歩いていく。うかうかしていたら、いい歳をして迷子になりそうだ。必死で追いついていく。
駅から出ると、今度はごちゃごちゃした商店街の風景が待っていた。田舎者の僕はクラクラしてきたが、3分ほど歩くと、一気に頭がクリアになった。
「ほら、これが、あれや」
「本当だ。あれだ……」
なんば駅から徒歩3分。あの、阪神タイガースが優勝するとファンが次々に飛び込むという、道頓堀。実際に見ると、かなり浅い。そして、向こう側には、大阪の象徴ともいえる、グリコの看板。本物だ。すげえ。
ここにきてカップルがすることといえば、もちろん……。
「すいません、撮ってもらえますか?」
僕がボーッとしているうちに、石橋さんが通行人に声をかけ、スマホを預けていた。
「ほらほら、ウチに寄って」
「は、はい……」
「ウチの肩、抱いて」
「えっ?あ、はい……」
「ピース!」
言われるがままに石橋さんの肩を腕を乗せて、石橋さんの腕は僕の肩に乗って、名前も知らない通行人の人が、石橋さんのスマホで僕らを撮った。
僕のスマホでも撮ってもらいたかったが、人見知りの僕は、石橋さんみたいに見ず知らずの通行人に気安く声をかけられない。
「写メ送ったるわ」
僕の気持ちを最初から見透かしていたのか、石橋さんのおかげで、すぐに僕のスマホにもツーショットの写真が読み込まれた。本当に夢じゃなかろうか。
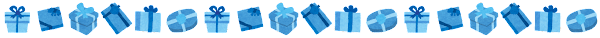
道頓堀には金龍ラーメンという有名なラーメン店があるらしく、さっそく近くを覗いてみた。巨大な龍のオブジェが印象的な店舗だが、人がいっぱいで、行列ができていた。
「心配せんでええで。近くに別の金龍あるから」
僕の服の袖を引っ張って、看板だらけで何が何やらわからない商店街のほうへと歩いていく。
道頓堀を離れて、5分ほど。コメダ珈琲店と松屋が並ぶ一角には、確かに金龍と書かれた看板があった。ただし、こちらはシンプルに金龍という文字が掲げられているだけで、道頓堀のそれのようなオブジェはない。よくある街のラーメン屋といった雰囲気だ。
「道頓堀とか御堂筋のほうは有名やけど、こっちの金龍は、そこそこミナミの地理知ってる者やないと、わからへんで」
誇らしげに券売機に小銭を入れる石橋さんに倣って、僕も食券を買う。メニューはラーメンとチャーシューメンのみの2択。簡素なテーブルと椅子が整然と並べられた店内は、ラーメン屋というよりも、町中華の食堂のような雰囲気がある。
「ここ、セルフやから。自分で食券カウンターに持っていかな一生食べられへんし、ニンニクとかもカウンターのを勝手に取る。カウンターにごはんあるけど、それタダで食べてええから」
店内のルールを説明してくれるのを聞きながら、とりあえずふつうのラーメンのボタンを押した。
「ウチはこっちの店のほうが、落ち着くから好きやねん」
「そうなんだ……」
「そういえば、さっきから、なんか自分、口数少なない?」
「えっ?あ、……そうかな?いや、めちゃくちゃ楽しいんだけど、大阪って大都会で、刺激だらけで、ちょっとそれに追い付けてないっていうか」
やっぱり石橋さんは凄い。すぐに僕を見透かしてくる。
大阪のあれこれが刺激的で驚きの連続なのはもちろん事実だが、実は、バレンタインデーのお返しのホワイトデーに何をあげるのかを全く考えておらずに3月の下旬にまで来てしまい、さらにはいきなり大阪に押しかけてきて、観光所の案内を任せっきりなのだ。
僕はとても幸せだが、僕は石橋さんに何を与えられているのか、不安になってきた。
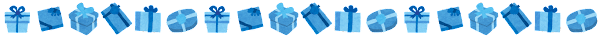
「ほら、ラーメンできたって。受け取りに行かな」
「うん」
金龍のラーメンは、濃厚そうな見た目に反して、喉にスルスルと入ってきた。わりとあっさりめの味で、むしろちょっとキムチやニンニクが欲しくなってくる。途中で席を立ち、キムチを入れてみた。ついでに、無料で食べられるというごはんも追加。
石橋さんは最初からキムチを入れ、ごはんも運んでいた。
「結局、池田くんも、同じことしてるやん」
湯気で沸いた石橋さんの笑顔を見て、身体が火照ってきた。キムチを入れるとラーメンの味が変わって、あっさりだと思っていたのが、だんだん濃厚になっていく。
完食したところで、店内を落ち着いて見回すと、来客は僕たちふたりだけのようだった。
ハイテンションな大阪のミナミの街並みを見るのはそれはそれで楽しいのだけど、田舎者の僕にとっては、やっぱりこういうところのほうが合っているようだ。なんとなく焦っていた気持ちが整理され、素直に現状を打ち明ける決心がついた。
「バレンタインのお返し、まだあげてないよね?」
「え?くれるん?」
「普通は、お返しするものじゃないの?」
「うん、基本は3倍返しやな。でも、大阪に来てくれたやん。それだけで普通に3倍くらいあるて」
「いや、それはたまたまお金があって、僕が勝手に来ただけだし。次の店、奢ろうか?」
「ええって。高い電車賃払わせてるんやし。次どこ行く?串カツ?風月?……ラーメンの後にお好みはさすがにきついかなあ」
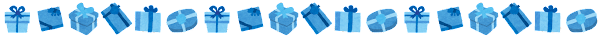
わなかで買ったたこ焼きを食べながら歩き、吉本新喜劇が行われているなんばグランド花月を観察し、店内がドラクエ仕様になっているローソンに立ち寄って、とても充実した1日を過ごした。
さすがに歩き疲れてしまった。なんばパークスというところには広い庭園のような休憩スペースがあるので、そこで休むことにした。
「ねえ、ホワイトデー、やっぱり何かしたい」
「しつこいなあ。……じゃあ、お返し、して、ここに」
そう言って、石橋さんは自分の右頬を指さした。それって、つまり……。ああ、でも、確かに、バレンタインデーにくれたものの「お返し」ではあるな。
しかし、ここは大阪の観光施設のなんばパークスである。周りは人で溢れている。いや、ここは定番のデートスポットなので、イチャついているカップルもたくさん目に入ってくる。僕だって彼らと同じ。何も恥じることはない。
…チュ……チュ……チュチュッチュチュ……
「……………………えらい激しいなあ。女の子の顔には、もうちょい優しくしてや……」
「ご、ごめん……」
「リテイク!」
「え?」
「やり直し!もう1回!」
「うん」
……チュッチュ……
今度は、さっきよりはマシにできたかな?
「もう1回!」
ええ?
……チュッ……
「これでいい?」
「ま、今日はこれくらいにしといたるわ」
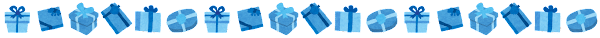
すっかり陽が暮れた空には、星がふたつ並んで浮かんでいた。しばらくふたりとも黙って座っていたが、やがて石橋さんが立ち上がり、唐突に歌い出した。
「愛しあう~、ふーたぁーりー、しーあわせのー、そら」
「ユーミンの歌に、そんなのあったっけ?」
「明日も大阪おるんやろ?次は大阪城やな。あと、桜之宮公園と、お初天神と………。もう1回!」
「え?」
「何回やってもええやろ。カップルやねんから」
……チュッ……
だんだん、コツがわかってきたような気がする。
「あーなーたーと、わーたし」
また石橋さんは唐突に歌い出す。
「ねえ、誰の歌、それ?」
質問に答えずに、石橋さんは歌いながら僕の手を引っ張って、ハイテンションなミナミの街並みへと、再び僕らは飛び込んでいった。
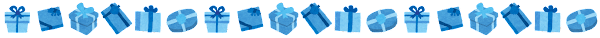
↓前作
いいなと思ったら応援しよう!

