
正しい判断をする!
『正しい判断』基準 ⇔ 八正道
日本の民主主義の社会制度は個々人により
『正しいと考え、思うことは異なる』
と判断すると言うことを大前提にして
作られ実生活の中で生かされています。
社会人として弁えて置くべきと言われている、
当たり前の知識や人として成すべきことを
『正しいこと』と話すと、若者から年長者は、
「押し付けがましいとか、今に合わない」
と言われることも度々あります。
これは『正しいと言う判断基準』も
年齢差などによって感性が大きく変化し、
時代の進化と共に大きく様変わりしている
と言うことの表れと受止めています。
しかし、本当にそう言った風に簡単に
妥協してしまって良いのでしょうか?
私見ですが、
どんなに時代が移り変わろうとも、
人間である以上その「心」は不変と考えます。
日本国内では、先年の東日本大震災後、
「自分の為より、誰かの為に」
というような思い遣りであるの利他の心、
人と人との繋がり方、婚活や様々なエコ
への取組みなどにも実際に表れたように、
『正しい』(≒常識・当たり前)と思っている
心の持ち方や判断基準に変化が見られます。
このことは人の心の原点に立ち返ることに
人々が気付き、今迄に自分自身が人として
「正しい」≒当たり前ことと考えていたこと、
判断してきたことを見直した証です。
即ち、主観を捨て現実を真剣に直視し、
平常心で公平に物事を判断することにより
人として「正しい」か否かの判断が導かれます
🌎正しい{思考}と{判断}は
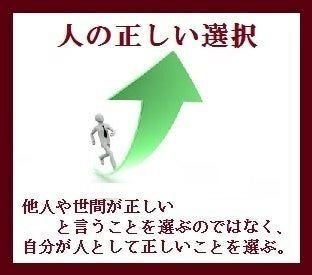
1.人として何が正しいのかを判断する
(道徳・倫理感)
2.原理原則を弁え、正論を導き出す
3.公正、公平に判断する
4.無私に徹する
(好き嫌いの感情を自制する)
5.利他、誠実、正義、勇気、
努力、博愛と言ったことを認識する
6.適正な判断のタイミング(ТPО)の認識する
7.強い意志力を備え持つ
8.悲観も楽観もせずに客観する
9.感情論を捨て決める
10.論理を元に、正確な状況判断と分析する
※自分はいつも判断を間違えてしまう
と言う人は、謙虚に自らの備え持つ
判断力では仕事・対人関係に必要な
充分に判断が出来ないと自覚認識し
「正しく判断が出来る人(先人)に謙虚
に助けを求め、サポートして貰う」
と言う自らの気付きの姿勢も大切です。
ここで、
温故知新の心を以ってこの「正しい」
について改めて古より日本にある
仏教の教えから考えてみたいと思います。
お釈迦様が
最初の説法の時にの八種の実践徳目
(正しい道)=八正道を解き明かしました。
八正道の解説

1)正見=正しい見解・正しい見方をすること。
2)正思=正しい思惟であり、
正しく考え正しい心構えを保つこと。
※思惟(シイ):考えること。思考。
3)正語=正しき言葉を使うこと。
4)正業=正しき行為。
5)正命=正しき生活。
6)正精進(正勤)=正しき努力と勇気。
7)正念=正しき憶念(オクネン)。
※憶念:深く思い絶えず忘れないこと。
また、その思い、執念。
8)正定=正しき禅定であり、
静慮にして精神を統一すること。
この八正道は、
古より日本に伝わり現在の社会環境
でも相通じる仏教の教えです。
この教えは、
人としての意識や物事・事象の『正しい』
を理解認識し心の判断基準作りのために
学び知り身に着ける必要があります。
これは正しい判断力を育む上で
無くてはならない
【心の基礎体力≒EQ】(下図)
に結びつくと考えます。

物事や事象、人の態度、意識などを
「正しい」と考える判断基準は社会で存在する
定められた様々なルールや法律(規律)以外は、
人夫々により差が生じ、異なるということを
予め弁えておくべきであると思います。
あくまでも私見ですが、
それは個々人が持つ道理に適っているか否かの是非、
物事の原理原則の認識の有無、夫々の人の育ち、
生活環境の経緯、経験・体験の多少、年齢、
立場(社会・生活上)、教養(学歴含)、精神状態、
コンプライアンスやモラルの基準、心の成長度合
などと言ったものが基となると考えます。
例えば、正しい判断をせず間違った判断をした時などは、
状況を見る視野が狭いか、偏った見方をしている場合が多く、
物事の見方が公平さに欠ける場合が多くあります。
そのような時は、主観的にならずに
他人称客観的視点に立って「公平に判断する」ことです。
※上図の八正道は、ととても奥が深いです。
📚辞書検索【正しい】
(三省堂 大辞林より)
物事のあるべき姿を考え、
それに合致している様を言う。
(1)道徳・倫理・法律などに適っている。
よこしまでない。道理に適っている
(2)真理・事実に合致している。誤りがない。
(3)標準・規準・規範・儀礼などに合致している。
(4)筋道が通っている。筋がはっきり辿れる。
(5)最も目的に適ったやり方である。
一番効果のある方法である。
(6)ゆがんだり乱れたりしていない。
恰好がきちんと整っている。
