
心理的安全性に振りきってみる! 新ノウハウ「Organization Deck」のご紹介
「当社はアドテクノロジーの業界なのですが、業界とプロダクトが分かりにくく、どのように会社の魅力を設計していけばよろしいでしょうか?」
そんなご相談をいただいたのが今からちょうど4ヶ月ほど前のことでした。
これまでにも、アドテクノロジー業界のお客様は多数存在しておりました。僕自身は多数企業様に触れたことがあるため、イメージがついているのですが、アドテクノロジー未経験の方からすると、イメージがつきにくいと思います。
そんな中、どのように採用活動における魅力を設計していけば良いのか?そんなご相談を受けたのですが、当社として、新しい魅力の「作り方」をいたしましたので、本ブログにてご紹介したいと思います。
0. 採用ブランディングとは
僕は人材業界出身ですが、「採用ブランディング」という言葉について、世間で明確に定義されているものは無いと個人的には思っています。しかし、採用ブランディングはコーポレートブランディングとは異なります。下記で定義をしておりますのでご覧ください。
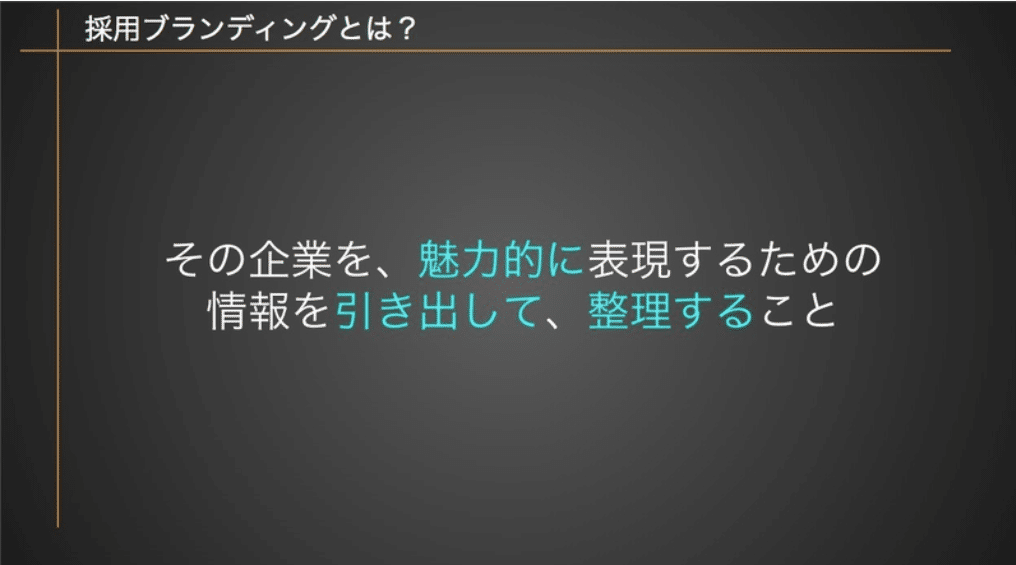
僕が考える「採用コンサルティング」の定義はこれです。主に採用領域において企業を魅力的に表現するための情報を引き出して整理することです。
詳細は下記ブログをご覧ください。
1. アクセルマークさま
今回、採用活動における魅力設計のご相談をいただいたのは、「アクセルマーク」という企業様でした。詳細な事業内容のご紹介は割愛するのですが、業界としては「アドテクノロジー」に分類され、前述した通り、本業界に触れたことがない方にとっては、馴染みの薄い業界かと思います。
そんな中で、当社の「採用ブランディング」というサービスにご興味をお持ちいただき、本サービス提供をさせていただきました。
2. 採用ブランディングの勝ちパターン
当社の採用ブランディングは、その企業様の「唯一無二」のポイントを見つけることを心がけています。ただ、日本には数百万社?の企業様が存在する中で「唯一無二」のポイントを見つけるのは困難ではあるのですが、これまで250社様ほどの採用ブランディングに携わらせていただいて、その情報も参考にしながら見つけて参ります。
「唯一無二」というと急に難易度が上がるように感じられるかもしれませんが、「採用活動において各社が「アウトプットしている情報」における唯一無二」というと少し難易度が低くなるように思います。
どういうことかというと、世の中に存在するたくさんの法人企業様の中で、
「いやいや、わざわざ採用活動においてそこまで情報公開していないよ」
というポイントが存在します。
つまり、「実態」としてはたくさん存在するけれども、採用活動における「情報のアウトプット」をしている企業という観点においては、唯一無二なポイントが存在する、というわけです。
もう少し具体的に申し上げると、
「採用媒体に掲載している記事には、ベビーシッター制度のことは書いていないんだけれど、実態としては申請すればベビーシッターを使用することができるんだよ」
「採用媒体には当社の働く環境について細かく記載していないんだけれれども、実態としては働く環境はものすごく良いんだよ。具体的には…」
「採用媒体には当社の代表が、3カ国において起業した経験がある事は記載していないんだけれども、実態としてはあるんだよ」
そんな具合です。
繰り返しになりますが、「唯一無二」なポイントを見つける事は難しいですが、採用媒体に掲載している記事は、御社の情報の中でもわずかな情報であるかと思います。そのため、
「他社はそこまで細かく出してないけれども、当社は必要以上に細かく情報を出している」
そんな差分を有効的に用いて、「唯一無二」のポイントを見つけることもできます。今回は、このテクニックを少々使わせていただきました。
3. 取引前の商談時から感じていたアクセルマークのあたたかさ
営業やコンサルティングのお仕事をしている方はご理解いただけるかと思いますが、初めてお話しする企業様については、最初の1分程度のコミュニケーションにおいて、その企業様の「会話における安全性」を感じることができます。ここで言う「安全性」とは、営業/コンサルティングをする側が、
「躊躇なく、言いたいことを言いたいタイミングで言える」という安全性のイメージです。
アクセルマークさんでは、CTOの佐野さん、人事の綱島さんという方とお話しさせていただきました。もちろん初対面でしたので、丁重に笑顔でお話してくださっているのかなと感じていたのですが、取引が開始した後も、こちら側(サービスを提供する側)がものすごく話しやすい雰囲気を作ってくれているなと感じておりました。そこで、
「社内でも、そのようなコミュニケーションを推奨されていらっしゃるのですか?」
という質問をさせていただいたところ、「Yes」という回答でした。
なるほど、とは思っていたのですが、この時点では「一般的な」心理的安全性がある企業様、くらいのレベルだと思っておりました。ただ、CTOの佐野さんがこんなことをおっしゃっておられました。
「“心理的安全性“ってGoogleが最初に言い出した?と記憶しているのですが、Googleが取り組んでいるから、という理由からGoogleの真似をして “心理的安全性” を取り入れていく企業様がおられると聞いたことがあるのですが、僕の場合は過去の自身の失敗体験からの教訓が、“安全性“を取り入れるキッカケになったんですよね」
ん?
CTOの佐野さんの過去の失敗体験を元に改善した結果が “心理的安全性“ であったと。つまり、心理的安全性が「目的」ではなく「結果論」であった、という話だったのです。
僕自身も心理的安全性が「目的」になるのは本質的ではないと思っていました。なぜならば、組織における課題を解決をした結果が“安全性“である必要性があると感じていたからです。これは心理的安全性における 「あるべき姿」であると強く感じました。
4. 大々的に「心理的安全性」に振り切った採用ブランディングをしてみてはどうか?
僕が採用ブランディングに入らせていただいた企業様の中で、“最も“安全性があると感じたのがアクセルマークさんでした。そして、第一回採用ブランディング ヒアリングの後に下記のメッセージを佐野さんにお送りしました。
こちらの下段に記載をしている内容に対して、佐野さんに思考していただきました。そして、佐野さんに濃い目なご回答を頂戴したのですが、本ブログでは割愛します。
そんな中、ご回答内容を整理して、今回の“心理的安全性“に纏わる採用ブランディングストーリーの仮案を作成しました。
◆ブランディングのストーリー
過去の失敗体験 Ver.1
トップダウンよりもボトムアップのほうが、アウトプットの質が2倍以上高いことを体感していた
メンバーへの環境提供
ボトムアップ組織にするために、メンバーにどのような環境提供をすると良いのか?
結果的に生まれた安全性
意図的に構築していたカルチャーが、俗に言う「心理的安全性」に酷似していた
過去の失敗体験 Ver.2
直近3年間で佐野さんが直面していた「壁」と「変化」について
心理的安全性の「要素」
アクセルマークの心理的安全性の「要素」とは
このような内容で設計しました。
上記のブランディングストーリーは7,000字にも渡る内容となっています。
本内容は佐野さんより公開許可を頂戴しておりますが、さすがに全文の拡散は難しいため、ご興味のある方は、僕のTwitter or FacebookよりDMを頂戴できますでしょうか?
山根のTwitterアカウントはこちら
山根のFaceBookアカウントはこちら
5. 「心理的安全性」の魅力をどのようにアウトプットするのか?
ブランディングストーリーが出来上がったことはポジティブですが、どのようにアウトプットをしようか考えました。その結果として、
・採用ピッチ資料
・採用広報
の両者においてアウトプットをしようと決めました。採用ピッチ資料と採用広報の目的の違いは上記の通りです。
実際に出来上がったモノを本ブログにて公開します。
5-1. 採用ピッチ資料
こちら是非ご覧いただければ幸いです。
5-2. 採用広報
前述した通り、採用ピッチ資料は「魅力を薄く/広く」に対して、採用広報は「魅力を狭く/深く」のイメージです。今回の採用広報は、心理的安全性を語る上で 3本の採用広報を企画し、インタビュー⇒執筆まで実施しました。概要は下記の通りです(採用広報記事を公開したらリンクを貼り付けます)。
1本目
- テーマ:「チャレンジをするために」もう一度挑戦へ。CTO佐野のキャリアの変遷 〜第1章〜
- 佐野さんの年次が若い頃の失敗体験
2本目
- テーマ:立ちはだかる壁に、試行錯誤した日々|理想的な組織ができるまで。〜第2章〜
- 失敗体験を元に試行錯誤しながらトライアンドエラーを繰り返す
3本目
- テーマ:手段としての「心理的安全性」|アクセルマークの目指す組織と求める人物像 〜第3章〜
- トライアンドエラーから確立された組織のあるべき姿
そんな中、ここで一つ課題が発生していました。
6. 候補者体験を突き詰めた際に「採用ピッチ資料」と「採用広報」だけでは足りないのでは?
「スカウトメールを受信する候補者さまはアクセルマークのことは “無知” な状態なはず。つまりスカウトメールをキッカケとしてアクセルマークを “認知” するタイミングで speakerdeckに掲載する採用ピッチ資料+4,000字以上の採用広報は重すぎないか?」
その通りだと思います。speakerdeckはスマートフォンから閲覧しにくいですし、長文の採用広報はスカウトメール受信時には最適なコンテンツとは言い難いです。そこで新しいノウハウが誕生しました。
6-1. Organization Deck
そんな中、誕生した新しいノウハウが「Organization Deck」です。
前述した通り、
・より気軽に、ラフに、わかりやすくを追求
・スカウトメール受信時に候補者さまがスマホでご覧いただくイメージ
・採用ピッチ資料や採用広報では表現しにくい体験を提供
このあたりを意識して作成しています。
実物をご覧ください。
すごく良い感じに出来上がったと思います。
7. 最後に山根より感じたことを徒然なるままに記載します
まず、素敵なノウハウを開発させていただくキッカケをいただいたアクセルマークさまにはお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
「心理的安全性」という言葉について、僕個人的には容易に使うのは賛成ではありませんでした。なぜならば「心理的安全性」をただ掲げるだけでは、「温い組織」が生まれると、なんとなく感じていたからです。
ですが、結論として「今」はそう思っていません。
なぜならば、組織として最大限の成果を上げるための手段の一つが「心理的安全性」の創出があると確信しているからです。何度も申し上げますが、心理的安全性は「目的」ではありません。組織が最大限の成果を上げるための「一つの手段」だと僕は思っています(個人的な意見です)。
また、組織が成果を上げるための「手段」の中で、最も理解が「正確に為されていない」項目の一つが心理的安全性だと感じています。つまり、各々で理解が異なると言いますか。理解が異なると同時に、重要性も理解されていない現状があると思っています。
ただ、組織における安全性の欠如は「最も危険な退職リスク」になり得ます。どんなに良いphilosophyであっても、どんなに良いproduct、cultureでもあってもです。これは僕は確信に近いです。
そんな中で、アクセルマークさまは、正確な理解をされていない&重要性も理解されていない「心理的安全性」について、これ以上なく独自にアプローチをされています。心理的安全性が「なぜ重要なのか?」も説明に含めておられます。
採用活動において「心理的安全性」に振り切るのは勇気が必要なジャッジだったかと思うのですが、少しでも採用活動が前に進むことを楽しみにしつつ、そして本施策が採用市場を前に進め、且つ、日本の経済が前に進むキッカケとなると嬉しく思います。
最後に
皆さんいかがでしたでしょうか。
※当社の採用/人事組織系支援にご興味がある方はお気軽にお声掛けください。
累計支援社数300社超の実績をもとに、システム活用(Opela) × オペレーション支援で貴社の最適な採用管理・オペレーションを構築・改善します。
採用管理システム(ATS)全機能を無償で提供しています。
今後も採用/人事系のアウトプットを続けていきます。
よろしければフォローもよろしくお願い致します(左上クリックいただき、「フォロー」ボタンがあります)👆
