
俳句のいさらゐ ◈∥◈ 松尾芭蕉『奥の細道』その三十八。「文月や六日も常の夜には似ず」
酒田の余波 ( なごり ) 日を重て、北陸道の雲に望。 遙々のおもひ胸をいたましめて、加賀の府まで百丗里と聞。鼠の関をこゆれば、越後の地に歩行を改て、越中の国一ぶりの関に到る。此間九日、暑湿の労に神をなやまし、病おこりて事をしるさず 。
文月や六日も常の夜には似ず

上の文は「文月や六日も常の夜には似ず」の前文である。
この俳句にとってこの前文は何の意味を為すのだろう、という感じがある。「奥の細道」に親しみ始めた頃、この俳句の意味がとれなくて、「暑湿の労に神をなやまし、病おこりて」という文が、俳句の中の「六日も」にかかっているのかと思った。つまり、六日間も「常の夜」とは違うそんな目にあっていたということなのかと。
しかしそれでは、愚痴を言っているだけのことで、何に感動した俳句なのかはわからない。解説書をしげしげとめくり、初めて六日が七夕前夜のことを示していると知って、俳句の意味は通じた。それでもなお疑問が残った。七夕のことをなぜ前文のどこにも触れていないのかと。
長らく考えて、芭蕉の時代には「文月や」という季語が、われわれに響く度合とは格段の違いで、七夕に密接に結びついていたのだと気づいた。
文月の語源は、七夕の短冊に歌や願い事などを書く行事、つまり文を書くことに由来するという。書いた詩歌を献じたりもしていた。芭蕉の時代の七夕は、現代のそれよりも、何倍も文 ( ふみ ) の雅が華やぐ日だったのだ。
だから前文に七夕の一言がなくても、「文月や六日も」だけで、七夕の前日、と打てば響くように理解されたわけである。
そして、「文月や」と並んで置かれている「荒海や佐渡によこたふ天河」にも前の俳句の「文月や」が響いて、織姫彦星のいる天の川、が詠まれているとすぐにわかる構成になっている。
参考に江戸時代盛んに描かれた七夕図の例を示す。



さらに読み取らなければならない疑問がある。「常の夜には似ず」とはどういう気分を表しているのか。
たとえば、七夕前夜の華やいだ気分だと考えるよすがとして、江戸時代ではなく近代以降の様子ではあるが、秋田県酒田の七夕祭りについて書かれた回顧談の一部を引用しよう。「文月や」の俳句が詠まれた直江津も、酒田と同じ商港の性格を持つ町である。
六日の夕方になると、近郊近在の百姓たちが、青ざさのついている七夕竹を沢山荷車につけて、「タナバタダケイ、タナバタダケイ」とふれてくる。町の主婦たちは皆走り出て、短冊を下げるのに適した枝ぶりのよい青竹を三本買い求める。またこの日の夕方から明け方にかけて、七夕市というものがたつ。そこへ近在の百姓たちが、七夕に飾る色々な品物を荷車につけて運んで来る。すいかやうりを山と積んでいる店も臨時に出来上がる。
これに近い雰囲気があったのかとも想像してみるが、芭蕉の文にも、また曽良の随伴日記でも「常の夜には似ず」を思わせるような、宵の町が華やいでいる雰囲気は述べていない。
「聴信寺ヘ弥三状届。忌中ノ由ニテ強テ不止、出。石井善次良聞テ人ヲ走ス。不帰。及再三、折節雨降出ル故、幸ト帰ル。宿、古川市左衛門方ヲ云付ル。夜ニ至テ、各来ル。発句有。」( 聴信寺での宿泊を当初の宿泊予定していたが、忌中のため変更になり、結局この日は古川市左衛門方に宿泊した )と、備忘録として記述されているだけだ。

そこから思うのは、この夜の町の様子は、この俳句を触発したわけではなく、もっと芭蕉の文学的観念性の熱い部分から発した俳句ではないかということだ。
そこで念頭に置くべきは、並んで置かれた俳句「荒海や佐渡によこたふ天河」である。この俳句は、本州とは離れた、容易には行けない場所、かつては流罪の島でもあった佐渡を前にした日本海の寂漠に、自由に会うことが許されていない天の川伝説を重ねた明らかに劇的な演出を施した俳句である。
研究・解説書を読めば、六日七日両日の天候 ( 曇天雨天 ) からして、芭蕉には天の川は見えていなかったようだが、実際に見たことにこだわらずとも、七夕の時期に、想像を超える日本海を眼前に見る地にいたのであるから、こう言えるのではないか。

「奥の細道」の天の川は、日本海という大きな反射鏡の上空に渡る天然の紋様であった。生涯において、再びはまみえることのない一夜の絵画的観念に浮かび上がった眺めであった、と。
それは、間違いなく上方や江戸にいて七夕を迎える気持ちとは大きく異なっていたはずだ。
この地この場で感じたことは、下に引いた「銀河ノ序」という題で残る、芭蕉が何度も推敲した俳文に、鮮烈な思いとして表現されている。「銀河ノ序」は、旅のあとで書いた文章であろうが、現場で感じ取ったものがよほど強い印象であって、それが核心になっていることを伝えている。
「銀河ノ序」( 最終稿 )
日既に海に沈で、月ほのくらく、銀河半天にかかりて、星きらきらと冴たるに、沖のかたより、波の音しばしばはこびて、たましいけづるがごとく、腸ちぎれて、そぞろにかなしびきたれば、草の枕も定らず、墨の袂 ( たもと )なにゆへとはなくて、しぼるばかりになむ侍る。
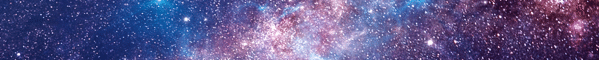
つまり、異郷で迎える明日の七夕を思えば、今宵 ( 六日 ) の宵空も、まったく江戸の庵において迎えて来た気持ちとは違っているものだなあ、という感懐が、「常の夜には似ず」の真意だろうと思うのだ。
冒頭で上げた疑問に帰れば、「酒田の余波 ( なごり ) 日を重て」で始まる前文は、そういう不快な旅の日々にあっても、「銀河ノ序」に述べたような感動は不意にやってくることを、逆面から修飾しているのであろう。
いやになるような旅路なのだけれど、そんな中にこそ感動の種はある、と言うため ( つまり「文月や」の俳句を持ち上げるための演出 )なのだ。
「荒海や佐渡によこたふ天河」は、諸書によれば紀行中屈指の名句という評価もあるが、「荒海や」の露払いのような「文月や」の俳句を前に置き、七夕の夜を自然に想像させることで生まれた情感の厚みが、評価に寄与しているのがわかる。
さらにその前文として、旅のアクシデントを述べることで、たやすく感動は得られるものではないことを、読者に考えさせているのだ。
なお、細部は異なるが、すでに詩人安藤次男が著作『芭蕉その詞と心の文学』で「常の夜」について述べている解釈と同じであることが、この稿を書くために調べていてわかった。
わたしなりの解釈には同書とは微妙な違いもあり、剽窃して使ったわけではないことを付記しておく。
令和6年10月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
