
詩の編み目ほどき⑦ 新川和江「野を往く」
野を往く 新川和江
秋晴れのとある日
東フランス ロレーヌ地方の
優しくなだらかな丘陵地帯を車で通った
わたしはあなたを思い出した
十年あまりも一緒に暮らし
そのあいだ
ただの一度も
大声ひとつ
あげたことのないあなたを
往けども往けども
丘ばかりで
往けども往けども
野ばかりで
牧夫も見えず
尖塔も見えず
ところどころに
白黒まだらの放し飼いの牛が
おとなしく草を食んでいるだけで
陽ばかりうらうら
やわらかくとけているだけで
わたしは次第に倦みはじめた
わたしはあなたを思い出した
わたしは次第にじりじりして来た
わたしはあなたを思い出した
モーゼル川は岸のポプラの影をうつして
睫毛を伏せて睡っていた
わたしはほとんどわめき声をあげそうになった
いっぽん道は
夜になってもまだ野の中に続いていた
往き交う車もなく
事故の起こしようもなく
パリの灯はぽつりとも見えて来なかった
わたしはほとんど泣きそうになった
ちょうどこのようにして
このようにして
あなたの中で
わたしは迷い 徐々に狂っていったのだ
柵もなく 唸る鞭もない
あなたの優しすぎる野の中で
迷いようもなく そのいっぽん道で
🧵 詩の解釈
上掲の詩を書いた新川和江の脳裏を漂っていたであろう一首を思う。与謝野晶子の次の歌だ。
ああ皐月仏蘭西( フランス )の野は火の色す君も雛罌粟( コクリコ )われも雛罌粟 与謝野晶子
明治45年5月5日与謝野晶子は出国し、シベリア鉄道を経由して、19日にパリに到着する。パリには夫、与謝野鉄幹がいた。晶子は、5月のフランスの野原に咲き満ちていた雛罌粟ーヒナゲシの花の輝きに、夫に会う胸中の思いを重ねた。名歌である。
新川和江の「野を往く」は、晶子の歌の対蹠と言える境地だが、詩の場面設定はそっくりだ。秋と初夏の違いはあれど、晴天の日、異国フランスの野、あなたを思い、■《 ほとんど泣きそうになった 》 気持ちの昂り。
新川和江には、仏蘭西の野では、火の色なす陶酔へ誘う何物を見ることもなく、平板な、無味乾燥な眺めから、己の精神世界の不毛ばかりが透けて見えたのだ。
著名な作品のある一節、一連、詩句が、創作の衝動として作用することがあるのは確かなことだが、それはオマージュ ( 賛意擬装 ) としての形を取るだけではないだろう。反面的に、妬心をない交ぜにした感情で、晶子の歌が、「野を往く」の底に沈んでいると見えて来るのだ。
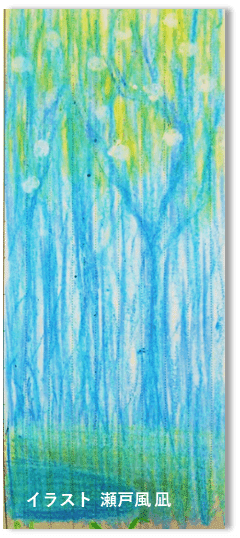
■《 十年あまりも一緒に暮らし 》
の言辞は、新川和江の人生の足取りを示している。昭和21年、17歳で結婚。 昭和39年、35歳の秋、新川和江はヨーロッパ一周の旅をする。その成果、詩集『ローマの秋・その他』は、著者36歳の時である。
■《 わたしは次第に倦みはじめた 》
■《 わたしはあなたを思い出した 》
夫との穏やかな暮らしを連綿と守ってゆくことが、詩人として新しい境地を切り開いてゆく上で、これから何ほどの益を与えてくれるだろうか、という懐疑の中に新川和江はいる。そこから抜け出さなければ、詩人たりえないのではないかとまで、思っているように感じ取れる。
新川和江の表現した《 いっぽん道 》は、創作者としての目覚め、その自覚、幼い日の悲しみや、甘美でほのかに苦い恋の夢、母性がもたらす皮膚感覚の優しい思い、こどもたちへの生命賛歌など、通りのいい女性らしさの世界をうたって来た詩人と受け取られているキャリアを暗示しているのだろう。
🎹 以下、この詩の細部からいったん離れる。
新川和江の詩の大きな特徴を、私は抑制という点に見る。新川和江の詩は畳みかけない。形容に形容を重ねるという、洋菓子のデコレーションのようなこれ見よがしな詩法を拒む。対照として、思い浮かべているのは、たとえば、畳みかけの見本のような、金子光晴の「金亀子(こがねむし)」である。( ※この詩が駄作と言っているのではない )
其夜、少年は秘符の如く、美しい巴旦杏( はたんきょう )の少女を胸にいだく。
少年の焔の頬は桜桃( ゆすらうめ )の如くうららかであった。/少年のはじらいの息は紅貝の如くかがようた。
おずおずと寄り添うおそれに慄えつつ/少年の悲しいまごころは、/花鰧 ( はなおこぜ )の如く危惧を夢みていた。
煩悩焦思の梢、梢を、/鶏冠菜( とさかのり )の如くかき乱れた。
少年は身も魂も破船の如くうちくだけた。
抑制と言ったのは、新川和江には、表したい思いが、作品の詩句の何倍も背後にあると感じられるからだ。
新川和江はルフランの名手 ( たとえば「わたしを束ねないで」「ノン・レトリック」など の詩) という評があり、それを否定はしないが、もうひとつ、場面の切り換えという詩法においても、新川和江はじつに巧みで、俳句でよく言われる、つきすぎず、離れすぎないという妙味を味わわせてくれる。
それなのに私は、新川和江のいくつもの詩を追って読んでゆくうちに、改行による場面転換に立ち止まることがしばしばある。
説明に堕している詩はだめだ、という論があり、それは正しい。新川和江の詩の場面切り換えの前で、立ち止まってしまうのは、説明になってしまう詩句を切り捨てて、次の場面へすっぱりと移ってゆくからであろう。説明してしまい、そのために詩の姿に、シャープさと彫りを失わせてゆくものを捨てている。それが、抑制されている、と私が感じる本質だろう。
■《 わたしはほとんど泣きそうになった 》
という詩句以降の最終連は、まさに説明の切り捨てられた場面切り換えである。この理由に思いを及ぼせば、詩の音色をさまざまに聴くことが出来るのだ。
■《 あなたの中で 》
《 わたしは迷い 徐々に狂っていったのだ 》
狂っていったのは、創作に向かう心の在り方というべきものだと思い及ばざるを得ない。
それは、たとえば「赤ちゃんに寄す」や「可能性」といった、詩集『ひとつの夏 たくさんの夏』 ( 昭和38年刊 著者34歳時 ) 所収の詩に読み取れる母性があふれた生活詩、抒情詩の道が、詩壇で注目される華やかな詩人になるにつれて、軛 ( くびき—※自由を束縛するもの ) に感じられるようになったということではないだろうか。
それは詩人の飽くなき創作欲に起因するものであったろう。あまりにつかみどころのないフランスの野ゆえに、唐突に新川和江を襲った不安感を、婉曲にほのめかすことなく、吐露した作品なのだと私には感じられる。

令和5年8月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
