
こどものころにこの本を読んでいたら、きっと友だちがひとりふえたと思う──加藤多一・作『エカシの森と子馬のポンコ』
子っこ馬のポンコが行く。
ポンコは女の子──
山のふもとのだれもいない草っ原を、歩いていく。
去年、北海道の乳牛牧場で生まれた。つぎの年牧場を逃げだして、いまひとりで生きている。だからここは〈ポンコの森〉だ。
ここで、ポンコはほんとうに自由だ。すきなところへ、すきなように歩いていく。草っ原の歩きかたも自由。
一直線にまっすぐ走りぬけたり、いきなりストップして横にとんだり……目をとじて眠ったふりをしているうちにほんとうに眠くなって、立ったまま眠ったり……。
***
加藤多一さんの物語『エカシの森と子馬のポンコ』(絵・大野八生)の冒頭部分です。

『エカシの森と子馬のポンコ』
扉絵より(一部トリミング)
わたし(編集担当)は、はじめて原稿を受け取って読んだときから、ずっとこの物語のはじまり部分が大好きです。
そして、10代になりたてのこどもたちに向けて書かれたこの物語を読むたびに、「あの頃のわたし」を思い出します。
***
10代になりたてのあの頃……
学校では委員会活動なんかもはじまって、低学年のお世話係なんかもやって、ずいぶんと「お姉さん・お兄さん」に見られるようになった。
6年生なんかになると、「来年は中学生。電車もバスもおとな料金」なんてこともいわれて、そのときどきでこども扱いされたり、おとな扱いされたり。じゃあ、いまのわたしはこどもなの? おとななの? って、自分に問いかけてばかりいた。
そして、わたしはずっと「おとなになりたくない」って思ってた。
雨の日に水たまりを見つめて、そこでお話を想像する時間をずっとずっと持ちつづけていたいと思ってた。おとなになったら、そんなことできないんじゃないか、と不安だった。
それは綿菓子のようにただ甘いだけのふわふわしたものだったかもしれないけれど、わたしはわたしの夢を持ってた。おとなになったら、そんな夢は捨てなくちゃいけないんだろうか、と思ってた。
おとなになったら、いまの「ありのままのわたし」はどこへ行ってしまうんだろう。おとなになるということは、「ありのままのわたし」に目をつぶるってことなんじゃないか。
でも、心の思いとはうらはらに、毎日、自分はおとなになっていく──。

『エカシの森と子馬のポンコ』の主人公のポンコは美しい北の大地の森で、長老の木・エカシや「ここにいるのに、どこにでもいる」不思議な存在のカメムシたちといっしょに暮らしています。
ある日の朝、ポンコが小さな川と大きな川がぶつかっていっしょになるところで、いつものように川に「おはよう」と大きな声であいさつをすると……きょうは、いつもとちがう。「おはよう」といってくれる声が小さい。とびはねるような、うきうきしたところがない。
ポンコはとても不安になります。
わたし、なにか変わってしまったのかも……。
エカシは「ポンコが心も体もおとなになりかけているからだよ」とやさしくいってくれます。
でも、ポンコはほんとうの自分を見失うようで、そのことが受け入れられない。
おとなになるって、どういうことなの?

いま、わたしはこの物語を本にまとめることができて、ほんとうによかったと思っています。
あの頃のわたし、なんでも話せる友だちがひとりふえたね! って。
そして、同じような思いでいる10代のこどもたちに「ありのままの自分で自由に生きていいんだよ」といえることが、ほんとうにうれしいです。
ポンコといっしょに、自然いっぱいの森を歩いてほしいと、物語のすべてのページに絵を入れる工夫もしました。
風や虫、水の声に耳をすまし、ありのままに自由に生きるポンコのすがたに勇気と力を得てもらえたら……。

この本は今年の「第67回青少年読書感想文全国コンクール 小学校高学年の部」課題図書に選ばれました。
たくさんの10代のみなさんと、10代だった頃を大切に生きているおとなのみなさんに、この物語を自由に楽しんでいただけたら、と思うと、どきどきとわくわくでいっぱいです。
また、この物語では、アイヌの人たちのくらしがポンコの目線で語られます。物語を楽しみながら自然にアイヌ文化にふれ、身近で多様な文化と歴史を知ることのできる作品でもあります。
10代のみなさんを中心にたくさんの方が、さまざまな見方からのいろいろな読書感想文を書いてくださったら、こんなにうれしいことはありません。
(文・編集部 小桜浩子)
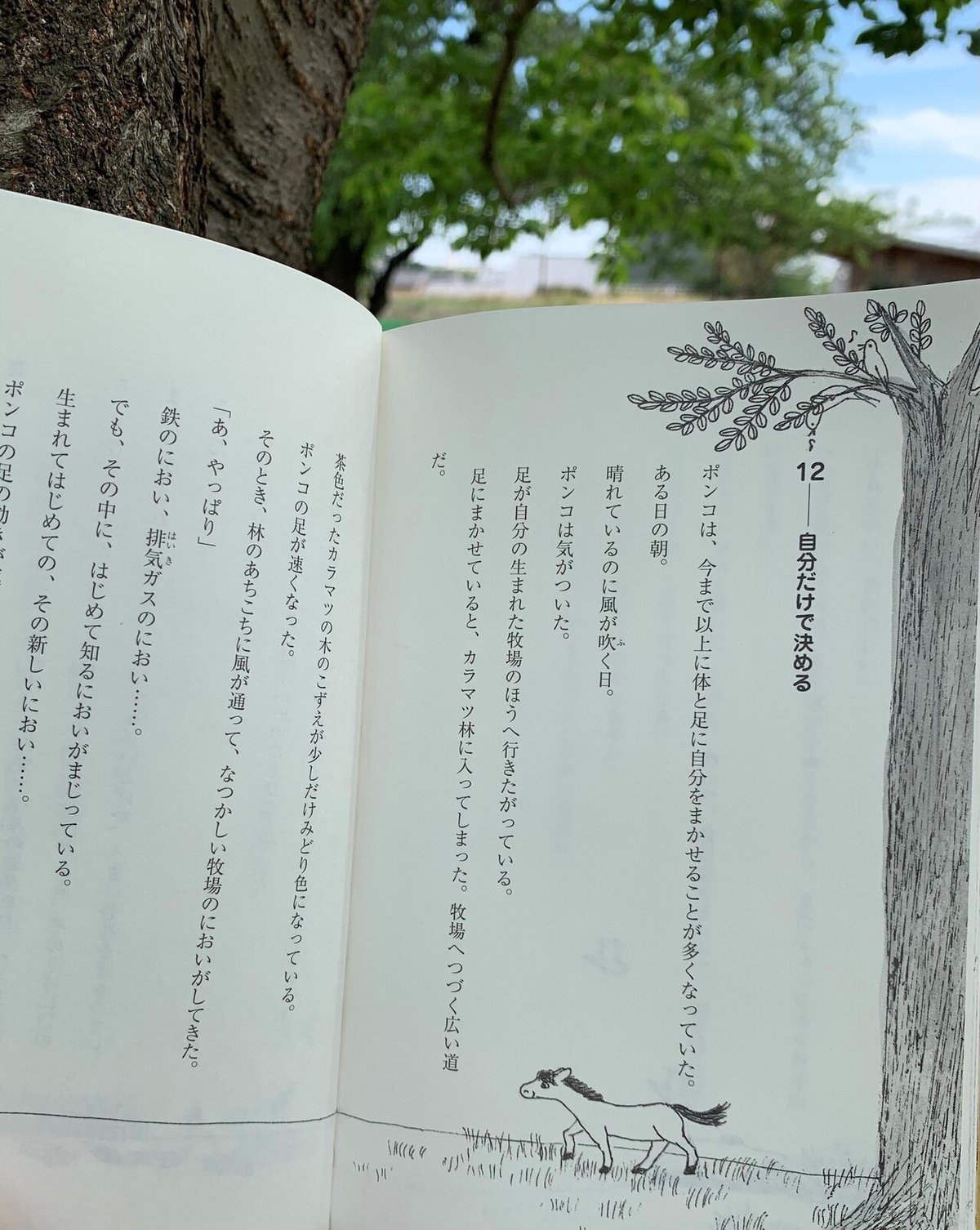
◎第67回青少年読書感想文全国コンクール公式サイト →こちら
