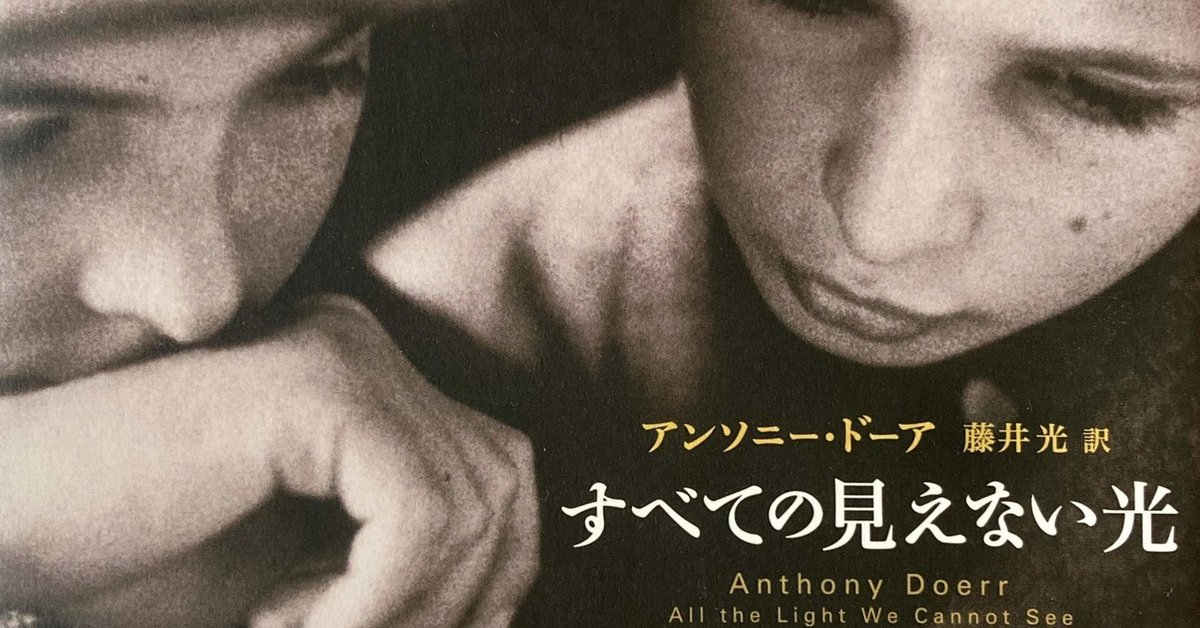
すべての見えない光
"彼はラジオを切る。静けさのなかに、教師たちの声が入り、彼の頭の片側からこだまし、もう片方からは記憶が語りかけてくる。目を開けて、その目が永遠に閉じてしまう前に、できるかぎりのものを見ておくんだ。"2014年発刊の本書は10年の歳月をかけ丁寧に編まれたビュリツァー賞受賞作にして、フランスの盲目の少女とドイツの少年兵の物語。
個人的には、何人かの読書好きの方に猛烈にプッシュされたこともあって、手にとりました。
さて、そんな本書は博物館で働く父親のもと、6歳の時に失明してしまったパリに暮らす聡明な少女、マリー=ロール、そして、孤児院で育ち、壊れたラジオを直した事で士官学校への勉学の道を切り拓いたドイツの少年、ヴァルナー。2人の人生が、短いもので1ページ、長くても10ページほどの短い断章を散りばめる形で丁寧に描かれていき、戦時下におけるフランスの海辺にあるサン・マロの町で2人はひとときの邂逅を果たすわけですが。
まず印象に残ったのは、戦時下における理不尽さに2人が、そして登場人物の多くが翻弄されつつも貫かれている。著者の人間に対する、社会に対する【共感と希望に満ちたまなざし】でしょうか。物語に奥行きを与えている『炎の海』という架空のダイアモンド、少女の父親の手作りの街の形を再現した立体パズルといった、2人を『繋げる役割をもったアイテム』それに導かれる様に少しずつ近づいていく、細部の余白はあえて読み手に委ねられつつも【緻密な展開、余韻溢れるラスト】と共に見事な完成度の作品だと感じました。
また、本書は少年が幼い時にラジオで"受信した"フランス語で若い男性が光について話す科学番組『それでは、ひとつたりとも光のきらめきを見ることなく生きている脳が、どうやって光に満ちた世界を私たちに見せてくれるのかな?』から始まり、少女が指で文字を探り当てて"発信する"海底2万里と『彼がここにいる。わたしの真下にいる』など、光、電波(ラジオ)が作品の主題として、豊かなイメージ【想像力にどっぷり浸れる魅力】を与えてくれているわけですが。本、小説ならではの【味わい深さ、単純な言葉に出来ないもどかしさ】堪りません。
第二次大戦を舞台にした作品。目には見えない光を辿っていくような、儚くも美しいイメージ、胸を打つ作品を探す方にオススメ。
