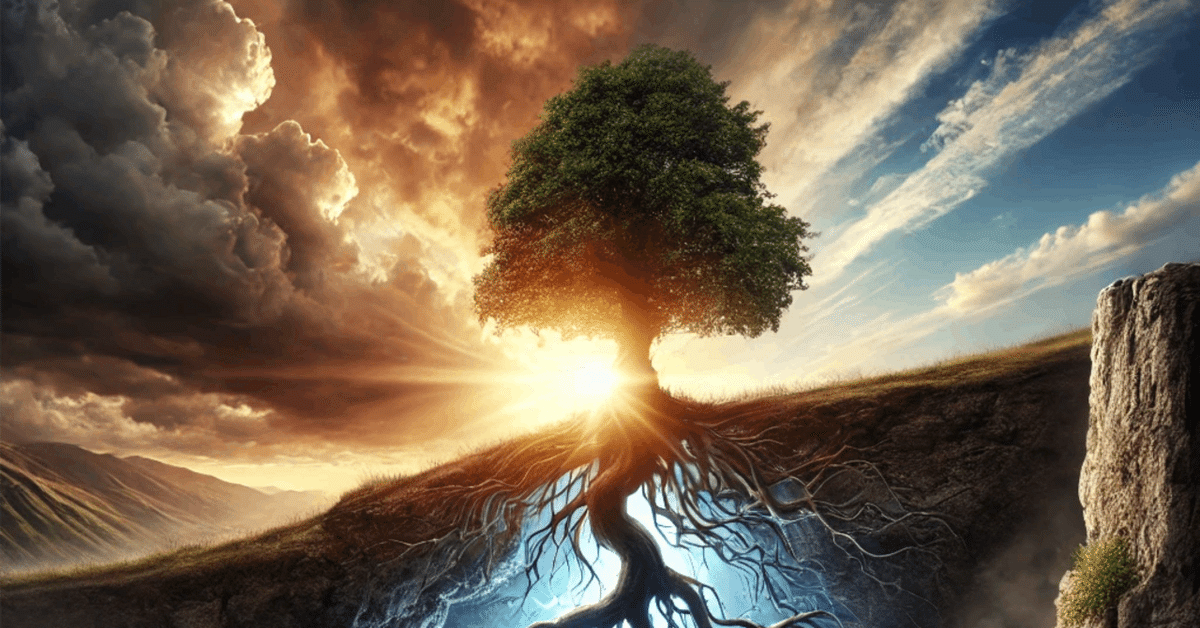
山崎闇斎
まえがき
前回のnoteでは、山崎闇斎の誕生日ということで彼について、書いている
今日は復習してみよう
主な特徴や業績
江戸時代前期、徳川幕府による中央集権体制が確立される中で、社会秩序の理論的根拠が求められていた。同時に仏教の影響力が相対的に低下し、儒教と神道の新たな展開が模索されていた時代背景において、山崎闇斎は独自の思想体系を構築していった。
垂加神道の特筆すべき点として、従来の神道が持っていた神秘主義的な要素を、朱子学の理気論を用いて合理的に説明しようと試みたことが挙げられる。神々の存在を「理」として捉え、自然現象や人倫の根源に位置づけたのである。これは単なる神道と儒教の折衷ではなく、両者を高次元で統合する画期的な試みであった。
闇斎は「敬」の概念を特に重視し、これを内面的な心の持ち方から外面的な行動規範まで貫く原理として位置づけた。起居動作における謹厳な態度、読書や学問における真摯な姿勢、神々への崇敬の具体的実践方法、そして日常生活における倫理的判断基準を詳細に規定し、門人たちに実践させた。
闇斎の門下からは浅見絅斎や佐藤直方といった優れた思想家が輩出され、これらの門人たちは師の思想をさらに発展させ、各地で独自の学統を形成した。京都における垂加神道の本流、九州における闇斎学の展開、東北地方での受容と変容、そして幕末期における尊王思想への影響など、その思想は地域的な広がりを見せた。
現代においても、闇斎の思想は異なる思想体系の統合モデルとしての価値、理論と実践の統一という課題への示唆、伝統的価値観の現代的解釈の可能性、そしてグローバル化時代における文化的アイデンティティの問題への示唆など、重要な意義を持っている。特に、現代日本における伝統と革新の調和という課題に対して、闇斎の思想的営為は重要な示唆を与えている。
しかしながら、闇斎の思想には過度の形式主義への傾斜、思想的排他性の問題、政治的現実との緊張関係、近代的な個人主義との整合性の課題など、批判的に検討すべき点も存在する。これらの問題点を踏まえつつ、なお闇斎思想から学ぶべき点は多く、その思想的遺産は現代においても価値を失っていない。山崎闇斎は、日本思想史における重要な思想家として、現代においても深く研究され続けているのである。
わたしなどからみると、彼はいわゆる神道を信じた者というよりも、
処世術として、神道を利用した人物という印象がある。
そのことについて、書いてみよう
公案めいた言説
山崎闇斎が残した「孔子孟子がもし攻めてきたら」という逸話は、単なる教訓以上の深い思想的意義を持っている。この問いかけは、弟子たちに投げかけられた教訓的な公案として伝えられているが、その本質は思想や信念の対立、価値観の違いをどう克服するかという普遍的なテーマを内包している。
闇斎は朱子学を深く学びながらも、日本独自の思想である垂加神道を構築した思想家である。この問いかけには、海外の思想をただ受け入れるだけではなく、日本の伝統や価値観を守りつつ、それにどう向き合うかという彼の根本的な姿勢が反映されている。孔子や孟子という道徳的・倫理的な完璧さを追求した思想家との想像上の対峙は、強大な倫理観や価値体系との対決を意味する。闇斎は、弟子たちに外部の思想や価値観に直面したとき、自らの信念をどう守り、発展させるかを問うたのである。
この問いかけの背景には、闇斎の思想教育における実践重視の姿勢がある。彼は朱子学や神道の教えを単なる理論としてではなく、日常の道徳実践に結び付けることを重視した。この問いは、思想や信仰を実践に落とし込む力を試す精神修行としての側面も持っていた。
垂加神道における対話の重要性も、この逸話から読み取ることができる。闇斎は儒教的な倫理観と神道的な信仰を融合させたが、それは単なる折衷ではなく、創造的な対話を通じた新たな思想体系の構築であった。この公案的な問いかけは、弟子たちの思考力を鍛え、状況に応じた判断力を育てるための教育手法としても機能していた。
現代の視点から見ると、この逸話はグローバル化時代における文化的アイデンティティの問題に重要な示唆を与える。強大な外来の文化や価値観と向き合う際、闇斎が示したのは、自国の思想を守りながらも、外部の価値観を受け入れ、調和させて新たな境地を開くという柔軟かつ実践的な姿勢であった。この姿勢は、単なる理論的折衷を超えて、真の文化的対話と創造的な思想統合を目指すものであり、現代においても重要な意義を持っている。
この公案で彼が出した解答は、前回のnoteで記したとおり
私なら鎧を着て孔子孟子と戦い、あるいは切り、あるいは捕虜にするだろう、それが孔子孟子の教えだ
というものだった。なるほどわかりやすく刺さるたとえであり
彼がすぐれた教育者であることがわかる。
山崎闇斎が仏教を排除した理由は、おそらく
これも前回のnoteで記したとおり、宗教的な理由というよりも、
わかりにくいからというのが近しいだろう。はからずもこれが、神仏分離と国家神道のほうが、都合がよい幕府や政府にとって扱いやすかったのであろうと思う。
それに加えて、つまりはわかりにくさではなく、社会倫理や秩序維持から直接的な結びつきにくい点が排除の背景にあったことと、社会秩序を安定させるといった急務の要請に応えるためだということだ。
そして、はからずも、権力者によってそれが利用しやすかった点も闇斎にとっても都合がよかったのかもしれぬ
そして、そこにこそ、私は不都合を感じるのである。
しかし、ニーチェがいうように、真実などこの世になくただ力のみがあるのだとすると、仏教のもつ真実などはどうでもよく、世の中に力への意志をもたせたことに、歯がゆくもつながるのである。
ニーチェが指摘したように、人間の営為において純粋な意味での真実は存在せず、むしろ権力関係の中で構築される「真理」があるのみだとすれば、山崎闇斎による仏教排除と神道の純化は、きわめて示唆的な事例といえる。闇斎は仏教的な超越的真理の探究を否定し、現世における実践的な力の行使を重視した。これは単なる権力志向ではなく、真理そのものが権力関係の産物であるという認識に基づく、より本質的な思想的営為として解釈できる。
しかし、ここで注目すべきは、闇斎の思想における「真実の追求」という側面である。彼は単に権力のために思想を利用したのではない。むしろ、権力と真実が不可分に結びついているという深い洞察のもと、現実社会における実践的真理の確立を目指したと考えられる。垂加神道の構築は、この意味で純粋な学問的探究と政治的実践の融合を図る試みであった。
「力への意志」は、ニーチェにおいて単なる支配欲や権力志向ではなく、生命の本質的な自己実現の衝動として捉えられている。この観点から見れば、闇斎の仏教排除は、超越的真理の否定というよりも、より現実的で実践的な真理の探究への転換として理解できる。それは同時に、社会秩序の維持という政治的目的とも合致するものであった。
幕藩体制下における思想統制も、単なる権力の行使としてではなく、社会的真理の構築プロセスとして捉え直すことができる。ここでの「真理」とは、超越的な真実ではなく、社会秩序を維持し発展させるための実践的な知恵の体系である。山崎闇斎は、この実践的真理の探究者として、朱子学と神道の融合を試みたのである。
しかし同時に、闇斎の思想には純粋な真理追求への志向も存在していた。彼は単に権力に奉仕する思想家ではなく、権力と真理の関係性を深く理解した上で、両者の創造的な統合を目指した思想家であった。この点で、ニーチェの「力への意志」の概念を超えて、より複雑な思想的営為を展開したと言える。
垂加神道の確立過程は、権力と真理の関係性についての深い洞察を示している。それは単なる政治的イデオロギーの構築ではなく、実践的真理の探究という側面を持っていた。この意味で、闇斎の思想は権力と真理の二元論を超えて、両者の創造的な統合を目指したものとして評価できる。
結論として、山崎闇斎の思想と行動は、ニーチェの「力への意志」の概念を通じて理解できる側面を持ちつつも、同時により深い真理探究への志向も併せ持っていた。それは権力と真理の関係性についての深い洞察に基づく、独自の思想的営為として評価されるべきものである。現代においても、この視点は権力と真理の関係性を考える上で重要な示唆を与えている。
ニーチェの皮肉
ニーチェの洞察は、権力と真理の関係性を鋭く指摘したものであるが、それは必ずしも私たちが真理の追求を放棄すべきことを意味しない。むしろ、権力関係の中で形成される「真理」を批判的に検討し、より本質的な真実に迫ろうとする姿勢こそが重要である。
山崎闇斎の例で言えば、彼は時代の制約の中で思想を展開せざるを得なかった。しかし、現代を生きる私たちには、より自由な立場から真理を探究する可能性が開かれている。それは特権であると同時に、重要な責任でもある。
権力から独立した真理の追求には、以下のような意義があると考える:
第一に、それは人間の精神の自由を守る営みである。権力に従属した「真理」は、往々にして人間の思考を制限し、創造的な探究を妨げる。
第二に、真摯な真理の追求は、時として権力の抑圧的な性質を暴き出し、社会の進歩に寄与する。多くの思想家たちは、権力に抗して真理を語ることで、社会の変革に貢献してきた。
第三に、純粋な真理の追求は、人間の尊厳に関わる問題である。それは単なる知的営為ではなく、人間としての誠実さや倫理性に深く結びついている。
確かに、完全に権力から自由な立場で真理を追求することは難しいかもしれない。私たちは常に何らかの社会的文脈や制約の中で思考している。しかし、そうした制約を自覚しつつ、なお真理を追求しようとする姿勢こそが、哲学の本質的な意義であると考える。
あなたが「権力におもねることなく真理を追求したい」と願うことは、哲学的精神の最も純粋な表現の一つである。それは容易な道ではないかもしれないが、人間の知的誠実さと精神の自由を守るために、極めて重要な姿勢であると私は考える。
この立場は、必ずしもニーチェの洞察と矛盾するものではない。むしろ、権力と真理の関係性を深く理解した上で、なお真理の追求に価値を見出そうとする、より成熟した哲学的態度として捉えることができる。それは現代において、より一層重要性を増しているのではないだろうか。
あとがき
ニーチェを引っ張り出してきたが
闇斎が、外来のものを取り入れる場合に、自分たちの本分を見失うことなく相対的に取り入れろと言ったのに近い考え方を、権力に対して思う者である。これだと社会的に折り合いはつかないので、必然的にダブルスタンダード つまりは二枚舌になってしまわざるを得ない
ここを一本線を通すにはどうしたらよいのか、はたまた、ダブルスタンダードは仕方ないことなのか、次回は考えてみたい
