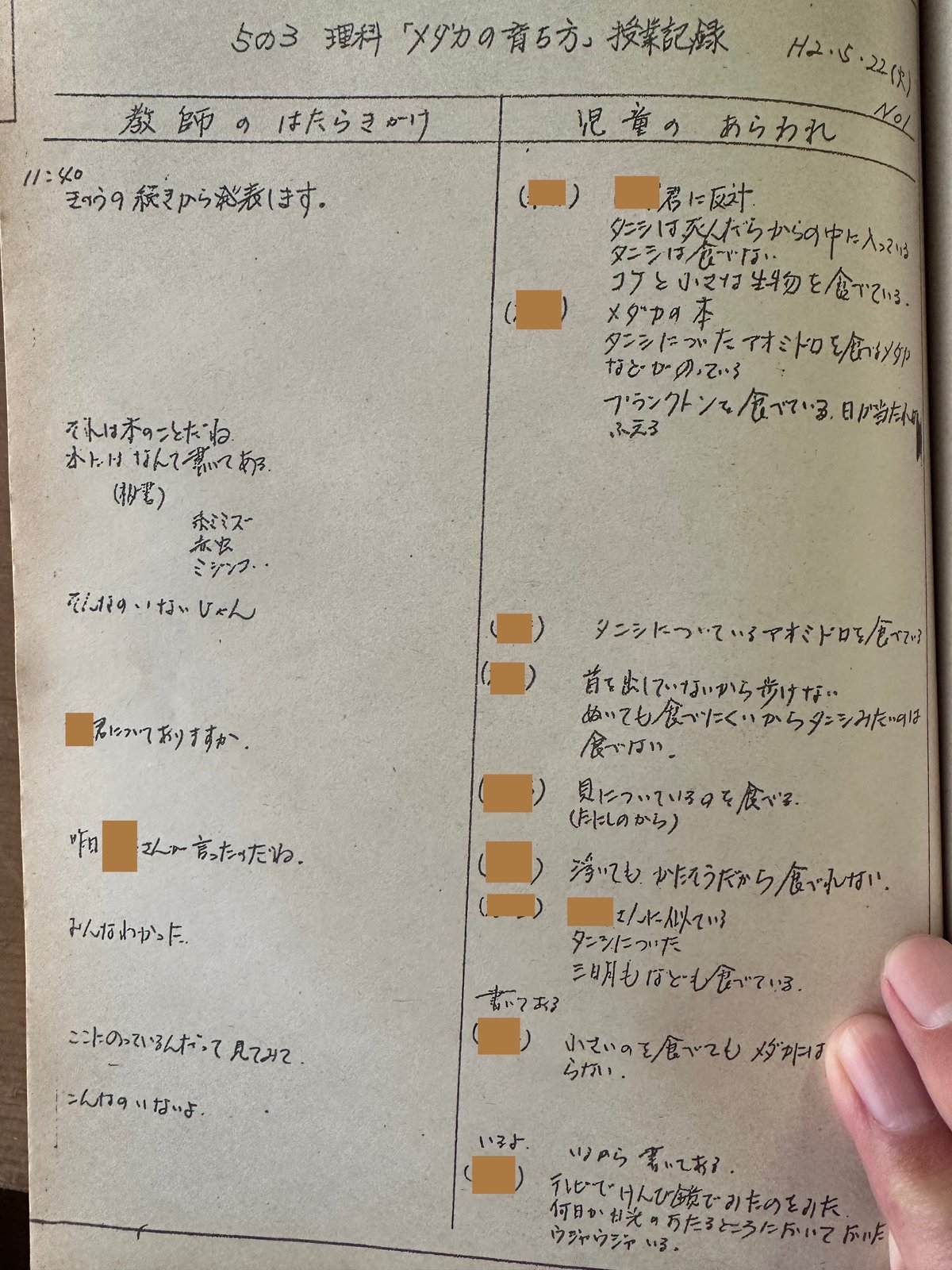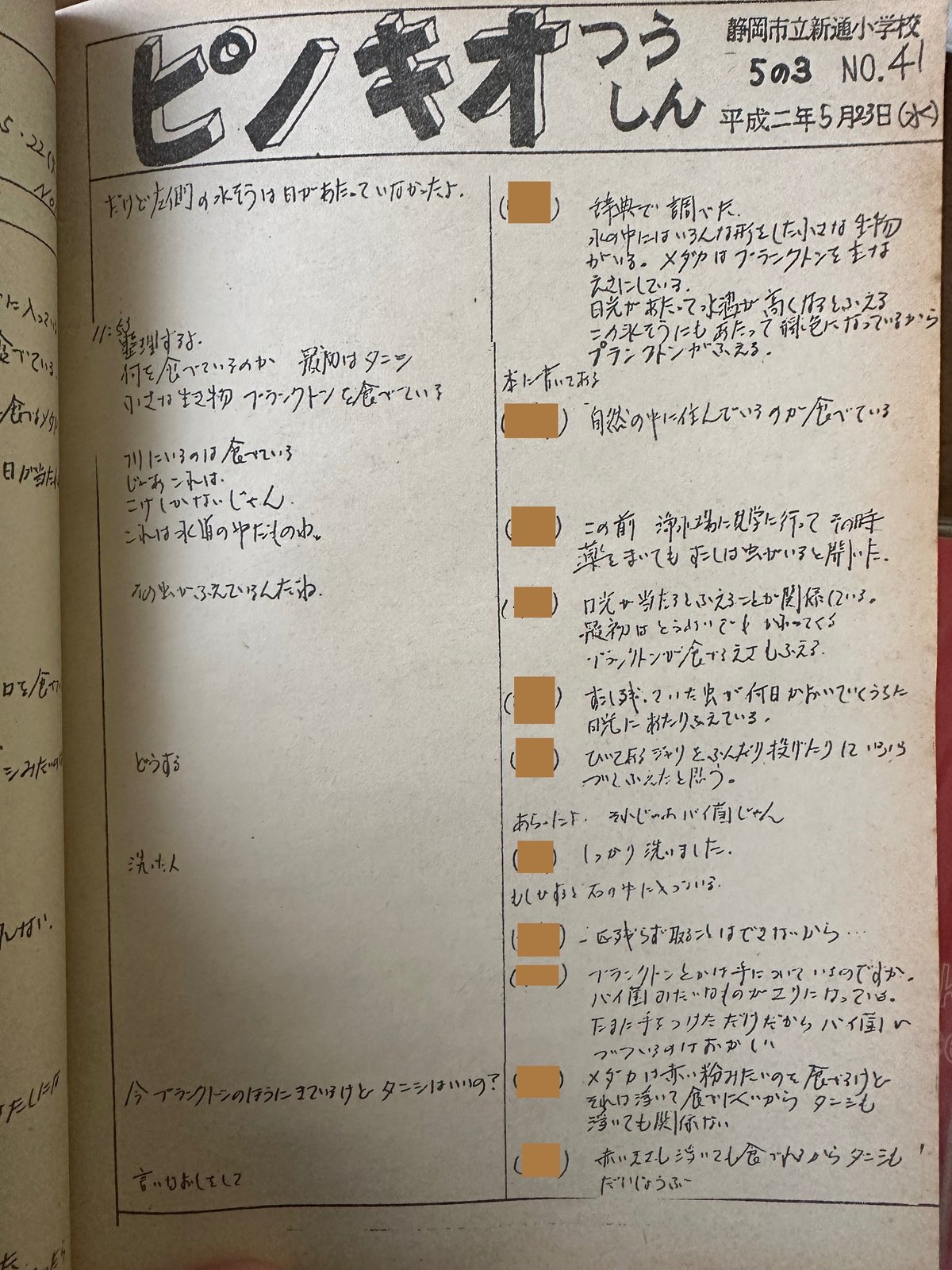学校で教えるのは知識ではありません
教師というのは授業をする前に「授業案」をいうものを書きます。
こんなふうに授業を進めるというものです。
その授業案をもとに授業をするのです。
そして実際の授業と子どもたちの様子から授業を反省し、より良い指導法を
探っていくのです。
今日はその研究授業の日。
連日連夜、授業案を検討し今日を迎えました。
(これが一年に何回かあります)
今日は「メダカのエサ」についての授業で、「何も餌をやらないのに
何を食べているのだろうか」という問題でした。
下に載せたのが授業のベタ記録です。
1組の先生が書いてくれました。
子どもたちが次々に発表するので、静岡市の委員会の先生も
びっくりしていました。
「児童の表れ」がたくさんあるということが「良い授業」の
一つの条件であるのです。
そういう意味では子どもたちが大変張り切ってくれて、鼻高の僕は
余計に鼻が高くなってしまいました。
理科の時間に国語辞典も使っています。
その後に実験をしています。
やはり五の三の子どもたちは素晴らしい。
子どもたちが、子どもたちで授業を進めていくのです。
僕は「舵取り」をするだけで良いのです。
そして知識でなく常に「学び方」「調べ方」を指導しています。
学校で教えるのは知識でなく「調べることの面白さ」なのです。