
20250109【酵素】って何ナン❓3日目
「Aloha(アロハ)🤙」
ハイクオリティヒーラー:ピリナ愛です。
昨日の投稿を読んでいただいた
みなさま
ありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします!
今日はじめて私の投稿を読んでくださる
みなさま
よろしくお願いいたします!
酵素に関して
ご紹介するのは本日が
最終日となります。
発酵食品ってどんなものがあるの?
発酵食品とは、
微生物の働きによって、
食材の持つもともとの性質が
人間にとって有益に変化した食品のこと。
発酵食品には
どんな種類があるのか、
私たちにとって
どんなメリットがあるのか、
どんな微生物が関わっているのかを
見てみましょう。
発酵食品一覧
私たちの日々の食卓は
豊富な発酵食品で成り立っています。
発酵王国といわれる
日本の食事・和食はもちろん、
洋食にも発酵食品を容易に
見つけることができます。
調味料
・醤油
・味噌
・酢
・みりん
・魚醤
・塩麹
・醤油麹
・酒粕
・かんずり
・豆板醤
・コチュジャンなど
野菜類
・ぬか漬け
・キムチ
・ピクルス
・ザワークラウト
・ザーサイなど
豆類
・納豆
・テンペ
・豆腐よう
・腐乳
・臭豆腐など
魚類
・かつお節
・くさや
・塩辛
・へしこ
・なれずしなど
肉類
・生ハム
・サラミ
・ペパロニ
・チョリソなど
乳製品
・ヨーグルト
・チーズ
・発酵バターなど
酒類
・日本酒
・ビール
・ワイン
・マッコリ
・焼酎
・泡盛
・ウイスキー
・ブランデー
・ウオッカ
・ジン
・ラム
・テキーラ
・白酒(パイチュウ)など
飲料
・甘酒
・碁石茶
・阿波番茶
・富山黒茶
・石鎚(いしづち)
・黒茶
・プーアール茶
パン・デザート
・パン
・ナタデココ
・チョコレートなど
発酵食品の5つの効能
発酵させることでできる発酵食品は、
食品の保存性が向上したり、
風味がアップしたりと、
それ自体に魅力がありますが、
発酵食品を食べる
私たちにとっても、
さまざまなメリットを
もたらしてくれます。
腸内環境の調整
善玉菌を含む発酵食品を食べることで、
便秘や下痢、肌荒れなどを
引き起こす悪玉菌の働きを抑制し、
腸内環境を整えてくれます。
この働きがある発酵食品:
・ヨーグルト
・チーズ
・漬物
・納豆など
代謝アップ
多くの発酵食品には
ビタミンB群が含まれており、
代謝を促進してくれます。
この働きがある発酵食品:
・酢
・キムチ
・納豆など
悪玉コレステロールの除去
大豆系の発酵食品には、
血管の壁に付着した
悪玉コレステロールを
除去する働きがあり、
高血圧の予防になります。
この働きがある発酵食品:
・納豆
・味噌など
抗酸化作用
発酵食品には、
ビタミンCやミネラル、
カロテン、
ポリフェノールなど、
抗酸化物質が豊富に含まれています。
抗酸化物質は、
病気や老化の原因である
活性酸素の発生を抑えてくれます。
この働きがある発酵食品:
・味噌
・赤ワイン
・バルサミコ酢など
ストレス軽減
アミノ酸の一種である
GABA(ギャバ)を
含む発酵食品には、
緊張やイライラなどのストレスを
緩和する抗ストレス作用があります。
この働きがある発酵食品:
・ぬか漬け
・キムチ
・ヨーグルト
・味噌など
発酵食品をつくる三大微生物
発酵食品をつくるのに欠かせない
微生物は主に
「カビ」「酵母」「細菌」の
3種類に分類されます。
カビには麹菌(コウジカビ)、
アオカビ、
カツオブシカビなどがあり、
酵母にはパン酵母、
ビール酵母、清酒酵母など、
細菌には乳酸菌、
酢酸菌、納豆菌など
さまざまな微生物があります。
そして、一つの微生物の
働きによってつくられる
発酵食品もあれば、
複数の微生物の働きによって
つくられる発酵食品もあります。
麹菌が関わる発酵食品
・味噌
・醤油
・米酢
・日本酒
・みりんなど
酵母が関わる発酵食品
・パン
・ビール
・日本酒
・ワイン
・味噌
・醤油など
乳酸菌が関わる発酵食品
・ヨーグルト
・チーズ
・漬物
・味噌
・醤油など
酢酸菌が関わる発酵食品
・酢
・ナタデココ
納豆菌が関わる発酵食品
・納豆
なぜ、日本は発酵食品大国なの?
日本がここまで
発酵食品大国になったのには、
気候や文化的背景が
関係しているようです。
高温多湿な日本では食料に
カビが生えやすく保存が難しい。
食料を長く保存するために
塩漬けにしたのは、
先人たちの
知恵によるものだったといえます。
そして、高温多湿な環境下で、
米に生育することを
好むカビの一種である麹菌を
うまく利用して、
数多くの発酵食品を
生み出してきました。
また、かつて日本では
仏教の影響から肉食を
避ける食文化がありました。
675年からおよそ1200年にわたり、
公に肉食が禁止されていたのです。
そのため、魚をたんぱく源とし、
魚が多くとれるときに
塩漬けにして保存。
その際に自然発酵が起こり、
魚醤や塩辛のような
水産発酵食品が
生まれたといいます。
日本人の主食である
お米も発酵食品と切り離せません。
麹菌は
お米を培地としてよく育ち、
稲わらには納豆菌も
付着しています。
さらに稲作と大豆の関係にも
注目です。
かつて大豆は水田のあぜ道に
植えられることが多く、
肉を食べなかった時代に
魚と共に重要なたんぱく源と
されていました。
味噌や納豆といった大豆を
使った発酵食品が生まれたのも、
こうした日本の食文化が
関係していたのです。
発酵食品に賞味期限はある?
保存性の高い発酵食品
私たちの食生活にすっかりお馴染みの
「発酵食品」。
日本は発酵王国といわれるほど、
発酵食品の種類が豊富で、
醤油や味噌などの
発酵調味料を含めれば、
発酵食品を口にしない日は
ないといえるかもしれません。
発酵食品は、原料に麹菌などの
微生物が付着してできますが、
その微生物の活動により
栄養成分や旨み成分が増し、
栄養豊富でおいしい発酵食品が
完成します。
微生物は発酵の過程で
悪い菌が入るのを防ぎ、
発酵によって生まれる
乳酸や酢酸、アルコール自体にも
殺菌作用があるため、
雑菌が増殖しにくい環境が生まれます。
このメカニズムにより、
世界には“○年もの・○十年もの”と
いった発酵食品が存在しています。
ではなぜ、普段私たちが
食べている市販の発酵食品には、
賞味期限が明記されているのでしょうか。
市販の発酵食品に賞味期限があるワケ
まず、市販の食品には、
安全に食べられる期間が設定されており、
パッケージに「消費期限」か「賞味期限」の
どちらかが表示されています。
これは各食品メーカーが、
国がまとめたガイドラインに
基づき設定しているもの。
パッケージを未開封のまま
書かれた保存方法を守って
保存していた場合に、
消費期限は製造から
おおむね5日以内に品質が
劣化する可能性が高い食品に表記、
それ以上の品質保持が
可能な食品には賞味期限が
表記されています。
また、市販の発酵食品は、
食品流通における衛生上の問題から
殺菌処理がなされ、
発酵を止めていることもあります。
発酵食品は長期保存が
可能であっても、
そのおいしさは永遠ではありません。
発酵食品をつくっている
食品メーカーは
おいしい時期を見極めて
出荷しており、
その「おいしく食べられる期間の保証」と
いう意味で、賞味期限を
設定する必要があるのです。
開封後や保存状態によっては
有害な菌が増殖するリスクが高まり、
食感や風味に変化が
生じることもあるため、
市販の発酵食品は賞味期限を
意識しながら、色や臭い、
食感などの変化にも
気をつけたいところです。
甘酒のカロリーは高い?
「飲む点滴」といわれるほど、
栄養満点
病院で使われる点滴の成分と
似ていることから、
「飲む点滴」と称される甘酒。
体にいいことは
想像にたやすいですが、
甘酒のカロリーは
どうなのでしょうか?
まず、甘酒は大きく
2種類に分けられます。
米麹を原料にした
「麹甘酒」と、酒粕を原料にした
「酒粕甘酒」です。
前者は炊いたご飯(またはおかゆ)に
米麹と水を混ぜて発酵させ、
後者は酒粕に砂糖と水を
加えてつくります。
「酒粕甘酒」は
使用している砂糖の量によって
カロリーも変わるため、
ここでは「麹甘酒」に
ついて見てみましょう。
麹甘酒のカロリーを見てみると、
100グラムあたり
「約76キロカロリー」(※1)。
同量のほかの飲み物と比べてみると、
りんごジュース(濃縮還元)が
「約47キロカロリー」、
牛乳が「約61キロカロリー」、
サイダーが「約41キロカロリー」と、
麹甘酒のカロリーは
高めであることがわかります。
ただし、成人男女の1日に
必要なカロリーは
1600~2000キロカロリー。
必要カロリーの2.4~2.9%程度と、
カロリー全体からすると
ほんのわずかです。
そして、注目してほしいのは
カロリーよりもその栄養価。
麹甘酒に含まれる成分の
20%以上をブドウ糖が占めるほか、
ビタミンB1・B2・B6、葉酸、
食物繊維、オリゴ糖に
必須アミノ酸などが含まれるなど、
栄養価の宝庫なのです。
麹甘酒の上手な飲み方
麹甘酒はいつ飲むかによって、
体に与える効果が違ってきます。
麹甘酒に含まれるブドウ糖は、
脳がエネルギーとして
利用できる唯一の栄養源。
朝に飲めば、
血糖値が上がり脳や体が
しっかり目覚めます。
また、昼に飲めば、
脳の働きが活発化し
集中力アップにもつながります。
ブドウ糖は体内に
吸収されやすいため、
運動後などに飲めば、
素早いエネルギー補給にも。
さらに麹甘酒に含まれる
ビタミンB群は疲労回復にも
効果的なため、
夜に飲めば、1日の疲れを癒やし、
翌朝の目覚めが
よくなるかもしれません。
食事や間食の代わりに
麹甘酒を飲むのもおすすめです。
麹甘酒は
お米が多く使われているため、
腹持ちが良く、少量でも
満足感が得られます。
また、食事やお菓子などには
脂質が多く含まれますが、
麹甘酒には脂質はほとんど
含まれていません。
そんな麹甘酒ですが、
飲みすぎには注意が必要です。
前述の通り、
カロリーは高めなので、
飲む量に気をつけたいところ。
1回におちょこ1杯から
コップ1杯程度、
1日には200mlほどを
目安にしましょう。
飲み方に気をつければ、
栄養満点でさまざまな
メリットのある発酵食品、
それが麹甘酒です。
米麹に含まれる食物繊維や
麹菌が生み出す酵素によって
生成されるオリゴ糖は、
腸内環境を整える働きもあるため、
便秘の改善や予防にもつながります。
適度に飲んで麹甘酒の
いいところを存分に吸収しましょう。
「コンブチャ」って一体なに?
別名「紅茶キノコ」で知られる、
発酵飲料
「コンブチャ」とは、
「紅茶キノコ」という名称でも
知られる発酵飲料です。
日本で飲まれている「昆布茶」と
はまったくの別物で、
紅茶や緑茶、ウーロン茶などの
お茶を原料に発酵させたもの。
諸説ありますが、
数千年以上前に中国北部や
東モンゴルで発祥したという
伝統的な飲み物です。
日本では1970年代に
紅茶キノコとしてブームになりました。
原料にキノコが
入っている訳ではないのに、
なぜキノコ?
と疑問に思うかもしれませんが、
つくり方にその理由がありました。
コンブチャ(紅茶キノコ)は、
原料の紅茶(お茶)に
砂糖を加えたものをベースに、
「スコービー(scoby)」と
呼ばれる酢酸菌と酵母からなる菌株
(1つの細菌から
分裂増殖した菌の集まり)を
入れて発酵させてつくります。
その菌株がゲル状の塊で
キノコに見えることから
「紅茶キノコ」と
呼ばれるようになったという説や、
ロシアで
「ロシアンティー・マッシュルーム」と
呼ばれていたことから、
日本語に訳された際に
「紅茶キノコ」となったという
説があるようです。
そして、この紅茶キノコが
欧米に持ち込まれた際に、
なぜか「コンブチャ」と呼ばれるように。
今度はスコービーが
昆布に見えたために
「コンブチャ」となったという話や、
酵母茶が訛って
「コンブチャ」となったという
話などさまざまあり、こ
ちらも真相は明らかになっていません。
欧米では定番ドリンクの
「コンブチャ」
海外では「KOMBUCHA」として
親しまれている「コンブチャ」。
欧米では2010年頃から
ブームとなり、
今ではスーパーなどの専用コーナーに
複数ブランドのKOMBUCHAが
並んでいるほど、
定番ドリンクという
位置付けになっています。
2014年頃から日本にも逆輸入され、
健康志向や発酵食品好きの人などには
知られる存在になっています。
その味わいは、
紅茶(お茶)由来の渋味と砂糖の甘み、
そして酢酸菌がつくる酸味と
酵母がつくり出す炭酸で、
フルーティーですっきりとしたもの。
そして、紅茶(お茶)に
含まれるポリフェノールには
高い抗酸化作用があったり、
酢酸菌のつくり出す繊維質や
酵母の細胞壁には腸内にある
免疫スイッチを刺激して
活性化させる働きもあったりするため、
美容や健康にいいとされています。
現在、日本にもコンブチャを
手がけるメーカーが数社あり、
オンラインショップで購入可能です。
海外産のものを含めると
、種類が豊富なコンブチャ。
気になった人は原材料やフレーバー、
飲み方などをチェックして、
お好みのものを見つけてみてくださいね。
「発酵バター」ってなに?
普通のバターとどう違う?
「発酵バター」と「非発酵バター」
お菓子づくりにはもちろん、
トーストに塗ったり、
料理の際に使ったりと、
私たちの食事に欠かせない「バター」。
その起源については
定かではありませんが、
紀元前4000年のイスラエル遺跡から
バターをつくる道具が
見つかったという話や、
紀元前2000年頃のインドの経典に
バターらしきものの記述があるなど、
古くからあったものだと推測されます。
バターとは、
牛乳の乳脂肪(クリーム)を
集めて練り固めたもの。
厚生労働省の
「乳及び乳製品の成分規格等に
関する省令」では、
乳脂肪分80.0%以上、
水分17.0%以下のものがバターと
定められています。
また、バターにも種類があり、
製造方法によって
「発酵バター」と「非発酵バター」に
分けられ、
さらにそれぞれ成分によって
「有塩バター」と「無塩バター」に
分類されます。
発酵バター
製造過程で原料の乳脂肪
(クリーム)に
乳酸菌を加えて乳酸発酵させたもの、
もしくは、できあがった
バターに直接乳酸菌を練りこんで
乳酸発酵させたもの
非発酵バター
一般的にバターといわれるもので、
生乳から分離させた乳脂肪
(クリーム)を撹拌(かくはん)し、
脂肪球を凝集させたもの
有塩バター
製造過程で食塩を加えているもの。
食塩が入ることで保存期間も長くなる
無塩バター
製造過程で食塩を加えていないもの。
ただし、原料の生乳にわずかな
塩分が含まれているため
「食塩不使用」と表記されている
紀元前につくられていたとされる
古来のバターは発酵バターで、
今のようにあえて
発酵させていたのではなく、
乳脂肪(クリーム)を
攪拌(かくはん)して
いくあいだに時間がかかり、
自然と発酵してしまったんだとか。
ヨーロッパでは
そのままバターが
食生活に浸透したため、
現在でも発酵バターが主流となっているそう。
一方、日本におけるバターの
歴史はまだ浅く、
今のようなバターが登場したのは
明治時代になってから。
近代的な製造技術と共に導入され、
非発酵バターが一般的になりました。
日本と同様に、
アメリカやオーストラリアでも
非発酵バターが主流になっています。
なお、バターと同じ
使い方をするものに
マーガリンがありますが、
バターが乳脂肪分から
つくられるのに対して、
マーガリンは
コーン油・大豆油・なたね油など
食用の植物性油脂に
水素を反応させてつくられるため、
まったくの別物です。
発酵バターの特徴
発酵バターは、
原料となる乳脂肪(クリーム)や
バターに乳酸菌を加え、
乳酸発酵させてつくるため、
深みのある風味やコク、
特有の爽やかな
酸味と香りを楽しめます。
これは乳酸発酵によって生まれるもの。
ただし、製法の違い
(どこで乳酸菌を加えるか)や、
原料の生乳及び
乳酸菌の種類によっても
味や風味に違いがあります。
使い方は普通のバター
(非発酵バター)と同じで、
トーストに塗るほか、
料理やお菓子づくりの材料としても
活用できます。
バターの香りや風味が際立つ
ソテーやソースなどに使うのが
特におすすめ。
また、お菓子づくりには
一般的に無塩バターを使います。
無塩の発酵バターを
マドレーヌやクッキーなどの
焼き菓子に使えば、
発酵バターならではの
豊かな香りが引き立ちます。
発酵バターと普通のバター
(非発酵バター)はもちろん、
メーカーによる発酵バターの味の違いを、
食べ比べしてみるのも
おもしろいかもしれません。
自分好みの発酵バターや
その使い道をぜひ見つけてみては
いかがでしょうか。
いかがでしたでしょうか?
酵素に関して3日間
ご紹介して参りました。
日頃意識せずに食してたものが
酵素を多く含んでいたので
私は
めっちゃ勉強になりました📝
特に
健康は意識して
食していた
納豆・バナナ・ヨーグルトは
これからも
毎日
取り入れ続けようと思いました。
今年は
味噌汁を追加したいですね!
ちょっと
面倒だと味噌汁はいっかぁ💦と
思っていましたが
レトルトでも良きと知り
それならお湯沸かすだけだし
続けられそうです(*´▽`*)
みなさまも
続けられそうなことから
ぜひ試してみてくださいね(*´ω`*)
それではカード占いのコーナーです!
担当カードを週替わりにさせていただきました。
今週の担当は
引き寄せ現実カードさんです。
よろしくお願いいたします。

それでは
引き寄せ現実カードさん
よろしくお願いいたします。
本日の占い内容
「今の私に必要なメッセージを教えください。」と
引き寄せ現実カードさんに聴いて
高次元からのエネルギーが選んだのは
以下の3枚となります。
お好きなカードを1枚選択していただきます。

左:「ピ」真ん中:「リ」右:「ナ」
向かって
左:「ピ」
真ん中:「リ」
右:「ナ」
結果は「ピ」から順に発表する
手法で占わせていただきますね😊
「ピ」を選択されたみなさまは
こちらのカードが出ました。

高次元からのメッセージ…
思考は実現する
「リ」を選択されたみなさまは
こちらのカードが出ました。

素晴らしい一日にしましょう
高次元からのメッセージ…
今までにないほど、
素晴らしい一日にしましょう
「ナ」を選択されたみなさまは
こちらのカードが出ました。
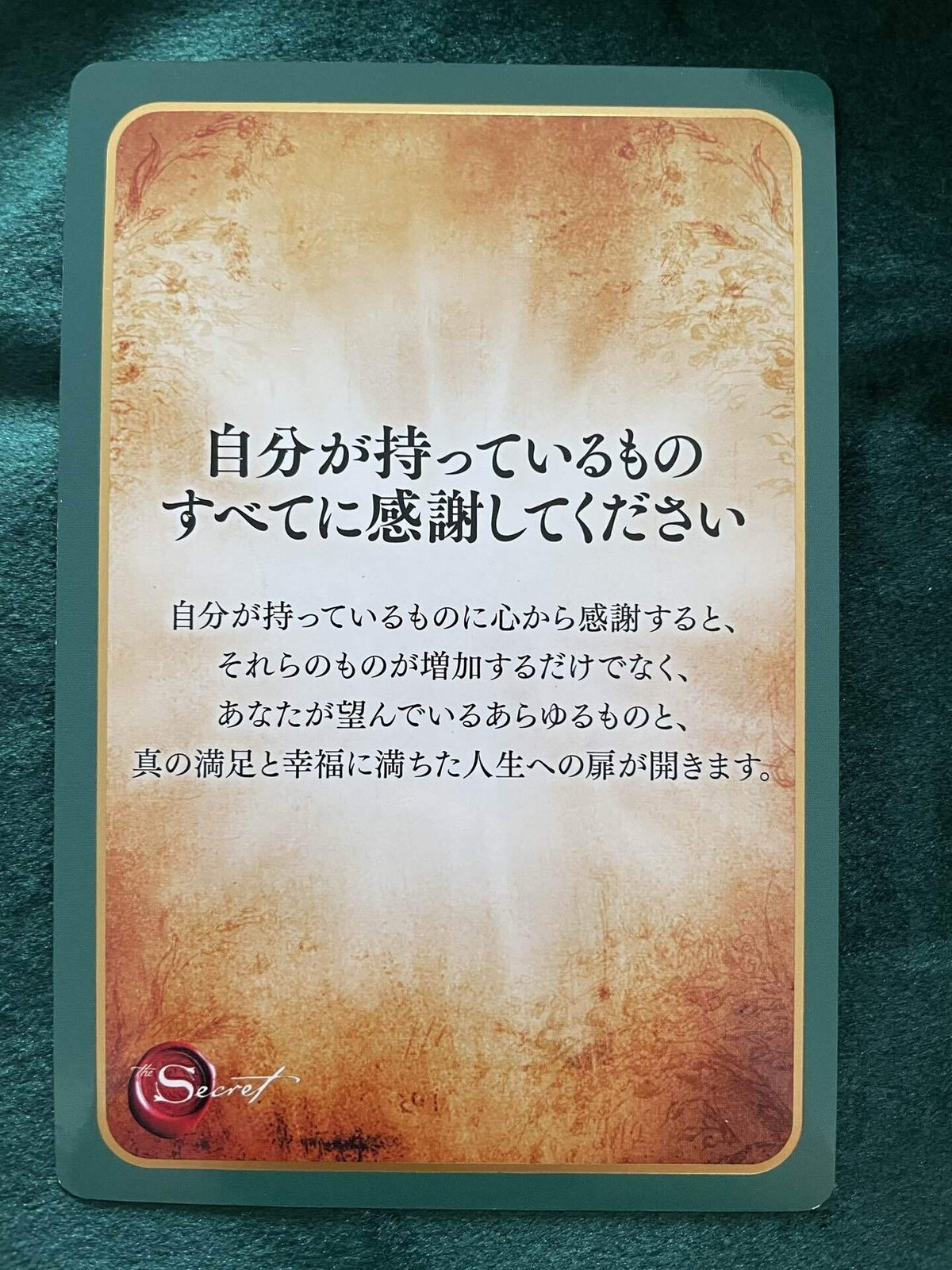
すべてに感謝してください
高次元からのメッセージ…
自分が持っているもの
すべてに感謝してください

左:「ピ」真ん中:「リ」右:「ナ」
みなさま結果はいかがでしたか?
カードに記載されているアドバイスを
なるほど🤔と
受け入れていただければ幸いですm(_ _)m
最後はこちらのコーナーです!
ハイクオリティヒーラー:ピリナ愛が
勝手にお祝い👏
Hauoli la hanau(ハウオリ・ラ・ハナウ)
(誕生日おめでとう!)
本日2025年1月9日(木)
お誕生日の方
🌸おめでとうございます🌸
誕生花:「スミレ」
「ノースポール」
「ハコベ」等
今日は何の日?
とんちの日
クイズの日
ジャマイカ ブルーマウンテンコーヒーの日
風邪の日
殉教者の日(パナマ)
宵戎
青々忌等
最後までお読みいただき「Mahalo(マハロ)」
(ありがとうございました)
みなさまにたくさんの「Hauʻoli(ハウオリ)」
(happy)が訪れますように…🍀
「A hui hou(ア・フイ・ホウ)✋」(またね!)
