
内部通報を利用して人的資本のリスク管理の開示充実を
※本記事は2023/11/07に株式会社パーソル総合研究所サイト内で公開された内容を再編集したものとなります。
コラム「内部通報制度は従業員に認知されているか」「人的資本情報開示に対する強い関心にも後押しされながら、今後、内部通報件数の利用例は増えていくだろう」と指摘した。それでは、有価証券報告書に新設された【サステナビリティに関する考え方及び取組】を通して、人的資本情報開示の一環として内部通報を記載する企業はどのくらいあったのだろうか。
本コラムでは、大手企業の有価証券報告書の記載状況を通して、この疑問に向き合ってみたい。
リスク管理としての内部通報
実際に記載状況を見る前に、人的資本情報としての内部通報の位置づけについて考えてみよう。人的資本情報開示が義務となったことで、最新の有価証券報告書にはエンゲージメントや教育研修投資などに関する取り組みや、その指標の記載が多く見られた。エンゲージメントや教育研修投資をはじめ、企業の成長性を感じさせるようなものが多く用いられていたことは、今回の開示の特徴のひとつといえるだろう。有価証券報告書の主要な読者が投資家であることを鑑みれば、こうした成長性の観点から人的資本情報開示を行うことは重要だ。一方、投資家は成長のみを見ているわけではなく、リターンとリスクのバランスを常に念頭に置いている。この点を考慮するならば、企業が行うべき人的資本情報開示にはリスクの側面が含まれるべきと考えることができる。その意味で、人的資本情報開示が成長性に関するものばかりになっていた場合、投資家の求める情報との間には、齟齬が生まれている可能性がある。
とはいえ、リスク管理の方法、とりわけリスクを発見する仕組みは、従来から数々実施されてきた。伝統的には、社内・社外監査によって自社内の不正を発見しようとしてきた。近年は社内だけでなく、バリューチェーン上の問題の発見にも努めることが増えている。人権デューデリジェンスはその代表的な方法である。基本的にこれらは本社側が現場を見に行く仕組みである。言い換えれば、現場から直接が声あがってくるようなものではない。そのため、現場でのふとした気づきが不正やその兆候の発見に生かされないといったことが起こりうる。
対照的に、内部通報は現場からの声を起点にする仕組みである。ただし、一定の頻度で行われる社内・社外監査や人権デューデリジェンスとは異なり、内部通報は設置されていても、通報がまったく、またはほとんどなされず、実質的に稼働しない場合があり得る。そのため、実効性の判断は、まず通報件数によってなされる。しかし従来、内部通報件数は公表しないものとして、経営層など一部での共有に限定し、モニタリング対象の数値として扱う企業も珍しくなかった。
内部通報制度を整え、運用する段階と、その件数を公表する段階の間には、大きな壁がある。公益通報者保護法が2020年6月に改正されたことを受けて、件数の公表も議論の俎上に載せたものの、「社内理解が追い付かないので、件数の対外公表は行わない」という結論に達した企業もあっただろう。他方、コンプライアンスを重視する企業が、内部通報件数を開示する方向で社内に呼びかけるような例もある[注1]。
上記をもとに、内部通報と情報開示の関係を整理すると、次の3つに大別できる。つまり、①件数は社内のモニタリングにとどめ、内部通報制度自体の開示も行わない場合、②内部通報の件数は開示しないが、制度自体の紹介は行う場合、そして③制度の紹介とともに、件数もあわせて開示を行う場合である。そして、①より②、②より③と、企業の抵抗感は増加する。他方で、社会的な動向に目を移すと、2023年の改正によって有価証券報告書に人的資本情報の記載が必要となり、その中には「指標及び目標」が含まれている。そして、上述のように内部通報件数は、リスク管理の観点から有用な指標と考えられる。そのため、これを機に内部通報件数の記載を検討した企業もあったことが想像される。それでは、実際に有価証券報告書を通して開示した企業はどのくらいあったのだろうか。
内部通報制度の記載状況
今回、有価証券報告書の確認対象企業としたのはTOPIX500指数構成銘柄のうち、2023年3月期決算の企業、380社である。その結果、新設された【サステナビリティに関する考え方及び取組】欄で内部通報制度について何らかの言及があったのは、27社だった。これは380社のうちの7%であり、かなり少ないように感じられる。
この理由について考えてみよう。コラム「有価証券報告書を通した人的資本のリスクの開示状況と課題」で、人的資本のリスクに関する記載箇所が【事業等のリスク】も含め3箇所あることを指摘した。今回の内部通報についても、こうした状況は同様であった。具体的には、【事業等のリスク】で内部通報についての言及を行う企業が70社以上あり、さらに【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】で言及する企業もあった。内部通報は、リスク管理の方法のひとつであり、その位置づけや運用方針は各社で異なる。こうしたことが、このような記載位置のバラつきを生んだものと考えられる。
内部通報の指標としての利用状況
内部通報は各社が不正やその兆候を理解するツールであり、またそれが機能していれば、それは従業員が何かを見たり、聞いたりした際に、確実に声をあげられる土壌が整っている証左でもある。そのため、内部通報件数は、各社が不正リスクを適切に管理できるかを示すものである。
こうした重要性を念頭に、【サステナビリティに関する考え方及び取組】において内部通報に言及していた27社が、人的資本に関わる「指標及び目標」として、内部通報件数を記載していたかを確認してみよう。その結果、27社のうち、実績値の記載があったのは4社だった。これは、「内部通報制度を整えている」という段階から、「内部通報件数を社外に示す」という段階には、依然厚い壁があることを示しているものと理解できる。
上述の通り、内部通報件数を記載する企業数は少なかった。しかし、件数とは別に内部通報に関連する興味深い「指標及び目標」を採用する事例も見られた。まず、不正などを発見した際に行動に繋がるように通報訓練の経験率を記載する企業があった。他には、内部通報制度の認知度を目標として掲げる企業があった。
コラム「内部通報制度は従業員に認知されているか」において指摘したように、内部通報件数はその経年変化の解釈が悩ましい数値だ。具体的には、内部通報は年ごとにその件数が変動するものの、それが「内部通報制度が知られていないから、件数が増えない(または減っている)のか」、または「内部通報の必要がないから、件数が増えない(または減っている)のか」を確認することは簡単ではない。これは、内部通報制度が整備・運用されているものの、そのことを知らない従業員が一定数存在していることに由来する。当然のことながら、内部通報制度の認知度が低ければ、不正やその兆候に気づいても通報される可能性もまた低くなる。反対に、内部通報制度の認知率が高い企業であれば、何かあった場合には内部通報に繋がることが期待できる。
内部通報制度の認知率が高ければ、例え不正が生じたとしても、早期発見・早期解決に繋がることが期待できる。有価証券報告書を読む投資家からすれば、こうした企業は大きなリスクを抱えにくいものとして理解しやすい。また、世界各国から調達を行う企業では、内部通報を社内だけでなく、バリューチェーンに対して広く開放し、その情報を取り込んでいくことが、人権に関するリスク管理として、一層求められることになるだろう。これはビジネスと人権への関心が高まるなかで、今後一層重要性を増すことが予測される[注2]。
まとめ
本コラムでは、リスク管理の観点から内部通報の位置づけについて確認し、2023年3月期決算の有価証券報告書の記載状況を確認してきた。リスク管理を語る上で内部通報の重要性を強調しすぎることはないが、現時点で人的資本情報開示として積極的に有効に活用されているわけではない。しかし、このような状況だからこそ、内部通報についての開示を充実させることで、優れたリスク管理を行う企業として投資家との対話に臨むことができるのではないだろうか。
[注1]佐々木聡「日本の人的資本経営が危ない」日本経済新聞出版
[注2]人的資本情報開示とビジネスと人権の関連性については、コラム「有価証券報告書、ISSB、TISFDから考える人的資本情報開示のこれから」を参照。
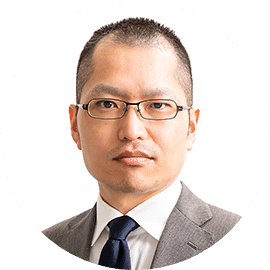
シンクタンク本部 研究員 今井 昭仁
