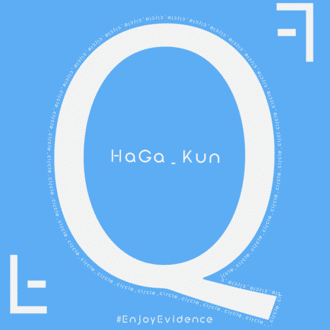なぜ、ネット・ゲーム依存症対策条例案は効果がないのか?ゲーム障害とはなにか?根拠を交えて真剣に調べてみた。
香川県のネット・ゲーム依存症対策条例案とは?
18歳以下の子どもがネット・ゲーム依存状態にならないよう、県や学校、保護者、ゲーム開発事業者などの責務を明確にしたもの。これまでは「子どものネット・ゲーム依存症につながるようなスマートフォンなどの使用」時間を平日は60分、休日は90分に制限するとしていたが、20日の検討会で時間制限の対象を「子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用」に修正。ゲーム以外の使用には制限を設けない方向性を示した。
条例案の全文についてはコンテンツ文化協会の記事が参考になります。
そんななか、先日noteでもこちら↓の記事を読んで、いろいろと思うところがありました。
すごくいい記事で、ゲームが好きな方の情熱がホンモノで、だからこそ憤りを感じていることがすごく伝わってくるんです。
でも、ゲームが本当に好きな方と、ゲームなんて有害だ!って思っているヒトの溝って、どうしてもこの記事だと埋まらない気がするんですよね。
ゲーム嫌いの人に風ノ旅ビト」という伝説的に素晴らしいゲームがあって、1週2時間ほどでクリアできて、仲間出来てすごいです。って言われてもたぶん通じないと思うんですよね、意味が。ネイティブゲーム世代じゃない人には特に。
今回は、なるべく賛成側と否定側の論点を整理しながら、客観的な根拠はどういったものがあって、何を規制し、どんな効果を得るべきなのか?
条例は、香川県の妄想の産物なのか?
もしくは、根拠に基づいた素晴らしい政策なのか?
しっかりと調査していきます。
始めに、私の立場から。
始めに、私はゲーム業界や関連会社との一切の利益相反がありません。エビデンスとしてゲームの時間制限によってより良い社会が作れるのであれば、賛成です。しかし、何の根拠も示されず、市民の権利が制限される条例であれば、他県の条例だとしても反対という立場をとらざるを得ません。
あくまで、客観的な事実に基づいて良いものなのかどうかを調査していきます。
ネット・ゲーム依存症対策条例案最大の問題点

私、この記事を書くにあたって全文を読んだんです。でも、この規制の根拠って一つも明確にされていないんですよね。
無知で申し訳ないんですが、条例とか法律って根拠を明確にしないものなんですかね?
子どもの学力低下
子どもの体力低下
睡眠障害の発生
ひきこもり
これらは大きな問題かもしれませんが、いったいどのように調査して、どの程度の悪影響が発生するのでしょうか?その点を明確にせずに議論をする余地はないんですよね。
まぁ条例って、従わなければいけないものという性質から、議論を生むような内容にするべきではないと思うんですが、これって”案”なんですよね。
”案”ってことは、”条例”として施行される前に問題がないかどうかをチェックするために作られるものじゃないんですかね?
”案”に根拠が1つも明確に描かれていないのは超大問題だと思います。
私の部下が、この商品はゼッタイ売れるんです!勘です!って言ってきたら突っぱねますよ。でも、しっかりとしたデータに裏付けされた売れる可能性の高い商品なら入荷して販売します。これって行政では当たり前じゃないんですかね?
チャレンジはゲーム以外で

序文には、子どもがその成長過程において何事にも積極的にチャレンジし、活動の範囲を広げていけるように、とあります。
残念ながら、e-sportsに挑むことはチャレンジにはならないようです。ゲームカルチャーに触れ、そのカルチャーを作る側や、楽しみを伝えてみんなを楽しませるヒトのチャレンジも、全て否定されています。
それでも、活動の幅、広まるらしいです。すごいね、香川県。
この序文は突っ込みどころ満載なんですが、ここで冷静になって、ちゃんと問題点を確認していきましょう。
ゲームは病気なの?

条例案にもある通り、世界保健機関において「ゲーム障害:Gaming disorder」が国際疾病分類の中に含まれたのは事実です。
国際疾病分類(ICD-11)の定義によると、ゲーム障害とは
1.ゲームの制御ができない(開始・頻度・強度・終了・背景について)
2.他の生活上の利益や、日常の活動よりも優先される範囲で、ゲームを優先してしまう。
3.ネガティブな結果が発生しているのにもかかわらず、ゲームを継続し、エスカレートする場合で、その行動パターンが個人・家族・社会・教育・職業・またはその他の分野の重大な障害をもたらすのに十分だと考えられるほど深刻であること。
*1~3の条件を満たし、その状態が12か月以上続くようなこと。
と、かなり厳しい基準が設定されています。
逆に、この基準に該当しない場合はゲーム障害とは言えません。
条例案の中では”ゲーム障害”という言葉が出てくるのは1回だけで、なぜか疾病には設定されていない「ゲーム依存症」という謎ワードが出てきます。ゲーム依存症=Game addictionはちょっと違った意味の言葉だと思うんですが、これはなんでしょうかね?最初だけあおっておいて、違う言葉にすり替え、疾病じゃないものを規制しようとしてるってことですかね。
さぁ、この定義を満たす人はゲームをしている人のいったい何%なんでしょうか?
ゲーム障害の基準を満たすヒトは決して多くない

2015年の研究によると、ドイツの調査では1.2%、オランダの調査では5.4%など調査によってばらつきはあるものの、数%程度の罹患者がいることが分かっています。
この数値が多いとみるか少ないとみるかはヒトによって違うと思いますが、今回のようにこども全員を対象にして制限をかける施策を肯定する数値だとは決して思えません。
国はSociety5.0に向けて、情報やインターネットをうまく活用できる人材の育成を掲げていますが、この条例はデジタルデバイスの不自由化を掲げる政策ですから、逆方向に進んでいるような気がします。
ゲームは覚せい剤を投与したときと同じ量のドパミンが出るから危ないんだ!
国と地方の協議の場(令和元年度第2回)における協議の概要に関する報告書:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyouginoba/r01/dai2/houkoku.pdf

じーくどらむすさんが指摘しているこの文章は私も気になります。
私は、そもそもドーパミンが出ることだけを根拠に話を進めることがどれだけ危険なのか?をお伝えしたいと思います。

例えば2005年にプリンストン大学で行われた実験では、スクロース(砂糖)を断続的に摂取すると、ドーパミンとアセチルコリンといった神経伝達物質の分泌が増えることが示されています。この研究では、砂糖が依存症の原因となる覚せい剤などのドラッグと同じポテンシャルがあるのではないか?と結論付けられています。
しかし、砂糖は日本では禁止されていません。体に必要な物質ですから、子どもも食べます。
砂糖の税金、砂糖税をかける国も海外にはありますが、
砂糖にはドーパミンが放出され依存症になるから危険。という意味不明な根拠をもとにしているワケではありません。
あくまで、世界中で肥満や、それに伴う生活習慣病の罹患が増加するにしたがって、公衆衛生上のリスクが非常に高まっているという数多くの統計データにより裏付けを得て行われた政策です。
ゲーム依存によって、フィジカル・メンタルヘルスや学力に高い影響を及ぼすかどうか?について考えるための材料となる研究はまだ出そろったとは到底言えません。質の高い研究も少ないです。
したがって、現段階で一気に規制をかけるのは時期尚早。少なくとも、『将来に向けた早期調査として、データ回収のために小規模で行う』くらいが妥当だと考えられます。
今回の条例の効果判定はどう行うんでしょう?
まさかまだ決まってない・・・ってことは無いですよね?
ゲーム時間を減らせば依存しないんだ!笑

超残念ながら、”ゲーム”に対する時間制限について質が高いレビュー研究は見つけられませんでした。しかし、疾病分類(ICD-11)により非常に近隣分野に指定されているギャンブル行動については多数の研究成果があります。
その多数の研究成果といえる系統的レビューを、さらにレビューした論文が2019年にAddictive Behaviors誌によって公開されています。この研究では、依存行動に対して時間制限を行うことで、ギャンブル行動が減るかどうか?調べられました。

■制限が意味なしとされた研究
過去行われた13の研究を統合した結果、47%の研究ではプラスの効果がなく、ギャンブル行動は継続されました。
・中でも1つの研究では、80%の参加者が制限を超えてギャンブルを継続。
・2つ目の研究では、30.2%が制限を超えてギャンブルを継続。
■制限が成功した研究
・ギャンブル行動が31.7%減少
しかし、その要因は”制限が個人の意思によって決められていた”ことだと結論付けられています。
したがって、強制的に時間を制限するような条例で、ゲームにかかわる時間を減らすことはかなり難しいと言えるでしょう。。
ただし、2013年には、ゲームマシン自体に時間のポップアップ機能をつけるだけで、遊ぶ時間が減るとの研究も出ています。小規模な実験であり、意思決定に使えるレベルの根拠とは言い切れませんが、制限はむしろゲーム業界側の対応が期待されるところかもしれません。
*そもそも、ゲーム時間が減る=疾病リスク下がるとは証明されていませんケドね・・・
デジタルデバイスの学力向上機能について
コチラの記事にも書いた通り、スマホを含むデジタルデバイスを使用した勉強は、高い効果と可能性を持っています。単純な時間制限のような時代遅れの規制は、将来を担う若者のポテンシャルを叩き潰しています。
学力的観点から言っても、デジタルデバイスは規制すべきではありません。
睡眠障害について
寝る前のデジタルデバイスの使用に関しては、睡眠時間を低下させるという根拠が蓄積されつつあります。子どもの睡眠時間の重要性を理解し、本人とともに家族が協力して生活リズムを作る努力は確かに必要です。
*だからといって一律規制に意味があるかは分かりません。
■ゲーム制限について

じーくどらむす氏は、ゲームの規制をするなら、個別規制すべきとの意見を書かれております。ゲーム一律時間制限は確かにナンセンスですが、ある程度の”包括指定”は許容される可能性があります。
例えば、以前は禁止薬物はすべて個別指定でした。ゲームで言ったら、マリオカート64はNG、マリオカートWiiはNG、マリオカート8は指定されていないからグレー(OK)のように。
しかし、合法ドラッグ・脱法ドラッグはどんどん最新作が出るせいで、規制しきれないという状況が長く続きました。それをどうにかするために、厚生労働省は包括指定を行いました。それは、”特定の構造を持つ”薬物すべてを一気に規制するものです。
したがって、ゲームにおいてアクションやシミュレーションはNG,パズルはOKのように線引きが生まれる可能性は非常に高いと言えます。ゲームの入れ替わりは非常に速いからです。
薬物とゲームは違うという意見もあると思いますが、こういった前例は尊重される可能性が十分にある。ということを示しておきます。もちろん、もし規制を行うならアクションゲームは有害で、パズルゲームは有益だ!というデータに基づいて行われるべきですが。
まとめ

今後、新たな規制方針などが出てくる可能性は高いでしょう。しかし、その場合必要なのは、どういった根拠に基づき、何を規制するのか?です。
今回の条例は明らかに根拠薄弱と言わざるを得ません。
今後すべきなのは、どういったジャンルのゲームが一体どのような影響を与えるのかをしっかりと調査する事。危なそうだから一気に規制しちゃおうでは話になりません。規制の効果もどういった基準で評価するのか、考えていなければ意味がありません。
規制を効果的に使える人を政治家に選ぶ努力も必要だと思います。
私は、今回の調査によってゲームの一律規制には反対だと結論します。
しかし、ゲーム障害の問題性はゼロではありません。子どもと親、家族が協力し、先ほど紹介したゲーム障害の定義に当てはまらないよう生活を調整していくような努力は必要です。しっかりと家族同士が協力し合える社会づくりは重要なこと。ゲーム一律規制なんておかしい!だけで議論が終わってしまわぬことを祈っております。
おしまい
【ツイッターについて】
ツイッターでは、noteの更新情報を発信しています。フォローしておけば、僕の記事を逃さず読む事ができます。連絡・相談等もツイッターまでお願いします。
【サポートについて】
私の記事は、ほとんどが無料です。
情報を皆さんに正しく、広く知っていただくため。
正しい情報発信を続けていけるよう、サポートで応援をお願いします。
引用
Rada, Pedro, Nicole M. Avena, and Bartley G. Hoebel. "Daily bingeing on sugar repeatedly releases dopamine in the accumbens shell." Neuroscience 134.3 (2005): 737-744.
Petry, Nancy M., et al. "Internet gaming disorder in the DSM-5." Current psychiatry reports 17.9 (2015): 72.
Kim, Hyoun S., et al. "Limit your time, gamble responsibly: setting a time limit (via pop-up message) on an electronic gaming machine reduces time on device." International Gambling Studies 14.2 (2014): 266-278.
いいなと思ったら応援しよう!