
自分の心が動く方向へ。ゼロから探る、あたらしい地域福祉のかたち。
新卒で就職した地方自治体に3年間勤務した後、より地域の方の顔が見える働き方を求めて大人の島留学へ。ゼロからのチャレンジで地域福祉の可能性を模索するなか、今、彼女が感じる自身の変化とは。
島根県の離島、隠岐島前地域で大人の島留学に参画した皆さんの来島前・来島後、そしてこれからについてお届けする「私、島で働く。」
来島のきっかけから島での仕事・暮らし、自分自身の変化など1人1人のストーリーをお届けしています。
R6年度大人の島留学生として海士町に来島。
福祉×まちづくりプロジェクトに所属する野田実優さんにお話を伺いました。

神奈川県出身 取材当時26歳
子ども時代の記憶が育んだ、「地域のつながり」への想い。
大学卒業後に就職した先は、自治体の生活保護の部署。大学で社会福祉を専攻していましたが、福祉だけにとらわれない観点からまちづくりに関わることがしたくて、事務職として役所に入庁。経理や庶務、労務などの業務を担当していました。
大学では主に高齢者福祉を学んでいて、その道を志すようになったきっかけは、今思い返すと高校時代に知った高齢者の「孤独死」のニュースだったと思います。

もともと、"おばあちゃん"“おじいちゃん”という存在がすごく好きで。長年の経験を聞くたびに自分の知らないたくさんのことを教えてもらえたり、お話しているだけでどこかあたたかい気持ちになるというか、安心するんです。そして、なぜだか、自分自身が小さいころからよく自分の老後の姿を想像してしまうところがあって(笑)
だから余計に、そのニュースを見たときは衝撃が走ったのを覚えています。周りには普段からたくさんの人が暮らしていたのに、誰にも知られることなく亡くなる人がいるという事実が、とてもショックでした。

自分自身も人が多い場所で暮らしているとはいえ、来島前に住んでいた場所では近所の人との関わりはほとんどなくて、お互いの顔もあまり知らない。孤独死は決して他人事ではないし、親も、周りの大切な人も、そして自分も、いつかそういう状況になったらすごく寂しいなと感じたんです。
身近な地域のつながりでどうにかできないだろうか――
高校生のときから、こんなことを漠然と考えていました。
振り返ると自分が子どもだったころ、自分の地元は地域のつながりがある程度濃かったように感じます。子ども会というものがあったので、同じ地区に住んでいる友達と一緒にイベントに参加したり、近所の駄菓子屋さんにふらっと遊びに行ってはお店のおじちゃんとおしゃべりをしていたり。

地元の駄菓子屋さんは今は閉店してしまったけれど、まだ子どもだったころの自分にとって、そこはひとつの居場所のようなものでもあって。
いつか地域の人も、そして自分も、心地よさを感じながらありのままに過ごせる、そんな心の拠り所のような場を作ることができたらな。
そんなことをぼんやり思い描いていて、老後は自分が駄菓子屋をつくって、そういった場にすることがひとつの夢なんです(笑)
その後大学では、まちづくりや地域コミュニティなどあらゆることにつながっていく領域の広さに魅力を感じ、社会福祉を専攻しました。授業の傍ら、高齢者の方の居場所づくりとしてコミュニティカフェの運営にも関わっていて。
自治体で働くも、「より顔の見える関係性」を求めてあらたな道へ。
卒業後に自治体を選んだのは、小学生の頃に役所で働いている方のお話を聞いたことが、おそらく最初のきっかけでした。また、事務職を選んだのは、福祉的な観点を大切にしたいと思う一方、それにとらわれ過ぎずに多角的な視点から行政の仕事に携わってみたかったから。
ある程度、決められたことを計画的に行う働き方は自分の性格に合っていたし、もともとそういう仕事を自分から選んだ部分もあるので苦ではありませんでした。
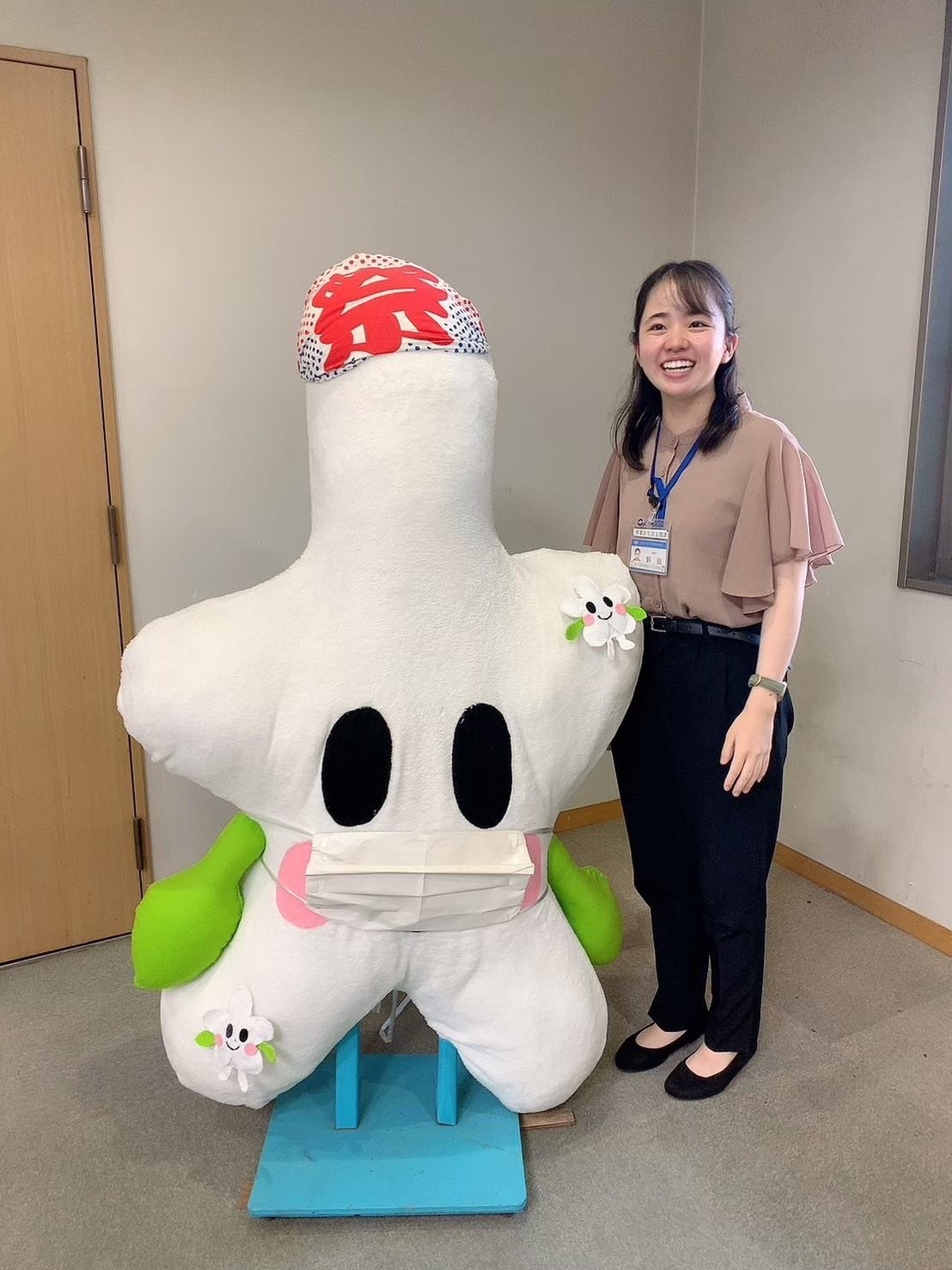
ただ一方で、デスクでパソコンと向き合う時間も多く、
「地域に出て、もっと近い距離で地域の人と関わりたい」
「ゼロベースで何かを企画したり能動的に動いてみたい」
という思いが常に自分のなかにあるのも事実で。
1対1で誰かと関わることで伝わってくる温度感や、声のトーン、わずかなニュアンスなど、五感を通じて相手のニーズを汲み取って、目の前の人が喜ぶ瞬間を直接見たい—―

大学時代に取り組んでいたコミュニティカフェを思い出したとき、そうやって「顔の見える関係性」で一人ひとりと丁寧に関わることが、自分にとってとてもやりがいのあることだったなと考えるようになっていきました。
また、もともとよく旅行で離島巡りをするくらい、離島という環境にもとても興味があって。旅行者としてではなく、いつか実際に生活してみたいと思っていたとき、たまたま見つけたのが「大人の島留学」の制度。
お試しで1年間離島で暮らすことができ、自分が求めていた「顔の見える関係性」で地域の人と近い距離で働くことができる。この制度を見つけたとき、すごくワクワクして
「やってみたい!」
と率直に思って、すごく心が動いたのを覚えています。そう思えることにめぐり会えたことがうれしくて、気が付いたらオンライン説明会に申し込んでいましたね。

もちろん、自治体の公務員の仕事はずっとやりたかったことでもあるし、とても大切な仕事だと今でも思っています。職場の方々にもありがたいことに恵まれて、大人の島留学制度を見つけていなかったら、そのまま続けていたと思います。
役所に入庁した当初は定年まで働かせてもらう気満々だったので、その当時の自分が知ったらひっくり返るんじゃないかなと思うくらい、自分でもびっくりな決断だなと。
でも学生のとき以来、社会人になってから何かにわくわくを感じることがあまりなかったからこそ、何かやりたいことがあるってすごく幸せなことだなと思って。
だからこそ、たくさん悩みはしましたが、自分が心惹かれるものに素直になろうという気持ちと、最後は直感を大切にという思いで仕事をやめて島に行くことを選びました。

島ではプロジェクトに所属。目指すは、専門性を超えて誰もが関わり合える地域福祉のかたち。
島では「福祉×まちづくりプロジェクト」(以下、福祉プロジェクト)に所属し、週2日は「ひまわり」の主にデイサービスで活動しながら、残り3日はプロジェクト活動をしています。
プロジェクトで考えていることは、
「人の入れ替わりを前提とした新しい地域福祉のあり方。」
これまで「福祉」と聞くと、専門知識や資格が必要なものという印象が強く、一般の人々にとっては少し距離を感じる分野だったかもしれません。実際に私自身もそのように感じることがありました。
しかし、大学での経験や、地域に暮らし、日常の中で人々と関わるなかで気づいたのは、福祉は専門的な仕事とは限らないということ。

たとえば、海士町に来てからは、シェアハウスの近くに住むおばあちゃんと何気なく話をすること、それだけでも、その人にとって大切なつながりや支えになっているかもしれません。これもまた福祉の一つの形だと思っていて。
今は大人の島留学生として、地域の方々とフラットに関わることができている。決まった肩書きや役職がない分、地域の方々も
「気軽に何でも相談してね」
「困ったことがあれば声をかけてね」
と、自然な距離感で接してくださって、地域の方々に助けてもらうことばかりです。ですが、時間が経つにつれて
「ちょっと手伝ってほしいから来てくれる?」
と連絡がくることも。特別なことはできないけれど、頼ってもらえる関係性になれたことがとてもうれしくて。

「支援する側」と「される側」という一方向的な関係性ではなく、自分が何か助けてもらったら、今度は自分からも何かお返しをする。
そうやって、お互いに支え合いながら地域のなかでやりとりできることが自分は心地よいと感じています。
何もかもゼロからチームで挑むという初めての経験。手探りのなかで地道に築く関わりしろ。
今年度に本格的に立ち上がったばかりのこのプロジェクトは、決まった形がないため、いわば「実験中」のようなものだと思っています。
決められた枠のなかで個人のタスクを確実に遂行することが重要視されてきた前職と違って、このプロジェクトではどのような形が理想なのか、どう動くべきなのか、常に手探りです。

最終的なゴールが霧の中にあるような感覚があって、すぐに成果がカタチとして見えにくく、0から1を生み出すことへの難しさや不安を感じることは何度もあります。
それでもやっぱり、体を動かし、頭を使いながら地域の現場に入って何かを生み出していくことは自分がずっとやりたかったことで、その分、やりがいは大きいし、こういった新しい経験は自分の糧になっていると思っています。

事業所とプロジェクト両方に関わるハイブリッドなこの働き方は、最初はどっちつかずのような感覚があって、事業所とプロジェクトをそれぞれ別のものとして考えてしまっていて。しかし、半年ほど経った今、少しずつですが、それぞれの活動のつながりや可能性を見出せるようになってきたのではないかと思います。
単にプロジェクトのみの所属だけでなく、地域の事業所の現場にも入って働かせてもらうことで、例えば海士町社会福祉協議会の職員さんと意見交換の場を設けさせてもらうことができたり、そこから、既存の組織に大人の島留学生を巻き込んだ地域福祉の可能性を探っていける糸口になるのではないかと思います。

事業所とプロジェクトの両方に関わっているからこそ、他の組織の方々と連携することができる。少しずつですが、それぞれの関わりしろを見つけることができるようになってきた気がしています。
また、仕事中に人とコミュニケーションをとることが増えたことは前職と比べたときの大きな変化だと感じています。例えば、新しく来島する大人の島留学3か月インターンシップ生の研修を私たちが作る際には、地域の方々にも協力していただけるように区長さんのもとへ直接お願いしに行ったり、そこからまた違った方を紹介していただいたり。
そうやって、地道ではあるけれど自分の足を運んだことで地域のさまざまな方と顔見知りになり、関係性が築かれていく。その過程は自分にとってやりがいでもあり、何より楽しいです。

自分の苦手なことへの捉え方も、チームで働くことを経験するなかで少しずつ変わっていく部分があって。
今までは自分の苦手なところを伸ばして、まんべんなくこなせることが理想だと思っていました。それこそ、4月から一緒にプロジェクトで働いているメンバーの冨田さんは私とはタイプが全然違っていて、例えば、アイディア出しや情報デザインなどが得意な彼女を見るたび、かっこいいな、自分もそうなりたいな、ってよく憧れます。
でも最近は、お互いに得意なことが違うからこそ、その違いを活かしてうまくチームワークが成り立っている気がしていて。
彼女の得意な部分は彼女にお願いをし、一方で私は、例えば地域の方や高齢者の方と関わることが好きなので、その際に自分の強みを発揮できたらなと考えるようになりました。

こうやってチームで働くことはあまりない経験でしたが、仕事への向き合い方や熱量など彼女とは根本にある軸が一致しているからこそ、今も一つのチームとしてお互いに補い合うことができている。
島に来た最初のころと比べて、もちろん、苦手意識のある部分を伸ばしたい!という気持ちはありつつも、それだけでなく、得意なことをさらに伸ばしていくことでチームとしての成長につなげることができるかもしれない。今ではそのように捉えられるようになってきました。
前職では思いもしなかった、島で広がる多様な視点と人とのつながり。自分の人生っておもしろい。
大人の島留学という制度があったからこそ島に飛び込むことができたし、今こうして、「地域福祉」という自分がやりたいことに取り組めています。
自治体の仕事をやめて、離島で立ち上がったばかりのプロジェクトにチャレンジできていることを今こうして改めて振り返ると、今まで想像しなかった道に進んでいて、なんだかおもしろいな!と感じます。
それに、島に来たことで、思いもしなかった人たちと出会えているのも確か。例えば、島に視察で来られた地方の市長さんとお話する機会があったり、普段仕事でも暮らしでも関わっている大人の島留学生たちは年齢もバックグランドも本当にさまざまです。

そう考えると、以前は比較的人口の多い地域に住んでいて、そこにはいろんな人がいたはず。でもこの島に来てからの方が、自分自身にとってはより関わる人の幅の広さを強く感じています。
地元にいたときは、学生時代も社会人になってからも、なんとなく自分と似た価値観や興味関心を持っている人といることが多かったです。それは居心地が良くて安心できる、自分にとって大切なコミュニティであることには変わりません。
でも、島という環境含め、多様な価値観や興味関心を持った方々に出会い、関わりの幅が広がり、自分自身の考えや選択の幅も広がったような気がしていて。少なからず、
「せっかく来たんだから、いろんな人と関わりたい!」
という自分のマインドの変化も影響していると思います。
今後は「海士町だからできた」でおわらせず、自分がどこに行ってもそのマインドを持ち続けたいなと思います。

来年度については、まだ未定です。大人の島留学生や地域の人を巻き込みながら地域福祉の新しいあり方を模索できるこのプロジェクトは自分にとって魅力的であるし、大人の島留学生という立場だからこそできることもあると思っています。
その一方で、別の場所や立場に身を置くことで、今持っている自分の視点、それだけではない地域との関わり方があるような気もしていて。
福祉プロジェクトでの経験を活かしながら、今度は異なる視点から海士町含めた地域というものに関わってみたいなとも思うようになりました。

現時点では今後「これに携わりたい!」という明確なものはありません。だからこそ、これから先、自分がどうしていきたいか、考えも日々変化しています。
少し不安になることもありますが、やっぱり、悩んだ上で自分の直感で決めたことは、その後の自分の支えになるような気がする。
自分の心が動く方向に素直に進んでいくことを大切にしていきたいなと思います。
「多様な人々が関わり合い、支え合うことで生まれる新しい地域福祉のあり方を広げていく。」
これからもこの目標に向かって、まずは小さく手の届くところから、地道であっていい。
顔が見える1対1の関係性を大切にしつつ、より多角的な視点を取り入れながら、今、自分ができることからチャレンジしていきたいです。

(取材・執筆|R6年度大人の島留学生 髙橋)
LINKS
▼大人の島留学のHPはこちら→☝️クリック!
▼最新情報は、公式Instagramをチェックです👀
