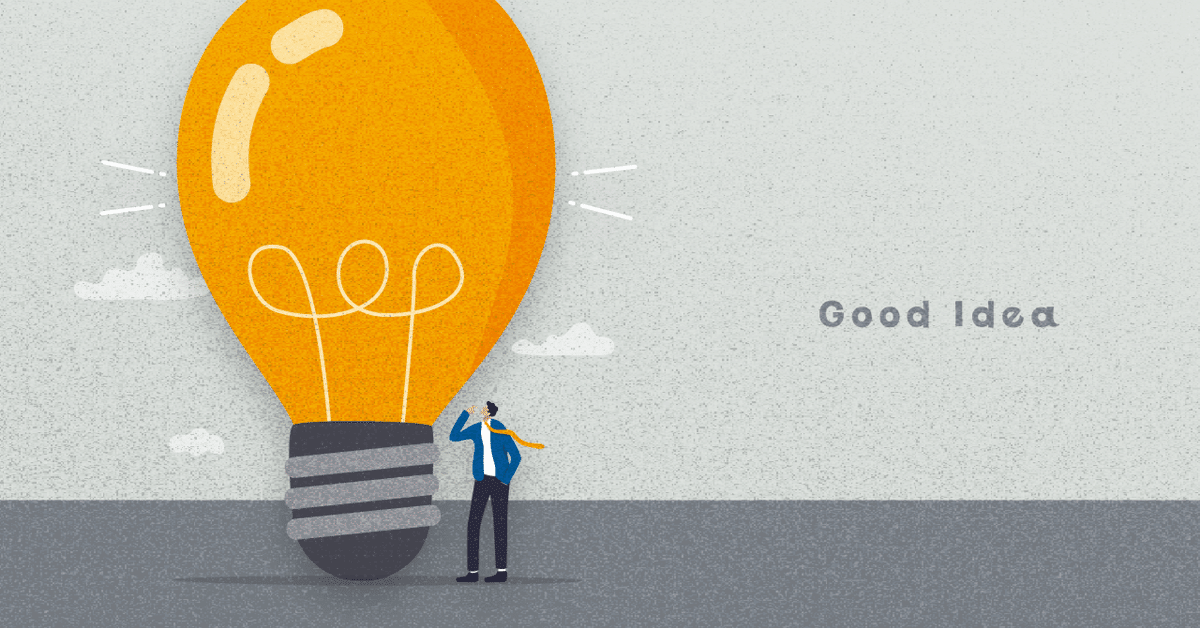
生後4か月~発想の転換で育児が楽に~
生後4か月になっても、息子の睡眠退行は続いた。睡眠退行とは、今までよく寝ていたのに昼寝が短くなったり夜に起きるようになったりと、うまく睡眠が取れなくなる状態のことを指す。これまでは昼も夜も指しゃぶりしながらではあるがセルフねんねできていたのに、急に寝つきが悪くなったので、これは睡眠退行ではないかと推測した。
生後2~3か月頃の息子は朝寝派で、朝起きてから1時間後には2~3時間たっぷりと朝寝をしていたが、生後4か月になるとその朝寝は消滅。そのほかの時間帯の昼寝は30分で終了。30分で起きて機嫌がよいのなら問題ないが、起きたらぐずぐず言い出す。さらに、セルフねんねができないようになった。お腹トントンをしてもなかなか入眠せず、抱っこをしても体をそらせるだけで、余計に泣くこともしばしば。
昼寝はリビングにさせており、そのリビングがとても日当たりがよくカーテンなどで部屋を真っ暗にできないような作りなので、その光が睡眠に影響を及ぼしているのかと思い、寝室で寝させるようにしたこともあったが、特に大きな成果は挙げなかった。
「眠いなら寝なさい!」と何度も思い、わーわーぐずぐず言っているのを放置したこともあるが、だんだんとヒートアップして激しく泣きわめくのがかわいそうで、お腹トントンしたり座布団をゆさゆさしたりして、必死に寝かしつけをしていた(我が家はリビングの畳コーナーにせんべい座布団を敷いてその上で昼寝をさせている)。
夜に関しては、ベビーベッドに置いたらギャン泣きまではいかなくても、ぐずぐずと激しい寝ぐずり。長時間続くわけではなく、30分ほど騒いだら勝手に寝るのは寝るが、これまでは寝ぐずりすることもなく入眠していたので、寝つきが悪くなったと感じた。
頑張って寝かしつけしているのに寝ない。昼間の大半はぐずついている。機嫌がいい時間が持続しない。あやしているのに泣き止まないのは、私の努力が不足しているのか。自分の努力がなかなか報われないことは、私にとって大きなストレスとなっていた。
そんなある日、そうした私を見かねて大学自体の友人が連絡をくれ、いろいろとアドバイスをくれた。「自分も涙を出して泣くまでは普通に放置」「手が離せないときはまじ泣きまで耐えてもらうこともある」「おもちゃを並べて遊んでもらうようにしていた」など、自分よりも数か月早く子どもを産んだ彼女の言葉には大きな説得力があった。
悩んでいるのは自分だけではない、無理に泣き止ませようと頑張らなくてもいいという安心感。たった数十分、数回のやり取りだったが、それだけで大きな励みとなり、心の負担が大きく軽くなった。
特にワンオペで育児をしていると、とかく自分が頑張らねばと気張りがちである。「子どもが泣いたら泣き止ませないといけない」「きちんと寝かせてあげないといけない」。そうした「○○しないといけない」という『思い込み』は、時に自分の首を大きく締め付けてしまう。
母親といっても一人の人間。何でも完璧にこなすのは不可能で、頑張り過ぎて余計なストレスを抱えるのは、自分だけでなく子どもにもよくない。育児に「○○しないといけない」ということはないのだ。そう思うだけで、心に余裕が生まれた。
そこからは、活動時間を目安に、直近の睡眠から起きている時間が2時間近くなったタイミングでぐずりだしたときは「寝かしつけなければ」ではなく「お腹トントンしてほしいのかな」と思いながら寝かしつけるようにしていて、心なしか息子もスムーズに眠るようになった気がする。ちょっとした考え方の違いではあるが、このちょっとが大きな変化をもたらしたと思う。
「○○しなければ」ではなく「○○してほしいのかな」という発想の転換。
「寝かしつけないといけない」と気合を入れて寝かしつけられて、さぞ息子も寝にくかっただろう。興奮しているところに、興奮した様子で来られては落ち着くこともできない。その当たり前を、日々の生活の中で忘れ去っていた。
赤ちゃんは母親の心の機微をよく捉えているものだ。「○○しないといけない」と思い込まないようにするだけで、赤ちゃんにもそのことは伝わる。母親が強迫観念にとらわれていては、赤ちゃんも暮らしにくい。赤ちゃんの様子を見ながら「こうしてほしいのかな」と思いをめぐらせ、母親はあくまでもサポート役に徹することが、無理のない育児につながると感じた。
また、生後4か月に入ってからは以前よりも首がしっかりと座るようになり、寝返りができるようにもなった。最初はぎこちなかったが、日数が経つにつれて、ころんとスムーズに寝返りするように。うつ伏せの状態をキープできる時間もだんだんと延びていった。生後4か月半を過ぎると、起きているときはうつ伏せでいるのが、彼のデフォルトになった。
指しゃぶりではなく手を口に入れてハムハムしたり、歯固めのおもちゃがお気に入りになったりしているのを見ると、口の中が歯がゆくなってきたようだ。大人が食事をしている様子をじーっと見るようにもなった。よだれも増量キャンペーンが始まったので、生後5か月になったら離乳食を始めてもいいかもしれない。
これまで与えられたおもちゃをぶん回すくらいだったのが、数十分は上手に握って舐められるようにもなった。おもちゃを握り直して、どんなものなのか確かめる様子も。顔の前に手をかざすと、指を握ったり摘まんだりして検分してくれるようにもなった。顔を近づけた場合は、手で顔をペタペタ、ぐにぐにと触ってくれる。いろいろなものに興味が出て、触ってみたい年頃になったんだなあと感じた。
目が合うとにっこり笑うことも増えて、ますます愛おしい。本当にかわいい。寝かしつけで悩むこともあったが、それ以上に息子の成長がほほえましくて、毎日癒されている。こういうふうに悩んだり、1日中一緒にいたりできるのは今だけなので、日々を大切にしたいとも思うようになった。
生後4か月の後半になると、手と足を上げて飛行機のようなポーズを取ることも増えた。どこでそんなポーズを覚えたのか、何が楽しいのか、背筋を鍛えながらかなりの笑顔。こんな仕草でさえもかわいい。
名前を呼ぶと反応することも相まって、ペット感がますます高まった。ひどいことを言うと思う人もいるかもしれないが、これまで実家で飼い猫を最大限にかわいがってきた私にとってペットは家族であり最愛の存在である。
大変なことは多いが、苦労が報われつつあると感じた、生後4か月だった。
