
◆読書日記.《フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ『悲劇の誕生』――シリーズ"ニーチェ入門"7冊目》
※本稿は昨年2021年4月7日に呟きの形式で投稿したレビューを日記形式にまとめて加筆修正したものを掲載しています。
フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ『悲劇の誕生』読了。
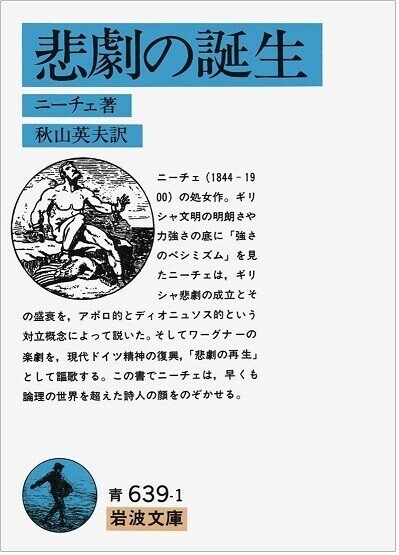
ニーチェの処女作であり、ニーチェの芸術論/美学論の源流をなす重要著作……と見なして読んでみた。因みに、先日から呟いている通りこの見解は三島憲一『ニーチェ』の説による。
ぼくの知る限り、多くのニーチェ解説本、入門書においてニーチェの代表作は凡そ『ツァラトゥストラはかく語りき』という事で一致している。
だが、珍しく『ツァラトゥストラ』よりも、この『悲劇の誕生』のほうにより多くの分量を割いて説明していた解説書が三島憲一の『ニーチェ』であった。
『悲劇の誕生』については「アポロン‐ディオニュソス」論という"初期"重要概念は提示してはいるものの、内容的にはショーペンハウアーの哲学を音楽的に表現し、また古代ギリシア精神を受け継ぐべき次世代のドイツ精神を再生する芸術としてワーグナーの音楽を称賛する……と言ったような解説をしている入門書が多い。
広く知られているようにニーチェは『悲劇の誕生』を書いた後年、ワーグナーに失望しているので、この『悲劇の誕生』についてもさほど重要性があるようには思われない。
だが、三島氏の見解では『悲劇の誕生』で論じている「アポロン‐ディオニュソス」論は晩年のニーチェの重要概念にも影響を与えているという事だった。
という事で、半ばこの三島憲一氏の見解を確かめるという意図も含めて本書『悲劇の誕生』を読んでみたわけである。
――やはり、実際に読んでみるべきだ。解説書のニュアンスに簡単に左右されてはいけない。
ぼく的には、この著作は三島氏の言う通り、ニーチェ思想を理解する上では非常に役に立つ興味深い論文だと感じた。
そもそも、本書はニーチェ解説本が説明するような、べたべたに「ワーグナーを称賛する」タイプの論文ではなく、主目的はあくまで「古代ギリシア悲劇が芸術の理想形である事、そしてその衰退過程の解説」にあると言えるだろう。
ぼくの見たところ、ワーグナーはこの論の末尾に付け足しただけという印象が強い。
事実、本書(岩波文庫版)の訳者である秋山英夫も解説で、まだ無名の若手であったニーチェが本書を出版させるために"付け足した"のが、ワーグナーをキーワードとして展開する末尾の20~24章の部分であったと書いている。
これによって、やっとワーグナーびいきの出版社から『悲劇の誕生』を出す事ができたのである。
ニーチェはワーグナーを「古代ギリシア悲劇が芸術の理想形である事、そしてその衰退過程の解説」の次段階としての「ギリシア精神的な芸術の再生」として、ワーグナーを例示して将来的に古代ギリシア的な芸術の現代的な再生への希望を語っている、といった感じなのである。結論が、ワーグナーではないのだ。
勿論、本書の執筆当時ニーチェはワーグナーの熱烈なファンであった事は事実だ。
だが、実際本書は"後に付け足した"20章に至るまでワーグナーの「ワ」の字も出てこない(ワーグナーに宛てた「序言」は別とするが)。
つまり、本書の内容は本来あくまでニーチェの「芸術論」として読むべきものだと言えるだろう。
◆◆◆
本書におけるニーチェの論旨を少しだけ纏めて書いておこう。
本書の初版の原題は『音楽の精髄からの悲劇の誕生』である。ニーチェは本書の中で「メロディーこそ最初の、そして普遍的なものなのだ」と主張している。
先日も説明したが、ニーチェは人間の原初の芸術衝動を「音楽的なもの」と考えていたようだ。
ニーチェの言う「音楽」は、人間の自然から受ける自然の芸術衝動であり、人間が受ける原初的な芸術の衝動であり、それがある種のディオニュソス的な衝動の一つでもあった。
何故ならそれは「言葉」のようにロジカルなものではなく、「言葉」によって森羅万象を分類して分断する事もなく、「言葉」のような理性的な道具ではないからである。
理知的に生み出されるのではなく抽象的で、人の心の内から自然と湧き上がる衝動の直接的な表現であるにも関わらず、聞けば誰でも「美しい」や「悲しい」や「楽しい」等と理解できるものだからして「最初の、そして普遍的なもの」であると言うのである。
抒情詩やその他の造形芸術は、この抽象的な芸術衝動をアポロン的に(秩序立てて、理知的に、形象化させて……)表現したものであるから、「音楽」に次ぐ二次的なものだと考えた。
原初の芸術衝動を「言葉」で表現すると「詩」になるし、それをキャンバスに塗り込めば「絵画」という形式になるというわけである。
ニーチェは、ギリシア悲劇の起源を、酒神ディオニュソスをたたえる合唱団から発生したと説明している。これは訳者の解説によれば古代文献学者の一致した意見でもあったようである。
つまり、悲劇は劇の形というよりかは、「音楽」の形をとった「悲劇の合唱」から発生したものだというわけなのだ。
ここで「言葉」や「筋立て」といったものは、ニーチェによればあくまで「音楽」の従となる位置づけのものであり、「メロディ」こそが主であったという。
ギリシア悲劇は、そのように原初的な芸術衝動としての「音楽」……つまりはディオニュソス的なものから発生したと考えたのである。
そのディオニュソス的なものに「言葉」……アポロン的な芸術衝動が与えられた事で、悲劇の芸術衝動は「合唱」となる。
つまりは、古代ギリシアで上演されていた悲劇のもともとのスタイルはアポロン的なものとディオニュソス的なものの合一した姿をしていたのである。
ニーチェはそこに、芸術の理想形を見る。
ギリシアの世界には、その起源からいっても、目標からいっても、造形化の芸術であるアポロ的芸術と、音楽という非造形的芸術、すなわちディオニュソスの芸術とのあいだに、ひとつの大きな対立があるということだ。この非常に違った二つの衝動は、たがいに並行して進んでゆく。たいがい、公然と反目し、おたがいが刺激になって、あの対立の戦いが種切れにならないように、それぞれ一段とがんこな子供をつねにあらたに生みおとしてゆく。こうしてその対立は、「芸術」という共通のことばでかろうじて橋渡しされる程度にすぎなくなるのだ。しかしついにこの並行して進んできた二つの衝動が、ギリシア的「意思」の形而上学的奇跡によって、たがいに夫婦となってあらわれる時がやってくる。そしてこの結婚によって、アッティカ悲劇という、ディオニュソス的であると同時にアポロ的でもある芸術品を生み出すようになるのである。(『悲劇の誕生』冒頭の一節より抜粋)
このように、対立関係である二者原理が合一する事によって――錬金術の世界観であれば「男性原理と女性原理の結婚」とでも言いそうだが――ギリシア精神というスタイルのニーチェ的な芸術の理想形が生み出されて行く事となる。
上に引用したようにニーチェとしては、この古代ギリシア悲劇という芸術の上昇段階は、紀元前6世紀の「アッティカ悲劇」の時代をひとつの頂点としている。
だが、このニーチェの理想とした古代ギリシアの理想的な芸術のステップは、ソクラテス、エウリピデスの登場をもって下り坂へと進んでいくこととなるのである。
これはハイデガー思想にも共通して見られる、古代ギリシア主義者たちの主張している「終わりの始まり」の到来を意味している。ソクラテス‐プラトン――そしてアリストテレスによって決定づけられる「終わりの始まり」である。
この流れが、伝統的西洋思想を決定づけた「主知主義」的な流れであり、「理性主義」の発展段階が始まる流れなのである。
この流れは、ニーチェによればアカデミズムでは哲学者ソクラテスが、芸術分野では悲劇詩人エウリピデスが推し進めていく事となるという。
芸術の分野に「ソクラテスと呼ばれる、まったく新たに生まれた魔神(ダイモン)」が侵入してきてからというもの、古代ギリシアの「アポロン‐ディオニュソス」の二項対立は「ソクラテス‐ディオニュソス」の二項対立となり、ギリシア悲劇はこの対立のために滅んだとニーチェは言う。
ニーチェの言う「美的ソクラテス主義」の最高原則こそが「美であるためには、すべてが理知的でなくてはならない」である。
つまり、ギリシア悲劇の芸術衝動における「アポロン‐ディオニュソス」のバランスが大きく崩れてしまった。
作り手も、観客も、もはやディオニュソス的な陶酔状況を脱し、理知的に「観察」し、「鑑賞」する「美的ソクラテス主義」的なものを強めていったのである。
で、その状況が西洋では近代まで発展し続け、アカデミズムでは遂にドイツ観念論で限界を迎える事となる。――つまり、ニーチェも「近代の超克(モダニズム)」を問題にしていたのである。
◆◆◆
「近代の超克」という問題は、様々に提示されていて一言ではなかなか説明しづらいものがあるが、つまりは伝統的な西洋思想の要である理知的な考え方の限界が様々なジャンルによって露呈し始めていた――というのが、19世紀当時の状況だったのである。
例えば、ドイツ観念論の成果から言えばカントは「神の存在は証明できない」という事を証明し、人の認識も完璧なものではない、という事を明らかにした。
また、自然科学で言えばダーウィンは進化論によって、人間が神に作られた、自然の頂点に立つ生き物であるという「人間中心主義」が崩れ、サルから進化した動物の一変種でしかないという事が明らかとなった。
キリスト教的な常識は、発展する科学によってぼろぼろに崩れ去り、西洋の基盤とする所の「キリスト教道徳」でさえも、立場が怪しくなってきていたのだ。
こういった時代だからこそ、なのだろう。
19世紀当時のドイツのアカデミズムにはゲーテ、シラー、フンボルトに代表される、古代ギリシアを、民主政治の模範としたり、普遍的な人間の姿を見、芸術的な美にも理想を見た……という新人文主義の精神があった。
このギリシアを一つの理想形として見る考え方は、ニーチェが少年時代に通っていたギムナジウムにもその精神が貫かれていたという。
上に紹介した三島憲一氏の前掲書によれば「古代ギリシアの人間像とそれにともなう古典の知識は知的エリートの不可欠の基盤として十九世紀後半に受け継がれていった」のだそうだ。
十九世紀は西洋では急速に工業化が進んでいた時代である。
<芸術時代の終焉>の代わりとして科学技術が社会を急速に文明化していき、社会の精神的基盤が揺らいでいた時期でもあったのだ。
だからこそ、ニーチェが古代ギリシアの芸術観に理想を見ていたのは、当時のアカデミズムに影響を及ぼしていた新人文主義に由来しているという部分もあるのだろう。
◆◆◆
では、ニーチェはギリシア悲劇の中に、どのような理想を見たのであろうか。
どうもニーチェは、ギリシア悲劇というものは、客観的に<鑑賞>するようなものではなく、観客も含めて「悲劇」の衝動の中に没入するディオニュソス的な衝動のほうを重要視していたように思える。
アポロン的な表現を通して、その内にあるディオニュソス的な「悲劇」の衝動にどっぷりと浸かった。
個人個人という分断された自我はその衝動の中に溶け合って正に全てが合一される。そこではおそらく「演者-観客」という区別もなくなり、皆が参加して一様に「悲劇」を高らかに謳う。
ユング的に言うならば「神話」の起源は、夢や幻覚という形で人々に与えられた「啓示(ヴィジョン)」が人々の間で共有された「共同幻想」でもある。
人々の意識はその中に集約され「集合無意識」が立ち上がってくる。
すべて現存するものは一つであるという根本認識、固体化を禍の根源と見る見方、芸術は固体化の呪縛を破りうるというよろこばしい希望であり、合一が復活されるという予感であるといったことどもである。――(『悲劇の誕生』本文より引用)
"私たち"は、悲劇の主人公となる。
悲劇の主人公たちは、正しい行いをしながらも生に苦悩し、自然の大きな運命に巻き込まれてやがて悲劇的な最期を迎える事となる。
「ギリシア悲劇」の理想形は、それを単に他人事として「悲しい」と消費したり、倫理的な見地から批評したりする事をよしとしない。それは"私たち"の事であり"私たち"も共に経験する事なのである。
「ギリシア悲劇」は、その人生の中の醜や不調和でさえも、芸術的領域の中で「肯定」する。
ニーチェはここに至って繰り返し、次の命題を掲げている。
「生存と世界は、美的現象としてのみ是認される」
つまりはニーチェにとって、「美」とは、「芸術」とは、「生存の肯定」を意味しているのである。ショーペンハウアー的に苦悩と恐怖と辛苦が約束されてしまっているこの暗き「生」は、「美」によって是認される。
"美による生の救済"!!
――『悲劇の誕生』のテーゼの中で、晩年に至ってまで連綿と続いていく重要な考え方が、これである。
三島憲一氏によれば、永劫回帰も超人思想も力の意思も――すべてはこの「美による生の救済」……ここに目的がある、というのである。
◆◆◆
以上のように、ニーチェ解説本や入門書によっては割とその内容がサラリと流されてしまう事もある『悲劇の誕生』であるが、これがニーチェの晩年に至るまで貫かれる「美的ユートピア思想」であり「美的救済論」の、まさに「誕生」となる一冊だ……と言えるのかもしれない。
それについては、今後もニーチェの著作を一冊ずつ紐解いていきながら、実際にこの目で確認していきたい所である。
だが、上に説明してきた通り、少なくとも本書は単なる「ワーグナー賛美本」でもなければ「若手研究者の若書きの書」として、晩年の思想と切り離して考えるには勿体ないと言えるだけの主張を十分含んでいるのである。
ここで分かるのは、生涯ニーチェはアポロン的に発展しすぎてしまった近代西洋に対する「ディオニュソス」的存在として、「詩人哲学者/芸術哲学者」である事を目論んでいた、という事である。
本書『悲劇の誕生』は、"哲学者ニーチェ"の「誕生」と同時に"芸術家ニーチェ"の「誕生」を告げる処女作でもあったのであろう。
