
◆読書日記.《井上真偽『その可能性はすでに考えた』》
※本稿は某SNSに2019年9月15日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
井上真偽の長編本格推理小説『その可能性はすでに考えた』読了。
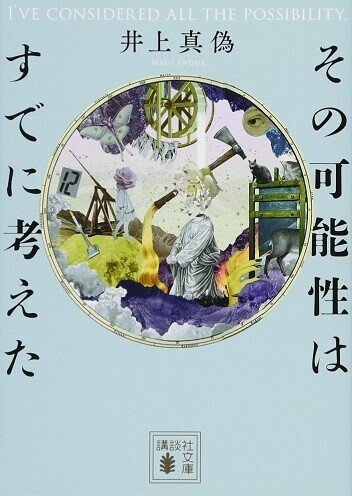
<あらすじ>
奇跡の存在を信じ、奇跡を証明する事を悲願とする探偵、上苙丞(うえおろ じょう)。ヘテロクロミアで青い髪の毛の美貌の私立探偵。
彼の元にある日、一件の依頼が舞い込む。
閉ざされた土地で共同生活を送るカルト教団に起きたある事件の謎を解いてもらいたいとの事。
依頼主は子供の頃にその教団にいた渡良瀬莉世と名乗る少女。彼女の記憶では、その教団の集団自殺事件があった日、友達だった少年・ドウニが意識朦朧とした少女を運んで逃がしてくれたのだが、彼は少女が正気に戻った時には既に死んでいた。
少年は――"首が切断された状態"で死んでいたのだった。
当時、その村の中で少年を殺せる人間は誰もいなかった。
渡良瀬莉世は、自分が殺したのではないかと疑っていたが、しかしどうやって?
少年の首を切断したギロチンは、彼の遺体とは遠く離れた場所にあった。
少女の力で遺体を運ぶのは難しいし、何より莉世は当時足を怪我していて、とても遺体を運ぶ状態になかった。
探偵・上苙丞は当時の資料を徹底的に調べ、考えられる現実的な状況を全て考え尽くした上で、ある結論に至る。
「今回の事件は――『奇跡』、でした」。
上苙はこの事件を『奇跡』だと主張するが、上苙と対立する様々な人物が彼の主張に反発し、探偵の理屈を覆そうとこの事件の真相についての仮説を持ち込んでくる!
――かくして、この事件を巡って元検察の老人、中国黒社会の大物の美女、上苙の元弟子だった天才小学生などあらゆる人物が「推理バトル」で挑戦してくる!
上苙は果たして必殺推理「憂思黙想(ブラウンスタディ)」を使ってこれらの敵を打ち砕き『奇跡』を証明する事ができるのか?頑張れ上苙!負けるな上苙!……というお話。
<感想>
この粗筋を見ただけで「中二病」感まる出しなのがお分かりになるかと思う。
本作は文庫版で、岡上淑子ぽいコラージュ作品の表紙に惹かれて手にしたのだが、解説文や粗筋を見ても「中二病」的な雰囲気は感じられなかった。
だが、中身は上のとおりムチャクチャこじらせてる感じ。あのですねぇ……。
そういうタイプのお話なら、そういうタイプのお話とちゃんと分かるようにしてほしいもんですねえ。
装画は上品なエルンスト系コラージュなんだから、そういう雰囲気だと思っちゃうじゃないですか。
でも、内容は明らかに中二病ラノベですよ。だからちゃんと表紙も当世風のアニメ系イラストレーションにしないと。
別にラノベ風な物語でも内容が面白ければいいんですよ。
でも、この著者の感覚は清涼院流水御大みたいなイタさがあるんですよね。ときどき出て来る「ずっこけギャグ」もなあ……。
しかも、東京のど真ん中にロシア連邦保安庁のスパイやら中国黒社会のビッグネームやらバチカンの枢機卿なんかがぞろぞろと集まって来る。
……勿論、これは国際謀略小説ではない。
では、いったいそんなそうそうたるメンツが、わざわざ東京に何をしに来ているか!?……それは、探偵と「推理バトル」をしに来ているのだ!
いや、いいですよ、別に。
これだけ荒唐無稽な素材を出しても。内容が面白ければ。
この著者は確かに野心的な事をしようといろいろ試しているようには思えますから、そこを期待しようと。
……ですが、いかんせん推理小説としても、その質には疑問が残る内容なわけで。
まず何より論理が美しくないんですよね。
「論理」を売り物にしているミステリなんだから、クイーンばりのロジックを立てて来るのかと思いきや、なんだか不安定でアヤフヤな理屈の応酬が終始続くわけです。
この事件は「奇跡」だと証明したいがために、この事件の「不可能状況」について考えられるあらゆる全ての可能性のある推理は「成立しない」「不可能な事が起きた=奇跡だ!」という事を証明するのがこの物語の探偵がやりたい事。
そのために、この事件の「不可能状況」について現実的に説明できそうな推理を全て反証しなければならないのですが、その反証の仕方が「その推理の状況では、おそらく"こう考えられる"。だから、そのトリックは成立しない(可能性が高い)」という反証の仕方。
つまり相手の提出してきた「この状況が成り立ちそうな状況」を、「可能性」の推測で打ち消しているわけです。
しかも主だった手がかりは少女の記憶ばかり。それ、そもそも「記憶違い」ってだけで不成立になるのでは?
こんな感じだから、出て来る推理はどれもこれも「それって反証、成り立ってる?」と思えてしまうわけです。
更に本作の「不可能状況」を成り立たせるための舞台もかなり非現実的というか……。
特殊なカルト教団の、絶対に人が外に出られない、外からも入ってこられない、という閉塞的な(というか「封鎖された」というか…)土地で事件が起こるのですが。
その土地は村への侵入者も村からの逃亡者も絶対に許さず、周囲は切り立った崖で閉ざされ、村人がよじ登らないように念入りに石膏でツルツルに固めてあり、更には崖の上に監視カメラまで設置されている用心深さ。
何故そこまで偏執狂的に村を閉ざす必要があったの?……というのがぼくには本作における「最大の謎」だったのですが、これについては特に作中に明確な説明はありませんでした。
村の中には、飼っている家畜を殺すために50キロもある刃を備えたギロチンが置いてある、って設定も「なんじゃそりゃ?」っていう感じが強いです。それどこの風習なの? ここ日本じゃなかったんです? 異世界ファンタジー?
この人は「現実的なもの」を考える想像力が行き届いてないんですよね。そういうのもあって、この物語はまず小説として苦しい。
著者は年齢不詳なんですけど、かなり書き方が若いという風に感じました。悪く言うと、この著者のメンタリティは清涼院御大と同じくらい「子供っぽい」んですよね。
登場人物はどれもこれも大人には見えないし、人間観察が浅いためか、人間同士のドラマも浅い。セリフも、どことなく幼い。そこが、ぼくとしては読んでいて最も辛い所でした。
