
◆読書日記.《ロビン・ベイカー『精子戦争 性行動の謎を解く』》
<2023年12月13日>
<概要>
射精された精液に含まれる精子の数は変化する。それは前回のセックスとの間隔や相手と一緒にいた時間に関係する―この驚くべき著者の理論は、全世界の生物学者を驚かせた。私たちの日常の性行動を解釈し直し、性に対する既成の概念を革命的に変える、まったく新しい観点から生み出された衝撃作。
<著者>
ロビン・ベイカー
生物学者。英国マンチェスター大学で教鞭をとっていた。1995年の『精子戦争』で一躍有名になった。その実証的な研究方法と結果は、多くの専門家たちを驚嘆させた。一般読者向けに書いた本書は、デズモンド・モリスも高く評価する。
ロビン・ベイカー『精子戦争 性行動の謎を解く』読了。
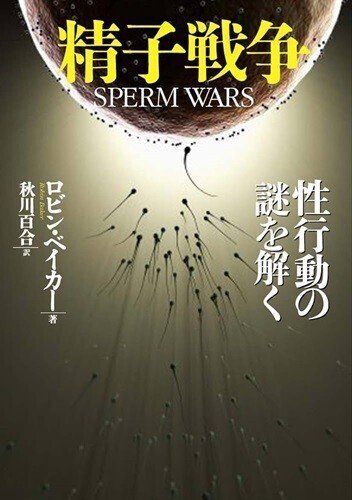
本書はマンチェスター大学で教鞭をとっていたロビン・ベイカーとマーク・ベリスが1995年に発表した共同研究の結果を一般読者向けに書き下ろしたものである。
彼らは人間の性行動についての謎を「精子戦争」という新しい概念によって解釈し直し、世界の生物学者たちにインパクトを与えた。そのため本書はこれまで27の言語に翻訳されて「今や<一般向け科学書の古典>の一つとまで言われる存在になっている(本書「文庫版あとがき」より)」という。
ぼくは学生時代に澁澤龍彦の『エロスの解剖』を読んでから「性科学」というものに興味を持ち、これまでもルネ・ネリ『エロティックと文明』や福田和彦『世界風俗じてんⅢ性風俗の巻』といった人間の性に関わる本を紹介して来た。本書もそんな人間の性に関わる内容の本である。
ロビン・ベイカーの研究結果はとにかく当時広く一般にも知れ渡り「精子戦争」という概念を一般化させる事になったようだ。
イギリスでもBBCの人気シリーズ『ヒューマン・アニマル』で、番組の科学アドバイザーであったベイカーの助言によって、彼の学説に基づいた映像が流れたという。
確かに、本書の学説は非常に魅力的で、世界的に注目を浴びるだけの理由があると思わせられるものだ。
何よりもまず、彼の学説は非常にシンプルな理論で成り立っており、そのシンプルなロジックによって人間の性愛行動の様々な「謎」を鮮やかに解き明かす事ができるという。
例えば、なぜ男女はしばしば不倫感情を抱くのか?なぜ男女ともにマスターベーションを行うのか?生殖行為が本能に従っているのならば、なぜ同性愛行為というものが起こるのか?……これらの疑問も、本書で説明されているロジックに従えばこの全ての答えられるのである。
本書を読めば、多くの読者は人間の性愛に含まれる多くの疑問に納得がいき、「ああ、そういう事だったのか」という驚きを得られるだろう。
また本書は、一般向けという事もあってその「見せ方」が非常に巧みだ。
まず、各章の冒頭に、人間の日常における性的なシーンを小説の断章風に描写する「シーン」を置き、後半でこの「シーン」における人の性的な行動の「謎」をロビン・ベイカーの学説によって解き明かしていくという構成になっている。この構成自体がドラマティックだったと言えるだろう。
内容の良し悪し別として、まず単純にこの学説は訴求力が高かったのである。
しかし――本書の訳者の「あとがき」には誉め言葉しか書かれていないものの――本書の内容には批判も多い、という事はいちおう本稿の冒頭でしっかり指摘しておかねばならないだろう。
例えば『乱交の生物学』の著者、英国シェフィールド大学教授のティム・バークヘッドは同書で「彼ら(※ロビン・ベイカーとマーク・ベリス)が不朽のものとしたヒトの精子競争についての説は、「不思議の国のファルス(男根)」とでもいえるような性的なファンタジー以上のものではない」とさえ言ってバッサリ切り捨てている。

ベイカーらの研究は生殖生理学者からしたら「科学のカリカチュア」だそうだし、彼らの研究の再現実験を行った者もその研究に再現性がないと結論付けている。
そんな中でベイカーとベリスによるこの研究の意義とは何だったのだろうか?と思えば、一つは一般に生物の「精子競争/精子選択」という動物界における雄雌両方の生殖的な葛藤の存在という問題を広く知らしめたという事が言えるかもしれない。
また、ある意味科学における「性の問題」についての注目度を上げたとも言えるかもしれない。
何しろこの手の性に関する科学は、サイエンス・ジャーナリストのメアリー・ローチの言を借りれば「性生理学の研究は、ごく少数の有名な例外はあるものの、一九七〇年代初めまでは存在しないも同然だった」といった状況だったからだ。
たとえば、セックス研究で有名なウィリアム・マスターズとヴァージニア・ジョンソンは、一九五〇年代末ごろの事情をこう記している。「……科学と科学者は、いまだに恐怖にがんじがらめにされて身動きがとれずにいる――世間の目、宗教の不寛容、政治の圧力、それに何より、先入観や偏見といったものが不安に姿を変えて、彼らの手足の自由を奪っているのだ。そういった脅威は、科学の世界の外にだけでなく、内側にも存在する」
性科学に関する研究がなぜ他の分野より遅れているのかと言えば、セックスに関わる問題が、すぐ解決しなければ何かしら生活上で支障の出るような逼迫した問題ではないと一般的に思われているという部分も多かろう。
それに、この手の研究は悪くすれば「優生学」のような悪質なイデオロギー問題に転換される恐れも出てくる。
実際、ベイカーの研究の特徴はヒトの生殖生物学に関する進化的アプローチに新たな視点を大胆に取り込んだという点があげられるが、これには誤解を招きやすい要素が多々見られるのである。
本書では人間の本能にプログラムされたある行動原理によって不倫や乱交といったものが起こされるという説明が成されているのだが、これを「生物としてそうプログラムされているのだから、不倫や乱交はヒトとして自然な事なのだ」と受け取る読者も少なからずいるだろう事は想像に難くない。
そういう誤解を与える危険性を感じる内容ではあるとは思えるが、本書はそういう見方を肯定しているものではないし、著者のスタンスはあくまでも「いかなるモラル的立場もとらないことが肝要である(本書P.15)」と言っている通りである。
ここで書かれているのは、著者による「人間という生物の生殖行為には、どういった特性があるのか?」という問題への一つの解釈だと思えば良いだろう。
そして、本書の最大の意義というのは、広く一般の人々にも、人間という生物の生殖行為の特異性とその謎に対する興味をかきたてた、という所にもあったのであろう。
◆◆◆
さて、本稿を以上の結論のみで終わらせてしまっても少々寂しいので、以下本書で説明されているロビン・ベイカーの「精子戦争」における独創的アイデアの数々も、幾つかご紹介させていただこうと思う。
まず、本書を貫く「シンプルなロジック」とはいったい何だったのか?という所から説明していこう。
本書では、生物の生殖行為の目的は「子孫繁栄」が大目標であり、男女の性愛に関わる行動や生理上の特徴に関しても、全ては「子孫繁栄」という目標に収束していくものだ、という事が前提になっているという事である。
「子孫繁栄」とはどういう事かと言えば、自分の遺伝子を受け継ぐ子や孫などの後世代の人間をどれほど増やす事ができたか、という事である。
これを著者は、ヒトの本能にプログラムされた「ルール」であり、それによって人の様々な恋愛や肉体関係や自慰行為といった行動に影響を与えている、と説明しているのである。
本書の「ヒトの本能にプログラムされたルール」の基本的な原則はこのシンプルなロジックであり、このロジックに従ってあらゆる性的な「シーン」の謎が解かれていくわけである。
著者によれば、男女にはこの「自分の遺伝子を受け継ぐ子孫をどれほど増やせるか?」という大目標に操られ、様々に無意識下の競争を繰り返しているのだ。
「子孫繁栄」という大目標を達成するには、男女ともに「より優秀な遺伝子を持つ個体」との生殖行為を行わなければならない。
ちなみに倫理や理性の働かない昆虫や鳥類や多くの動物は、この目標があるために、基本的には「乱交」がスタンダードだと言われている。
男性であれば、外見から体つきが良く健康で感染症にも強く、子供を産んだら成人するまで育て上げるだけの体力のある女性に自分の遺伝子を託したい。
それも、「子孫繁栄」という目標を考えれば、より多くの女性に自分の遺伝子を残さねばならないだろう。
だが、現実は多くの男性が同じ事を考えており、「妙齢でより健康な優れた個体の女性」というものは競争率が高い。そういう女性とお近づきになりたいと思っても、その女性のパートナーが不倫を許さないだろうし、自分になびいてくれるかどうかも分からない。
自然、男性も女性もパートナー選びは妥協、妥協を強いられる事となる。
だが、妥協しているだけでは「子孫繁栄」の目標を達するために、多くの個体に遺伝子を配る事は出来ない。
パートナーがいる男女の脳裏に「不倫」がかすめるのは、このルールが本能に刻まれているからだ、というわけである。
また、ヒトの女性は排卵期がいつなのか、女性がいま妊娠できる時期にあるかどうか、男性側から知る事の出来る材料がほとんどない、という条件もこの精子戦争の条件を複雑化させる。
女性がいつ妊娠できる時期なのか分からないからこそ、一夫一婦制の文化圏の男性は、常に配偶者の子宮内に自分の精子を一定数満たしておきたいと考えている。
ヒトの夫婦が、新婚でもなく、特にパートナーの肉体に欲情を示しているわけでもないのに、何故か惰性的に「ルーティン・セックス(夫婦が日常で定期的に行っている性交)」を行っているのは、こういった男性の「本能的なルール」に従っているためなのだ、というわけである。
「優れた遺伝子を持つ女性」というものは競争率が高いので、女性が他の男と不倫しないように、男性は女性を囲わなければならない。
男性は「精子競争」では、女性側よりも不利な立場にあるのだ。
何故ならば男性は、女性が産んだ子供が本当に自分の遺伝子を受け継いでいるのかどうか、わざわざDNA鑑定でもしないかぎり判断がつかないからだ。
実際、血液型の研究から算出した結果によれば全世界で約10%の子供達は、自分が父親だと思っている男性の血を引いていないと言われている。
また、実父鑑定テストを行うチャイルド・サポート・エージェンシーの報告によれば、世界的に見て子供が思っている父親が実の父でない確率は約15%であったとも言われる。
パートナーがコッソリと不倫をして、不倫相手の子供を産んだ場合、男性は自分の遺伝子を受け継いでいない子供を育てなければならなくなる。
これは「子孫繁栄」という目標から考えれば、男性側の敗北なのである。
そう考えると「結婚制度」という厳格なパートナー契約が人類に生まれたのも、男性側の不利を覆し、自分とパートナーとなった女性を他の男性と触れさせない「男性側の囲い込み制度」だったのかもしれない、とも考えられるのである。
女性の側も、この「子孫繁栄」という目標からは逃れられない。
女性も、男性の遺伝子を選ぶ際は妥協、妥協の連続を強いられなければならない。
必ずしも優れた遺伝子を持つ男性とのセックスに成功できるわけではないし、また現在自分とつきあっているパートナーが常に女性の不倫を警戒する。
著者によれば、社会的にも地位の高く、優れた遺伝子を持つ男性のパートナーとなった女性ほど貞節なのだという。
これは、不倫がバレる事によって優れた遺伝子を持つ男性とのパートナー契約が解消される事は「子孫繁栄」という目標を考えると非常にリスキーだからだと考えられる。
だが、女性側も常に自分の現パートナーよりも優れた遺伝子を持つ男性を求めており、その男性との関係が繋がれば「不倫」という選択肢が脳裏をかすめる事となる。
男女ともに不倫がパートナーに内緒で行われるのは、それがパートナーに発覚した場合のリスクを想定しているからでもある。
特に女性は、「優れた遺伝子を持つ男性」が、必ずしもイコール「自分の産んだ子供を成人するまで育て上げる事のできるだけの安定した収入のある男性」ではない、という事情が絡んでくる。
自分が産む子供を安全に成人まで育て上げられるだけの安定した社会的地位を持っている、という事は、他の生物に例えれば「ヒナが健康に成長するように、安定してじゅうぶんなエサを獲得してこられるオス」だと言えるだろう。
著者によれば、女性は本能的にそういう男性をパートナーとするようプログラムされているというわけである。
そして、そういう「安定した収入のある男性」との関係性を壊す事はリスクになるが、現パートナーよりも「優れた遺伝子を持つ男性」を持つ男性の遺伝子は欲しい……という本能的葛藤も同時に存在している。
「子孫繁栄」という人間にプログラムされた本能に突き動かされると、そういう不倫という考え方が生まれるというわけである。
このように、本書では「子孫繁栄」という脳に刻み込まれたルールによって、人間の様々な性的な行動が生まれるのだと主張しているのだ。
くりかえし見てきたように、射精とオーガズムに関する男女の戦略のほとんどは無意識のうちに行われ、ムードやリビドー、刺戟に対する反応の速さなど、一連の動きを通して体によって調整されている。確かに、本書に述べられている行動のほとんどは同じく無意識のうちに行われていて、脳による理性的思考ではなく、遺伝子のプログラミングの産物である。しかし、それにもかかわらず、男女とも「試みと失敗」をくりかえしながら自分たちの感情を満足させる最良の方法を学んでいくので、意識的な要素も重要な役割を果たしている。
このロビン・ベイカーによる人間の生殖観というのは、「エスと自我の関係は暴れ馬と騎手の関係に近い」と考えたフロイトの精神分析を思わせる考え方でもある。
特に男女の性愛であったり恋愛関係というのは、まさしく理性よりも本能に強く突き動かされ、それを暴れ馬の様に理性がコントロールしなければならないというフロイト的な図式そのままなのではないかとも思わせられる。
◆◆◆
……以上、本書におけるロビン・ベイカーのアイデアの一部を紹介してきたが、冒頭にも説明した様に、著者の学説は世界各国に広まって今では性科学の分野でも非常に著名な説となってはいるものの、様々な方面からの批判もあるという事はもう一度繰り返しておこう。
本書は、著者自身が「科学的知識をもち、学問的な厳格さを求める読者は、どうかマーク・ベリス博士と私の共著を手にして詳しい情報と説明を得ていただきたい(本書P14)」と書いている通り、多くの部分「結論」のみになっているのが、ちょうどぼくとしても気になった所ではあった。
この本における信頼性と説得力については、著者らの本を直接あたらねばならないと棚上げされたわけである。
本書を読んでいて最も興味を惹かれたのは「どういうプロセスからこの結論に至ったのか?」という所であり、その大半の部分を省略されてしまったのが、ぼくとしては不満を感じた部分でもあったのだ。
本書で少しだけ触れられている彼らの研究方法の一部は――例えば男性のペニスにファイバー・スコープを取り付けてセックスを行っている最中の男女の生殖器はどのような状態になっているのか映像で記録した――または「キンゼイ報告」のように四千人に及ぶ多数の男女のカップルを調査した――など非常に独創的でそれだけでも非常に興味を惹かれるものではあったものの、やはり「プロセス」というものは重要なのだ。
例えば、本書で扱われる「シーン」の具体的場面にしても、それがあまりに英国の男女関係にあわせた場面設定であり、それが果たして他の文化圏でも通用する状況なのか?という事は、読んでいる間何度も疑問に思ったものである。
これは他のあらゆる文化圏でも同じ調査を行って文化や社会や環境上の違いがどの程度あるのかという人類学的なアプローチをして確認するべきだろう。
本書で紹介される学説は、確かに多くの批判や間違いが指摘されているものの(その具体例はティム・バークヘッドが一部『乱交の生物学』で紹介しているのでそれも参照されたし)、科学研究における間違いは、必ずしも悪い事ではない。
過去どういう調査でどういう結果が出たのか……だけでなく、それがどういう観点で間違っていたのか、というのは科学の礎を築くには重要な事なのだ。
科学は硬い岩盤の上にあるわけではない。科学の理論の大胆な構造は、いわば沼地の上に建てられているようなものだ。つまり<沼地に杭を打ちこんで建てられた建物>で、その杭はどんな自然の基盤にも、「既定の」基盤にも届いていない。私たちが杭を打ちこむのをやめたからといって、それは強固な地盤に届いたからというわけではない。ただ単に、さしあたってこの構造が倒れない程度には、杭がしっかり刺さっているという点で満足したにすぎないのだ。
科学的に言えば失敗は「無意味」ではない。
ただ、本書の研究は「科学的な研究かどうかは多くの疑問に付されている」という注意書きを付された上で参照されるべきなのだ。本書の「訳者あとがき」のように、この研究のすばらしさばかりを強調するのではなく。
この研究が大きな問題となったのは――様々な問題が指摘されているにも関わらず、この学説が大きく世界に広まり過ぎてしまったという点にあるのだ。
本書の訴求力が、あまりに強すぎたのである。
