
◆読書日記.《サキ『サキ傑作集(岩波文庫版)』》
※本稿は某SNSに2022年8月30日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
サキ『サキ傑作集(岩波文庫版)』読了。
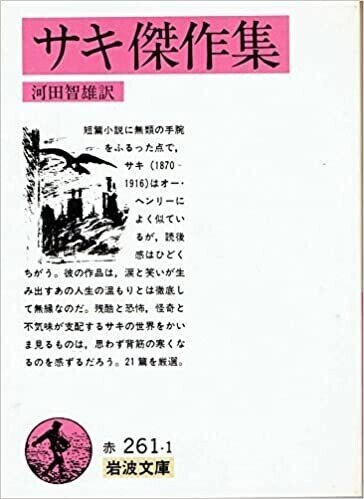
ミャンマー生まれのイギリス人小説家。19世紀末から20世紀初頭、ヴィクトリア朝時代に活躍し、ブラックユーモアと意外な結末を持つ短編の名手として有名である。
ぼくはサキについては全く詳しくなく、本書についても前知識は岩波文庫の表紙の文面のみしか頭に入れずに読んだ。
「短編小説に無類の手腕をふるった点でサキ(1870-1916)はオー・ヘンリーによく似ているが、読後感はひどくちがう。彼の作品は、涙と笑いが生み出すあの人生のぬくもりとは徹底して無縁なのだ。残酷と恐怖、怪奇と不気味が支配するサキの世界をかいま見るものは、思わず背筋の寒くなるのを感ずるだろう。21編を厳選。」
――サキ『サキ傑作選』岩波文庫版・川田智雄訳・表紙の解説より引用
自分はイギリス文学には明るくないので、この作家が英国文壇でどのような位置づけにあるかは知らない。上に引用した文章でも本書の解説でも、オー・ヘンリーの名が出されているように、「短編小説の名手」として、その個性の違いをオー・ヘンリーと比較される事が多いのがサキという作家らしい。
ここら辺も、ぼくはオー・ヘンリーなど興味がないので読んだ事がないために何とも言えない。
斯様に英国文学には全く疎いものだから、サキの作品についても「当時の評価」や「当時の文壇の位置づけ」等を踏まえて評価する事はできない。
という事で今回はあくまでぼく自身の「現代日本人の目線」というスタンスで現代の作家と同じように本書の評価をするという事を、いちおう先にお断りしておこう。
何より、本書を手に取ったのは、やはりミステリ・ファンとして、サキの作風のキー・ワードに挙げられる「残酷と恐怖、怪奇と不気味」であったり「意外な結末」であったりといった部分にミステリ的な興味を惹かれたからである。
「推理小説」とまでは言わないまでも、ロアルド・ダールやスタンリィ・エリン等と言った意外性があって奇妙で残酷で不気味な「奇妙な味の短編」等とも通じる面白さがあるのではないかという所に目星をつけて読んでみたのである。
◆◆◆
さて、読んでみた感じ、本書は約200ページというわりと分量の少ないページ数に21篇の小説が掲載されている事からも分かる通り、一編一編の分量が短い。
これは短編小説というより、ぼくの感覚だと掌編小説、ショートショートに近いものではないかと思った。
このレベルで短いと、そうそう波乱万丈の起伏ある筋書きを描くだけのスペースはなく、ストーリー・ラインは非常にシンプルだ。
解説にも「サキの短編にはきちんとした起承転結があり」と書いているように、かっちりとした一本道のストーリーという印象がある。
ストーリーがシンプルだからこそ、オチの捻りがより一層効いてくるのだろう。やはり、このやり方を見てもショートショートに感覚は近いと思わせられる。
しかし、これだけシンプルだと、オチも予想がつき易く、長年ミステリを読んできたぼくみたいな人間からしてみると、本書に載っている作品群のどんでん返しでは全く物足りないと感じられた(この辺の感覚は、さすがに当時のイギリス文学の状況がぼくには分からないので現代人の感覚でしか評価できない。当時の人々をあっと言わせるようなアイデアだったのかもしれないし、そうではないかもしれない)。
サキの創作パターンというのも割と分かり易いものがあって、本書に収録されている21篇のみで判断するならば、この人の特徴は何かしら「コミュニケーションの問題」が物語に関わっている事が多いと感じられた。あるいは、そういうパターンがあったからこそ、ぼくなどはサキのオチの付け方を早々に予想がついたのかもしれない。
本書に収録されている短編には、どれも「コミュニケーションのすれ違い」であったり「一方通行のコミュニケーション」であったり「コミュニケーション上のトラブル」であったり、あるいは「悪意あって故意にコミュニケーション上のトラブルを発生させる」等といった事が、後々に大問題に展開していたり悲劇に繋がったりするという「コミュニケーションのトラブル」に関わるのである。
この辺の詳細は以下、個々の短編にも触れて説明したいと思うので、万が一本書の短編の内容やそれぞれの小説のオチを読みたくないという方はお気を付けを。
◆◆◆以下ネタバレあり◆◆◆
サキにおける「コミュニケーションの問題」というものは、既に冒頭の『アン夫人の沈黙』から、ありありと現れている。
エグバートはアン夫人と夫婦喧嘩をしていて、夫人はエグバートから声をかけられても一切口をきこうとしないのである。……が、これは最後に、実は「夫人は二時間前に死んでいたのである」という事が分かるというオチになっている。
要するに、これはエグバートが最初から最後まで一方通行的に夫人に話しかけているだけの話なのだが、エグバートは「相手は喧嘩中なので沈黙しているのだ」と思い込んでいるという、コミュニケーションの決定的なズレを描いているのである。
この「片方だけが思い違いをしている一方通行的なコミュニケーション」というコミュニケーション上のトラブルは、続く三篇目『二十日鼠』でも繰り返されるパターンである。
セオドリックは汽車旅行に出かけ、車室のシートに座ると自分の着ていた服の下に二十日鼠が入り込んで動き回っている事に初めて気が付く。
二十日鼠を追い出すために彼は「そっと足踏みしたり、体をゆさぶったり、めったやたらにつねってみたりしたが、侵入者はいすわったまんまである」という状況。
いっそのこと服を脱いで二十日鼠を追い出したいのだが、あいにく相席にセオドリックと同い年くらいの女性が座っているので、そんな恥ずかしい事は出来ない。
……という事で相席の女性に気付かれないように二十日鼠を服の中から追い出そうと七転八倒するのだが、最終的に相手の女性は目が見えない人であったという事がわかる。
主人公のセオドリックは相手の女性に気遣ってあれこれと喋りかけながらも、相手に気付かれないように二十日鼠を追い出す苦労をしなければならないのだが、そういった苦労も全て意味のない「一方通行の気苦労」であったという結末なのである。
ここでも、主人公が相手に対して必死に裏に表に投げかけるコミュニケーションが「一方通行」で空回りしているというパターンが貫かれる。
サキの書く小説のキャラクターたちは、このように様々な意図をもってコミュニケーションを相手に投げかけるのだが、それがすれ違っていたり、裏の悪意に気付かずに大変な目にあったり、互いに理解しきれずに不幸な結末を迎えるのである。
サキの代表作の一つとされる『スレドニ・ヴァシュター』が、最終的に悲劇的な結末を迎えるのも、ひとえにこの「コミュニケーションの問題」が登場人物の間に存在しているからに他ならない。
虚弱体質の10歳の少年コンラディンの面倒を見るデ・ロップ夫人は、彼の従姉であり彼の後見人でもあった。
夫人は彼の事を「嫌っているなんて、一度もおもったことはなかった」という。彼女は彼女なりに、コンラディンのために「あれをしてはいけない、これをしてはいけない」と口うるさくおせっかいを焼くのである。
そんなデ・ロップ夫人の事をコンラディンは嫌っているのである。「自分の空想の世界からデ・ロップ夫人をしめだしていた。あんなけがらわしい奴は入れてやるもんか」と考えて、自分だけの空想の世界に引きこもるのである。
ありがちなすれ違いではあるが、この両者のコミュニケーション上の問題が大きくなって行き、果てはラストに現れる凄惨な事件が発生する事になるのである。
「飼い主はペットにだんだん似てくる」というが、『グロウビー・リングトンの変貌』は飼っているペットの種類が変わるごとに飼い主の性格が変わり、ある種のトラブルを起こすというもの。最終的にコミュニケーション不全に陥るお話だ。
『開いた窓』もサキの代表的な作品の一つらしい。これは、田舎に移住してきた主人公が牧師館を訪ねる話。
そこの娘から、牧師館の主人とその弟が狩猟に出たまま亡くなってしまったという話を聞いた後、部屋に入ってきた夫人と主人公は談笑する。彼がふと窓の外を見てみると、夕闇の中を牧師館のほうへ歩いてくるこの館の主人たちの影が見えてきて、主人公は震えあがって逃げ帰ってしまう。
だが、「牧師館の主人が死んだ」というのは、娘のついたホラ話で「即興の作り話をするのがこの娘は得意であったのだ」というオチがつく。
これも、娘から嘘を吹き込まれた主人公の慌てようと、何も知らずに主人らの話をする夫人の間で、潜在的にコミュニケーション・ギャップが発生しているという事を読者は俯瞰視点で見る事となる。
どうもこの作者は、このような「潜在的なコミュニケーション・ギャップ」というものが好きなのかもしれない。
『毛皮』も、その手の話で、ある女性が、知人同士の二人の双方に別々の話(小さな嘘)を吹き込んで「潜在的なコミュニケーション・ギャップ」を生み出し、この女性の小さな「悪意」を満足させる話であった。
こういう風に並べて見ると、サキの扱う「心理的なドラマ」というものは、裏と表を使い分けて体裁を整えたり見栄を張ったり密かに恨んだり……という他人に対する表向きと裏向きのコミュニケーションの使い分けによって発生するコミュニケーションの問題が多い様に思われる。
しかし、これらは決して特殊な状況を扱っているわけではなく、どちらかと言えば「あるあるネタ」に近い、誰でもそういう「裏」はありそうだ、といった心理が扱われているのである。
そうではないだろうか? 裏ではまるで別の思いを抱いていながら、社交上、そういった事は表面には出さずにコミュニケーションをとっている事など、われわれの日常ではそう珍しい事ではないのではないだろうか。
その「表」と「裏」との使い分けというものがサキの小説では一つのポイントとなって、結末で「トラブル」といった形で表面化する事となる。
そういった心理が「ありがち」だからこそ、サキを読む読者にはそういう心理から発展していって至る残酷なオチに、面白がりながらも無視できない魅力を見るのではないかとも思う。
