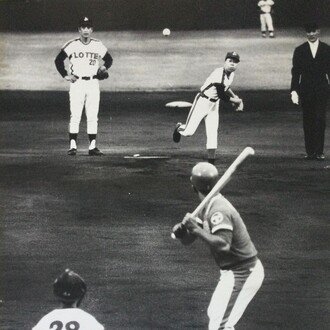【全史】第1章 なぜ、毎日新聞社は撤退したのか?/1949(昭和24)年~1960(昭和35)
始まりは、少し重いテーマからとなる。
毎日新聞の撤退は、その後のパ・リーグ史に大きく影響を与えたとともに、オリオンズの歴史は違ったものになっていたかも知れないからだ。まずは、毎日新聞の参入から撤退までの歴史から辿っていく。
(1)1949(昭和24)年 正力松太郎と永田雅一が仕掛けた、毎日新聞の加盟
1949(昭和24)年、毎日球団は産声を上げたが、毎日新聞の参入は球界関係者の念願だった。
仕掛けたのは、日本プロ野球の祖・正力松太郎(読売新聞社社長で大日本東京野球倶楽部(現・読売ジャイアンツ)創立者だが、戦後、A級戦犯に指定され、この頃は公職追放中だった)と、大手映画会社・大映社長で大映スターズオーナーの永田雅一だった。後に永田の大映と毎日の関わりが毎日撤退の一因になるのだから因縁を感じる。
この年、プロ野球(日本野球連盟)は1リーグ8球団で運営されていた。戦後4年、ようやく国民は落ち着きを取り戻しつつあり、戦前は学生野球に押され気味だったプロ野球人気も安定しつつあった。中心で動いていたのは正力だったが、この年から「金星スターズ」を買収し、球界に参入した永田を頼りにしていた。正力はある構想を持っていた。
「永田君、1リーグ8球団で2リーグ制が理想であるが、一遍に飛躍できないから、とりあえず来年度、すなわち1950年度を10球団にして1連盟でいこう。そして1951年度にまた二つ増やし、そこで1リーグ6球団の2リーグ制をやり、日本選手権を争おうじゃないか」。
正力は、プロ野球人気に確信を得て、さらなる飛躍を目論んでいた。正力は腹の中を永田にさらけ出した。
「こうすることが日本のプロ野球の漸進的なものの考え方だと思う。それで今8球団あるのだが、とりあえず2球団増やすとしてどこを入れるかね。関西から毎日を入れたいと思うが、どうだ」
永田は「プロ野球のことについては、あんたが大先輩だから、なんなりと大いに協力しましょう」と答えた。
正力は2リーグに分かれた際、片方のリーグを永田と毎日新聞に託したかったのだ。
時期は、はっきりしないが、正力と永田は、まず毎日新聞に声を掛けた。永田はこの時のことをこう話している。
「正力さんと私が毎日新聞社の本田(親男毎日新聞社社長)さんに会ったわけだ。ところが毎日は「野球なんか」といった調子で乗ってこない。そこで、正力さん乗らんじゃないかといったら『話を持っていってすぐ乗るのは安っぽくなるからね』と言っていた」。
永田はその後2~3か月渡米したというので、持ち掛けたのは5月か6月頃だったのではないかと推察する。その永田が帰国すると状況は一変していた。
「毎日も腰を上げて花道に出たそうだ。この分なら大丈夫だ」と正力から報告を受けたという。
永田が渡米している間に、正力と本田の間でどのようなやり取りがあったのか今では推測するしかないが、とにかく、結果として毎日が積極的になり7月には非公式に加盟申請を打診してきたという。正力の読み通りだった。
ところが事は思惑通りに運ばなかった。永田は毎日と近鉄を加えて10球団を提案したが、読売は西日本新聞社が乗り出すので、西日本を加入させたいと話はこじれた。
九州では西日本鉄道がすでに加盟を表明していた。当初は福岡県を基盤としている西日本鉄道と西日本新聞が共同出資して九州に新球団を設立する方向だった。しかし、西日本新聞が新球団を設立する決意をした。読売の仕掛けだった。東京の読売、大阪の毎日、愛知の中日、福岡の西日本。新聞による宣伝効果を期待していた。
当初は永田も近鉄に1年待ってもらい、西日本を入れて10球団もやむなしと考えたようだった。しかし、近鉄は納得しなかった。加えて、大洋、広島も新規参入を表明。状況は混迷を極めた。
永田が「妥協する、しないで紛糾に紛糾を重ね、とうとう二つに割ってしまった」と話したとおり収拾がつかず、2リーグ制が決まった。
先に結成したのはパ・リーグだった。11月29日、毎日新聞本社別館で南海、阪急、大映、東急の4球団が太平洋野球連盟を結成。ここに新規球団の毎日、近鉄、西鉄の新規加入を認め、リーグが発足した。
一方セ・リーグは12月15日、読売本館で読売、太陽(翌年から松竹と業務提携して松竹)、阪神、中日に加え、新規球団大洋、広島、西日本の7球団でリーグが発足。翌50(S25)年1月に国鉄が加盟して8球団となった。

2リーグに分かれた理由について、永田は西日本新聞の顛末について語ったが、永田が触れなかった大きな理由が他にもあった。さかのぼること9月29日、既存球団の代表者会議が行われたが、すでに数球団から加盟申請が相次いでいたことから「受入派」と、球団を増やすと共倒れになると主張する「反対派」に割れていた。受入派は阪神、南海、阪急、大映、東急の5球団、反対派は読売、中日、太陽の3球団だった。
ところが、10月に入ると阪神が反対派に転じた。これで真っ二つに割れてしまった。この阪神の転身には読売の説得があったという。すでにリーグ分裂を見越していた読売は「伝統の一戦」をリーグの看板にしたかったという理由と、当時公職追放の身であった正力に対する読売内の反対勢力の巻き返しだったという理由だ。

正力と永田の構想からは1年早まったが、とにかく、1950(昭和25)年からの2リーグ制が決まった。しかし、事は簡単に収まらなかった。選手の引き抜き合戦が始まったのだ。当然である。8球団から一気に15球団と球団の数が倍近くに増えたが、人気選手の数が増えた訳ではない。人気選手はどの球団も欲しかった。
最初に仕掛けたのは毎日だった。阪神の監督兼投手だった若林忠志の他、中心選手だった別当薫、本堂保次、大館勲、呉昌征らの移籍が決まった(後から土井垣武も移籍した)。裏では、阪神の寝返りに対するパ・リーグの仕返しだと言われた。ただ、阪神球団のゴタゴタに、一部主力は球団に嫌気が差していたところに、阪神球団の裏切りで一気に移籍に傾いたという指摘もある。
それ以降も各球団入り乱れて引き抜き合戦は激化し、泥沼化した。時はまだGHQが統治している戦後の混乱期である。年が明けた1月26日、GHQ総司令部経済科学局長マーカットが声明を発表した。
「不正引き抜きは止めるべし。野球関係外のコミッショナーを置くべき」を骨子とした「不正引き抜き一掃」の声明文だった。
とにかく、1950(昭和25)年3月10日に福岡・平和台と下関でセ・リーグが、11日には西宮でパ・リーグが開幕。2リーグ制という新しいプロ野球とともに、オリオンズの歴史がスタートした。
ただ、歓迎され、揚々と参入した毎日新聞だったが、一年目を経過すると球団運営に引き気味になる出来事が早くも発生するのだった。
(2)1950(昭和25)年 初代日本一王者 毎日オリオンズ

毎日新聞社は、東京の「東京日日新聞」(1872(明治5)年創刊)と大阪の「大阪毎日新聞」(1882(明治15)年創刊、創刊時は「日本立憲政党新聞」)を源流とし、1911(明治41)年に合併した全国紙(毎日新聞として呼称を統一したのは1942(昭和17)年)である。
両紙ともスポーツイベントの支援に熱心で、大阪毎日新聞は、1920(大正9)年に「大毎野球団」(後の大毎オリオンズとは別物)を結成、人気だった東京六大学を始め、卒業生の受け皿となった。1924(大正13)年には選抜中等学校野球大会(現在の選抜高等学校野球大会)を、東京日日新聞は、1927年(昭和2年)に全日本都市対抗野球大会(現在の都市対抗野球大会)を主催者として開始するなど、野球との関わり合いは古い。
大毎野球団はアマチュア(セミプロ)強豪チームで、同じくチームを結成した阪神電鉄やクラブチーム、大学、高校と対戦した。その中で、現在の日本プロ野球機構(NPB)が出来る前に結成されていた職業野球チーム「宝塚運動協会」との一戦は一番の人気で、関西の野球熱の盛り上げに一役買っていた。1925(大正15)年には、アメリカにも遠征している。
その毎日新聞がいよいよプロ野球に本格参戦することになった。初代総監督(投手兼任)に就任したのは湯浅禎夫である。湯浅は毎日新聞社の社員として、大毎野球団の一員だった。解散後は記者として活躍し運動部長だったが、毎日オリオンズの結成時に総監督として白羽の矢が立った。立場は「毎日新聞社からの出向」だった。
湯浅率いる35名の毎日は3月11日の開幕戦(西鉄戦)に9-1で勝利すると、3月を8勝3敗と勝ち越す。4月も13勝6敗1分の好成績で南海とデッドヒートを繰り広げる。そして、5月8日の近鉄5回戦をルーキー荒巻淳の完封で勝利すると、6月4日の阪急8回戦に10ー3で勝利するまで約1か月負け知らず。当時のプロ野球記録となる15連勝を記録し、一気に南海を突き放した。
この15連勝中、5月31日の東急7回戦では打線が爆発。23ー11で勝利したが、この時の1試合23得点は長らく球団記録として残った。記録が破られたのは、千葉ロッテマリーンズとなっていた2005年。3月27日の楽天2回戦(千葉マリン)だった。この試合は26ー0で勝利したが、この時まで55年間球団記録だった。なお、この東急7回戦は千葉県市川市の市川国府台球場で行われたオリオンズ歴史上唯一の公式戦だった(二軍は1953(昭和28)年から二軍の練習場として使用していた)ことも、千葉県との浅からぬ縁を感じる。
なお、50(S25)年の記録として、シーズン勝率7割0分4厘、1試合最多四球「13」(50年4月3日、対東急3回戦(後楽園))が現在も古い球団記録として残っている。1試合最多四球「13」は、2021(令和3)年4月24日のソフトバンク5回戦(ZOZOマリン)でも記録している。
その後も順調に白星を積み重ねた毎日は、10月25日の東急18回戦(後楽園)に4-2で勝利して、11試合を残して初代パ・リーグ王者に輝いたのだが、優勝決定後の消化試合で今では考えられないことが起きた。前述で湯浅を紹介した際、「初代総監督(投手兼任)」と紹介したが、実際は総監督という登録だった。しかし、11月5日の阪急20回戦(西宮)の先発マウンドに上がったのは湯浅だった。この時、湯浅は48歳1か月。総監督として登録されており、選手としては登録されていなかった。しかし、規則も緩かった時代、問題にならず記録は残った。対する阪急の先発は浜崎真二監督兼投手、48歳11か月。こちらはシーズン中からマウンドに上がっており、数々の最年長記録を記録していた。合わせて96歳という対決だった。
湯浅は4回2安打6四球2失点。防御率4.50は湯浅の唯一のプロ野球記録として残った。4回で降板したため勝利投手にはならなかったが、球団のメンバー記録には総監督兼投手として残った。ちなみに浜崎は4回途中まで投げ、8安打7失点。試合は9-2で毎日が勝利した。
シーズンが終わってみれば81勝34敗5分(120試合制)、勝率7割0分4厘(前述の現在も球団記録)、2位の南海に15ゲーム差をつける独走だった。
個人記録は、投手部門は最優秀防御率と最多勝利は荒巻淳、最高勝率は野村武史と独占。打者部門は本塁打王と打点王の2冠に別当薫。表彰選手は最高殊勲選手に別当薫、新人王に荒巻淳が選出され、毎日勢が席巻した。

初の日本シリーズは「日本ワールドシリーズ」と呼ばれ、毎日はセ・リーグの覇者松竹ロビンスとの対戦となった。現在と同じ7回戦制だったが、シーズン中の強さそのままに4勝2敗で初代王者に毎日オリオンズが輝いた。
さて、強さを見せつけた毎日だったが、翌年以降もパ・リーグの中心球団として期待が高まった。試合は集中開催が多かったため、球団別の観客数の資料はないが、伝統の南海、九州の西鉄とともに、創設1年目ながら阪神時代の人気選手もいたため、毎日人気は明らかに高かった。
しかし、その強さが仇となる。毎日新聞社がプロ野球界を撤退する遠因になったと思われる出来事が起きたのだ。それは、大映スターズオーナーの永田雅一の提案だった。
(3)1951(昭和26)年 毎日新聞は1年目から球界に不信感を抱いていた? 2つの理由

さて、2回にかけて創設時の顛末を記したが、とにかく、毎日オリオンズは船出した。
しかし、様々な資料を当たり、当時の状況や断片的な証言などをつなぎ合わせていくと、どうも創設直後から毎日側はプロ野球界に不信感を抱いたのではないかと思えてくる。
今回の記述には確たる証拠はない。ただ、私が持っている「うがった見方」「こういう考えもあるのか」という体でお読み頂きたい。
ここから先は
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?