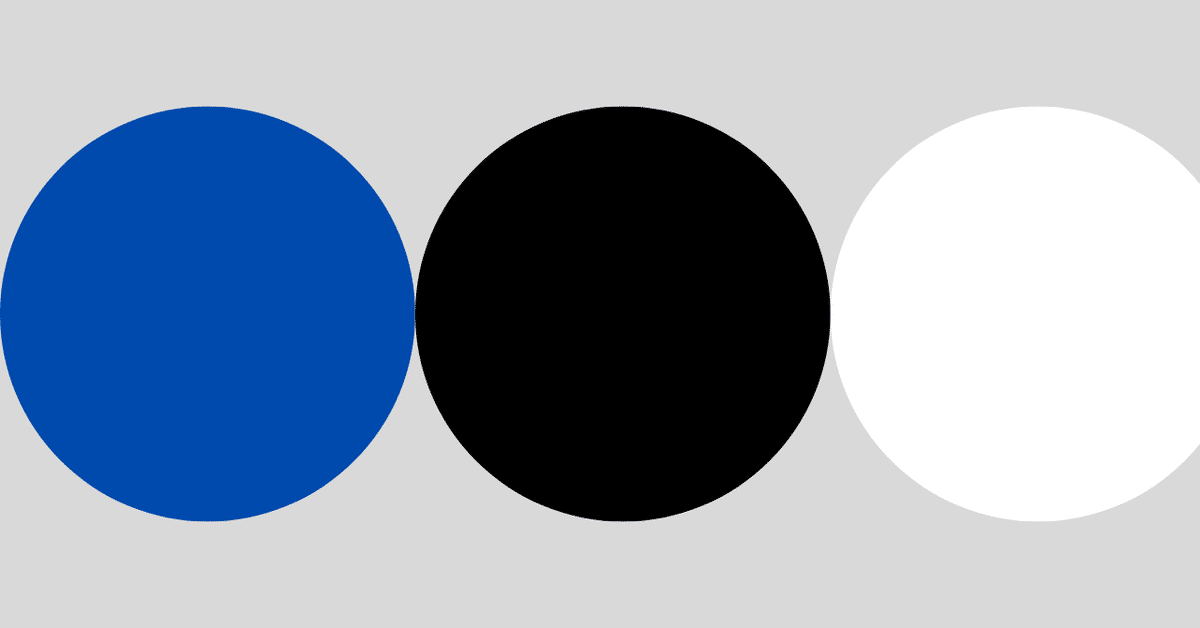
グレーバーらに4か月間翻弄された「万物の黎明 人類史を根本からくつがえす」(デヴィッド・グレーバー (著), デヴィッド・ウェングロウ (著), 酒井隆史 (翻訳))
こんな読書体験は初めてだった。
先日も紹介した浜松オンライン読書会さんの読書会に参加。2月からスタートして、2章ずつ読み進め、昨日、最後まで読み終わりました。
Ⅹアカウント https://x.com/hamamatsuOD
<リマインド>
— 浜松オンライン読書会 (@hamamatsuOD) June 24, 2024
6/24(月) 21~22時 Discord
『万物の黎明』読書会(最終回)
範囲
第11章 ふりだしに戻る―先住民による批判の歴史的基盤について
第12章 結論―万物の黎明
なんというか、冒頭でも書いたけど、こういう感じの読後感は初めてだった。
※Amazonのアソシエイトとして、本記事は適格販売により収入を得ています。
とりあえず長い(笑)。
本文だけで600頁近く、解説とか索引も入れると700頁を超える。
本書は、今までの歴史の捉え方そのものがちゃんちゃらおかしいとちゃぶ台返しをする本だと思う。
いわゆる前近代的な時代があって、啓蒙思想が取り入れられて、西洋的な近代に移行し、現代まで発展してきたというような割と普通に受け入れられている歴史観をちゃぶ台返しする。
いわゆる近代以降と近代以前を比較したら、近代以前のほうが圧倒的に長い。
我々は近代以前のことをあまりにも知らなすぎるのだ。。。
そのエビデンスとして取り上げられるのが、人類学・考古学。さまざまな人類学的考古学的知見を取り上げ、考察していく。デヴィット・グレーバーは、人類学者、デヴィッド・ウェングロウは考古学者である。
ただ、この本を「今までの歴史観に対して、前近代とされていた部族や民族も優れていた面があるから、現代に生きる我々は前近代とされていた彼らからも学ぶべきものがあるのだ」的な見方でまとめてしまうと、この本の面白さはまだ半分だと思う。
この本は、もっと壮大にひっくり返そうとする。我々の中で、常識とされている歴史の全体像は、事実とは何の関係もないことを示そうとする。
その概念の大転換は、グレーバーとウェングロウの数十年の長期間にわたる研究が裏付けとなっている。
人類史のほとんどは、闇に埋もれてしまっているのだ。
それにしたって、長い(笑)。
2月に読書会がスタートして、2~3週間おきずつ、2章ずつ読み進め、昨日やっと最終回までたどり着いた。
この2章ずつ分割して読み、読書会をしながら進む、という読み方が本書については有効だった。
というのも、著者たちは、序盤、壮大な問いを発し、風呂敷を広げ続け、それでいて、なかなかに核心的な部分をどんどん引っ張るのである。
例えば、第1章のラストはこんな記述
ルソーのようなヨーロッパの思想家からは完全に袂を分かち、むしろ、かれらにインスピレーションを与えた先住民の思想家に由来をおくパースペクティヴを検討しようと決めたとき、わたしたちのやりとりのなかで、真のブレイクスルーが訪れた。
第2章の最後
しかし、わたしたちにはもはや、あらかじめ答えをもっているなどとうそぶくぜいたくにふける余裕はない。カンディアロンクのような先住民の批評家にみちびかれながら、人類の過去の証拠に新鮮な目でもって取り組む必要があるのだ。
第3章の最後
ところが、謎がある。何千年にもわたってヒエラルキーの構築と解体をくり返してきたというのに、最も賢い類人猿とされる「ホモ・サピエンス」が、なぜ永続的で御しがたい不平等のシステムを根づかせてしまったのか。
中略
わたしたちがいま直面しているのは、こうした問いである。
第6章の最後
これらのことから、必然的に疑問が浮上してくる。農耕の導入は、人類――あるいはすくなくともその一部――に、暴力的支配から距離をおいた歩みの可能性を与えた。とするならば、いったいどうしてそれがおかしくなったのか?
第10章の最後
これまで知られていなかった場所に大規模な集落や印象的な構造物があるという証拠が年々蓄積されていく。それにつれて、わたしたちも賢明にならねばならない。すなわち、それらの裸の表面に現代的国民国家のイメージを投影することに抗し、それらがひそかに語っている別の種類の社会的可能性を考察しなければならないのだ。
実は、第10章まで読んでも(全12章)、「真のブレイクスルー」って結局なんやねん!となる(笑)。
これは、一人では絶対に読めなかった。
2章ずつ読んでいって、「真のブレイクスルー」って何なんだろう、一体何なんだろうと言いながら読み進める。まだ書いてない、うーんはっきりしない。次の章で書いてあるんですかね。10章まで来て、うーん、「国家」っていう考え方自体がおかしいのはわかった、うん、それで「真のブレイクスルー」って結局何なんだ。
で、第11章のタイトル
第11章 ふりだしに戻る
なんやねーんwww
4か月近くグレーバーたちに翻弄された。
しかし、第11章にフリガナとして伏せられたサブタイトルは「フルサークル」だったのだ。
そう、実はこの構造自体にヒントがあった。
そして、
第12章 結論
第12章ではじめて、「万物の黎明」というフレーズが出てくる。最終章ではじめてタイトルを回収するのだ。
ここで「直線的時間」という言葉が出てくる。歴史はどこかに向かっているという考えから、過去から未来へ流れていく時間の流れの中で、歴史的事象が蓄積していく。累積的に連続しながら展開するという「歴史的」考え方である。
あるいは、比較的最近(近代)になって、人類社会が最終的に均衡状態をみいだし、そこに落ち着き、あたらしい状態を正当化するための共通のイデオロギー的枠組みをひねりだしたのだ、つまり、現代の「伝統的」な考え方は比較的最近に見いだされたのだとする考え方がある。
このどちらの考え方も、不条理であると著者らはいう。
では、何なのか?
「万物の黎明」とは何だったのか?
私が、そのことにちゃんと気が付いたのは、最後の二行だった。
(もっとしっかり読んでいればもう少し早く気が付いたのかもしれない)
結局、私は、著者らの掌の上で、踊らされていたのかもしれない。
彼らの遊戯に乗せられていたのかもしれない。
それ自体が遊戯だったのかもしれない。
4か月間700頁の壮大なちゃぶ台返し。ひっぱられてひっぱられて、付きあわされて、グチグチ言いながら一回振り出しに戻らされて、最終的に、著者の手のひらのうえで踊らされていたかもしれないと気づく(笑)、それはある意味で、著者らが仕組んだ人類史を根本からくつがえす壮大な仕掛けにまんまとハマったということなのかもしれない。
そしてある意味で、本書の結論からすれば、この構造そのものが彼らのいいたいことなのかもしれない、そんな気すらしてくる。
でも、それにしたって長い(笑)。
この読書体験は、読書会形式じゃないと絶対に味わえませんでした。
値段高いし、長いし、ちょっとムカつくけど(笑)面白い本だと思います。
浜松オンライン読書会さん、ありがとうございました!
ということで、人類史を根本からくつがえして、「今日一日を最高の一日に」
