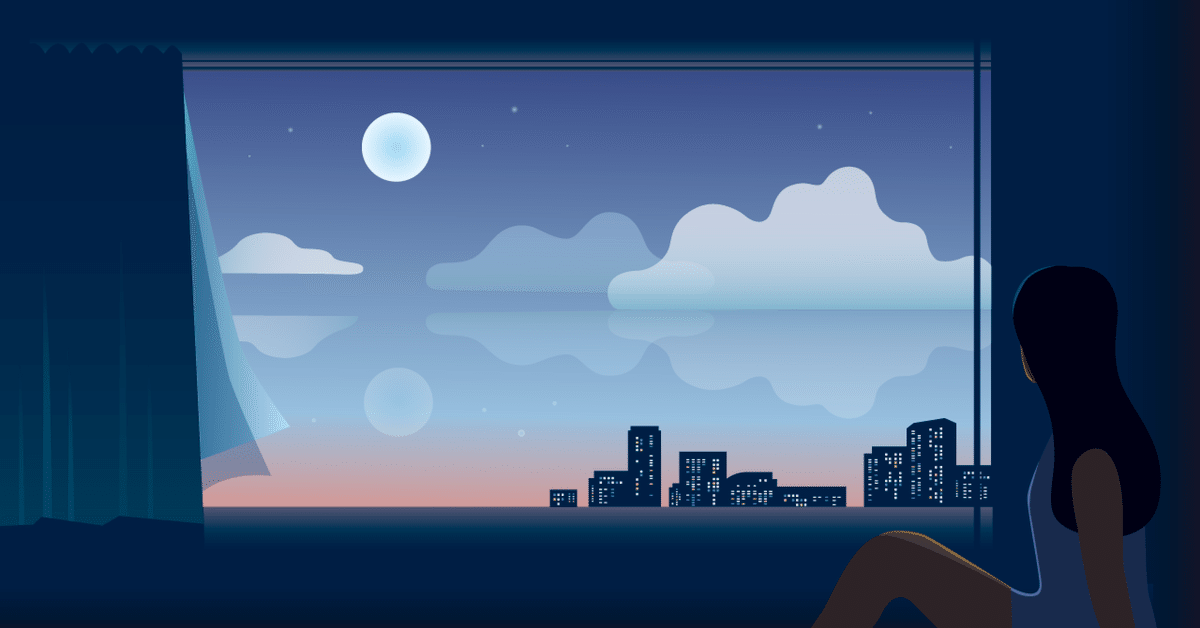
日本の人材の未来はどうなる? ー 未来人材ビジョン(経産省)から考えてみる
働き方改革。人生100年時代。LIFE SHIFT。FIRE。
働き方に関する話題を毎日のように目にします。
本屋さんに行っても、仕事術や働くことに関する本が特設コーナーで目に飛び込んできます。
この記事では、人材の未来について日本で提言されている内容とそこから私自身がどう考えるかを紹介したいと思います。(この記事はあくまで個人の考えを述べたものです)
簡単ですが、自己紹介を。
LAPRAS株式会社という転職や副業などの仕事面でエンジニアと企業をマッチングするサービスを提供しているITスタートアップで広報・PR、toBマーケなどをやっています。
日本が考える未来人材ビジョンとは(未来人材会議)
経済産業省で未来人材会議なるものが2021年12月から2022年4月まで計5回されているのをご存知でしょうか。
本会議の委員会メンバーは、
DeNAの南場さん、日立製作所の東原さん、人口流れ星で有名なALEの岡島さんなど大企業からベンチャーまでの実業界のリーダーに、東京大学の教授などを加えた方々。
日本として人材はどのようにあるべきか、そんな未来人材ビジョンがこの会議で議論されました。
国としてどんな課題を持っているのか、どんな方向性を検討しているのか。
ここからサクッと5分で読めるようにポイントをお伝えします。
こちらの記事でも紹介されていますのでご参考にどうぞ。
https://project.nikkeibp.co.jp/HumanCapital/atcl/column/00057/031700007/
ちなみに、この話を今の会社メンバーにしたら、とっても空気は重くなりました。笑
なぜなら、「日本の人材の未来は真っ暗やん。」的な感じになるからです。
ただ、最初に断っておくと、それだけ日本の危機的な状況を示していると私は受け止めています。結局人材の未来を明るくするか、しないかは私たち一人ひとりの意識と行動次第と思っているので、この内容を聞いて何か考えるきっかけになればそれでいいと思います。(偉そうなことをなんか、言ってますね。。。)
2050年に事務職の4割減少、IT技術者が2割上昇
このレポートの中で2050年の業種・産業別の労働需要が発表されています。
いくつかメディアも取り上げていますが、数字だけ見ると「事務職は半分近くなくなるのか。」と思ってしまいますが、それは少し表面的すぎます。
まず、この前提としているのが、DXや脱炭素が進んだ場合の高成長シナリオをもとにしていることです。2050年までに日本でDXや脱炭素が急激に進むか、正直かなり微妙な印象を持っています。(私たち世代が進めていかないといけないのですが…)
さらに、事務職とは具体的に何の職種を指すのかが明確に読み取れないことです。(私の読み方が浅いだけかもしれません)
現在の一般的な経理などオフィスで仕事をする人を事務職に当てはめたとしたら、デジタル化や自動化に伴って人がやる作業は減るかもしれませんが、その代わりに新しい仕事が増えます。
例えば、SaaS企業におけるカスタマーサクセス職はデジタル化のソフトウェアビジネスによって生まれた職種の一つだと思います。
このような新たな職種が生まれていくので、一方的に悲観する必要はないと思います。
人材に求められる能力が大きく変わる
この未来人材ビジョンでは、2050年に求められる能力が変わることが示されています。

これまでは、「決められたことを正確に素早くできること」が求められていましたが、今後は「何をやるべきかを定められる能力」が求められると言えます。これだけ世の中の不確実性が高まり、私たち生活者の価値観も多様化する背景を反映した結果ですね。
ただ、ここでも注意したいのが、「信頼感・誠実さ」といった人間性は大前提必要で、今よりも重要になると思っています。
100%正しい予測することは誰しもが不可能な中で、何かを進めていくためには、「この人が言うんだったらちょっとリスクはあるけど一緒に頑張るか!」と思ってもらえる必要があると思うからです。
問題発見を重視するがあまり、口だけの「問題指摘野郎」にならないように気をつけないといけないと思います。このポイントがこの結果からだけだとミスリードしそうですね。
日本型雇用システムの限界

終身雇用などの日本型雇用システムが限界ということはすでにこれまでも示されていますが、この中ではさらに具体的に以下のことが示されました。
(詳しくは資料のP33〜40あたりをご覧ください)
日本企業の従業員エンゲージメントは、世界全体でみて最低水準にある
世界と比べても日本は「現在の勤務先で働き続けたい」と考える人は少ないし、「転職や起業」の意向も少ない。
かといって、企業は人に投資せず、個人も学ばない。
どう思いますか?
なんかもう、どよーんとしてきませんか?笑
(会社で話をしてて、この辺りがかなり暗い感じになりました…)
しかし、モノは捉えようということです。
限界にきているけど、変わっていないということはそれだけ根深い問題なのだと思いますが、それでもコロナによって外的な大きな力が働き、今は変わろうとしています。
なので、この雇用システムを20年後に変えることができたら、未来は明るくなるのではないかと。少なくとも今の会社ではその一躍を担うべく頑張っているのですが、他にも様々な取り組みをやっている会社や個人がいます。
根深いからこそ経産省も変えようとこのような会議での悲観的なレポートを出してくれているのだと捉えたいと私は思います。
企業の人材戦略の指針「人材版伊藤レポート」
社会の仕組みとして大企業の影響力は大きいものです。
コーポレートガンバナンスを企業に浸透させたことで有名な一橋大学の伊藤教授が作成した「伊藤レポート」。
その人材戦略版である「人材版伊藤レポート」が、2020年9月に経済産業省から発行されました。

このレポートでのポイントは、動的な人材ポートフォリオによる人材の流動性の向上です。
簡単に言うと、一つの組織で働き続けるのではなく、将来を見据えて組織を出たり入ったりして人材が経験やスキルを積み、価値を高められるようにするということ。
そのために、学びの仕組みや時間や場所にとらわれない働き方といった環境や制度が必要ということが示されています。

ここで重要になるのは、この図式には現れてこない「人の心理」だと思います。
働き慣れた環境を出ることや、新たなことにチャレンジすることに対して人は不安を覚えます。私自身、昨年に人生で初めての転職をしましたが、不安がなかったかといえば嘘になりますし、やはり慣れるには相当のエネルギーを使います。
そんな不安を解消したり、不安にさせない仕組み作りも必要だと思います。それは転職や副業が当たりまえとして受け入れられる社会の空気感もありますし、転職の新しいあり方も必要かもしれません。
この人材版伊藤レポートは、特に組織規模の大きな大企業を対象に書かれているもので、大企業が変わらないといけないと言う課題感が伺えます。
しかし、まだまだ実践には遠いような状況です。
そこで、2022年5月に「人材版伊藤レポート2.0」が発行されました。
2.0では、具体的にどのように実践すればよいか、実践方法の指針と企業の事例などが発表されました。
ここでも少し私なりの意見を言うとすると、事例が出ているとは言え、まだまだ変わっていないということです。
前職は大企業だったので非常によくわかりますが、大企業の従業員の平均年齢は40オーバーのところが多いです。旧来の日本型雇用システムで生きてきた人ばかりの組織です。その層が中心の組織を変えていくことは相当な難しさがあります。
好事例の裏には失敗事例や解決できていない課題が山ほどあります。
少しずつではあるけれどいい方向に変わることを期待しています。
(今は私はスタートアップという位置から、大企業や社会の変革を生み出す作用を作ることでチャレンジをします。)
まとめ
経産省の未来人材ビジョンでは、現状の危機感がまとめられた内容になっていました。日本の雇用システムの限界や大企業への変革の指針も示されて徐々に動きつつあります。
私が感じるのは企業の変革以上に、人々の働き方や価値観の多様化のスピードの方が早いということです。
今のままではダメだということがコロナによって分かったり、リモートワークが当たり前になったりして、一気に変化のスピードが加速しました。
キャリアについての価値観の変化も加速しているように思います。
私の前職の人事役員はシンガポールにいる外国人でしたが、ずっと心に残っている印象的な言葉があります。
「自分のキャリアの責任は自分自身だ。
会社を選んでいるのは自分自身。会社が何かをしてくれるんじゃない。自分のキャリアの責任は自分で持ちなさいと。」
会社に過度に期待するのではなく、悪い会社を変えるのか、違うところで働くのか、自分のキャリアを考えて自分で選択せよということでした。下記の記事でも似たようなことを紹介されていたので、キャリアに対する日本人の考え方はちょっと独特なんだと思いました。
これまでは会社が人を選ぶ時代でしたが、個人が会社や選ぶ立場に変わってきています。
そんな変化の背景を考えると、企業が人材戦略やシステムを刷新しないといけないのと同時に、働く私たち自身のマインドセットを変えることがとても大切なんだと思います。
未来人材としてどんな人材を目指すのか、誰も正解を持っていない中で大事なのことは自分がどう考えて行動するか。
これまでの常識と社会通念に縛られすぎずに自分の頭で考えていきたいなと思いました。(なかなか難しいけど)
今回はちょっと固い話でしたが、
最後まで読んでくださりありがとうございました!
何かを考えるきっかけになれば幸いです。
