
不登校の子どもが歩む段階とそのサポート方法
おこのみ会代表の国賀です。
私は愛知県安城市で不登校の小中学生と親の居場所『おこのみ会』を運営しています。
不登校を経験する子どもたちが社会的自立にたどり着くまでには、多くの段階があると言われています。
今日はその段階についてお話しようと思います。
すべてのお子さんがすべての段階を経験するわけではありませんし、かかる時間も人それぞれではありますが、見通しが立つことで少し周囲の大人も冷静に対処出来るのではないでしょうか。
子どもは各段階を行ったり来たりしながらも、自分のペースで成長していきます。
不登校の子どもが歩む段階
第1段階:登校不安期
子どもの状態
登校に不安を抱え、行き渋りが見られる。
普段に比べて元気がない。感情の波が激しい。
不安を口にする。
体の不調、朝起きられないなどの症状が続く。
対処法
子どもの出すサインをよく観察しましょう。
子どもの話を聴く。(否定も肯定もせずアドバイスもしない)
不調が出ていると感じる場合は休息を取ることも必要です。
家庭や学校外で安心できる居場所を作ることも重要です。
学校の先生に相談をし、不安を和らげる方法を一緒に考える。
第2段階:不登校開始期
子どもの状態
完全不登校に移行することが多い。
怒りや悲しみを爆発させる場合がある。
家族への依存や周囲への反発が強まることも。
外出、人と会うことを拒む。
何事をするにも不安が増す。
対処法
無理な働きかけを控えましょう。
休息を取ることを優先させましょう。
必要に応じて専門機関やカウンセリングを利用することも有効です。
第3段階:エネルギー補充期
子どもの状態
エネルギーが低下し、何事にも意欲が湧かない状態。
ゲームやYouTubeなどに対する依存が高まる。
朝起きられず、外出や人に会うことを嫌がることが多い。
部屋で過ごす時間が増える。
食事や入浴などへの意欲が低下し、拒否することが増える。
昼夜逆転が見られる場合もある。
対処法
ゲームやYouTubeなどへの依存や昼夜逆転は辛い現実からの逃避行動と理解する。一見すると「怠けている」ように見えることも。実際にはエネルギーを蓄えるための重要なプロセス。
生きていることで精一杯で、必要最低限のことしか出来ないことを理解する。
子どもが安心して過ごせる環境を整える。
学習や外出を強制せず、子どものペースを尊重することが大切です。
第4段階:再活動希望期
子どもの状態
「何かやりたい」という気持ちが芽生え始める。
「暇だな。〇〇しようかな」などの発言が出てくる。
友だちと遊びたいなどの欲求が芽生えるが、実際に行動に移すことにはまだ不安がある
対処法
親としては希望が見えてくる時期ですが、焦りは禁物です。子どもの発言や行動を受け止め、必要以上にプレッシャーを与えないようにしましょう。
やりたいと思っても実際には出来ないこともありますが、やりたいと思えたことを評価し、自ら動き出せるまでじっくりサポートすることが大切です。
第5段階:リハビリ期
子どもの状態
不安定ながらも、学校や学習活動に少しずつ参加するようになる。
学校以外の居場所に通う頻度が増える。
やりたいことが増え始める一方で、疲れやすい状態が続く。
対処法
子どものペースを尊重し、無理に日常に戻そうとしないことが大切です。
短時間登校、放課後登校など本人の不安に寄り添った無理のない範囲の学校との関わりを探る。
学校以外にも選択肢を広げ、柔軟に対応しましょう。
第6段階:社会復帰期
子どもの状態
学校や学習活動に安定して参加できる。
社会的な繋がりを築き、活動範囲が広がる。
自立心が芽生え、日常生活を安定して送れるようになる。
将来の目標や希望を描き始める。
対処法
『社会復帰』とは必ずしも『学校復帰』とは限りません。自分に合った学びの手段を理解し、選び、自分なりに社会と繋がって生きることが大切です。
危なっかしい場面もありますが、本人の意思を尊重して見守り、つまずくことがあればサポートするよという姿勢を示すことが大切です。
不登校の子どもを見守るということ
この段階を知ることで、うちだけじゃないんだと気づいたり、少し先の子どもの段階を知ることが出来て安心する方もいらっしゃると思います。
またまだこんなに段階を踏まないといけないのかと途方に暮れる方もいるかもしれません。
今のお子さんの様子を見ていると次の段階が来るなんて想像もつかないという方もいらっしゃるかもしれませんね。
親御さんとお話をしていても、親御さんの様々な葛藤が見受けられます。私自身も同じ思いを経験しましたので、共感しかありません。
しかし多くのお子さんを何年も見守り続けていると、多くのお子さんがこの段階を辿っていることに気が付きます。
多くの場合1年~数年という長い時間をかけてゆっくりゆっくり進んでいきます。
特に第三段階のエネルギー補充期は長期化することも多く、先が見えないと感じる時期でもあります。
目に見える成長を感じられない時期でもあるので親御さんは不安になりますが、目に見えないだけで、エネルギーを蓄えているのです。
息子が不登校になり、先が見えなかった頃、不登校児の子育て経験のある先輩ママさんに声をかけてもらいました。
「今は成長してないように見えるかもしれないけど、今は地面の下で根っこを張っている時期なんだよ。じっくり時間をかけて根っこを張った子はその後大きく成長するし、とても強いんだよ。」
その時はそうなんだと励まされる反面、それってうちの子にも当てはまるのかなと半信半疑でもありました。
でも実際その後の息子の成長をみて、あの言葉は確かだったと実感しました。
子どもの成長は一定ではありません。周りの子どもたちと一緒とも限りません。その子なりの道で、速度で、必ず成長していきます。
『不登校の子どもを見守る』ってどういうことなんだろうと考えたことがあります。
私は『この子は大丈夫!』と信じるということだと思いました。
そこに根拠なんてありません。
でもただ子どもの成長を信じる。
そして子どもと一緒に自分(親)も成長していけると信じたことも前を向くきっかけにもなりました。
人と違う道を行く子どもたちを支えることはとても忍耐力のいることです。
しかし、必ず乗り越えた先には親子ともに成長し、自分らしい道を見つけていけると思います。
次週は葛藤を抱えた『不登校児を支える親御さんの歩む段階』について記事にしてみようと思います。
【応援会員募集中】
不登校の子どもたちに安心できる居場所を!
おこのみ会の活動を応援しませんか?
あなたのサポートが子どもたちの未来を支えます!



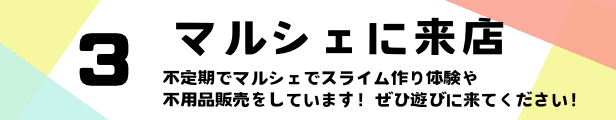



いいなと思ったら応援しよう!

