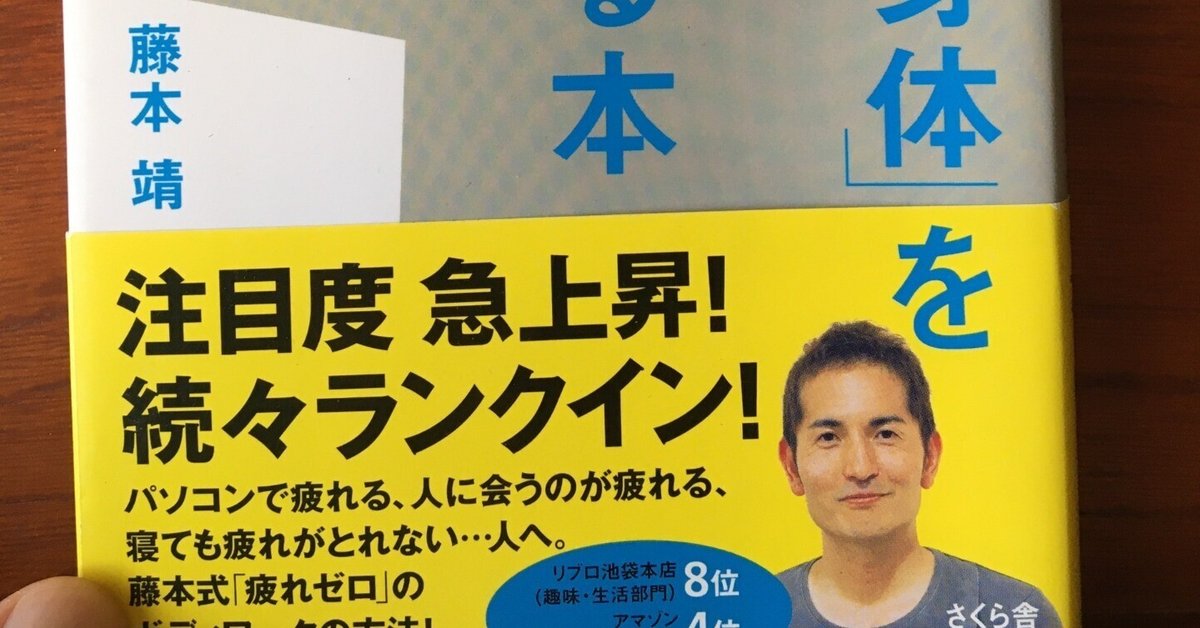
#121『疲れない身体をいっきに手に入れる本』藤本靖
なかなか興味深い。本書はボディケアの観点から書かれている。食事や生活習慣などではない。で、普通この種の本だと、姿勢の話になるし(当然)、そのためには骨盤とか歩き方とか、そちらの方に話題が進む。つまり「こう体を使うのですよ」と。
しかしこの本は面白いことに感覚器の方から入る。つまり五感である。
例えばだが、
・見ようとすると前傾になる。
・聴こうとすると後傾になる。
…ほんとだ!
多くの本は「自分の意識の働きかけによって姿勢を整える」という発想である。本書は「外部からの感覚によって姿勢が影響される」という発想。ここが面白い。
現代社会は視覚情報過多なので(まあ、昔からずっとそうだが)、どうやら音楽を聴くことや自然音に耳を傾けることによって私たちは本能的にバランスを取ろうとしているのだろう。自然の叡智である。
また、頭蓋骨の中心には蝶形骨があるが、これが関係してくる。
嫌な話を聞かされると耳が緊張し、そして蝶形骨が緊張する。
目を酷使すると目が緊張し、そして蝶形骨が緊張する。
更に、共に「内臓空間」に属する蝶形骨は、横隔膜と繋がっている。
横隔膜は呼吸に関わっているので、横隔膜が緊張すると呼吸が浅くなる。
以前、自分の歌唱の問題で色々調べていた時、蝶形骨ー横隔膜の連動を学び、これを自身の幼少期の心の傷と繋げて理解することが出来たのだが、今回の本では物理的な方面からよく理解できた。
また更に内臓空間の最後は骨盤底であるので、これにより視聴覚の影響がいかに全身に及ぶかということが分かってくる。
それでその緩め方が紹介されているが、ざっと説明すると、
・耳を掴んで優しくぐりぐり。
・目を指を当てて優しくごろごろ。
そんな感じである。
感覚器の緊張から全身が緊張するので、逆に言うと感覚器を弛緩させると全身が弛緩する。
そのための方法が色々紹介されているのだが、私的にそこはスルー。世の中には体マニアの人がいるが、著者はそんな感じの方で色々細かい。私は真逆なので、「なるほど」と分かって自分なりにほぐしていこうと思う。
更に嗅覚も。
実際に匂うかどうかではなく、嫌な人とこれから会うと思うと、本能レベルの反射として鼻にある鼻根筋が緊張し、しかめっ面になる。#110『脳にいいことだけをやりなさい!』に書いてあったが、しかめっ面をすると免疫機能が低下し、鬱に対する抵抗力も下がる。
総評としては、感覚器ー蝶形骨ー横隔膜(ー骨盤底)ー自律神経という影響関係の流れが新しい視点だった。言われてみればその通りだし、だから心地よい音をいつも聞くようにしたりとか、自然と気を付けている。しかし肉体の内部ではこういう連結があったのかと知れたのが面白かった。ますます趣味や波動の悪いものを遠ざけ、良きもの美しきものに触れていきたいものである。
このように繊細な内部プロセスを表現している著者なので、逆にその繊細な部分が、本の全体性や読者の需要に対して障子一枚隔てているような印象を持たせる。なんというか、スピリチュアルに向かおうとしてドアノブに手をかけかけているフィジカルというような感じ。著者はどこに向かっていくのだろうか?
もう少し一気に踏み込んで禅僧とかになった方が更に説得力が出るのではないかと思えた。何となく、そんなお顔つきだし。
その他引用。
・横隔膜が固まると上半身・下半身が分断、呼吸が浅くなり、交感神経優位、緊張する。
