
ちと個性的な23年の大学入試共通テスト英語読解解説(大問4)
★連絡先
メールでの連絡先は、
Twitterアカウントは
YouTubeチャンネルは
ココナラのオンライン家庭教師は
23年の大学入試共通テスト英語(読解)の独自解説・第4問編です。1~3番もご覧になりたい方は下の画像をクリックしてください。今回も自分が生徒にこの問題を解説する場面を想定しながら文章を綴りました。
どういうわけか、家庭教師として英語を教える場面が今季は非常に少ないので、ブログでは英語の記事を意図的に多くしています。

第4問
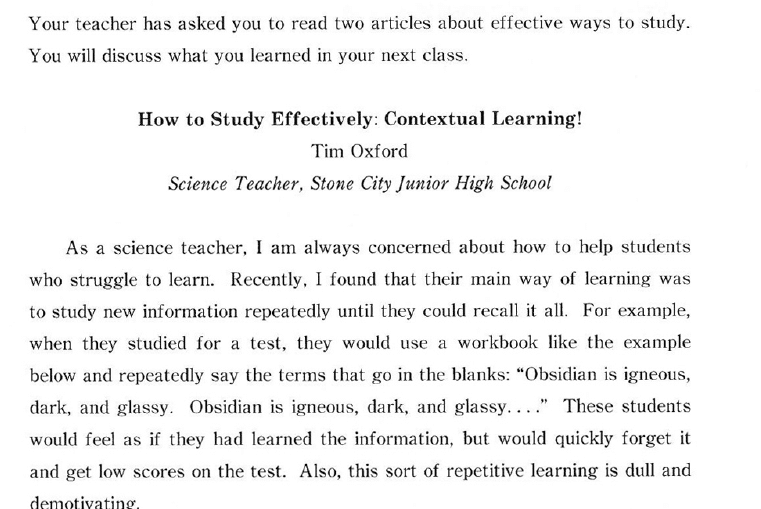
Obsidian is igneous, dark, and glassy.
obsidian: 黒曜石
igneous:火成岩の
obsidianという英単語は私も知りませんでした。黒曜石といえば鏃(やじり)で有名ですね。非常に切れ味がよいので、現代でも繊細な手技を必要とする外科手術に用いられることがあります。
手術用のマルテンサイト系ステンレス鋼のメスでも、金属製の刃物のブレードを顕微鏡で拡大してみると刃先に凹凸が確認できるが、黒曜石のブレードの刃先は滑らかだ。また、黒曜石のようなガラス製ブレードは、刃先も金属製ブレードより薄くできる。
ーーー石田雅彦「縄文人は『黒曜石』で外科手術をしていた?」
また、igneousは火成(岩)のという意味ですが、語源のignisはラテン語で炎を表します。車のエンジンの点火装置をカタカナでイグニッションといいますが、ignitionもこれの類義語にあたります。
さて、この問題のテーマは「効率のよい学習法について」です。前半では理科教師のTim Oxford氏がContextual learningについて述べています。この先生は味気ない問題集を繰り返し解くのではなく、新しい知識を生徒自身の経験や体験に結びつけるような授業を試しに行ってみたそうです。具体的には生徒に岩石を配って観察してもらい、その特徴を白紙に書き込むという作業を課したとのこと。ただ、問題点として、こういう学習法をずっと実施する時間が常にあるというわけではない点が指摘されていました。
こうした「学習における身体性」は、実は最近になって再び注目が集まっているように感じます。本の手触り、厚み、紙の質、部屋の香り、椅子の座り心地……。人間は脳だけを使って何かを学んでいるのではありません。実は五感をフル動員しています。
「歴史における身体性」は、人々の問題関心から長らく忘れ去られていました。そこに注目して、過去のにおいや音など、感性の面から歴史を再構築する試みが1980年代から盛んに行われるようになりました。

私も中学生の頃、「技術」の学年末試験の前夜にどうしても暗記できない箇所があり、夜中に寒い中外に飛び出して街頭の下でガチガチ震えながら丸暗記したことがあります。どういうわけか、その時に覚えた内容は未だにかじかんだ指先の感覚と共に今も脳裏に焼き付いています。
Oxford先生が指摘するように、身体性と紐付ける学習法はおそらく非常に有効ですが、教育現場ではそれを実践する時間がたっぷりあるわけではないというのが最大の問題ですね。
後半ではStone City UniversityのCheng Lee教授がspaced learningの有効性について議論しています。Lee教授は実験データを元に、一気呵成にまとめて学習するよりも、少し時間をおいてから復習する方が、記憶が定着しやすいと主張しています。
これを読んでいて思うのは、大学のセメスター(ゼメスター)制の弊害です。私が大学生の頃は通期授業がほとんどで、4月に講義を選択し、夏と冬を経て学年末テストを1月に受けるという形式でした。
ところが今の大学では半期授業が一般的になっているようです。セメスターの方がより多彩な授業を選択できるというのが売りのようですが、私の経験では、やはり通期で受けた授業の内容の方を今でもよく覚えているように思います。それもまたspaced learningと関係があるのかもしれません。
昔から教育産業でよく引用されるのが、「エビングハウスの忘却曲線」ですね。何かを覚えて一日経過すると、人はかなりの部分を忘れてしまうので、繰り返し復習しないと定着しないっていうやつです。

この忘却曲線が表しているのは、「覚えた単語を後日どれだけの割合で覚えていたか」ではなく、節約率すなわち「ある単語を初めて覚えるまでに書き取りが必要だった回数に対し、それを翌日思い出すまでに必要だった書き取り回数の割合」である点に注意して下さい。例えば、初回Xという単語を覚えるのに100回の書き取りが必要で、翌日それを思い出すのに10回の書き取りが必要なら、節約率は90%になります。
ここからは語彙やフレーズをいくつか確認しておきましょう。
As a science teacher, I am always concerned about how to help students who struggle to learn.
be concerned about ~:~を心配している、懸念している
これは私が英語を教えるときにしばしば「懸念のabout」と呼んでいる前置詞です。worry about、be anxious about、be uneasy aboutなど、枚挙にいとまがないです。
Mr. Oxford's thoughts on contextual learning were insightful.
insightful: 洞察力に富んでいる
これはStone UniversityのLee教授による文章です。大学教授があなたの作品を評価するとき、まず褒め言葉から入ったときは、身構えなければなりません。私も何度も経験がありますが、これは「今からけっこうきついことを言うからね」という符丁・枕詞なのです。実際、この下の部分にOxford先生への批判が出てきます。
さて、接頭辞のin- / im-は「でない」を意味すると覚えている人はいませんか? これは中学校の初期で学習する「possible / impossible」の関係が多分に影響しているように感じます。「sane / insane」「active / inactive
」「finite / infinite」も接頭辞のinが否定を表しています。
しかしながら、insightful、ingeniousのように、inは「中」を表すこともあり、このパターンの単語も意外と多いです。include、inherit、inhaleなどが挙げられます。
調べてみると、否定を表すin-と中を表すin-は語源が異なっており、フランス語でもドイツ語でも接頭辞in-が両方の意味を持っているようです。
Wikipediaの説明も参考になります。

共通テスト英語読解の解説は4番だけでけっこうな分量になってしまいました。問題や文章の内容・設問そのものは、おそらく赤本や黒本といった過去問集が詳しく解説してくれると思うので、私はこちらのブログで自分が授業するときに付け加えたい話をメモ代わりに書き留めておくことにします。
連絡先
メールでの連絡先は、
oitatutor@gmail.com
Twitterアカウントは
YouTubeチャンネルは
ココナラのオンライン家庭教師は
