
アートコレクター冒険譚 ② -所有者ができること・できないこと-
親愛なる芸術愛好家の皆さま、ごきげんよう。YORU(大久保亞夜子)でございます。このエッセイは、アートコレクションにまつわる内容を、私が美術品を買い始めてから現在までの、作品所有の基礎知識やマナー、トラブル予防、先人達の知恵、実体験の記録を織り交ぜて公開する試み。どうぞお側に置いてお役立てください。芸術を愛するあなたの魂に、巡る季節の女神たちHōraiの響きがあらんことを…
前回はこちら▼
本日のテーマ「コレクターになったらコレだけは押さえたい!」
まずここさえ押さえておけば、大抵のトラブルは回避できる!と思われる、身近なトラブルに特化した部分に絞っていきます。それ以外は専門家の助けが要るイレギュラーな問題 (※1) です。その際は法律の専門家に相談しましょう!それでは、順に押さえていきますね。
⚫︎ 作品を所有したら「できること」


はい、上記2つの内容は、とても身近ですね。
これらは著作権者の許諾を得ずに著作物(作品)を利用できます◎
《著作権法で定められた例外は、他にもあります》
著作権を制限する規定という、著作物の公正な利用を図る趣旨によって、上記以外にも許諾なく利用出来ることがあります。更に学びたい方は、こちらのページ内「著作権法で定められた例外」 が分かりやすいかと思います。
⚫︎ 作品を所有したら「事前許可が必要なこと」

(著作権法第2条9-4)

(著作権法第2条9-5)
実はこれ・・・!無意識にやってしまっているという方、いるかもしれません・・・。最もグレーに染まりやすく、体感値として近年トラブル増加中だと感じるのが、この上記2つ。著作権譲渡の契約がない限り、作品を所有しからといって撮った写真を「公」にはできません。公衆送信(著作権法第23条)に該当し、公開するには著作権者の許諾が必要です!許可を得て公開しましょう。インターネット時代に、もっと周知されてもいいマナーです。
できれば売買のタイミングで許諾をとってしまう事がスマートです。後日、メールなど文面で残るかたちで確認を行っても良いと思います。近年私は購入の時点で「SNSやWebなどで作品画像を掲載しても良いですか」と併せて聞くようにしています。
⚫︎ 作品を所有したら「権利があっても、配慮した方が良いこと」 "修繕"

大変!作品が破損してしまった……?!
そんな時、ご自身での修繕は選択肢から外しましょう。異なる手法やメディウムが選定された場合、作品の価値を毀損してしまう恐れがあるためです。故人の作品も含め、購入時に修繕案内がなくて困った時は販売者に問い合わせるのが第一の選択肢と思われます。よほどの経緯や状態でない限り、相談を門前払いするギャラリーや作家は極めて稀です。
私は一度、修繕を依頼した経験があります。
5年前、石灰を使った特殊な技法の絵画を購入し、棚に飾っていました。ある時、強い地震の振動で絵に大きなヒビが入ってしまい、修繕が必要な状態になってしまいました。購入時に修繕案内はなかったので、まずは作品の状態を写真に撮り、ギャラリーに相談。作家自身も技法による脆さを懸念していたとの事で、作家さんがすぐ修繕対応を行なってくださいました。この時は無償で対応いただきましたが、金銭面に関しては必ず確認して進めた方が良いかと思います。
《美術品の貸与リスクと保険事情》
コレクターとして所有作品の貸借の打診があると、文化貢献にもなって嬉しい機会ですよね!でもまず確認したいのは、貸出中に破損した時の責任の所在です。私は過去2度ほど中規模以下の展示で破損トラブルと実際のクレームの現場を目にしたことがあります。いずれも余談となりましたが、事故率が高めなので特筆しておくべきでしょう。
まず、[貸出先の展示実績が初回・或いは不明 / 責任者の所在が不透明]な場合は注意してください。 小規模展示などの場合、保険に入っていない事が多いため、保証もなく余談となるケースがあります。先方とよく相談し合い、万が一破損があった場合はどうするかを先に決めておきましょう。破損の恐れが高い作品を貸し出す際は、ご自身で充分リスクを加味して貸し出しを判断するのが賢明です(例: 展示中の破損 / 輸送中の破損 / 直前に撮った証拠写真には破損が見られないが、梱包した方法が悪く、到着までに破損した、など)。もし不安があれば、貸し出す義務はありませんし、展示主催者となる場合にもこれらのリスクが伴うことを考慮すると安全です。
昨今は個人で美術品に保険をかける方もいらっしゃいます。美術館など大規模な展示作品に保険をかけるのは国際的な慣行となっていますが、「大丈夫だろう」と鵜呑みにせず、貸し出す際は担当者に確認を行なってください。
⚫︎ 作品を所有したら「権利があっても、配慮した方が良いこと」 "売却"
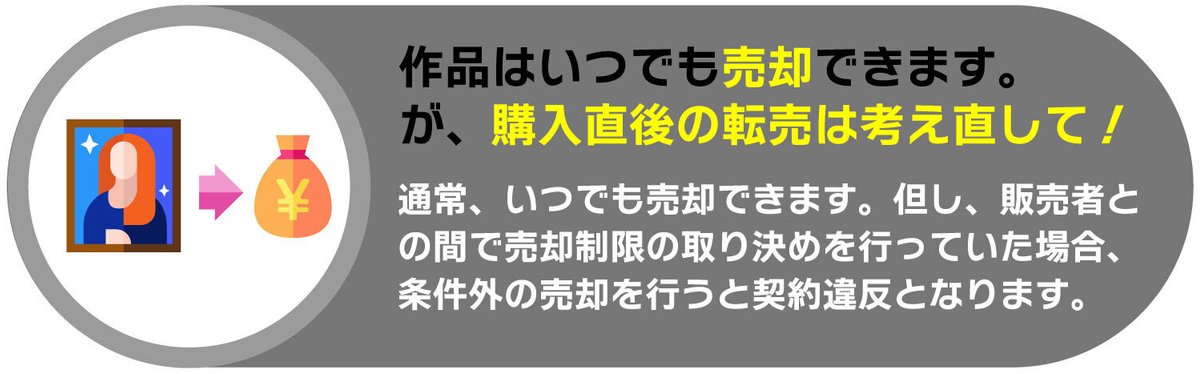
世界中で問題視されている、現代アート作品の転売問題…….。
「え?所有者の当然の権利じゃん。いつ売却益を出したって違法性は無い」という主張は確かに正論です。しかし、業界にとって購入直後の転売行為は作家やギャラリーを苦しめる頭の痛い問題なのです。それは何故なのか。
⚫︎ 安易な転売は・・・どうぞお控えください!!
転売(売却)は所有者の正当な権利です。
では即転売の何が問題か。その行為が引き起こす懸念は主に2つあります。
・価格が急に跳ね上がると、若手作家の場合は活動寿命を縮めてしまう
・転売者はブラックリスト行き(美術業界は噂が広まるスピードが早い)
美術の世界でのプライシングは、ゆっくりとセカンダリーに出回ることで作家の相場が市場の中で少しずつ定まっていき、価格も少しずつ上昇していくのが理想とされます。
なぜゆっくりの成長が望ましいのか。
ここには二つの観点があります。
①プライマリーで値付けされた価格基準は、簡単に下げることが出来ない
②作家の成長と共に、ファンとしての質の良いコレクターが育ちやすくなる
例えば。ある転売ヤーが売った作品がオークション等で爆騰し、短期間で著しく注目度が上昇したとします。すると、投機目的のコレクター或いはその層を狙ったビジネスが美術作品を金融商品として注目し始めます。売れば絶対上がるとわかっているため、新作発表では更に転売される確率が上がります。プライマリー・プライスを決めるギャラリーは、転売を抑止するためにもセカンダリー・プライスとの差を考慮した価格設定にせざるを得なくなり、値上げしなくてはなりません。すると、発表を続けるたびに価格帯が上がっていく構造が生まれます。完全にバブルです。
さて、このバブル構造の悪しき点、手頃な値段から出発した若手作家がターゲットだった場合、純粋なファンとして買い始めたコレクターは急な価格上昇についていけず離脱してしまいます。コレクターとして育つ機会を損失してしまうと、当然ながら美術業界だけではなく、作家やギャラリーにとって大きな痛手です。
つまり、投機商品としてしか作品を評価して貰えなくなってしまうと、いつかバブルは弾けます。相場が崩れた時に投資家達はあっさり手を引きます。価格を下げることが困難な美術品のプライマリー・マーケットでは一度上げた価格水準を下げることも出来ず、苦渋の決断を迫られます。安易な値下げは作家の評価を下げる懸念があるため、高値を続けなくてはならないというジレンマが発生。しかしギャラリーもお商売ですから、売れなければ、売れる作家にポジションを差し替えたり、展示控えに繋がりかねません。最終的には作家の発表の機会損失となり、ひいては作家の寿命を縮めてしまいかねない難しい構造を孕んでいるわけです。
* * *
このように、所有者に当然の権利があったとしても「慮る(おもんぱかる)」文化的姿勢が問われる側面が美術業界には存在します。
慮れ?そんなふわふわした善意頼みじゃダメだ!問題解決にならんぞ!と、立ち上がった勇気あるギャラリスト達も当然います。近年は「紹介制」「コレクターの購入実績」「購入から〇〇年は売却しないなどの売却制限を設けた売買契約書を交わす」など、対応を行うギャラリーは国内外問わず増えています。しかし、契約書は単なる抑止力でしかなく、完全に食い止めるのは所有者の善意頼りなのが、現状です。ブラックリストも役に立ちません。売られる時は秒で売られます。地道に訴え続けるしか、ないのです。
※1 《著作権の問題で困ったら》
著作権テレホンガイド(相談のみ。紛争になっている場合も応じない)
電話:03-5333-0393
※受付時間 10:00~12:00 13:00~16:00(土日、祝日を除く)
https://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
今後の冒険譚
▶︎ 次回
さて、身近な所有権についてわかったところで・・・
次回は「作品を手放したくなったら、どうする!?作品の廃棄問題」について書きます。
アート作品を当事者になってから問題意識が芽生え、慌てて調べるけれど明確な回答がわからないこと第一位は恐らく、購入した作品を手放したいときだと思うんですよね。一緒に考えていきましょう!
※※次回は一部業界の話が入る部分があります。転売行為に直結する恐れのある後半の一部のみ抑止の目的で有料公開といたします。ご了承くださいませ
▶︎ 更新頻度
月に1~2回頻度での不定期更新です。
どうぞフォローいただき、気長に更新をお待ちください!^^
きょうのカバー画像

Gillis van Tilborgh the Younger (1625 – 1678) ベルギー、ブリュッセル生まれ。フランドルの画家として父とDavid Teniersの伝統に倣う。初期は農民の生活や居酒屋など風俗画を描いたが、のち上流階級の群像画を得意とした。聖ルカ・ギルドのマスターでもあり、ティボルグの作品は生涯を通じてハプスブルク家の宮廷人たちやイギリス王族によって収集された。現在ではワシントンD.C.のナショナル・ギャラリー、マンチェスター・アート・ギャラリー、メトロポリタン美術館などが所蔵。複数回オークション出品され、最低額は5米ドル。最高額はこのカバー画像、2018年2月にサザビーズ・ニューヨークで落札された "An elegant interior with twelve gentleman surrounded by paintings and leather wall coverings with a game of backgammon at center (1660s)" の91万5000米ドル(※当時の日本円で約一億)。この絵のユニークな点は、描かれている7枚の絵が実在のものであり、その多くは著名な美術館に所蔵されている。
執筆者紹介

いいなと思ったら応援しよう!

