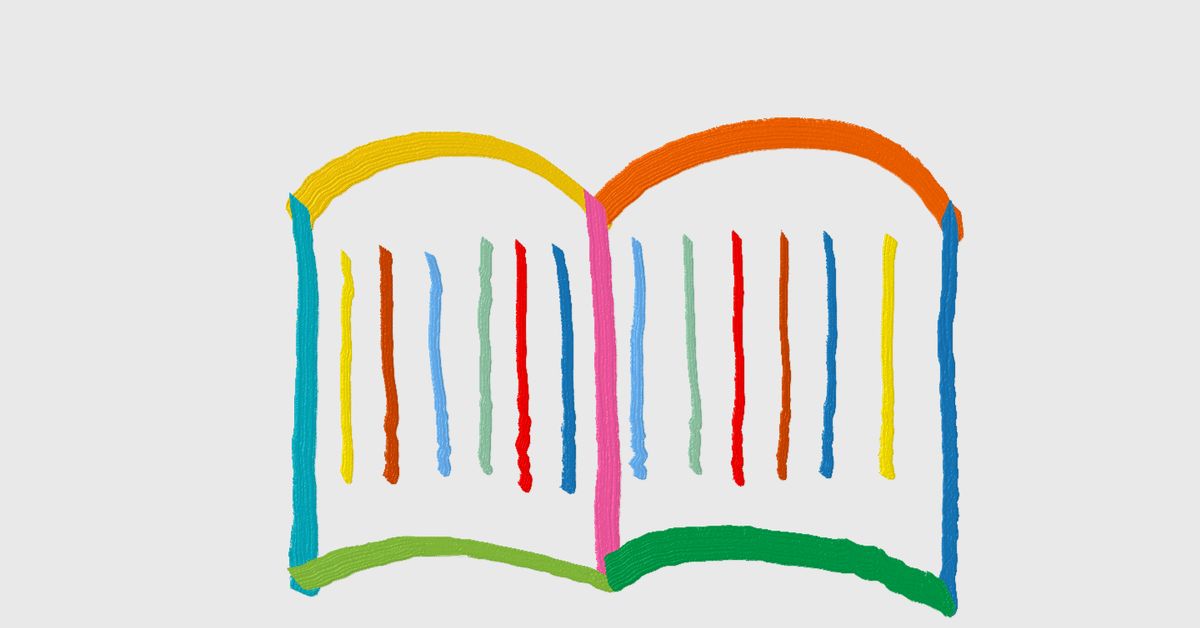
視点が変わってる。たぶんやけど。
昨日、本屋さんで見つけた「風と行く者」を夢中で読んでいた一日。
本を読む合間に会議に出て、掃除をして、ジャージャー麺を作る。
主人公が中年女性で、腕利きの用心棒というこの異色のファンタジーとわたしが出会ったのは、何年前だろう。
そして、いま向かっている机の横の本棚をふと見上げて気づいた。
わたし、この本持ってたわ(笑)
偕成社の児童書の装丁で出版されたソフトカバーのやつ。
ストーリーがぜんぜん記憶になくって、びっくりするほど号泣しながら読んだ。自分の記憶力のなさに改めて驚くけど、新鮮な気持ちで読めたのは、ある意味オトクなのかもしれない。
それにしても、このシリーズを読んできて、こんなに号泣したことがあっただろうか、というぐらい声を上げて泣いた。
こみ上げるのは、決まって主人公バルサの回想の中での、養父であるジグロとのシーンだ。
養父ジグロは、親友の娘であるバルサを助けるために、国を捨て、バルサを育てながら護衛士をする。回想の中の十代半ばのバルサは、護衛士見習いとしてジグロと共に、命を懸ける。
「あんた、大丈夫?」
キイの声がふってきた。
「びっくりしたよ。大の男が、本気で、娘を拳でぶんなぐるなんて、はじめて見た。」
バルサは、ゆっくり顔をあげた。宿の窓からもれている明かりに、キイと、その背後にたたずんでいるサリの半身が照らされていた。
「……本気じゃないよ」
バルサは、つぶやくように言った。鼻がつまっているので、こもった声しか出なかった。
「本気だったら、骨が折れてる」
キイが顔をしかめた。
「それだってさ、叱るんなら、平手で殴りゃいいじゃないか」
バルサは、ゆっくりと身体をまわし、井戸に背をあずけて、地面に足をなげだした。
「……拳で殴られるのなんて、ガキの頃から日常茶飯事さ」
言ってから、バルサは誤解をされぬよう、言いそえた。
「わたしらの暮らしは、あなたたちとは違う。拳で殴られることになれてなかったら、命とりだから」
殴られるというのは、なれていない者にとっては恐ろしいものだ。殴られる痛みになれていないと、一発殴られただけで気が動転してしまって、次の動作に移れなくなる。実戦では、その、わずかな動作の遅れが死につながるのだと言って、ジグロは拳でバルサを殴った。
バルサを殴るとき、ジグロはいつも、歯を食いしばっていた。その顔を思いだしたとたん、胸の底に、やるせない哀しみがしみだしてきた。
まだかぼそい女の子の顔を殴るのは、つらかっただろう。自分なら、殴れない。
それでも、ジグロは殴った。武術をしこむと決めた日から、ジグロは己の心の痛みなどに拘泥せず、戦いに勝ちのこるために必要だと思えば、どんな汚い技も教えてくれた。―バルサが戦いの中で命を落とすことがないように、ただ、それだけを念じて。
このシリーズは、第一作目「精霊の守り人」の時点で、ジグロはすでに故人だが、シリーズを通して、ジグロとの思い出に、かなり多くのページが割かれている。わたしはこれまで、それらのシーンをバルサ目線で読んできたような気がする。厳しくも暖かい養父への感謝と、自分のために祖国を捨てたことを償いたいけれど、その方法が分からないというもどかしさ。
けれど今回は、いつの間にかジグロ目線で読んでいた。自分が年頃の娘であることなど思ったこともなく、幸せになるということを体中で拒否している棒きれのような少女。未熟であるにもかかわらず、必死でジグロの命を守ろうとする娘。その娘に、ひとを殺すことを教えこむことでしか愛情を示すことができない自分。
トシをとったということなのか、わたしが見たいと思うものが変わったのか。いや、もしかして覚えていないだけで、前回読んだときも同じところで号泣していたのかもしれない疑惑も、捨てきれない。。
***
第4期ライティング・ライフ・プロジェクト、満席につき募集を終了しました。ありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!

