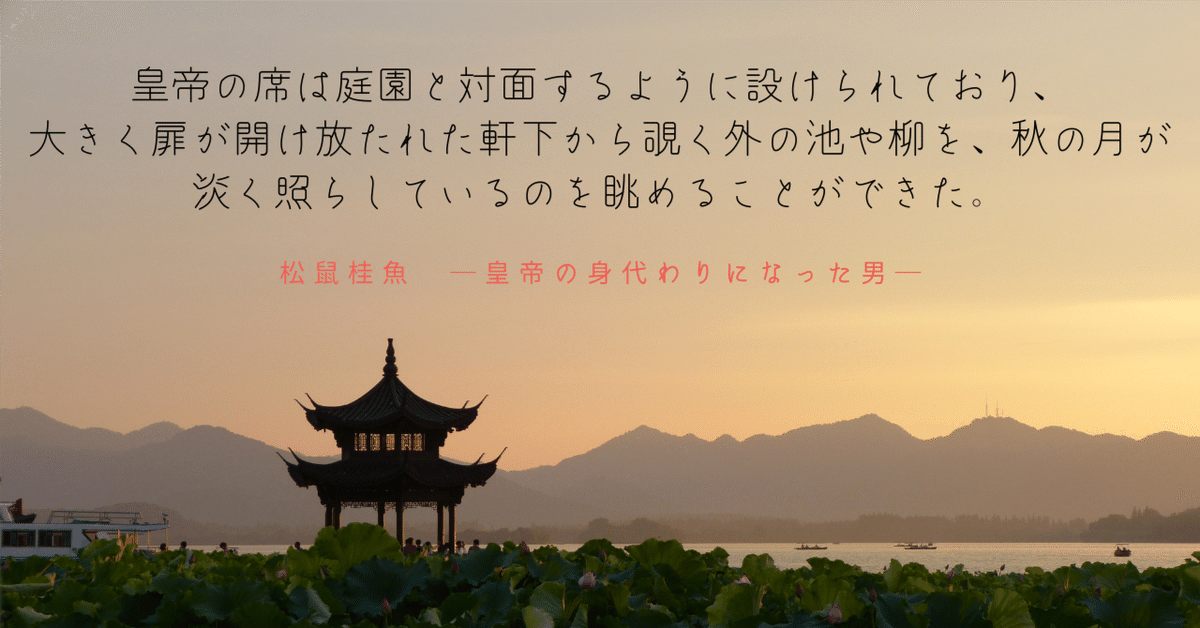
【短編小説】松鼠桂魚―皇帝の身代わりになった男―
1 都の端の門の衛兵
その夜、浪国《ろうこく》の都である康城ではいたるところでかがり火が焚かれていた。敵の犀国《さいこく》の侵攻を前にして、臨戦態勢がとられているためだ。
冷たさを増す秋の宵闇に包まれる都を、松明の炎が明々と照らす。
ときおり風にゆらぐその煌めきを、岳紹《がくしょう》は都の端の門の衛兵として眺めていた。
(じっと立っているのは、敵が近づいて来ていても眠いな……)
岳紹はあくびを噛み殺して、槍の柄を握りしめた。下級兵士である岳紹の装備は簡素な革の鎧と最低限の武器だが、それでも連日立ち続ければ疲れはたまる。
しばらくすると、見回りに各所を巡る屯長が歩いてきて、岳紹と共に見張りに立つ衛兵に尋ねた。
「復陽門。問題はないか」
屯長の問いかけに、隣の衛兵の楊がはきはきと答えた。
「はい。異常はございません」
「では引き続き、任務を果たせ」
表情を崩さずに屯長は頷き、部下を連れて闇夜をまた歩き出す。
それからはまた、炎の燃える音だけが響く静寂が始まった。
隣の楊《よう》は真面目な性格なので、岳紹が雑談をしようしても話題にのってはくれないのだ。
(でもまあこうしていられるのもあと少しだけだ。せいぜい何もない時間を味わうとしよう)
松明の光が吸い込まれていく暗い夜空を、岳紹は見上げた。
岳紹が生まれ育った世界にはいくつもの国があり、ずっと争っては滅んだり、新しい国が建てられたりしていた。詳しい出来事は知らないが、聞くところによるともう百年近くも前から戦乱が続いているらしい。
長い戦争の歴史の中で、土地は荒廃し死と苦しみが日常になった。戦災、匪賊、疫病に飢饉。ありとあらゆる理由で、大勢の人が殺され死んだ。
岳紹は大地主の農地を耕す農奴の子に生まれ、物心ついたときには働いていた。農奴に課せられた労役はつらかったが、それが当たり前だった岳紹は人生とはそういうものなのだと思って過ごしていた。
だが戦乱により仕えていた家は滅び、岳紹は戦闘で起きた火災に焼け出され一応は居場所だった土地を失った。
流民となり働き口を求めて都にやってきた岳紹は、そのまま浪国の兵士になった。度重なる戦争によりどこの国の軍も人手不足になっているので、若くて健康な男なら誰でも兵士になることができたのだ。
(運良くここまで衛兵として戦場に行かずにすんだが、その幸運もここまでか)
岳紹は一人、空にため息をつく。
元々兵隊暮らしには明るい噂を聞かなかったし、実際に食事の不味さや宿舎の汚さなどは噂通りで良いものではなかった。衛兵として戦場ではなく都にいられたからこそ、何とか耐えることができただけのことである。
しかしまたこの康城が戦場になれば、岳紹は再び生きることに苦労しなければならない。
(どうせ頑張ったってそういいことがあるわけでもないし、別に死んでもいいと言えばいいのだが……)
生まれてから三十年近くたったが、岳紹は幸せに生きて死んだ人を見たことがなかった。それは岳紹が出会ってきた人々が特別不幸だというわけではなく、どうもこの戦乱の世では最後まで幸せな人生というものは本当に稀らしい。
岳紹が農奴として仕えていた大地主の家が焼かれたように、激しい戦火は身分に関係なく人を過酷な状況に追い込んでいく。たとえどこかで幸せになったとしても、いつか必ず戦がすべてを壊すのだ。
だから岳紹は自分の人生は、人並みの不幸なものなのだと思っていた。
誰よりも不幸だとは思わないし、他人が自分より幸せに見えるわけでもない。それ以下でも以上でもないのが、戦乱の世の末端を生きる岳紹を取り巻くすべてだ。そうした得るものの少ない人生だから、失ったところでそれほど惜しいとは思わない。
この結論にももういい加減に飽きてきたところだが、岳紹の生きる日々が変わらず終わらないのだから仕方がなかった。
何度も繰り返した灰色の思考の中で、岳紹はただやがて訪れるはずの見張りの交代を待った。
そして月や星の場所が変わるくらいに時間は過ぎたころ、岳紹のいる門へと誰かが歩いてくる音がした。
(もうそろそろ、交代が来たか)
岳紹は次の見張りが来たのだと思い、足音の方を見た。
しかしそこに立っていたのは代わりの衛兵ではなく、見回りの屯長よりもさらに階級が上の校尉だった。
校尉はしかめっ面で、岳紹に問いかける。
「お前が岳紹か」
「はい、そうですが」
なぜわざわざ上官が自分を訪ねて来るのかと、岳紹は不思議に思った。何か間違いをしたのだろうかと、ここしばらくのことを思い返すが心当たりがない。
だが校尉は事情を詳しく説明することなく、大仰な調子で口を開いた。
「ある御方が、お前に用があるそうだ。ついて来い」
その返答に疑問だけが増えた岳紹は、隣の楊と顔を見合わせた。
規則順守を気にする楊は、二人一組が原則の見張り役が一人になることを気にしている様子だ。
「代わりの衛兵は手配してある。早くするんだ」
校尉は楊の目での訴えに鬱陶しげに答えて、岳紹を急かす。
「かしこまりました」
仕方がなく岳紹は拱手をして、同僚を一人残して上官の後に従って歩いた。
2 身代わりの依頼
岳紹は校尉によって、普段はまったく足を踏み入れることのない宮殿の敷地内に連れてこられた。中へと通されたのは人気のない古びた建屋で、壁のあちこちが崩れかけ、歩くと床が軋む音がする。
(こんな場所に案内されるということは、俺は内通者と間違えられて尋問されるんだろうか)
最悪な場合を想定しながら、岳紹は奥の部屋に進んだ。
今までは平均的な不幸しか知らなかったが、もしかするとここで度を超えた不幸を経験するのかもしれないとも思う。
岳紹は、暗い気持ちで部屋の中を見た。
油皿の小さな明かりで照らされた狭い室内には、古びた建物とは不釣り合いな小奇麗な雰囲気の青年が椅子に座って待っていた。高官が着るような立派な袍を着ているので、位の高い人物だということはわかる。
岳紹はどう反応すればいいのかわからないまま、とりあえずひざまずいた。
まず校尉は、岳紹をその男に紹介した。
「敬然《けいぜん》様。この者が岳紹です」
「なるほど、彼が」
まるで何かと比べるように暗闇で目を凝らし、男は岳紹を上から下までじろじろと見る。
そして校尉は目の前の青年が誰であるかを、今度は岳紹に説明した。
「この方はこの浪国の侍中、敬然様だ。失礼のないように、礼儀正しく接するように」
校尉は厳しく岳紹に言い含めると、二人を残して席を外した。
この敬然という青年と二人っきりにならなくてはならない用が、岳紹にはあるらしかった。
「侍中……。そんな偉い人が、なぜ俺を」
未だ状況がまったく呑み込めない岳紹は、ひざまづいたまま敬然を見上げた。
侍中といえば皇帝の側近であり、小汚い革の鎧を着た兵士である岳紹とは縁の遠い人物である。
感情の読み取りにくい硬質な声で、敬然は答えた。
「端的に言えば、お前の顔や背格好が皇帝陛下に似ているからだな」
岳紹は理由について考える前に、自分が皇帝に似ているという事実にまず驚いた。
「俺が、皇帝に似てるんですか?」
岳紹の顔は嫌われるほどなく醜くもなく、好かれるほど整ってもいないごく平凡な中の下である。背もそれほど高くはないし、印象に残るものは何もない。
年齢がそう変わらないことは知っていたが、まがりなりにも一国を統べる特別な存在である皇帝が岳紹のような取り立てて特徴のないごく普通の外見であるのは意外だった。
驚いた岳紹が声を上げても、敬然はまったく表情を変えずに淡々とした調子で頷いた。
「そうだ。お前の顔は瓜二つというほどではないが、陛下によく似ている。だから皇帝の替え玉として、お前は兵士の中から選ばれたのだ」
「替え玉……ですか?」
あまりにも短い言葉で語られる事情に、岳紹は敬然が自分に何を求めているのかがまだ理解できてはいなかった。
だがそれなりに長い半生の中で多数の中からわざわざ選ばれたことは初めてである気がして、岳紹は喜んでいいことなのかわからないのにも関わらず、早くも得した気分になり始めていた。
さすがにもう少し考えようと思い、岳紹は敬然に尋ねる。
「しかし替え玉というのは、王の代わりに王として振る舞う人のことですよね。そんなことは、一兵士の俺にできるとは思えないのですが」
やんわりと岳紹が実現の難しさについて言及すると、敬然は自嘲気味に説明した。
「そう長い期間の話ではない。明後日の夜、この都に犀国の軍勢がやって来て、この宮殿を占拠するまでの間の話だ」
敬然の神経質そうな白い顔が、くすんだ笑みを浮かべる。
犀国に都を落とされる日は近いと言われていたが、どうやら明後日この康城は終わるらしい。
だんだんと岳紹は、自分に与えられようとしている役割を理解した。
「つまり身代わりを置いて、皇帝陛下は脱出されると」
「ああ。お前は囮として死に、皇帝は生き残る。そして国は続いていく。気の毒だが、お前に断る権利はない」
敬然は皇帝の代わりに死ねという命令を、このうえなく冷たく言い放つ。
相手に選択肢を与えるふりすらしない敬然の強引さには、人に従うことに慣れている岳紹もさすがに少々どうかと思った。だがそれ以外は特に断る理由は思い浮かばない。
(皇帝の替え玉として死ぬ……。それはそれで悪くはないか)
兵士として戦っても死ぬ可能性が高く、生き残ってもそう良いことがあるとは思えないのがこの乱世の現状である。それなら他の人には経験できない何かを知ってから死にたいと、岳紹は思った。
岳紹は皇帝に深い敬意を持っているわけではない。また見知らぬ誰かのためになりたいわけでもない。
ただ逃げた皇帝の代わりに皇帝として死ぬことで人生を終わらせることそのものへの興味で、岳紹はその選択肢を選び取る。
「そういうことなら、俺がやるしかないですね。わかりました。引き受けます」
目を伏せて息を吐き、岳紹はそのままあっさりと替え玉になることを承諾した。
埃っぽい床では油皿の明かりがつくる影が、ゆらゆらと揺れていた。
すると静かに響く敬然の声が、岳紹の頭上で答えた。
「話が早くて助かった。すまないが、頼んだぞ」
こうして、岳紹は皇帝の身代わりになることになった。
3 王の装束
その夜はもう遅かったので、岳紹は敬然と別れた後は宮殿の中にある一室の寝台を借りて休んだ。
そして王の替え玉としての待遇は、翌日から始まった。
岳紹は宦官たちにそこらの民家よりも大きな湯殿へと連れていかれて、ぼろぼろの衣服を脱がされ汚れた髪や体を洗われた。
湯上りには髪を乾かし梳かれながら、同時に手の手入れも行われる。まったく貴人らしさの欠片もなかった岳紹のひび割れた爪は、付け焼刃ではあるが多少は綺麗に整った。
きっと自分が年頃の娘だったなら、起きている変化にももっと喜べるのだろうと岳紹は思う。
下準備がすむとまた違う建物に移動し、今度は丁寧に乱れなく髪を結われて、豪華な装束を着せられた。
帯で何度もきつく巻かれ、幾重にも重ねられていく衣。結果出来上がったのは、銀糸で龍の織り込まれた袖のついた黒地の衣に赤色の裳を身につけた派手な服装だった。
そして最後に板に宝玉を連ねて垂らした飾りが載ったかたい冠を頭に被せられて、皇帝の装いは完成する。
「当然のことだが、皇帝に似た男に皇帝の服を着せれば普通に皇帝に見えるものだな」
着替えが終わったころに現れた敬然は、興味深げに皇帝の替え玉として着飾った岳紹をしげしげと見つめた。
岳紹は地味な自分には過分な服装だと思ったが、本物の皇帝も同じであるらしいので仕方がない。
「姿はこれでいいとして、言葉はどうするんですか?」
昨日まで着ていた革の鎧よりも重くなった衣服に、岳紹は早くも若干の疲れを感じていた。格調のある衣裳に自然と姿勢が良くなるというよりは、きつい着付けに物理的にうまく動くことができない。
すると敬然はそっと近づいて手を伸ばし、岳紹の衣服の襟を見苦しくない程度にゆるめた。その手は見せかけではなく本当に、貴人らしく白く整っていた。
そして敬然はせせら笑いを浮かべて、岳紹の耳元でささやいた。
「大抵の返事は、左様かと言っておけばすむだろう。これなら学のないお前でもできる。実際、本物の皇帝もそんなものだ」
その言葉は明らかに岳紹だけではなく、皇帝本人も侮っていた。
だが岳紹は人を小馬鹿にした敬然の態度に憤るよりもむしろ、馬鹿にされている皇帝に親しみを感じた。
(本当に皇帝も、そんなものなのか……)
岳紹はどこか安心した気持ちで、これから演じることになる皇帝について考える。
皇帝には一度も会ったことがないのにも関わらず、岳紹は次第に思った以上に何もできないらしい彼が身近な人であるような気がし始めていた。
4 宴席と白酒
替え玉としての岳紹のほとんど最初で最後になる仕事は、犀国の総攻撃の前夜に行われる最後の宴に出席することだった。
これから宴が行われる館舎へと続く渡り廊下を、岳紹は敬然とともに不思議な気持ちで歩いた。
敬然の話では、もう本物の皇帝は他の腹心と共に城外へ逃げているとのことである。今の岳紹は、名実ともに皇帝の身代わりなのだ。
館の入り口にある、万字の文様が組まれた格子のはめられた引き戸を召使いが開ける。岳紹は敬然に先導されて、中へと進んだ。
すると入り口近くに立っていた官吏が、館中に皇帝の登場を告げた。
「皇帝陛下のお成りである」
「誠に、お喜び申し上げます」
官吏の朗々とした呼びかけに応えて、席で待っていた臣下たちが声を揃えて挨拶をする。
広々とした館の中には数十もの席がしつらえてあり、それぞれの身分にあった袍を着た男たちが坐っていた。
岳紹は官吏に案内されるまま、黙って移動した。その場の人々の視線が偽の皇帝である岳紹に集まっているが、違和感を抱いた様子の者はいない。
(まずは大きな問題なかったらしいな)
他の出席者から少し離れた所へと用意された敷物の席に腰を下ろし、岳紹は堂々とした気分で顔を上げる。
皇帝の席は庭園と対面するように設けられており、大きく扉が開け放たれた軒下から覗く外の池や柳を、秋の月が淡く照らしているのを眺めることができた。
席ごとに置かれた小卓には蒸し鶏の燻製に豚の腸詰、白菜の酢漬けなどの様々な肴饌《こうせん》が木や竹の小皿に小分けして置かれ、緑釉のかかった盃には芳香の漂う白酒が並々と注がれた。
「まだこれからも料理は来る。そこに置いてあるものは適当に酒のつまみにするだけで大丈夫だ」
すぐ側の席に座った敬然が、岳紹に小声で説明する。
岳紹は生まれて初めて見る品数を前にして、まだ他にも料理が用意されていることに驚いた。
やがてすべての盃に酒が行きわたると、宴会を取り仕切る係の官吏が立ち上がり、宴の開始を告げる。
「皇帝陛下の御世と今宵の月に、乾杯」
官吏は盃を掲げ、酒を飲み干した。
同時に楽師の奏でる琴や鼓の音色の調子も変わり、酒杯の応酬が始まる。
岳紹も盃を手にとり、一気に飲んだ。
(これが偉い人たちの飲む酒か)
白酒は岳紹はこれまで自分が口にしてきたものとはまったく違う、醇美な味がするものだった。その濃く甘いまろやかな口当たりに、岳紹は早くもほどよい酔いを感じた。
盃が空になると、酒器を持った召使いがすぐにまた満たす。
岳紹は酒を飲み進めながら、肴饌に箸をつけた。
鶏肉の燻製はコクがあって美味しく、どの品も酒によく合うしっかりした味のものばかりだった。
やがて最初の一口が一段落したころになると、どこからか七、八人ほどの妓女が現れた。彼女たちはゆったりとした鮮やかな色の衣装を着ており、軒下に設けられた舞台で音楽に合わせて舞踊を披露した。
月夜の庭園を背景にして並ぶ妓女たちはどの者も見目麗しく、長い袖を揺らして舞う姿は同じ人間だとは思えないほどに華やかだった。
(まるで夢みたいだな……)
語彙の少ない岳紹は、妓女たちの美しさに見合った言葉が見つからないままに見惚れた。
しばらくすると妓女たちは舞いながら宴席へと移動を始め、そのうちの一人は岳紹のいる皇帝の席の方へとやって来た。
「初めまして。お目にかかれて、光栄です。皇帝陛下」
そう言って岳紹の隣にちょんと坐ったのは、まだ少女に近い雰囲気を残した年の若い女人だった。
漆黒の髪は金色の髪飾りを挿して綺麗にまとめられ、薄く化粧をした顔は兎のように愛らしい。薄空色の襦に濃紺の裙《くん》を履き、淡く透ける薄絹の肩掛けを羽織った小柄な姿は可憐で、半ば開いた胸元からのぞく肌は雪のように白かった。
特に人と接することもなく順調に替え玉を演じていたところを突然美女に話しかけられて、岳紹は判断に迷って敬然の方を向いた。
敬然は支持を仰ぐ岳紹に、そっと耳打ちした。
「その女は替え玉の事情を知っている者だ。この先は彼女に適当に合わせれば良い」
敬然に説明されている岳紹を、妓女は訳知り顔で笑って見ていた。どうやら彼女は本当に岳紹がぼろを出しても問題ないように用意された人間らしい。
納得した岳紹は頷き、早速質問をした。
「なるほど。それで名前は?」
「彩珂《さいか》です」
奏でられている楽の音と同じくらい澄んだ声で、妓女は答えた。
「良い名前だな。踊りも上手だった」
岳紹は彩珂の舞踊を詳細に覚えていたわけではないが、とりあえず褒める。
すると彩珂は、蕾がほころぶように美しく笑った。
「そうですか? 踊るのが一番好きなので、嬉しいです」
彩珂が岳紹に微笑むのは、それが妓女である彼女の生業だからである。
だがそれをわかっていても、岳紹は彩珂が十二分に好ましいと思った。
岳紹に身を寄せて坐る彩珂は目を輝かせて、召使いが盆をもって歩いてくるのを見た。
「あ、次の料理が来たみたいですよ」
「そうだな。どうやらこれは鶏湯のようだ」
召使いが小卓に置いた椀の中身を食べるため、岳紹は匙を手にとった。
椀の中で湯気を立てているのは、花びらのように綺麗な溶き卵が入った鶏だしの湯だ。
「私、卵好きなんです」
ねだるように甘えた声で彩珂が言ったので、そこから先は二人で分けて料理を食べた。
5 揚げ魚の甘酢あんかけ
宴席には次から次へと新しい料理が運ばれてくるので、量の問題はまったくなかった。その豪華さは、敵の軍勢を前にして自暴自棄になっているとしか思えないほどだ。
(この服装じゃなければ、もっと良かったんだが……)
岳紹は帯がきつく、普段よりも食べられないことを残念に思った。
ふと気づくと、敬然はいつの間にか姿が見えなくなっていた。
何か用があったのかもしれないが、彩珂と二人きりにするために気を遣ってくれた可能性もあるにはあった。
「この饅頭、熱いうちに食べた方が美味しいですよ」
「ああ、これは確かに旨い」
彩珂が二つに割ってすすめてきたので、岳紹は肉入りの饅頭を頬張った。
ひき肉を具にした饅頭は、生地がしっかりとしていて食べごたえがあった。
食事と共に酒も進み、岳紹はただ蕩けそうな頭で楽しさだけを感じた。
「本当に、替え玉になって良かった」
岳紹はしみじみとつぶやいた。
自分が皇帝の身代わりであることについて発言しても、今一番に盛り上がっている宴の最中では彩珂以外に耳を傾ける者はいない。
梁から吊るされたいくつもの灯籠に明々と照らされた館の中は、楽士の奏でる音色と人々のざわめきに満たされて最後の煌めきを見せていた。
「皇帝の身代わりで死ぬ役目なんて、嫌じゃないんですか?」
不思議そうな顔をして、彩珂は岳紹を見つめる。
岳紹は盃を手にしながら、小さく笑った。
「いいや、今の俺は本当に幸せ者だよ。王の身代わりになったおかげで美味しい酒を飲んで豪華な食事を食べれて、彩珂のような美女と話せたんだから。明日死んだって、おつりがくる」
「それは言いすぎだと思いますけど」
つらつらと本音を述べる中に褒め言葉を混ぜると、彩珂は照れたように頬を赤らめる。岳紹は彩珂のそうした人に媚びながらも素直なところが、とても魅力的に感じられた。
だが一方で岳紹がその先を語れるのは口説き文句ではなく、自分が最後に引いた当たりくじについてのことだった。
「だって大変なのは、これからもこの悲惨な国と共に生きていかなきゃならない皇帝の方だろう? そんな可哀想な男よりも、最後の最後に幸せがあっての死ぬ俺の方がずっと幸せだ」
岳紹はもはや開き直った明るさで、盃の酒を飲み干し空にする。
あんまりにも気分がいいので、岳紹はこの場にいることができなかった皇帝に同情しはじめていた。しかし岳紹と同じ顔らしい彼がここにいたとしても、岳紹と同じように楽しめたかどうかはわからない。
岳紹の極論にさすがに反応に困ったようで、彩珂はただ隣で笑っていた。
するとちょうどまた、召使いが新しい料理を運んで来る。
「よくわからないものが来たな。魚なのか?」
召使いの置いた大皿に載っていた餡かけのその料理は、岳紹には何であるのかすぐに理解できなかった。
頭と尻尾は魚に見えるが、上身のあるはずの場所には人の指先ほどの太さの毛のようなものが密集している。添えられた青菜が赤い餡に映えて鮮やかだが、外観はかなり不可解だった。
いぶかしむ岳紹に、彩珂は箸をとって料理の説明をした。
「ああ。これは松鼠桂魚《りすけつぎょ》っていう魚の揚げ物です。包丁で細かく切れ込みを入れた魚を揚げると白身が逆立ち、栗鼠の毛皮みたいに見えるって料理なんですよ」
彩珂が箸で身をつまんでとると、中は確かに魚の白身だった。
「そういう料理だったのか」
腑に落ちた岳紹は、興味深くその揚げ魚を見つめた。
皇帝の替え玉として偽りの姿でいる身として、栗鼠に似せて揚げられた魚に自分と重なるところがあるような気がする。
(魚も松鼠《りす》になったりするものなんだな。俺よりもすごい変化だ)
岳紹は面白がりながら、箸をつけてみた。
そして口に入れた瞬間、その美味しさに驚いた。
(思ったよりもずっと旨いな、これは)
見かけ倒しの料理に感じられてそれほど期待はしていなかったが、松鼠桂魚の味はとても良かった。
さっくりと薄い衣は熱々で香ばしく、甘酸っぱい餡が白身の淡泊な味わいを引き立てている。細く刻まれた魚は新鮮でやわらかく、小骨も少なく食べやすかった。
岳紹はもう大分満腹に近かったが、あまりの美味しさに箸を止めずに食べた。様々な料理を食べることができた一日だったが、一番気に入ったのはこの松鼠桂魚だった。
ときおり彩珂も食べたので、魚はあっという間に頭と尻尾だけになった。
食べ終えた岳紹は満足な気分で、息を吐いた。
彩珂はそんな岳紹を見てくすくす笑って、顔を近づけた。
「ここに餡がついてますよ」
そっと頬にふれて、彩珂は微笑んだ。
彩珂の澄んだ目が、皇帝の装束を着た岳紹の薄い顔を映し出す。
ごく至近距離で見ても何も瑕疵が見当たらないほど、彩珂は美しかった。
その白い胸元に少し気が迷って、岳紹はおもむろに彩珂に口づけをした。紅をさした唇はやわらかく、そして案外冷えていていた。
岳紹はそのとき浮かんだ漠然とした想いを、何も言葉にはできなかった。
だが彩珂は岳紹を拒まなかったし、むしろ誘うように岳紹の背中に腕を回した。
それは彼女は妓女という職業であるためある程度は当然のことであったが、岳紹は自分が受け入れられたのだと思った。
彩珂の動きに呼応するように、岳紹もまた彩珂の腰を抱いた。
それで幸せなのかはわからないが、きっとこの先も彼女は強かに生きていくのだと岳紹は静かに思う。
(俺は明日死ぬけど、だから)
席の裏にあった衝立の影へとそっと彩珂を押し倒し、岳紹は今度はその細い首筋を求めた。
6 皇帝の身代わりになった男
宴も無事に終わった翌日、岳紹は欄干のある宮殿内の一室で、椅子に座って敵が来るのを待っていた。
透かし彫りの花鳥に飾られた欄干の向こうに広がる青空を見上げ、岳紹は隣で書物を開いている敬然に尋ねる。
「そういえば、敬然殿も俺と死ぬのか?」
「さあな。利用価値があると思われれば、殺されずにすむだろうが……」
いつの間にか敬語ではなくなった岳紹の問いに、敬然はどうでもよさそうに答えた。敬然もまた岳紹と同じように、あまり今後の人生に執着があるようには見えない。
「ちなみに岳紹。一応聞いておくが毒とか剣とか、お前に死に方の希望はあるか?」
「特にないな。敬然殿が一番皇帝の替え玉らしいと思う方法にしてくれ」
「そうか、了解した」
敬然は死に方の候補を挙げたが、岳紹は死因についてのこだわりは特になかったので判断は任せることにした。学のない岳紹には皇帝らしい死に方が何なのかわからないが、国の高官として物事に詳しい敬然なら最良の選択をしてくれるはずである。
特に二人親しいわけでもないのでやりとりはすぐに終わり、その後は長い沈黙が流れた。
岳紹は特に何も考えることもなく、ただぼんやりと気を楽にしていた。
すると今度は敬然が書物から顔を上げ、口を開いた。
「西の果ての異国には奴隷が偽の王を演じる祭礼があるという話を、お前は聞いたことがあるか?」
「いや、知らないな。どういう祭りなんだ?」
突然向こうから振られた話題に少し驚き、岳紹は敬然の方を見た。
敬然は賢そうな横顔で、異国の不思議な祭礼について語った。
「祭りの間、偽王として選ばれた男は王として好き放題に過ごすことができるが、祭りが終わるときには生贄として殺される。そういう祭礼が西方にはあるらしい」
それは岳紹がまったく見聞きしたことがない、博識な高官の敬然だから知っている遠い国の話であるはずである。
だがその祭りで起きていることは、ここ浪国でも今起きていることだった。
「どこかで聞いたような話だ」
「そうだろうな」
岳紹はわざと距離を置いた反応をとる。
すると遠くを見るように目を細めて、敬然は自虐めいた微笑みを浮かべた。
どうやら敬然は、岳紹への罪悪感から異国の偽の王の話をしているらしかった。
敬然に岳紹のことを慮る気持ちがあったことは、やや意外な気がした。だが思い返せば最初から、あえて言い訳も取り繕うこともしないのが彼の優しさだったのかもしれない。
しかし岳紹は敬然に申し訳なく思ってもらう必要がまったくないほどに、替え玉としての結末に満足していた。
岳紹は宴で食べた料理や彩珂と過ごした時間のことをそっと思い出し、心の中でつぶやいた。
(どうせ戦争ばかりの世の中だ。最後に楽しんだ後で死ねるなら、本物の王より偽王がいい)
そして一瞬農奴や兵士として生きた日々のことを振り返った後、自分と同じ顔の皇帝について考える。
岳紹は死ぬ自分ではなく、生きる皇帝こそが本当の生贄なのだと思った。
滅びゆく国を背負い続ける皇帝の犠牲があるからこそ、岳紹は本来彼が得るはずだった死を手に入れることができたのだ。
(逃げてくれて感謝しているよ、皇帝陛下)
皇帝の犠牲に感謝して、岳紹は晴れやかな気持ちで目を閉じた。
毒か剣か、はたまたそれ以外か、あとは隣の敬然が偽の皇帝にふさわしい死に方を選んでくれることだろう。
↓次章
↓各章目次
いいなと思ったら応援しよう!

