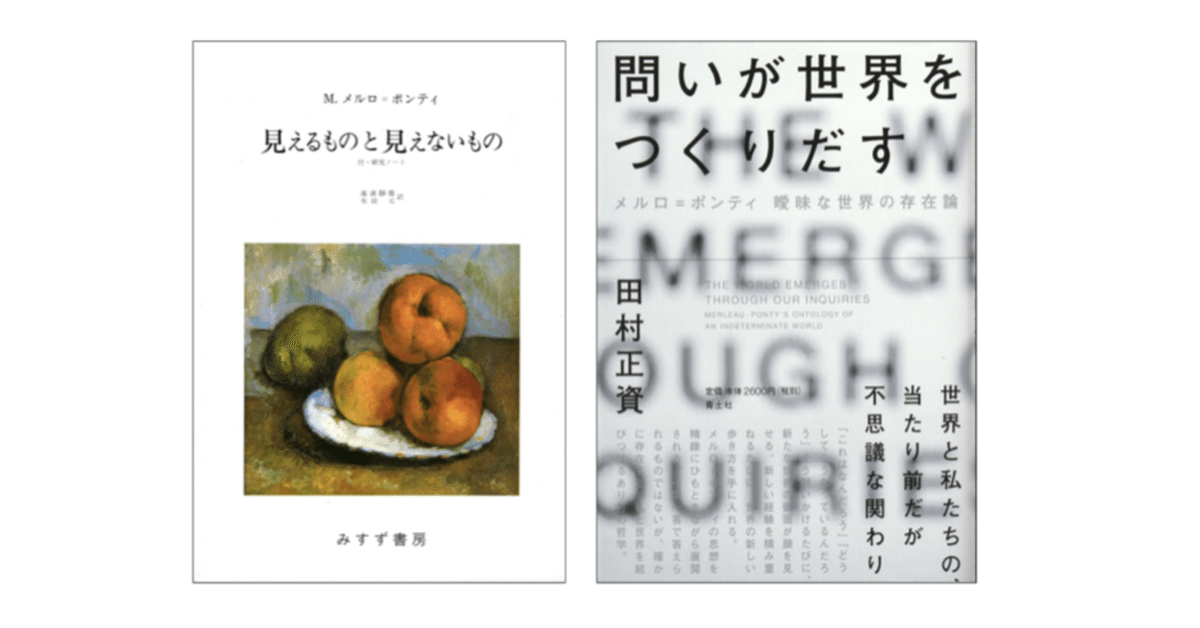
田村正資『問いが世界をつくりだす メルロ゠ポンティ 曖昧な世界の存在論』/メルロ=ポンティ『見えるものと見えないもの』
☆mediopos3583(2024.9.10)
田村正資『問いが世界をつくりだす
メルロ゠ポンティ 曖昧な世界の存在論』は
そのメインタイトルが示している通り
「問いが世界をつくりだす」ように
「私と世界」とが結びついていることを論じている
サブタイトルにある
「曖昧な世界の存在論」という表現は
「世界のなかに何があるか、何が見出されるかは、
世界と私たちの関わり方によって決まってくる。」
「ある意味でこの世界で私たちが見出すすべてのものは、
私たちの発明」であって
「世界にはもともとそのいずれも存在しなかった。
それらは、ただ曖昧な領域だった」という意味での
「曖昧な世界」ということである
「曖昧」だというのは
私たちの認識が不十分だから「曖昧」なのではない
「単に私たちの経験がそのような特徴を備えているだけ」で
「経験のうちに見出された特徴が、
それ自体経験される世界の特徴でもある」というように
「経験に内在的な特徴の探究から
経験に外在的な世界の探究へのこのうらがえり」が
重要な観点となっている
その観点から導き出される
世界は「問いかけられることによって
具体的な在り方を発現させる」という在り方を
メルロ=ポンティは「試問的な様態」と呼んでいる
「試問的な様態」における世界は
「決してア・プリオリに「・・・・・・である」と
定義されうるようなものではない」
「知覚とは、いまだ「何ものか」に留まっている世界を
具体的なものとして創造、更新していく営みであって」
「いま私たちが見ている
具体的な事物で構成された世界は、
ア・プリオリに存在する世界と私たちの物理的な身体の
相互作用によって導き出された結果なのではなく、
知覚視的信念によって結びついた
世界と身体が創造した解答」なのである
世界はいまここで創造されているがゆえに
「私たちが生きる世界は「未完成の作品」であり、
つねに私たちの新たな問いかけに対して開かれている」
このように世界が
「試問的な様態で存在する」という観点は
「自由の哲学」とも深く関係している
「自由の哲学」には現象学的視点はなく
比較的単純で短絡的な議論内容となっているが
重要となるのは
豊かな「問い」がいかに可能となるかでもある
それを可能にするのが
知覚の豊かさと概念形成力である
貧しい知覚と固定観念で閉じられた概念からの「問い」は
それに応じた世界しかつくりだすことができない
■田村正資『問いが世界をつくりだす メルロ゠ポンティ 曖昧な世界の存在論』
(青土社 2024/8)
■M.メルロ=ポンティ(滝浦静雄・木田元訳)
『見えるものと見えないもの――付・研究ノート 』(みすず書房 1989/9)
**(田村正資『問いが世界をつくりだす』
〜「はじめに 世界は「問い」を待っている」より)
*「私たちはいろんな仕方で世界に「寄りかかって」いる。僕が何かを見つめているとき、つねにその背景にはぼやけた曖昧な領域が広がっている。ぼやけた領域にあるはずのものたちは、僕の意識から退いている。しかし、メルロ=ポンティの言葉を借りるならば、このものたちは意識の地(背景)となることによって、いま僕が見ている図(対象)の経験を支えている。私たちの世界の経験はこんなふうに、自分と対象の周囲に広がる環境に支えられている。
そしてこの環境のさらに背景には、見果てに世界が広がっている。この世界は、私たちの生を超えている。私たちはこの世界のすべてを見通すことはできない。私たちは、つねに「いま・ここ」、すなわち自分のパースペクティヴからしか、世界を生きることができない。」
*「自分固有のパースペクティヴからしか世界を経験できないことは、私たちの欠陥ではない。むしろ、それは「世界の経験」が本質的に備える構造なのである。世界とは、(・・・)見果てぬものとして背景に退きながら、具体的なものの経験を生じさせる、それ自体としては曖昧な領野なのだ。(・・・)世界のなかに何があるか、何が見出されるかは、世界と私たちの関わり方によって決まってくる。私たちがこの身体で、自分たちの関心から問いかけなければ、この世界には何も現れてこない。だから、ある意味でこの世界で私たちが見出すすべてのものは、私たちの発明である。世界にはもともとそのいずれも存在しなかった。それらは、ただ曖昧な領域だった。問いかけられることによって具体的な在り方を発現させる、このような在り方をメルロ=ポンティという哲学者は世界の「試問的な様態」と呼んだ。」
**(田村正資『問いが世界をつくりだす』
〜「序論 現象学においてなぜ曖昧な世界が問題となるのか」より)
*「本書は、モーリス・メルロ=ポンティ(一九〇八—一九六一)の哲学を、「曖昧な(indéfini)世界の存在論」として解釈し、再構成を試みることである。彼はエトムント・フッサールの現象学を心理学の成果と結びつけながら深化させ、二〇世紀を代表する哲学者の一人となった。そんなメルロ=ポンティは生涯にわたり、世界と、その世界のなかで生きる主体の関係を考え続けた。結論を先取りするならば、晩年のメルロ=ポンティが到達したのは、私たちが生きる世界は、私が見ている対象を取り囲む視野と同じように曖昧なものだ、という見解である。彼はこのような立場を、「実在する世界は試問的な様態で存在する」というテーゼとして表明することになる。」
「メルロ=ポンティによれば、私たちは、自分たちの生きる世界が、何であるかを明確に述べることはできない。けれど世界は私たちが具体的な何かを求めて問いかけを発する地平として、私たちを包み込むように拡がっている。つまり、私たちが具体的な何かを世界のなかで経験しているとき、当の世界はその経験の周縁に「何ものか」というスタイルで存在している。
この世界は、曖昧な何ものかとして実在する。それは、私たちが世界を十分に把握できていないという意味で言われているのではない。確固たるものとして経験される私の机や本棚、部屋のそのさらに背景には、それ自体の特徴として曖昧さを備えた世界が控えている。」
*「本書で試みるのは、第一に「経験を構成する曖昧さ」が果たす役割の解明であり。大にに「曖昧なものとして実在する世界」の在り方の解明である。第一の試みから第二の試みへの移行は、現象学的な枠組みのなかでは決して自明ではない。だが、メルロ=ポンティの哲学のなかには間違いなくこのような移行を捉えるためのプロジェクトを指摘することができる。すなわち、経験について問われていた「曖昧さ」がいつの間にか実在する世界の特徴として論じられるという、現象学的な前提のうらがえりが、メルロ=ポンティの議論を包括的な視座から理解するために解明されなければならない事態として浮かび上がってくるのだ。」
*「近年「思弁的実在論」と呼ばれる潮流に端を発する「現象学の終焉」論に対しても応答することができる。現象学はそこで、主観性と客観性を切り分けることのできないものとして扱う相関主義的な立場の代表格として扱われ、「私たちにとって」経験された世界の外部に決して到達することはできないと批判されている。しかしながらメルロ=ポンティは(・・・)「私たちにとっての即自」として現れてくる世界の基層に私たちを包み込む曖昧な世界を見出そうとしていた。即自としての世界と経験された世界を二元論的に区別するのでもなく、まったく切り離すことのできない渾然一体のものだと論じるのでもない可能性を、メルロ=ポンティの「曖昧な世界の存在論」は提示している。」
**(田村正資『問いが世界をつくりだす』
〜「第一一章 試問的な様態で存在する世界」より)
*「事物よりさきに曖昧で未規定的な世界の持つ実在性があり、そのさなかで、私たちは知覚的な問いかけによって実在的な事物を切り出してくる。「実在する」という術後が最初に適用されるべきなのは、個物ではなくそれらと私たちを包み込む世界なのである。しかしながら、具体的な経験において私たちが出会っているものは世界ではなく特定の対象である。そして、この特定の対象と出会うことから、他の対象、他の場所へと、世界の探究が始まる。このような、ある意味で倒錯した在り方をする世界のことを、メルロ=ポンティは「全体的部分(patrie totale)」と呼んでいた。」
「全体的部分としての世界は、「試問的な様態で存在する」。これが、メルロ=ポンティの哲学を「曖昧な世界の存在論」として再構成するときにもっとも強調しておきたいテーゼである。」
「試問的な様態のもとにある世界の存在は、決してア・プリオリに「・・・・・・である」と定義されうるようなものではない。だからこそ、私たちの問いかけに一問一答のように確定した答えがはっきりと与えられることをメルロ=ポンティは期待していない。実在する世界のなかで生きること、それは終結することのない連続的な問いかけのなかに身を置き続けることである。未規定的な世界のさなかで、環境と習慣に絶えず動機付けられながら世界に問いかける実存。このモデルのうちで、私たちは外的な地平から、目の前の事物が客観的で実在的なものであるという認識を汲み出している。私たちはすでにある事物に直接触れるのではなく、世界のただなかで事物を見つけ出す。このようなメルロ=ポンティの捉え方を踏まえれば、私たちと事物とのふれあり、そこで認識される真理について考えるときに隔たりや奥行きといった空間的な距離に由来する概念を強調することも理解できるだろう。」
*「問いかけとは「その現実化が決して私たちの想像するようなものとはならないようなある全体、それにもかかわらず、私たちが倦むことなくそれを信じているがゆえに、私たちのうちで秘かな期待を満たしているある全体の前もっての所有」である。そこで所有されるある全体、すなわち「世界」以前の世界については、どんなものであるのか、決して規定することはできない。問いかけられる対象がどのようなものなのか、どこにあるのかも分からないまま私たちはそこに問いかける。曖昧な世界と問いかける知覚的存在者のあいだに具体的な事物がたち現れてくる。それは動機付けによって私たちがあらかじめ思い描いていたかたちで実現するとは限らない。曖昧な世界は、そのような私たちをつねに裏切ってしまう可能性、すなわち根源的な偶然性を秘めてもいる。メルロ=ポンティの「問いかけの存在論」は、このような世界像を私たちに提示しているのである。」
「いま私たちが見ている対象というのは、「反対側がしかじかである「かのような」対象」なのである。メルロ=ポンティは、「かのように」という仕方で経験される性質を実在する世界にも帰属させようとしている。それは「かのよういん」という曖昧な性質をはらんでいるからこそ、実際に問いかけるように主体を促す。主体はそのように「世界によって」促されているのである。これは観察者についてのいかなる想定にもつきまとう。世界は理想的な観察者にとっても確定的な記述で覆い尽くすことのできない仕方で存在している。以上のような主張をメルロ=ポンティ読解から引き出すことをもって、本書の試みは達成される。」
*「私たちの知覚経験は、もとより確定的に存在していた世界の発見ではなく、あたかもそれが事後的な発見であるかのように世界をいまこの場で創造する表現として捉え直されなければならない。」
「知覚とは、いまだ「何ものか」に留まっている世界を具体的なものとして創造、更新していく営みであって、その意味においてもはや単純な感覚刺激の受け取りだけではなく、身体を用いた振る舞いや、メルロ=ポンティにおいては身振りの延長線上で捉えられた文化的な表現までもが、広義の知覚として位置付けられることになる。」
**(田村正資『問いが世界をつくりだす』
〜「結論 志向性の探究の果て 未完成な作品としての世界」より)
*「フッサールに端を発する志向性の探究としての現象学的な伝統を引き継ぎながら、メルロ=ポンティは「私たちにとっての即自」をどのように理解するのか、という問題に取り組んだ。私の志向性にょって賦活されたものであるからこそ、私たちがそのなかで生きる世界や、私たちが働きかけるその対象は、実在的なものとして現れてくる。そうした経験がまさしく志向的なものとなっているとき、それを支えているのは図として与えられた対象や意味ではなく、地として明確に意識はされない未規定的な領野、そして動機付けなのであった。
私たちの経験を志向的なものとして成り立たせているこれらの曖昧さは、私たちの認識が不十分であるからこそいまだ残存しているような類のものではない。つまり、単に私たちの経験がそのような特徴を備えているだけであって、世界の実態は決して曖昧なものではないのだ、と切り捨てることができるようなものではない。メルロ=ポンティはここで、経験のうちに見出された特徴が、それ自体経験される世界の特徴でもあるのだ、と考える。経験に内在的な特徴の探究から経験に外在的な世界の探究へのこのうらがえりこそ、メルロ=ポンティのテクストを検討することによって本書で追求したいものだった。そしてその試みは「世界は試問的な様態で実在している」という象徴的なテーゼの解明として、ひとつの区切りを迎えたことになる。
メルロ=ポンティによるうらがえりを支えたのは、知覚のような志向的な経験が生じているとき、つねに経験に先行する「何ものか」が在るはずだ、という私たちの根源的な態度(知覚的信念)の剔出である。私たちがつねにすでに世界のうちに組み込まれているということは、私たちが世界をつねにすでにそこに在るものとして知覚のうちで捉えていることと決して切り離すことができない。このような組み込みの様態、すなわち、知覚的信念を伴う知覚の在り方そのものが問題となるのだ。
本書では知覚的信念の議論に端を発するメルロ=ポンティの立場を「私は知覚する。それゆえ、私に先立つものがある」というテーゼにまとめた。「先立つもの」についてのテーゼと、それら先立つものは曖昧な「何ものか」である、というテーゼが合わさって、メルロ=ポンティ独自の見解となっている。
このような立場からすれば、いま私たちが見ている具体的な事物で構成された世界は、ア・プリオリに存在する世界と私たちの物理的な身体の相互作用によって導き出された結果なのではなく、知覚視的信念によって結びついた世界と身体が創造した解答である。そしてこの解答はまた、規範という仕方で私たちの生を動機付けていくことになる。」
*「私たちが生きる世界は「未完成の作品」であり、つねに私たちの新たな問いかけに対して開かれている。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
