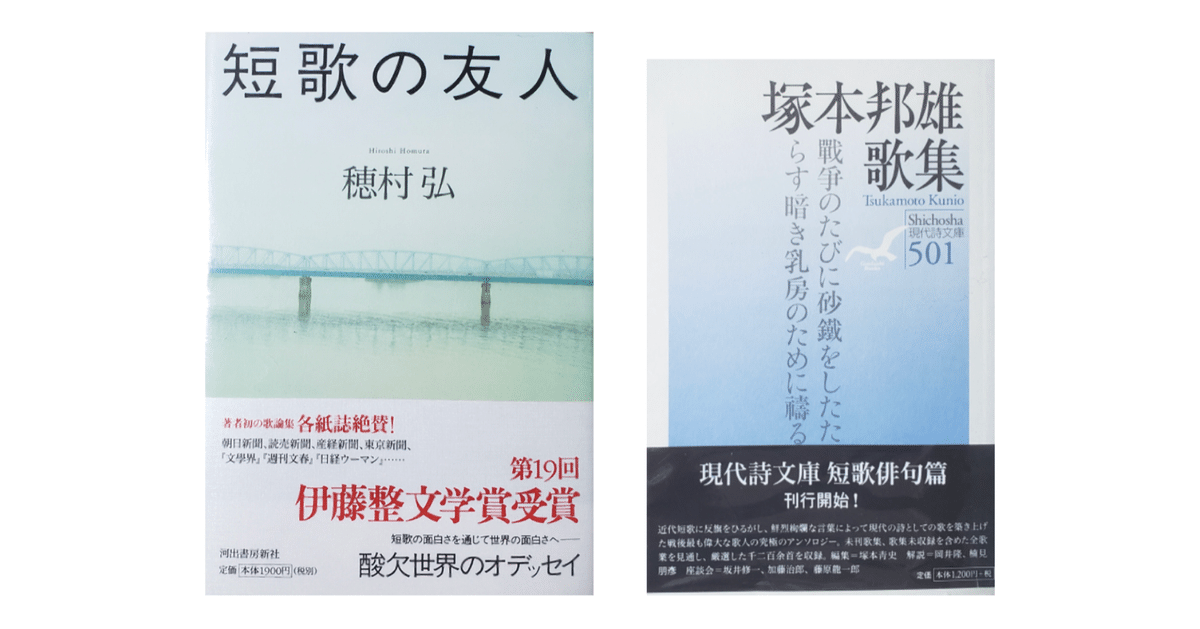
穂村弘『短歌の友人』/『塚本邦雄歌集』
☆mediopos2783 2022.7.1
とくにここ数年
「短歌」をよく読むようになった
主に塚本邦雄の影響である
いまや塚本邦雄の言葉を目にしない日はないほどだ
ほとんど「短歌」のたぐいを
まとまってよむようなことは
古典もふくめてあまりなかったのだが
塚本邦雄を(個人的に)再発見したおかげで
時代を超えて同時並行的に
塚本邦雄の周辺やその後を含む現代と
古典から近代までの和歌が交錯しながら
ときには時代錯誤さえしながら読んでいる
「歌」の受容というのは
とくに現代においては多様である
それは音楽の受容にも似ている
これはまったく個人的な
おそらくかなり特殊な受容の仕方なのだが
ぼくにとっては「短歌」だけではなく
「音楽」もほとんどその時代的な順序が
シャッフルされたかたちで受容されてきた
むしろロックとポップスの時代の後に
現代音楽とジャズの時代が来て
その後クラシックや古楽の時代が来ることになり
今では上記の「短歌」と同じく
交錯かつ時代錯誤的な受容を行っている
ある意味ではこうした受容の仕方は
インターネット的な関係性の網目のなかの
時代やジャンルを越えたところでの受容の仕方と
通じたところがあるのかもしれない
そんなこんなもあり
ぼくのばあいはオーソドックスなクラシックの前に
「現代音楽」という
いわば前衛的ともかつていわれた音楽があり
〈近代〉を代表する歌人としての斎藤茂吉の前に
〈戦後〉を代表する歌人としての塚本邦雄がいる
しかしあらためて古代から現代まで
時代を追いながら「歌」をみていくと
ある時代にはその時代においてしか
生きて機能しない表現があることがわかる
その時代にはその時代でしか作ることのできない
「新しいオモチャのような歌」があるのだ
いまや「現代音楽」はすでに
「新しいオモチャのような歌」
ではなくなっているように
「前衛短歌」とされている歌も
(個人的にはすいぶん惹かれるけれど)
「新しいオモチャのような歌」ではなくなっている
穂村弘『短歌の友人』は
15年ほどまえに刊行されたものだが
この15年ほどのあいだに
「新しいオモチャのような歌」は
つくられてきただろうか
いまもつくられているだろうか
ようやく「歌集」を読み始めた初心者にとって
現在つくられている短歌の世界の地図は
まだ見えてこないところがある
できうれば「新しいオモチャのような歌」が
続々と生まれてきますように
「新しいオモチャのような歌」かどうかは
まだわからないけれど
最近気に入っている歌集に
川野芽生『Lilith(リリス)』と
大森静佳『カミーユ』がある
気に入る歌集はなぜか女性の作者のものばかりだが
どうも女性の言葉のほうが
するりと入り込んでくるところがある
魂の深いところにとどく言霊の力があるのだろうか
■穂村弘『短歌の友人』
(河出書房新社 2007.12)
■『塚本邦雄歌集』
(現代詩文庫501 思潮社 2007.10)
(穂村弘『短歌の友人』〜「第6章 短歌と〈私〉」より)
「〈近代〉を代表する歌人として斎藤茂吉、〈戦後〉を代表する歌人として塚本邦雄を想定するとき、我々は次のような印象を抱かないだろうか。すなわち塚本邦雄の歌は確かに凄い、でもどこかオモチャのようでもある、一方、斎藤茂吉の歌はやはり凄い、そして全くオモチャのようではない、と。この印象の違いはどこから来るのだろう。
斎藤茂吉の歌を支えているものを、私は生のかけがえのなさの原理だと思う。他人とは交換不可能な、一度限りの、かけがえのない〈われ〉の命の重みによって、その作品は保証されている。だが作品の説得力とは、そら自体が独立して存在することはあり得ず、常に読者に対する説得力ということでしかないはずだ。そう考えるとき、現在の読者の目に茂吉の歌が全くオモチャのようには見えず、凄いとしか感じられないとしたら、それは我々が〈近代〉的な生のかけがえのなさの原理に、今なお強く呪縛されていることの証とは云えないだろうか。〈近代〉という時間が、茂吉作品における生のかけがえのなさの原理を支え、今も支え続けているのである。
一方、塚本邦雄の作品の核にあるものを、戦争への呪詛と言語のフェティシズムの原理として捉えてみる。生のかけがえのなさの原理を〈近代〉が支えたように、戦争のモチーフと言語のフェティシズムを〈戦後〉という時間が確かに支えたはずである。だが、それによって倦まれた成果が我々の目にオモチャのように映る部分を残しているとしたら、それは、生に対する影響力の点で、〈戦後〉という時間が生んだ最大のものすら〈近代〉の産物に及ばなかったということになりはしないか。
オモチャ的な印象を負っているのは、主に言語のフェティシズムの要素だと思う、それによって短歌定型は空間化して言葉はモノ化した。〈戦後〉の空気の中で、我々は揃ってそのような言葉のモノ化にどっぷりと浸かりながら、しかし心からそれを受け入れ納得することはできなかったのだ。
もう一点、時間の追い風の受け方ということで云えば、茂吉的な言葉が〈近代〉の理念に対して完全に従順であったのに対して、塚本的な言葉は〈戦後〉の理念に対して単純に順接でははあり得なかったという違いがあると思う。
本当は(という云い方は無意味だが)子規も茂吉も、塚本同様に短歌をオモチャ化したはずなのである。すべての変革とは、その瞬間を切り取れば常にオモチャ化とイコールなのだから。ただ今日の我々の目にそのように映らないだけである。その理由は、繰り返しになるが、我々が今もなお〈近代〉のモードの内部を生きていることに拠る。
〈近代〉や〈戦後〉の時間が生み出す磁場には、そのときどきで明らかに強弱の変化がある。比較すると、やはり我々は〈戦後〉の理念や言語のフェティシズムの中を生きる以上に、生のかけがえのなさの原理を生きていると思う。ここ十年ほどの間にその傾向は一層強まっているように感じる。(・・・)」
「三つの時間の中で〈今〉はもっともわかりやすい。どのような時代のどのような人間も〈今〉を生きるしかない。〈今〉とは常に生の特異点なのである。だが、我々の〈今〉には、その上にさらに特別の意味が付加されるのではないか。〈近代〉や〈戦後〉のような、いや、そうした日本固有の時を離れて、もっと大きな意味で特別な時間になる可能性がある。
ひとつには情報革命に絡んだ動きが挙げられる、インターネットには確かに未来を生きている感覚がある。さらに我々の〈今〉には「もっと大きな意味で特別」なことがある。それは、人類の終焉の生起を生きる、という意味である。人類史上もっとも幸福で、しかし心のレベルとしては最低の生を生き、種の最期に立ち会おうとしている我々の〈今〉が特異点にならないはずがない。
我々は新しい歌を作らなくてはならない。新しいオモチャのような歌を。それは人間が存在しない世界に向けての歌になるかもしれないのだから。」
(穂村弘『短歌の友人』〜「第7章 歌人論」より)
「(塚本邦雄)の作品世界の本質には、「戦後」的な喜びと快楽に満ちたレトリックによって「戦後」の流れを撃つ、という二律背反があったと思う。「戦争」への憎悪、及び「戦後」的なるものへの違和を詠い続けた塚本邦雄は、その表現面の特質において、確かに「戦後」の短歌表現の起点でもあったのだ。
塚本作品のアンビバレントな波動の強さに、「戦後」に首まで浸かった私たちは怯え、混乱しながら、さらに惹きつけられていった。人ではないく歌そのものを直にみる選歌眼の鋭さも驚嘆の的だった。(・・・)
だが、長い時間の流れの中で、塚本自身の内なる呪詛は徐々にその生々しさを失っていったように思える。おそらくはその反映として表現は機械的な繰り返しの印象を帯びるようになった。多彩なレトリックは対象を撃つための武器から転じて超高度な玩具に変質したように感じられた。始めからオモチャの言葉で遊んでいた私は生きを呑んでそれを見つめた。
塚本邦雄はモチーフと表現の両面から(その二律背反性をも含めて)、まさしく「戦後」を象徴する歌人だと思う。彼の死によって「戦後」は終わった。後に残されたのは「戦前」とも「戦争」とも無関係な、無重力時間としての「戦後後」である。
今、私たちが目の前で手をひらひらさせると、そこには重力も方角もない世界。武器どころかオモチャとしての言葉さえ溶けてしまうそんな場所で。私たちは、私はどんな歌を作ることができるのだろう。」
