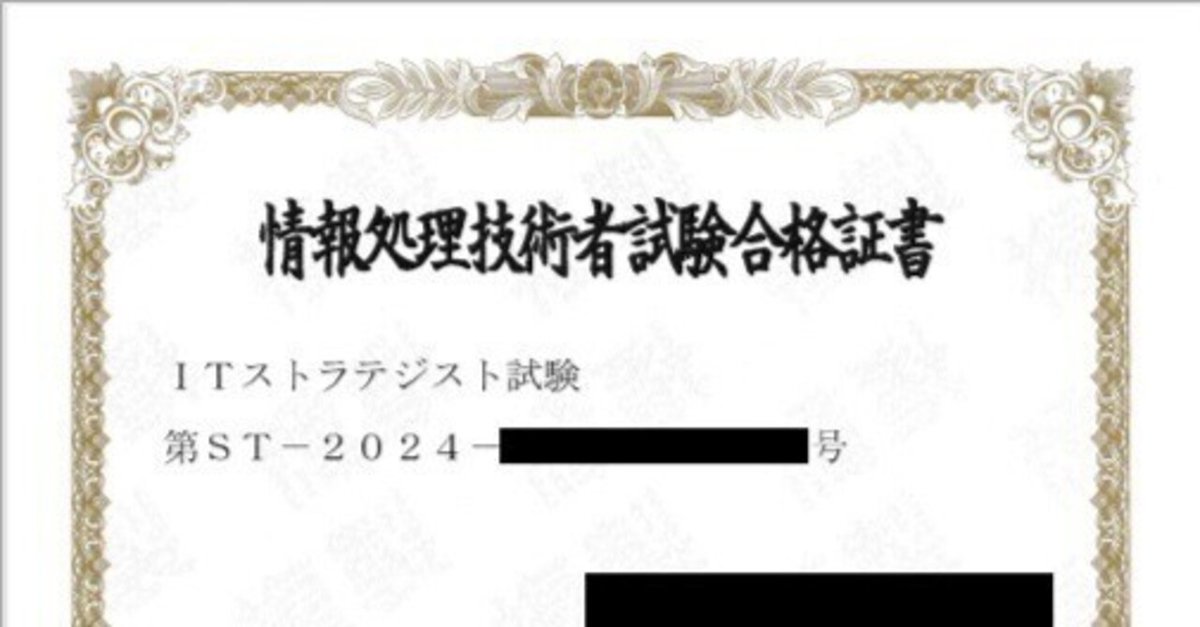
ITストラテジスト試験に独学で合格した勉強方法(合格体験記)
2024年4月のITストラテジスト試験に合格しました。
私は、2回目の受験で合格することができましたので、1回目の反省点も踏まえ、合格体験記として、勉強方法等をご紹介いたします。
私の体験が皆さまの一助になれば幸いでございます。

参考までに、1回目の試験結果は以下のとおり、午後Ⅰ通過ならずでした。
→ 午前Ⅰ:免除、午前Ⅱ:92、午後Ⅰ:56、午後Ⅱ:-(採点無)
1.ITストラテジスト試験とは
■対象者像
高度IT人材として確立した専門分野をもち、企業の経営戦略に基づいて、ビジネスモデルや企業活動における特定のプロセスについて、情報技術(IT)を活用して事業を改革・高度化・最適化するための基本戦略を策定・提案・推進する者
■受験資格 ・受験料
・年齢、学歴等に制限はなく誰でも受験可能
・受験料:7,500円(税込)
■試験時間・出題形式・出題数(解答数)
・午前Ⅰ 9:30~10:20(50分)
多肢選択式(四肢択一)
出題数:30問 解答数:30問
・午前Ⅱ 10:50~11:30(40分)
多肢選択式(四肢択一)
出題数:25問 解答数:25問
・午後Ⅰ 12:30~14:00(90分)
記述式
出題数:3問 解答数:2問
・午後Ⅱ 14:30~16:30(120分)
論述式
出題数:2問 解答数:1問
2.試験合格のメリット
ITストラテジスト試験に合格することで、経営戦略とITとの橋渡し(経営戦略の中にIT技術を取り入れる)するために必要な知識や実践能力が身についているものとして国からお墨付きが貰え、企業によっては、報奨金の対象や昇格の条件になっています。
ITストラテジスト試験の合格者は、他の資格試験で免除される項目があり、将来的にこれらの資格取得を目指している方は、視野に入れておくとよいかと思います。
■試験と免除される試験内容
・中小企業診断士試験:第一次試験科目の一部免除
・弁理士試験:論文式筆記試験の選択科目(理工Ⅴ・情報)が免除
・技術士試験:第一次試験の専門科目(情報工学部門)が免除
・ITコーディネータ(ITC)試験:ITC試験の一部が免除される専門スキル 特別認定試験を受験可能
3.受験理由
IPAの試験は、20代の頃に基本情報技術者試験(2回目で合格)、ソフトウェア開発技術者試験(現:応用情報技術者試験、2回目で合格)、情報セキュリティアドミニストレータ試験(現:情報セキュリティマネジメント試験、初回合格)を受験しておりました。以降、久しくIPAの試験から離れておりました。
そうこうしている内に40代になり、他企業の方とも交流を深める中で多くの良い刺激をいただき、「久々に勉強してみようかな」という気持ちになったことが大きなきっかけになったと思います。
その後、2019年に情報処理安全確保支援士(初回合格)、2022年にネットワークスペシャリスト(初回合格)に合格し、2023年にプロジェクトマネージャ試験に合格(2022年度は不合格)したこともあり、さらに論文試験に挑戦しようという気持ちになりました。
加えて、仕事がらシステム企画に携わる機会(とはいってもDX+ビジネス創出や大規模システムといったレベルの高いものではないです)も少々ったことから、「経営とITの橋渡し」は自身の必要テーマと位置づけ受験を決めました。
上述のとおり、2023年の試験は午後Ⅰの論述試験が通過できず残念な結果となりましたが、2024年の試験で無事に合格することができました。
4.午前Ⅰの勉強方法
(勉強時間→10~15時間 ※免除のため参考目安)
正直、午前Ⅰは午前Ⅱ以降への注力を考慮すると、「免除」の権利を取得しておくことが望ましいです。
応用情報技術者試験・安全確保支援士試験・他高度試験の合格、または、他高度試験・安全確保支援士試験の午前Ⅰのみの合格により、合格後2年間は「免除」の権利を取得することができます。
午前Ⅰから受験する場合は、過去問演習を中心に実施しましょう。
高度午前Ⅰはその回の応用情報の午前問題から30問を抜き出して作られるので、応用情報午前問題と問題範囲は同様となります。
よって、解説のついている応用情報の過去問対策サイトで直近5~6年分を
対策しておけば問題ないと思います。
5.午前Ⅱの勉強方法
(勉強時間→15~20時間)
こちらも過去問対策サイト(masassiahさんのサイト)で平成25年度分から令和5年度までの過去問を解きました。
ただし、2024年の試験では新問題がいくつか出題されました。
よって、答えだけを暗記するのではなく、「なぜそのような回答になるのか」を過去問対策サイトの解説を確認しながら体系的に理解するようにしましょう。午後に必要な知識定着にもつながるのでお勧めです。
高度系の情報処理技術者試験の午前Ⅱ対策においては、前年度の過去問はやらないのが定石(同じ問題が連続で出題されることはほぼない)なのですが、過去問をアレンジしている傾向が見て取れることから、念のため直近の令和5年度の問題も解き、正解以外の選択肢も一通り目を通しておきました。
6.午後Ⅰの勉強方法
(勉強時間→初回受験時(60時間)、2回目受験時(15時間))
過去問中心の学習で問題ないかと思います。
翔泳社 の問題集一冊で勉強しました。
PDFとはなりますが、過去問の解説も豊富で、私は、iPadMiniにダウンロードし活用しました。「標語集」のようなものも含まれており、大変参考になりました。
過去問の傾向として、平成30年度の試験から徐々に新技術関連の問題が出題されていると感じますので、最低限、平成30年度以降の問題は実施しておいた方がよいかと思います。
ちなみに、令和5年度以前の問4は、現在の「エンベデッドスペシャリスト試験」の範囲ですので、問1~3までを解くイメージで良いかと思います。
高度試験初めての方は、以下のとおりフェーズを分けて解くことをお勧めします。高度試験が2回目以降等、長文読解問題に慣れている方は、フェーズ2から実施してもよいかもしれません。
■フェーズ1
最初は時間をかけてもよいので、全問解き切ることを意識し、解答後はじ っくり解説を読み込み、なぜそのような解答になるのかを自身に腹落ちさせましょう。例えば、平成30年度と平成31年度の6問を当フェーズで実施する等も一案です。
昨年度との勉強方法の大きな違いはこの点です。やみくもに過去問を解くのではなく、勉強期間内に自身に腹落ちさせるフェーズを設定することが肝要と考えます。
■フェーズ2
時間を図って解く「訓練」を行ってみましょう。
例えば、令和3年度から令和6年度の12問を当フェーズで実施することも一案です。
ちなみに、基礎基礎知識から体系的に学びたい場合は、以下参考書を活用しても良いかと思います。
7.午後Ⅱの勉強方法
(勉強時間→初回受験時(50時間)、2回目受験時(20時間))
午後Ⅰと同様、翔泳社の問題集を活用しました。
加えて、以下論文事例集を活用しました。
午後の最大の鬼門となる論文試験となります。
上述のとおり、論文テーマを「とある損保会社の新たなサービス(健康増進型特約付き医療保険)の企画」に絞り、自身でイメージしやすいかたちでエクセル表にまとめたことです。
具体的には、以下の要素を整理・可視化していくことで、企画内容を具体化していきました。特に、以下の観点を体系的に整理していきました。
(一部、私の事例を記載)
■テーマ
損保会社の新たなサービス(健康増進型特約付き医療保険)の企画
■プロジェクトの概要
〇ウェアラブルデバイスとAIを活用した保険の新サービスの構想
〇金融・保険、1,001~5,000人、営業・販売
〇その他(パブリッククラウド上にサーバ約10台、保険契約者のウェアラブルデバイスやモバイルデバイス数十万台規模)
〇ネットワークの範囲→他企業・他機関との間、利用者→3,001人以上
〇総工数:※検討に要した関係者工数 約8人月 → 開発全体は500人月
〇総額 :※検討においては実費用無 約 0百万円 → 開発全体は500百万円
〇期間 :2020年7月~2020年8月
〇あなたが所属する企業・機関:一般企業などのその他の部門
〇あなたの担当業務・役割 :情報システム戦略策定・全体責任者
〇あなたが所属する構成員 :1~5名
〇あなたの担当期間 :2020年7月~2020年8月
■プロジェクト期間
〇システム開発12か月(2020年9月~2021年8月)
・アプリ(アジャイル開発)
要件定義・設計・開発・受け入れ検証:2020年9月~2021年4月
・インフラ(ウオーターフォール開発)
要件定義:2020年9月~10月
設計・構築・検証:2020年11月~2021年~4月
・システムテスト:2021年5月~6月
・総合テスト:2021年7月~8月
〇試行販売6か月(2021年9月~2022年2月)
・新サービスの有効性の検証を目的とした試行販売の実施:2021年9月~11月
・新サービスの評価と課題対応:2021年12月~2022年2月
■ステークホルダー
〇経営企画部 ※自分
〇商品企画部 商品・サービス開発
〇営業推進部 販売・販売促進
〇コンタクトセンタ 既存契約者やその他問い合わせ者の対応
〇情報システム部 システム開発・保守・運用
〇経営管理部 予算統制
〇リスク統括部 リスク・コンプライアンス
〇人事部 新サービス(商品)研修、DX人材育成
〇情報システム子会社
■事業概要
××社は、売上1400億円、従業員数1500名、総契約件数約400万件の損害保険会社であり、自動車保険等の損害保険に加え、医療保険も取り扱っている。損保業界の中では中堅(シェアは10%)であり、主な顧客層は日本全国の20~60歳台である。
■事業環境・事業特性
SWOT分析の結果の切り口でまとめると整理しやすいかと思います。例えば、事業環境は機会・脅威の観点、事業特性は××社の強み・弱みの観点で整理する等
■事業目標・事業戦略
事業目標は××年後に売上××%UPの×××億円にする等です。また、事業戦略はアンゾフの成長マトリクス等の切り口を織り交ぜながら整理すると、より具体性・説得力が増すと思います。
その他、過去問の切り口から以下の内容についても整理しました。
■実現したサービス・業務プロセス
■サービス提供者(ターゲット)
■事業目標達成への貢献内容
■ニーズ、便益、提供価値
■活用したディジタル技術
■活用したデータ
■収益モデル
■投資効果
■ITの導入プロセス
■初期利用者の獲得
■推進体制
■評価を受けて考慮した事項
■評価と改善
■新サービスの問題認識と改善要望
■緊急性が高いシステム化要求に対応するための優先順位・スケジュールの策定について
ちなみに、プロジェクトマネージャ試験の時と同様、サンプル論文の写経等は行っておりません。
一部実施されている方もいらっしゃいますが、やはり、写経より論文骨子を「考えて」「構成する」方が自身の血肉になった実感がありました。
なお、ITストラテジストを一から勉強する際は、以下書籍も参考になると思いますのでご紹介します。
上述のとおり、私は「とある損保会社の新たなサービス(健康増進型特約付き医療保険)の企画」をテーマにネタを収集・整理していったため保険業界にかかる書籍を閲覧しイメージアップを図りました。
↓業界のしくみとビジネスがしっかりわかるシリーズです。
8.試験当日の状況・留意事項等
プロジェクトマネージャ試験の時とほぼ同じムーブです。
■前日と朝
1回目、2回目ともに午前Ⅰ免除でしたが、余裕をもって、前日は22時か23時頃に就寝、当日6時30分に起床のスケジュールとしました。
早起きの理由としては、試験会場には、余裕を持って遅くとも1時間から1時間半前には到着したかったためであり、電車遅延時にも速やかにリカバリできる態勢にしておきました。
朝ご飯は割としっかり目に食べ、コーヒーを飲みながら午前Ⅱの最終確認を行うことで、脳のウォーミングアップになりました。
■お昼
昼食は早めに試験会場に到着する場合は、近くのコンビニで購入することもありですが、私は前日に準備を済ませました。(カロリーメイトフルーツ味4本入り、トマトジュース、麦茶、チョコレート)です。
■試験中
他の皆さんも記載しておりますが、高度試験区分は特に脳を使うので、午前Ⅱ、午後Ⅰ、午後Ⅱの前には必ずチョコレートを食べて糖分を摂取するように心がけました。
午後Ⅰは国語の試験という方が多いですが、1回目・2回目に受験した際もその要素は高く、「設問のヒントや答えは必ず問題文中にある」印象でした。(稀に、知識を問う穴埋め問題ありますが)
よって、自身の思い込みや根拠のない解答にならないよう配慮しました。
午後Ⅱは月並みなことですが、問題文の「重要である」や「必要である」箇所に気を付けながら、題意を把握します。また、問題に記載されている例示(例えば、、、)は参考にしても良いですが、過去の講評でそのまま記載している旨指摘されたこともあるため、例示を参考にしつつ、具体的に(少し掘り下げて)記載するように配慮してください。
また、設問で問われていることには、一つずつ丁寧に論文に盛り込むように配慮してください。以下のとおり、副題として整理すると比較的抜け漏れなく盛り込めると思います。
以下はあくまで例です。副題内にさらに(1)(2)等分けることも有
1.設問1の主題
1-1.設問1の副題1
1-2.設問1の副題2
2.設問2の主題
2―1.設問2の副題1
2―2.設問2の副題2
2―3.設問2の副題3
3.設問3の主題
3―1.設問3の副題1
3―2.設問3の副題2
