
自主防災・避難誘導マニュアル(風水害編)第一章 大雨・洪水災害発生の危険があるとき
1.市内を流れる魚野川などの水防警報について
「水防団待機水位」 通常の水位から上昇し水防団の出動準備の目安となる水位
↓
「氾濫注意水位」 水防団の出動の目安となる水位(警戒水位)
↓
「避難判断水位」 自治体の高齢者等避難発令の判断目安
↓
「氾濫危険水位」 自治体の避難指示発令の判断目安(洪水特別警戒水位)
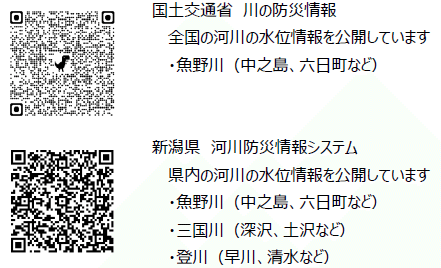
2.警報や避難情報の種類

【注意】
自治会が自主防災組織として災害時の対処行動を開始する起点は【警戒レベル3】高齢者等避難の発令時点となります
また、【警戒レベル4】発令以降は、自治会(自主防災組織)としての避難支援や救助支援活動などの継続が実質的に困難であり、自身と家族の安全確保を優先し、近隣の住民と声を掛け合い、助け合って速やかに個々の避難行動に移行することになります
3.市から住民への情報伝達について
市内で災害が発生、又は発生するおそれがある場合、市の緊急広報部はテレビ、ラジオ、防災行政無線、FMゆきぐに、ホームページなどあらゆる手段を用いて注意を呼びかける、また、広報車等により住民の避難の確認に努めるとしています
電話・緊急速報メール・緊急告知ラジオ・個別訪問・広報車等による呼びかけ及び印刷物の配付・掲示など
市の情報伝達フローでは行政区長に発令の連絡が入ることになっています
県からテレビ、ラジオ、新聞など各報道メディアへ報道依頼が出されます
FMゆきぐにでは緊急割り込み放送を活用した情報提供がされます
インターネットによる情報発信(パソコン、携帯サイト、多言語サイト)など
■自治会の情報伝達フローについて

■広報にしいずみだX(旧ツイッター)
https://x.com/nishi_izumida_1
日頃から区のお知らせ発行などを通知していますが、地域で重大な事案(火事や事故、クマが出たとか)が発生したとか、市から避難準備情報などが発出されたなどの情報も周知する予定ですので是非、フォローしてください

4.西泉田周辺の浸水エリアについて
市の大雨・洪水災害発生時の予測では、西泉田の域内のほぼ全てで浸水深さ0.5M~最大3Mと想定されており、発災の場合には西泉田区のほぼ全世帯が避難指示の対象地域となります

5.指定避難所の開設について(市の開設基準)
南魚沼市内で震度5強以上の地震が観測され必要とするとき
避難に関する情報が発令されたとき(高齢者等避難など)
台風などの進路予測により、災害発生の可能性が高いと判断したとき
国民保護事象が発生し、住民の避難が必要と判断したとき(某国がミサイル発射とか…)
その他、市長が必要と認めたとき
6.西泉田区民が向かうべき避難所について
●大雨・洪水災害などの際に西泉田区民が避難先とするのは、以下を最初の目標としてください
総合支援学校の体育館(172人の避難が可能)Tel025-773-3770
【注意】西泉田公民館(集会所)は、災害時における区の一時避難所となっていますが、河川に近く浸水深さも高いため大雨・洪水災害の際には避難の要所となりません
また、日中の児童就学時間帯における発災の際には、全ての市内の各小学校、中学校、高校の体育館は指定避難所となっていることから、急いで迎えに行かなくとも子供たちは教員などの誘導によりそちらで安全に避難していることとなります
●総合支援学校がいっぱいで入れないなどの代替避難所
南魚沼市民会館(1,272人の避難が可能)Tel025-773-5500
但し一旦は総合支援学校に到達できていたなら、時間帯や天候、周囲の状況を充分考慮して慎重に、市の災対職員や自治会役員などと相談しましょう、市民会館の周辺部は0.5M程度、冠水している可能性もあります
7.指定避難所(総合支援学校)の開設と開錠について

8.避難の経路と方法
近年豪雨をもたらす線状降水帯は8割近く夜間に発生しているとのこと、昨今の気象予測はとても精緻ですので情報に注意して、既に明るくない時間帯であったとしても速やかに避難所へ向かうべきか、このまま家の2階以上へ退避すべきか判断してください
避難にあたっては、できるだけ速やかに浸水危険エリアから脱するため、一旦は291号線を超えて国道17号線まで西を目指します、そこで安全を確保できたら慌てずに国道沿いに移動して総合支援学校まで到達してください
既に道が大雨などで冠水している場合、側溝や排水路の区別が分からなくなっていますので、できるだけ集団で高齢者や子供と手をつなぎ、先導者としんがりを必ず大人が担ってください
避難指示が発令されると域内の車の通行は規制されます、総合支援学校には、もともと車を止める広いスペースはありませんので、避難指示等が発令されてから車で向かっても周辺道路で混雑し渋滞で近づけない、入れない、留め置く場所もない可能性が高いと考えてください

【ひとこと補足】
大事な車を是が非でも守りたい方は、大雨・洪水警報などの時点で、あらかじめ自分で決めておいた場所へ車を逃がしましょう、西の方面に行けば空地はたくさん在ります
9.避難時の服装や準備しておく物など
動きやすい長袖、長ズボン、履きなれたスニーカーで避難してください(長靴は水が入ってしまうと歩行が困難になるため避けましょう)
台風などによる大雨災害なら、なにが風で飛んでくるか分かりません、転倒に備えて頭を守るためにも必ず帽子やヘルメットをかぶりましょう
道路が冠水していると側溝の位置や段差、溢れて蓋がずれているマンホールなどが分かりません、杖や傘があると足元を探って確認しながら進むことができます
避難時に必要なものはリュックに入れて両手を空けておき、できれば軍手を着用してください
非常用持ち出し袋は避難する際の負担にならないように必要最小限にします
飲料水(ジュースやお茶より、用途が広い水がお勧めです)
食料品…ビスケット、クラッカー、チョコレート、レトルト食品、缶詰など
懐中電灯、携帯ラジオ
携帯電話と充電器、モバイルバッテリー
着替え、タオル
マスク、除菌ウェットティッシュ、常備薬、生理用品など
紙皿、紙コップ(マイ箸やラップあれば便利だと)
貴重品(預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など)
乳児がいる場合は、抱っこベルト、ミルク、紙おむつ、哺乳びん、おしり拭き、ゴミ袋など
10.区は災害時には自主防災組織体制へ移行します
<高齢者等避難【警戒レベル3】発令時より>
自治会役員は自主防災組織体制へ移行し可能な時点で区の災対本部へ参集、区長の指示のもと情報連絡体制を確立し市災対本部と連携業務などをおこなう
●大雨・洪水災害時 → 総合支援学校が区の災対本部となる
●その他の災害時 → 被災していなければ公民館を区の災対本部とする
■自主防災体制へ移行後の主な役割り分担について(災害の初期段階)
[区長 ]全体統括と指揮、市災対本部、警察・消防、福祉機関などとの連携調整
[副区長] 域内の情報収集と自主防災組織の連絡統制
[会計] 情報の集約と整理、憂慮事案の対応履歴の記録及び経過報告
[消防委員長]消防団との連携連絡窓口となり支援要請や対応状況の把握を担う
[公民館長]防災備品等を随時利用可能とするため速やかに公民館を開錠する
[各区伍長]区民の安否確認、不明者の所在確認や捜索支援要請など
[総務委員]市の災対職員と協働して避難所の速やかな開設と円滑な運営を支援する
[土木委員]消防団と協働して冠水時における危険個所などにおける避難誘導を支援する
[環境委員]避難所の環境班・物資班として環境整備と資材支援物資の管理を担う
11.避難者が避難所へ着いたら最初に協力いただきたいこと
①避難者受付簿の記入
避難できた方を確認するため、最初に代表者から「避難者受付簿」に記名してください
市の災対職員が不在の場合は自治会役員が受付を担います
→巻末参考資料 別紙5-2「避難者受付簿」
② 避難者カードの作成
避難者スペースでひとまず落ち着くことができた段階で、家族全員の安否を確認するため「避難者カード」を世帯単位で作成しますのでご協力ください
伍長さんと自治会役員などが手分けをして聞き取り作成します
→ 南魚沼市指定避難所運営マニュアル 別紙6「避難者カード」
前記①②は、域内に行方が分からず連絡の取れない方や、とり残されていて助けが必要な方がいないかなどを把握するために、とても重要な情報収集と確認ですので、ご理解ご協力をお願いします
③ ペットの取り扱い
避難者が居住するスペースにはペットを連れ込むことはできないそうです
避難所の敷地内もしくは近くにペット専用の場所を確保できるよう、市の災対職員が施設管理と協議して配慮してくれることになっていますので相談してください

12.災害後の検証(ふたたび災害のおそれの時のために)
水害の経過後に安全が確保されたら、区長、土木委員長、消防団は、損壊箇所、冠水エリア、その他必要な個所の巡視をおこない水害の発災要所となった地点を確認する、総務委員は地域の被災状況の記録をおこなうこと
自治会は、市、河川管理者、道路施設管理者等の復旧計画を把握し、災害再発防止の視点から充分な補強対策が網羅、包含されているか確認すること
この後、ふたたび大雨・洪水災害のおそれがある際において、監視と警戒が必要な重要個所として防災計画等に対処を盛り込む、防災マップ等に記録し伝承する必要性の有無及び、平常時における新たな防災取り組みの検討が必要か、検証し記録を残すこと
13.防災用備品等の配置と点検(平常時、公民館長と消防委員長)
区の防災用備品及び設備等は、公民館防災キャビネット、館内の収納庫の他、水防倉庫に分散配置され、自治会役員などにあらかじめ貸与したヘルメット等については役員交代の際に継承とします
● 西泉田区防災設備の配置表(別紙を参照)
防災用備品と設備等については、公民館長と消防委員長の管理とし、毎年度当初に配置設備の確認と正常動作、消耗品(乾電池や消火器など)の耐用期限などを確認し、更改修繕などの要否について区長に報告します
区の半鐘サイレン動作確認など、消防団所掌設備の健全性確認は、毎年度の防災訓練等の機会に、消防団と相談して協働実施します。また、春の一斉清掃実施時に合わせて、区民広場地下にある防火貯水槽の貯水量などを点検確認します
あらかじめ充電が必要な小電力無線機(トランシーバー)等については、年度の当初に公民館内で充電しておき、定期的(四半期ごと程度)に点検し再充電する
非常用発電機の燃料については、発電機に充填されていた燃料は概ね1年程度で劣化するため、前年度、全く使われなかった場合は次年度当初に一旦、廃棄し新たに充填します。また、ガソリン携行缶詰の燃料については使用期限が3年間ですので、いつ充填したものかタンクに充填日付を書いて貼り付けてください
