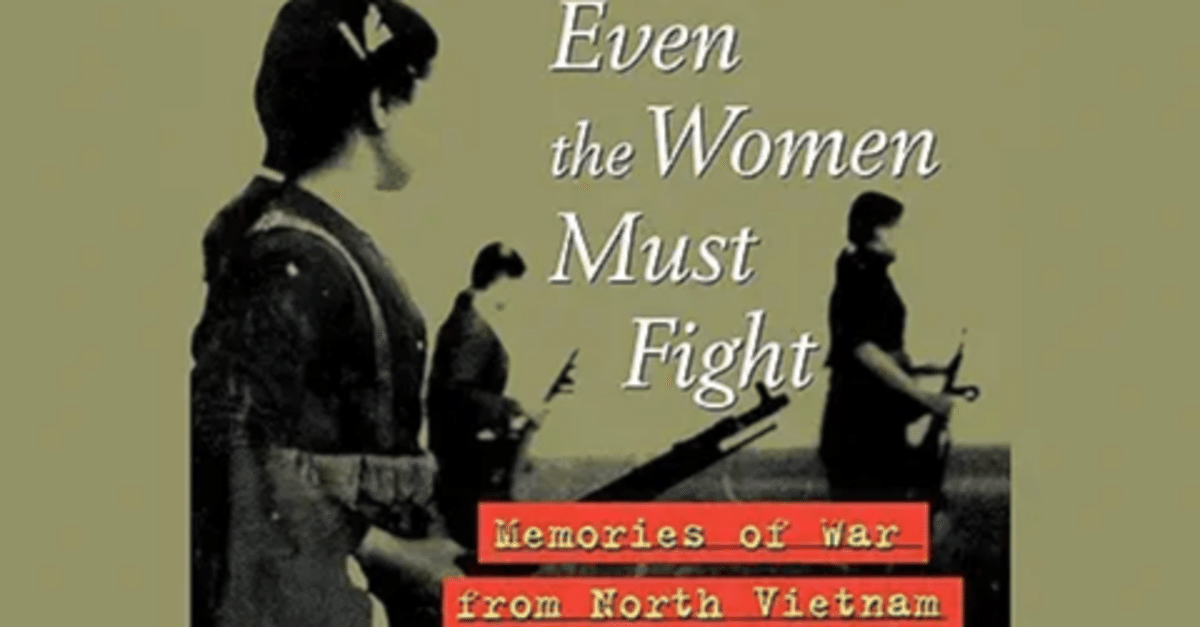
Ⅰー42.文献篇(4)カレン・G.ターナー&ファン・タイン・ハオ著『女でも戦わなければならない 北ベトナムからの戦争の記憶』(1998年)(前篇)
文献篇(4)カレン・G. ターナー&ファン・タイン・ハオ著『女でも戦わなければならない 北ベトナムからの戦争の記憶』(1998年)
Karen Gottschang Turner with Phan Thanh Hao, Even the Women Must Fight:Memories of War from North Vietnam, John Wiley & Sons,Inc, New York, 1998. 全224ページ。
はじめに
本書は、アメリカの女性研究者カレン・G.ターナーが、ベトナム人女性の友人ファン・タイン・ハオの協力をえて、北ベトナムの女性たちにベトナム戦争について聞き取りしたものを見聞録風にまとめたものである。
著者のターナーは米国ホーリークロス・カレッジ准教授で東アジア史専攻。ハーヴァード・ロースクールで東アジア法研究プログラム研究員もしていた。同プログラムで中越の女性の法的地位の比較研究に携わっていた。1993年、ハノイの国民経済大学に赴任した夫に従い、ハノイに滞在した。
ファン・タイン・ハオはターナーのハノイ滞在時の隣人で、40代なかばのジャーナリスト。1960年代後半に青年突撃隊に入隊し、ハノイでの爆死者の搬送などに従事した経験がある。
本書は、アメリカ人による、北ベトナム在住女性を対象とした(難民ではなく)、ベトナム戦争に関する最初のオーラル・ヒストリーだと思われる。以下では本書の梗概を紹介していきたい。

本書の構成
本書は、以下の通り、イントロダクション、全三部(全9章を含む)、エピローグによって構成されている。
●イントロダクション
●第一部:メーセージ
第1章:ヘヤーネットを通して:母親、戦士、そして民族
第2章:戦争の人々:女性のレンズを通して
第3章:破られた約束:民兵の生活
●第二部:記憶
第4章:花瓶のための砲弾:家を救うために家を離れる
第5章:シャベル、鍬、そして銃:ホーチミン・ルートの女性たち
第6章:兵士だけ:戦争中の女と男
第7章:女だけ:母親兵士
第8章:破片を集める:家に行く
●第三部:意味
第9章:ご飯のないご飯
●エピローグ
Ⅰ.イントロダクション:幸運な距離
◆私は戦争から「幸運な距離」があったので、ベトナム女性にとっての戦争・家族・よき人生の意味をよく理解していなかった。1993年5月、2人のベトナム人女性の友人が戦争が意味することを語ってくれて、見方が変わった。1965~1975年のアメリカ戦争(筆者注:ターナーは「ベトナム戦争」という言葉を使わず「アメリカ戦争」という言葉を使う)で、ベトナム女性は男性とは違ったやり方で戦争に奉仕し、高価な代償(不妊、非婚、中傷など)を支払った。特に市場経済化され、若さと競争精神が重要な時になると、女性たちの犠牲は見逃され、その貢献は矮小化された。もはや戦争のことなど思い出したくないとする風潮もあるが、すべてのベトナム人が過去を振り返ることなしに新しい時代を歓迎しているわけではない。
ベトナムのことわざ「戦争が家の近くで起きたら、女も戦わなければならない」とあるように、ベトナムでは女性は戦士であり母親でもある。
1993年6月、私はアメリカに帰国した。
◆女性、戦争、ベトナムについて考え始めた。なぜベトナムの女性戦士は、大半のアメリカ人にとって目に見えないものとなっていたのか。戦争の話は、戦場で戦った男性の領域とされ、女性は脇におかれ副次的地位を占めるだけだった。ベトナム女性の姿は、米越両国ともに、闘争と勝利の国家の記録からあまりに消えている。ベトナムでは傷痍軍人の公的救済は男性に対してが主で女性には考えられず、英語のベトナム戦争関連書籍では人民戦争は男性像のみである。ふつうの女性の記憶はオーラル・ヒストリーのみにて保存される。
◆1996年初、女性の退役軍人(筆者注:ここでは元青年突撃隊隊員を含む)聞き取りをするためにベトナムに戻った。アメリカにいた3年間、私は女性戦士を革命の輝かしい英雄たちとだけ考えていた。一方、ハオは集合的悲しみを取り上げ英雄的モードを否定しようとした。
最初、私は、いかに女性たちが戦争を記憶しているか、国の歴史のなかでどう位置付けているかを記録するため、この本をオーラル・ヒストリーから書こうとした。
ほかには、文学や文書資料(手紙、日記、詩、捕虜尋問調書)を利用する道もある。米軍による捕虜尋問調書はサイゴンに送られ、合同文書開発センター(Combined Document Exploitation Center, CDEC)に保存された。この中には女性兵士の記録もある。これらは諜報機関によって分析された後、国家文書館に送られ、現在、マイクロ・フィルム94リールがボストンのマサチューセッツ大学で利用可能である。歴史家にとって貴重な資料だが、あまり利用されていない。ベトナムにおける戦時中の著作物、テレビ番組、映画などもある。
南ベトナムでの状況については、ベトナム難民の証言・オーラルヒストリーによって、アメリカでは比較的よく知られている。たとえば、ジェームズ・フリーマンの『悲しみの心:ベトナム人の生活』(James Freeman, Hearts of Sorrow: Vietnamese Lives, Stanford U. Press,1989)などがある。またレ・リー・ヘイスリップ(Le Ly Hayslip)とレディー・ボートン(Lady Borton)の著作もある。

邦訳『天と地』ベトナム篇上・下(角川文庫、1993年)

北ベトナムの女性の戦争奉仕についてはあまり知られていないので、本書では北ベトナムでの戦争における女性の研究に限定する。女性のパーソナル・ヒストリーを書きたいが、その人達を傷つけたりリスクを負わせたりしたくないので、名前とシチュエーションを変更したところがあるが、話し手の声と記憶の統合性は保とうとした。オーラルヒストリーを使うことの限界と報われる点の両方がある。大半の女性は民族の闘争のストーリーからパーソナル・ヒストリーを外すことを望まない。青年突撃隊元隊員の女性の集まりで、本書の原稿の一節が読み上げられて、参加者に感激されたことがあった。
◆1996年にファン・タイン・ハオと私は一緒に仕事を始めた。ハオが情報収集と翻訳のチェックをし、私が執筆した。戦後、男性の退役軍人の経験が文学やメディアでは主に支配し、女性の経験は無視されてきた。女性にアクティブな役割を与えることによって、標準的な男性の戦争話に対抗するものを書いてみたい。本書のタイトルには、私はヒロイズム、勇敢さを示すものにしたいと思ったが、ハオは犠牲や悲しみを示すようなものを望んだ。アメリカ人は、ベトナム女性をフェミニティーの完全なモデル(父と夫の権威に従順で、受け身で依存的で家庭的)だと見がちで、ベトナム女性の怒りと生き残り戦術を見てこなかった。
◆私がアメリカ人であることの障害もあった。米軍の北爆により家族や友人を亡くしてアメリカを嫌い、語ろうとしなかった人もいる。ハオも家族4人を北爆で失っている。アメリカ人として罪を感じるところだ。しかしハオと私の間の最大の障害は、アメリカがベトナムに爆撃したことではなく、家族と個人の責任についての考え方が違っていることであった。ハオは爆撃については許したが、私が離婚して家族をこわしたことは許容しなかった。ハオは、家族のために戦い、生き残って家族をもてたことは幸運だった、そして女性が戦争について真実を語る時だけ、真の平和がある、と語った。

Ⅱ.第一部:メッセージ
第1章:ヘアネットを通して:母親、戦士、そして民族
◆グエン・クオック・ズン教授:軍事史研究者、退役軍人
空襲に対する防衛の多くは女性によっておこなわれた。
北ベトナム軍の正規軍、民兵、地方軍、専門チームに所属する女性の
総数は約150万人にのぼる。このうち6万人の女性が正規軍に加わ
り、数千人の専門職女性が政府省庁、病院、大学に派遣された。
青年突撃隊のことはほとんど知られていないが、1965~1975年に最低
でも17万人の若者が参加し、その70~80%を女性が占めた。
◆女性の話として戦争を語り直すことにおける3つの目標;
①アメリカ戦争中の女性たちの個人的経験をもって、いかに女性たち
がアメリカ戦争の時を思い出し、いかに彼女らが長期的な民族闘争
の歴史のなかで自分たちを位置づけるのかを示す。
②女性がベトナムの軍事史に入った時、境界がシフトすることを示し
たい。歴史家は、女性が活動した時期と場所が明らかになると見方
を変えるかもしれない。
③ベトナムの事例は、戦争についての道徳的・哲学的問題に重要な考
察を付け加える。女性の存在は戦闘する男性の士気にどのように影
響するのか? 女性の相対的肉体の弱さは戦闘状況における負担な
のか? 女性は男性兵士のように冷静に恒常的な暴力と危険に耐え
ることができるのか? そしてフェミニスト理論家にとって最も困
難で厄介な問題は、戦争は自然な男性の領域であり、平和構築が女
性の本質的タスクであるのか? 母親的思考者・行動者としての女
性と愛国的復讐者との間に実際には矛盾はないのか?
アメリカは歴史上、女性が武器をもつような事態にならなかったが、
世界の近代史上、女性も抵抗運動に参加した。とりわけソ連では1943
年までに軍隊に占める女性の割合は8%で80万人~100万人にのぼっ
たといわれる。
◆戦うベトナム女性の伝統
●徴姉妹(紀元40年)、趙夫人(240年)、ブイ・ティ・スアン(西
山党、18世紀末)
●1922年、ホー・チ・ミンは、女性の抑圧と植民地支配を結び付けて
捉える。
●グエン・ティ・フン(Nguyen Thi Hung)やグエン・ティ・ミン・
カイ(Nguyen Thi Minh Khai)など、農民や労働者の娘から共産党
員になる女性が登場。
●抗仏期、ディエンビエンフーの戦いでは、26万人以上の民工が動員
されたが、半分は女性だといわれる。
●抗仏戦争では参加するかどうか決められたが、抗米戦争では戦わな
ければならなかった。
●1965年6月21日、指示71号により「抗米民族解放突撃青年隊」設
立。5万人を選抜し、41チーム、337隊に編制。
●1966年7月16日、ホー・チ・ミンは若者の大量動員を呼びかける。
1965~1968年にのべ約7万人の女性がホーチミン・ルートで仕事。
1969~1971年に米軍の爆撃が一時停止され、多くの若者が郷里に帰
り、道路は修復された。
1972年に北爆が再開されると、状況は変わり、ほんの1か月間で2
万人以上の青年突撃隊隊員がリクルートされ、4千人がラオス、
8350人が交通運輸省関連で働き、4550人が他の場所に送られた。戦
略道路・地点の防衛や補給などの仕事の70%以上が女性によって担
われた。
●少なくても南部の14万人の女性がスパイ・宣伝工作者・武器製造者
として北ベトナムを支援し、約6万人が「ベトコン」の兵士として
軍事行動に参加していた。約100万人の女性がサイゴン政権から村
を守るのに関与した。
●南ベトナム解放軍副司令官グエン・ティ・ディン(Nguyen Thi
Dinh)の活躍(筆者注:彼女の伝記の邦訳に次のものがある。ビッ
ク・トゥアン著、片山須美子訳『椰子の森の女戦士ー南ベトナム解
放軍副司令官、グエン・ティ・ディンの伝記ー』穂高書店、1992
年)

第2章:戦争の人々:女性のレンズを通して
◆グエン・ティ・ドゥック・ホアン:抗仏・抗米戦争の退役軍人、女
優、映画監督
公的でヒロイックな戦争の話とは異なる話をメディアで伝えた数少な
い女性の一人。彼女の監督した映画作品は、戦中・戦後に女性が直面
した最もセンシティブな問題を扱っている。平和構築者として行動す
る元女性戦士。
●「ジャングルから(Từ một cánh rừng)」(1978年):ホーチミ
ン・ルート建設のためにジャングルに送り込まれたハノイの若者の
姿。女性連絡員の有能さ。
●「愛情と隔たり(Tình yêu và Khoảng cách)」(1984年):戦争で
傷ついた夫を愛せない妻の話。
●「幻影(Ám ảnh)」(1988年):恐怖で南ベトナム軍に逃走した北
ベトナム軍兵士を同情的に描く。
●「川辺の愛(Chuyện tình bên sông)」(1991年):戦争孤児の姉
妹の話。
<筆者注:以上の映画は YouTube で見ることができます。英語の字幕
付き>

第3章:破られた約束:ある女性民兵の人生
◆ゴ・ティ・トゥエン(Ngô Thị Tuyển)
タインホア省のハムゾン橋防衛に尽力し、当時たくさんの報道がされ
た有名な民兵。女性博物館に展示されているその写真はヒロイックな
メッセージを伝えているが、戦後の彼女についてはもう一つのナラテ
ィブがある。彼女は子どもをもつことができなかったので、伝統的な
家族規範が残っている戦後社会において、憐憫の対象となった。
●3つの「担当運動」などにより、職場における女性の数は、1965年
の17万人から1969年には50万人に増加した。
●協力者のハオは、1991年にタインホア省にあるトゥエンの家に招か
れていた。その時のトゥエンの話:「1965年に結婚して数時間後に
夫は南部に出征した。民兵として私はハムゾン橋防衛にあたり、重
い弾薬箱などを運んだりした。その後、夫が戦死したとの知らせを
受けた。解放後、ごく最近、私は傷痍軍人と再婚した。子どもが欲
しかったが、戦争中の重労働で子どもが産めない体になっていた。
養子をもらうつもりだけれど、養子だと私たちの貧困に憤るかも知
れない。あなたがまた会いにくる時にはお子さんを見せて、世話を
させてください」
結局、その約束は果たされなかった。
●1965年の指示71号以後、タインホア省は1万4500人の若者を青年突
撃隊に送り込んだ。他省のおよそ2倍。また3万3000人が地方民兵
となった。同省では、抗仏・抗米戦争で、5万5000人の兵士が戦
死。3人以上の子どもが戦死した母親は136人。2人以上が2511
人。夫と息子の両方が戦死した母親は94人。

Ⅲ.第二部:記憶
第4章:花瓶のための砲弾:家を救うために家を離れる
◆グエン・トゥイ・マウ:1966年から青年突撃隊隊員。C814所属。
戦後、彼女は教育程度があった数少ない例で
学校教師になることができた。未婚で子ども
がいない。また元隊員は退役軍人として認め
られず、退役軍人手当を受給できないのに不
満を抱く。彼女の自宅のテーブルには砲弾か
らつくった花瓶が置かれていた。
●1966年以降、多くの女性が青年突撃隊に入隊した。大半は農村出身で
7年生以下の学歴で、17歳から20歳が多かった。国全体では、17万~
18万人の隊員が生きていて仕事をしているが、公式データによると、
アメリカ戦争中に戦争に奉仕していたのは13万人。
ふつうは兵役を免除されていた男性も、1966年以後は出征。免除され
ていた例は、一人っ子、子だくさんで妻が病弱、中国系、カトリック
信者など。
●1966年以後、北ベトナムでの生活はふつうではなかった。すべては戦
争でくつがえされた。マウと青年突撃隊C814の隊員はハノイ郊外の農
村の家庭を1966年に離れて、ホーチミン・ルートで働いた。彼らの生
活は一変した。彼らが家を救うために家を離れなければならないと語
った時、ほかに選択肢はなく、女性も平和のために暴力に向かうこと
ができたのだと分かった。

第5章:シャベル、鍬、そして銃:ホーチミン・ルートの女性たち
◆女性隊員たちが耐えなければならなかった困難で汚い仕事環境。
1965ー1975年の10年間、チュオンソン山脈で道路建設で働いた2500
日のうち、2000日は自然の力への対処についやされた。
マウと彼女のC814部隊が道路建設に従事した時、彼女らのパーソナ
ル・ヒストリーは、戦争での激戦地の一つ、ホーチミン・ルートの武
勇談と結びついていた。
ベトナムにとって、ホーチミン・ルートは戦略的な重要性とともに象
徴的重要性ももっていた。1965年までに、小道から数万キロにおよぶ
輸送路網となり、北部のクアンビン省と南部のタイニン省を繋いだ。
チュオンソン・ルートは3つのセクターに分けられ、それぞれに559
部隊の司令部がおかれた。
複数の報告によれば、少なくても1968年テト攻勢以前は、病気や自然
災害による被害者の方が敵の攻撃によるものより多かった。1965年後
半では、士官たちは敵の来襲よりは食糧不足やマラリアとの戦いに気
を使った。ファン・チョン・トゥック少将の話によれば、1965年から
の最初の数か月で128号線の労働力の20%以上がマラリアにかかり、
なかには80%におよんだ部隊もあった。
党中央委員会は、1967ー1968年にむけて、559部隊は活動を強め、北
部から南部へ移動する9万~10万人の兵士を扱うよう指示した。
20号線沿いを中心に熾烈な戦闘があった。ある証言では、危険ななか
での女性の勇敢さや意気軒高ぶりだけではなく、相互扶助についても
述べている。死者へのケアーは人間性の本質的なものだと彼女らは考
えていた。
ホー・チ・ミンは、青年突撃隊の指導者に対して、家族に代わって隊
員の世話をし、最低限の必要を手当をするように命令していたが、そ
れは守られることはなかった。
(前篇 了)
