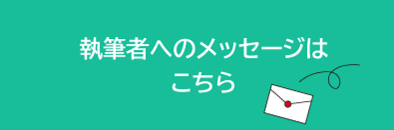今こそ世界に伝えたい。お互いを応援する気持ち。「世界を応援しよう!」に込めた思い。
「パリオリンピック・パラリンピック2024」が開幕。世界が熱気に包まれ、アスリートだけでなく、コーチ、家族、スタッフ、大会関係者そして観客すべての人たちの思いが、集まる瞬間がやって来ました。
その一方で世界では、戦争やテロが絶えず、難民、貧困問題も広がっています。また気候変動による自然災害も多くの人々を襲い続けています。
「世界はひとつ」と言いながら、現実には世界が大きく分断してしまっているのではないか…。
そんな世界に、今こそ広がってほしいな…と思っているコンテンツがあります。それが、NHK「世界を応援しよう!」というプロジェクトです。
今年から、小学校3年生の道徳の教科書にも登場した「世界を応援しよう!」。いったい、どんなきっかけで生まれたのか。ちょっとお付き合いください。
「世界を応援しよう!」って何?
改めまして、この記事に出合っていただきありがとうございます。チーフ・プロデューサーの神原一光です。

2002年に入局して以来、「天才てれびくん」「おやすみ日本 眠いいね!」「平成ネット史(仮)」「令和ネット論」などの番組を担当したり、ピアニスト・辻井伸行さんや音楽家・小室哲哉さんを取材したドキュメンタリーやインタビュー番組、そして「NHKスペシャル」の討論シリーズまで、ありとあらゆる番組を制作してきました。
その中で今回、皆さんに知ってもらいたいNHK「世界を応援しよう!」というプロジェクトは、僕が東京オリンピック・パラリンピックの仕事に関わっていた時に企画したものでした。
東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年、大会に参加する200以上の国と地域それぞれの言葉で応援しあったら、世界の皆さんと友達になれるのではないかと思って考えたプロジェクトです。
日本に「ニッポンチャチャチャ」という応援コールがあるように、世界各国・地域にもそれぞれの「応援コール」が存在します。それをすべて紹介できたら、開催国の日本と世界が応援でつながり、もてなすことができるかもしれないと思いました。
まずは一度ご覧ください!


きっかけは、1本のニュース記事
きっかけは、2018年12月のこと。「NHK NEWSWEB」に掲載されていた1本のニュース記事でした。
「News Up あなたの街は何タウン?超多国籍都市“トーキョー”」というリポート記事。その中に、東京都が公表している各区に住む外国人の国籍別データを分析した取材で「東京23区だけで182の国と地域の人が住んでいて、ほぼ世界中を網羅していることがわかった」という旨の記載がありました。
最も多い区は港区で実に135の国と地域。最も少ない区である千代田区でも71の国と地域の人が住んでおり、いかに東京に世界中の人が集まっているか、ということがわかるニュースでした。
「東京23区に世界中の人が、こんなにも住んでいるのか…。世界は遠いものじゃなくて、近い存在になっているんだな」とニュースを見て思いました。
そこでハッと思い出したのが、ある光景です。
世界規模のスポーツイベントで、外国人観光客の方たちと肩を組んで写真を撮ったり、抱き合ったり、ハイタッチするといったシーン。皆さんも「あるある!」と思ったことありませんか?
1998年の長野オリンピックや2002年に日本と韓国で開かれたFIFAワールドカップなど、日本が開催国(開催都市)になった時の盛り上がりも思い出しました。
実は僕自身、NHKに入局するまでは、心底テニスに打ち込み、大学ではスポーツの文化や歴史についても学んでいました。
ジュニアの日本代表選手として、世界を転戦したこともあり、国を代表して世界を駆け回るアスリートや、それを支え、応援してくれる人のありがたさを実感していたこともありました。

スポーツを通して、世界がひとつになれる瞬間。国境を越えた「連帯」や「思い出作り」が生まれる瞬間。そこにNHKとして関われるとしたら…という発想から「応援」というキーワードが浮かび上がってきました。
国際大会、特にサッカーや、バレーボールなどの国別対抗の団体戦では、しばしばその国の応援コールが連呼される時があります。
こうしたコールは「チャント」(chant 詠唱・唱和)と呼ばれ、比較的単純で一定の音程やリズムを繰り返すもので、しっかりとした「お手本」があれば覚えやすい。
だとしたら、世界の応援動画を1つずつ作っちゃおう!
東京23区だけで、180以上の国と地域の人が住んでいるなら、日本全国も含めて探せば、実現できるのではないか。という思いで企画を練っていきました。
地道な出演者探し・慎重かつ丁寧な制作
…とはいえ、実際にプロジェクトを進めていくと苦難の連続が待ち構えていました。簡単に出演者が見つかる国・地域がある一方、まったくつてがない国・地域が思いのほかあったのです。
世界にはなんといっても200以上の国と地域があります。NHKが取材などでつながりを持っている在日大使館の大使・参事官・スタッフの方々をあたるだけでは到底カバーすることは難しく、ロケ日程を固めるどころか、取材すら難しい状況が続きました。
そこで、ディレクターやリサーチャーに海外ロケに精通した方や外国人のスタッフにも入ってもらい総出で、留学生や日本で働くビジネスマンの方々など、人づてに紹介してもらう作戦に切り替えました。
スタッフが「●●(国・地域名)の方、いませんか?」「お知り合いに●●(国・地域名)の方いらっしゃいませんか?」と聞いて回る毎日。
海外と「姉妹都市」を結んでいる自治体があれば足を運んで情報を聞いたり、街に出て、外国料理専門の料理店やレストランを探し歩いたり、電車ですれ違った外国の方に話しかけてみたり、検索して「今日珍しい国の人に会ったよ」というブログがあれば、その書き手に連絡を取ってみたり、外国人がたくさん集まっているSNSグループにメッセージを送ってみたり、日本語の語学学校に通って生徒の皆さんに聞き込みをしたり、はたまた外国の方に集まってもらう交流パーティーそのものを開催してみたり…。
ありとあらゆることに取り組んで、1か国・地域ずつ、地道に粘り強く探して、撮影にご協力いただきました。

駐日大使・参事官(当時)など大使館スタッフが総出で出演してくださいました。
印象的だったのが、ヨーロッパの小さな国・アンドラの方を見つけた時のことです。
取材で知り合ったある国の方から、「対戦型のオンラインゲームに遊びに来る方にアンドラの方がいる」という情報を聞き、スタッフがそのゲームをダウンロード。ゲーム画面に張り付いて、いつログインするかわからないアンドラの方を探した…ということがありました。
実は、探し当てたその方は日本を離れてしまっていたということで、努力が水の泡になるかと思ったのですが、同じアンドラの友人の方が都内のビジネススクールに通っているということを教えてくれ、見事めぐりあうことができました。

「もはや探偵!?」
「人を見つけること自体を番組にした方が面白いのではないか…」
そんなことをスタッフと話しながら探し当てた皆さん。ロケをする中で、特に響いたことがあります。
それは
「日本の子どもたちに世界の“多様性”を知ってもらえるなら協力したい」
「日本ではほとんど知られていない我が国のことを紹介できる絶好の機会だ」
「”日本が多様性を大事にしている国だ”と母国に知らせることができる」
という声でした。

気がついたことは、世界は日本のことを「トモダチ」だ、と思ってくれている、ということでした。
これは日本が、政治・経済のみならず、スポーツ・文化においても国際的な式典や会議、大会を行ってきたことや、JICA(青年海外協力隊)に代表される人を通じた海外支援などを続けてきたという有形無形の「草の根外交」の積み重ねではないかとも感じます。
ちなみに、イギリスのコンサルティング会社の調べによると日本のパスポートは、ビザなしで訪問できる国・地域が194と世界1位にあるそうです(2024年時点)。
僕たちがふだん思っている以上に、世界は日本のことを身近に感じてくれているのかもしれません。
コロナを越えて到達
2020年3月。なんとか制作を続け180以上の国と地域が集まってきた「世界を応援しよう!」に危機が訪れます。新型コロナウイルス感染拡大です。東京オリンピック・パラリンピックの大会そのものが延期され、多くの外国人も次々と自分たちの故郷に帰国してしまい、制作のめどが立たなくなってしまいました。
世界が同時にコロナという未曽有のウイルスに苦しんでいるニュースが日々飛び込んでくる中、オリンピック・パラリンピックに出場する選手たちを応援するどころではなくなってしまいました。
選手ではなく、世界に生きている皆さん、人類そのものを応援しなければならない状況になってしまったのです。
そんな時に、心の支えになったのが、企画に協力していただいた方々と交わした言葉でした。
コロンビア
「自分の国を日本の人に知ってもらえるとてもいい機会になった。声をかけてもらえてうれしい」

アメリカ
「留学で来日まだ2週間ですが貴重な体験をさせてもらえてとても楽しかった!」

エジプト
「この企画はとても素晴らしい!日本だからこそできる企画ですね!」

そうだ、今こそ「世界を応援しよう!」。世界が苦しい時こそ、世界を応援しなくちゃと心を強く思い直せたのです。
東京オリンピック・パラリンピックに参加する国と地域は、207。残り27をどう制作するか。
頭を抱えた末に「日本に住む方を探す」という道をあきらめ、現地に在住する日本にゆかりがある方を探し、リモートで収録するという方法を用いて、なんとか制作。
こうして、2021年4月下旬に207すべての動画をアップ。制作から足かけ3年、ついに目標にしていた数に到達することができたのです。
「無観客開催」その時…
2021年夏の東京オリンピック・パラリンピックは無観客を余儀なくされてしまいました。
こうした中、「世界を応援しよう!」にお声がかかります。
選手たちの事前キャンプ地や練習会場となった全国各地のホストタウンで「世界を応援しよう!」の映像を使いたいという声がNHKに届き始めたのです。
そこで、急ぎ取り組んだのが「あなたの応援!動画大募集」企画です。応援コールを全国の視聴者の皆さんにチャレンジしてもらい、その動画を合成したものを世界の選手たちに届けようというものです。
自国・地域の人たちが応援コールをするだけではなく、「日本の人たちが、あなたの国・地域を、あなたが聞いたことがあるコールで応援していますよ…」ということが伝わったらいいな…という思いでした。
投稿は、一般応募のほか、趣旨に賛同していただいた大学や専門学校の皆さんにも参加していただきました。

「みんなで世界を応援しよう!」という思いは、数になって現れます。投稿は最終的に2000件を突破。投稿いただいた動画は、番組などを通して紹介することができました。
そんな盛り上がりを受けて、すばらしい提案が舞い込みます。大会の組織委員会から、選手村や複数の競技会場で「世界を応援しよう!」の映像を上映しませんかという依頼です。

コロナ禍で開催されたオリンピック・パラリンピック。開催国の放送局として、世界にできることは「応援だ」と思っていたことが、最後の最後で実を結んだのです。
福島で行われたソフトボールの試合。イニングの間に、無観客の会場に流れたのはメキシコの応援コールです。その声に気づき、会場のビジョンに流れる映像を見たメキシコの選手たちが喜んでくれたシーンが中継映像で流れました。その様子を見て、胸にこみ上げてくるものがありました。
レガシーとして
東京オリンピック・パラリンピックの開催をきっかけに制作した「世界を応援しよう!」。実は、大会が終わっても、活動を続けています。
NHK WORLDの番組で応援コール動画に出演してくださった皆さんをお招きしたトーク座談会が開催されたり、Eテレ「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」の「がんばれ!地球おうえんだん」のコーナーで「世界を応援しよう!」が放送されるなど、さまざまな企画が展開されています。
また、応援コール動画も「FIFA ワールドカップ2022カタール大会」「ラグビーワールドカップ2023フランス大会」と国際大会を重ねるごとに、参加国・地域の数が増え、今では210になりました。
この数は、国連加盟国(193)や国際オリンピック委員会に加盟している国・地域(206)よりも多い数になりました。
言ってみれば「世界を応援しよう!」は、世界でもっとも多くの数の国・地域をカバーするコンテンツと言えるかもしれません。
ぜひ皆さん、外国人の方と会う機会や、皆さん自身が海外に旅行された際に、応援コールを交流のきっかけにしていただけたらうれしいなと思います。
最後に
最後にひとつだけ。 最近よく「多様性」という言葉を耳にします。「共生社会」という言葉も耳にします。
でも、そういった概念を声高に言うのではなく、お店や、近所、はたまた同じ学校といった、すでに身の回りにいる海外の皆さんたちに向き合うことが大切なのではないかと感じます。
ふだんから、その国・地域にリスペクトを持って、接していく“癖”のようなものを身につけること。それが本当の「多様性」であり「共生社会」の姿なのではないでしょうか。
そのきっかけとして「応援」があったらうれしい限りです。
「世界を応援しよう!」のプロジェクトに込めた思いをお伝えして、この記事を終わります。最後まで、読んでいただきありがとうございました。

応援されるとうれしくなる。
きっとそれは世界共通の感情です。
もしも世界のどこかで、まだ出会ったこともない誰かが、
「ニッポンチャチャチャ!」と口ずさんでくれたら、
それだけで元気が湧いてきちゃったりしませんか?
応援は、その国・地域の人なら誰もが知っている言葉であり、リズムであり、心。 今こそ、200を超える国と地域の人々が、 互いにエールを送りあったなら、 世界はもっと近くなる。世界はきっとひとつになれる。
さぁ、世界を応援しよう!
そして、世界と思いをつなげよう!