
聴覚障害のある私が、アナウンサーをめざしたわけ
こんにちは、アナウンサーの後藤佑季です。
ことし、パリで開かれたパラリンピックについて、現地からリポートしました!
アスリートナビゲーターの国枝慎吾さん(車いすテニス)と、毎日さまざまな競技会場から、その熱気や選手たちのパフォーマンスのすごさや意味などをお伝えしていました。
大会後半にはメダリストインタビューを担当し、メダルを獲得した選手たちの思いを伺いました。

現地の車いすユーザーの方とともに調査するロケも行いました。
また、東京パラリンピックの前から取材し、東京パラリンピックを伝えた身として、パラスポーツにおけるパリ大会の意味や位置づけ、その変化についても取材してお伝えしました。
そんな私、実は重度の聴覚障害があります。
生まれた時から聴覚障害があり、小学3年生のときに人工内耳という機械の装用手術を受けました。
人工内耳というのは、耳にかけている機械で音を拾って電気信号にします。その後、頭に磁石でくっついている丸い送信コイルを通して、皮膚の下にある装置へ信号を送っています。

私の場合、今は左耳につけている人工内耳を外すと、全く音が聞こえません。人工内耳を外した耳元で大きな声で叫んでもらっても、その 「音」がかすかに聞こえるか聞こえないか、という程度です。
人工内耳をつけても、万能というわけにはいきません。
人工内耳は、中途で聴覚障害になった方によれば、「ロボットのような声」に聞こえるそうです。
私の場合は、ざわざわした場所では聞き取りにくかったり、スピーカーから出る音を聞き取るのが苦手だったりします。というのも、ざわざわした場所では音が重なって聞こえてしまうから、スピーカーなどの音源媒体を通して聞くと音の輪郭がぼやけてしまうからなんです。視覚化すると、下記のようなイメージです。

聞きたい声が、何を言っているのかを判別するのが難しいです
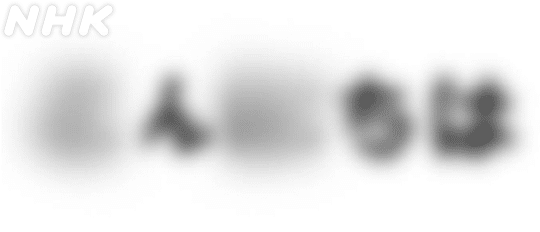
何かを言っていることはわかるけど、何を言っているのかは理解できないのです
また、私は音だけでなく、口の動きや前後の文脈などからも情報を得て、会話を聞き取っています。
「英語の穴埋め問題」のようなイメージ。音だけではなく、口の動きや表情、文脈からの予測といった情報を組み合わせることで内容を理解しているのです。
状況によって異なるのですが、こんな感じです☟
音:4割
口の動き(読唇):3割
文脈からの予測:2割
表情:1割
※状況によって割合の変化あり
…上記の聞こえ方を踏まえて、ふだんの雑談で周りがざわついていて聞き取りが難しいときには、こんな感じで聞こえることも。
A「◎$♩×¥●&?#%」
B「へえ~そうなんだ~!いいなあ~!」
C「ね!わたしも@■#*!」
A「〇%×$☆¥でしょ~」
なんだかすごく盛り上がっているけど、何に盛り上がっているのか全然わからない…から、会話に入れない…
しかも、会話を止めてまで聞く内容ではないのかもしれない…
と思うことはしょっちゅう!
それでも、少しずつ周りの人に聞こえ方を理解してもらって、いまの私があります。
ちなみに私は、地域の小学校・中学校・高校・大学で、聞こえる人たちと学校生活を送っていました。
「聴覚障害は見てわからないから、自分で困りごとや助けてほしいことを説明しなさい」と両親から言われ、新学期になるとクラスのみんなに、何が困るのか、どうしてもらえると助かるのかを説明していました。
今思えば、この基礎があったから、「説明する・表現する」ということが苦ではないのだと思います。
今回はそんな私のことを少しだけお話しさせてください!
私の人生を変えた、パラアスリート取材
自分がメディアで働くなんて、正直思ってもみませんでした。
転機となったのは、大学3年の夏に「障害のあるリポーター」の公募を見たことです。大学でのある経験から、聴覚障害が「目に見えない障害」なんだと痛感したことが、心に残っていました。
それは、自分の障害を説明した時に、「今こうして話せているのに難しいの?」と言われたこと。
「あぁ、私の障害はやはり目に見えないのか」と感じたと同時に、「みんな年老いたら耳も遠くなるし、視力も落ちていく。 記憶力も落ちる。 なぜみんなが向かう未来なのにこんなにも意識されていないのだろうか」と思ったことを、今でも覚えています。
そんな時目にしたのが、NHKが、2020年の東京パラリンピックに向けて障害のある人を対象にリポーターを募集するという新聞広告。
私のような「目に見えない障害がある人がいることも知ってほしい」という思いから、 応募しました。
リポーターとしての主な仕事は、パラアスリートや共生社会の実現に向けた取り組みを取材して、伝えること。
伝えるときには、ナレーションをしたり、プレゼンをしたりします。
ただ、人は聞いた音をもとに発話をしているので、聴覚障害があると聞き取れている音の範囲での発話になり、どうしても声に特徴が出てしまいます。
リポーターになったとき、こんな声が届くこともありました。
「ナレーション、へったくそ」
「聞きにくい、何あれ」
「やっぱり聴覚障害者には無理なんだよ」
そうした中で、 「聞こえる人のようにきれいに読めないといけないのだろうか」と思うこともありました。
一方でこんな言葉も頂きました。
「聴覚障害があるのにきれいな発音だ」
「滑舌がアナウンサーとは違うから、よりきちんと聞こうとして集中できた」
それは、小さいころから練習して努力してきた“私の声”です。
ただ、それは同時に、私の障害を「見えにくく」しました。
私は今も言語聴覚士の先生のもとに通って、トレーニングを重ねています。 日常生活を送る分には必要ないのですが、 少しでもたくさんの人に“私の声、 私の思い”を聴いてもらいたいと思って、取り組んでいます。
私のリポーター生活の最も大きな仕事は、東京パラリンピックでの中継でした。期間中、陸上の会場からの中継を中心に、毎日生放送で選手や競技の魅力を伝えてきました。
そんな中で心がけたのは、
「障害とともに生きる選手の姿」を、「同じ世界にいる人間なのだ」と伝えること。
そのために2つのことを中心に取り組みました。
ひとつは、「レジリエンス」という言葉を軸に、世界のスーパースターたちを紹介したこと。レジリエンスとは、“跳ね返す力”、“曲がっても折れない心”という意味です。
彼らにとって障害は決して克服したものではなく、時には向き合い、時には諦め、時には受け入れてきたもの。その過程の中で「困難な状況に応じて生き抜く力」「折れない心」を備えてきたのだと、取材をしていて感じました。
世界にはさまざまな理由で障害を負ったアスリートたちがいます。
戦争で足を失った選手。医療が発達しておらず、治せたものが治せずに障害を負った選手――。
パラアスリートたちは、障害者たちは、いつだって、やりたいことをやろうとするだけで、社会に、環境に阻まれてきました。
そんな選手たちが、どのような経験から、どんな信念をもちはじめ、パラスポーツに取り組み、何を伝えようとしているのか。
それを伝えることは、コロナ禍にあった東京大会で、やりたいことが思うようにできなかった視聴者のみなさんの心に伝わるものがあるのではないかと思い、「レジリエンス」をキーワードに、世界の選手たちの言葉を伝えるシリーズを企画しました。
とても好評をいただき、東京大会が終わってからもひとつの「キーワード」となっていることをうれしく思います。
2つ目は、選手の「競技以外の情報」を伝えること。
オリンピアンが、なぜ応援されるのか。それはもちろんメディアでとりあげられることが多いこともありますが、それ以上に、そのなかで彼らの人柄が伝わるからではないかと思いました。
何が好きで、何が苦手で、どんなことを考えながら生活していて…そういうことを知ることで、「自分たちと同じ世界にいる人間なんだ」と心のどこかで思い、親近感がわく。そうして、応援したくなるのではないかと思ったのです。
パラアスリートは、アスリートであるうえに障害があり、より「自分たちとは違う世界の人」と思われがちです。
でもみんな、同じ社会に、同じ世界に、生きています。
私たちと同じように何かを好み、何かを苦手として、何かに熱中しているんだと、そんな一面を伝えられたらより親近感を持ってもらえるのではないかと思い、各選手のパーソナルな部分を伝えてきました。
この選手はいつもお気に入りのネイルで気持ちをもりあげているんです。
この選手は絵が得意で、こんなものを描いているんです。
実は猫が大好きで、家ではこんな風に過ごしているんです…などなど。
こちらもありがたいことに、「親近感を持てた」とか、「遠い存在じゃないように感じた」という声を多くいただきました。
こうした2つのことを軸にできたのは、やはり私自身も聴覚障害とともに生きてきたからだと思います。
私だって、聞こえる方がよかったけれども、現実は聞こえない。
じゃあその中でやりたいことをやるために何をすればいいのか、考え続けてきた人生でした。
「障害者ってなんかとっつきづらいよね」と言われたこともあります。
それでも、私が聴覚障害とともに生きてきた人生で経験したことが、この2つの軸につながりました。
私だからこそ見つけられた軸に出会えて、本当によかったと感じています。
リポーターとして働く中で
こうしてリポーターとして働く中で、番組の制作現場に障害の当事者がいる必要性を感じました。
IPC(国際パラリンピック委員会)は、障害のある人は社会に15%いるとしています。
しかしテレビでとりあげている題材や出演者の中に、障害のある人は15%もいるでしょうか?
人々の意識の醸成に影響を及ぼすメディアだからこそ、実際の社会を反映しないといけないと思っています。
東京パラリンピックの期間は、画面に障害のある人がたくさん映っていました。NHKだけでなく、ほかの局やコマーシャル、街中の広告まで、パラアスリートが多く目につくようになりました。
そうして、社会が障害のある人の存在に“慣れて”いったと感じるのです。
でも、パラリンピックが終わったら元通りになってしまう。
視聴者の方から、
「後藤さんを通して「人工内耳」というものがあることを知りました」
という声を寄せていただいたこともありました。
せっかくこういう経験ができたのだから、テレビに出続けていくことが大事なのではないかと感じるようになったのです。
先ほど紹介した私の聞こえ方についての説明は、すべて、東京パラリンピックに向けたリポーターとして働く中で獲得してきたことばたちです。獲得には本当に長い時間がかかりました。
社会はなんてマジョリティによってマジョリティのために作られているのだろうと感じます。マジョリティによって作られた言葉は、マイノリティの困りごとを説明しきれません。
だからこそ、マイノリティ側が、マジョリティに伝わるように言葉を模索しないといけないのだと、リポーターになって体感しました。
社会には、自分にとって何が困難かをまだまだ説明しきれない人たちも多いと思います。マイノリティのひとたちの声を、“伝わる言葉を模索して”伝えていきたいと思うようになりました。
また、「現場で一緒に働くこと」の大切さも感じました。
制作現場では、パラアスリートや障害のある人に取材をした経験はあっても、一緒に働いた経験はない人が多くいました。
一緒に働く中で、障害当事者が現場にいるからこそ、気づくことが多かったと言われるようになりました。
たとえば、「何に困るのかどうしたらできるのか、考えるようになった。
なにより聴覚障害のある人を取材するときに戸惑わなくなった」という言葉です。
一緒に働くことで伝えられることが増えるかもしれないと思い、アナウンサーとして採用試験に応募することを決めました。
NHKのアナウンサーに!大阪での駆け出し時代
そうして、2022年にNHKにアナウンサーとして入局しました。
最初の赴任地は大阪。

初めて障害のあるアナウンサーを、それも聴覚に障害があるアナウンサーを迎えたことで、現場では戸惑いもあったようです。
最初に大変だったのは、改めて私の聞こえ方を理解してもらうこと、そしてどう工夫すればよりよいコミュニケーションがとれるのか?を伝えることでした。
見えないからこそ、伝えないと困りごとがわからない、説明にコストがかかるのです。リポーター時代に獲得した表現と、自分の聞こえ方の説明書を作って、一緒に働くすべての人に毎回説明し、理解してもらうように努めてきました。

上司や一緒に働く先輩たちも、最初は私に何ができるのか、視聴者からどんな反応があるのか、未知な部分が多かったと思います。
それでも、“障害”が先に来るのではなく、まずは“私”という個人を見てくれて、「障害があるから障害のことやパラスポーツのことばかり取材するのではなく、アナウンサーとしての基礎を身につけよう!」と、幅広く、さまざまな仕事を経験させてくれました。このことが、本当にうれしかったのです。
どうしても「障害があるから難しいよね」から入る人が多い中で、「やってみようよ!」とか「こうしたらいいんじゃない?」と提案してくれる上司や先輩のおかげで、基礎をしっかりと固めることができたと思います。
大阪局では地域のさまざまな取り組みを中継や企画で伝えました。
初めての中継でお世話になったのは、高校の靴づくり部のみなさん。
てんてこまいしている私を温かく見守ってくださり、「後藤さんやから大丈夫やで!」「後藤さんに取材してもらえてよかったわ!」とうれしい言葉をかけてくださいました。
また、視覚障害のある人の声から生まれた、雨音の静かな傘をつくっている企業を取材したことも。
視覚障害のある人は街中を歩くとき、音で周りの状況を判断するため、傘に当たる雨音がうるさいと状況が判断できなくて、外出が億劫になるという声を聞いた企業の担当者が、長い時間をかけて開発した傘です。
私自身も、傘に当たる雨音がうるさくて雨の日は会話が難しかったのが、「この傘だとこんなに人の声が聞こえるんだ!」と感じ、そのことを伝えました。
すると、「そういう需要もあるのかと気がついた。聞こえる人の中にも、雨音が心地よく聞こえるという人がいて、改めて障害のあるなしに関わらず、生活を豊かにできるかもしれないと誇りに思えます」とおっしゃっていました。
ああ、さまざまな視点を持つ人がいることは大切なのかもしれないと思いました。
大阪で取材に協力してくださったみなさんは、私の障害について、いい意味で「気にせず」接してくださったことも、私の支えになりました。
ありがとうございます!!
そうして幅広いテーマをもって働く中で少しずつ、たくさんの仲間たちが私の障害に慣れていくのも実感できました。
一緒に働くアナウンサーからは、「後藤ちゃんがマスクがあると口元が見えなくて聞き取りにくいと話してくれていたし、本当に聞き取れていないんだと体感できたから、中継で聴覚障害のある方について触れる時に意識することができた」と言ってもらいました。手話や指文字を覚えてくれた同期もいます。
視聴者の方からの反応も、
「なんでわざわざ聴覚障害のある人をアナウンサーに」
という声から、
「後藤さんの声を聞くのが楽しみなんです」
「こんなにきれいに発音するなんてどれだけの努力をしたのかと思いました」
という声に変わっていきました。
正直にいえば、つらいこともありましたが、リポーター時代に経験した「やり続けていれば見てくれる人がいる」という経験を胸に、目の前のことを必死にやっていたら、実際に変化が起きるということを感じられたのはとてもうれしいことでした。
大阪局に赴任が決まった時はすべて0からのスタートで、不安も大きかったですが、大阪局の仲間や取材先の皆さんのたくさんのサポートがあって、「障害」という色眼鏡で見ずに、私という個人を見てくださったおかげで、異動するときにはとてもさびしく感じました。
パリを、超えて
2023年11月からは、東京に異動。
パリパラリンピックでは、現地キャスターとして競技や選手の魅力などを伝える役割を担うことになりました。
パリパラリンピックに関わることが決まったときは本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。
私がアナウンサーになろうと思った理由の一つに、
「東京パラリンピックを伝えた身として、そこからどんな変化があったのか、何が変わっていないのか」、そして「パラアスリートたちが伝えたい思い」を一つでも多く伝えたいと思ったことがあります。
せっかく機会をいただけるので、東京パラリンピックが終わった時に感じた「これが終わりではなく、始まりなんだ」という思いを胸に、皆さんに少しでも多くのことを伝えられるように頑張りたいと思いました。
大変だったのは、現地で最大のパフォーマンスを発揮できるようにシステムを組むことです。
スポーツ中継では、試合がどんな風に進むか、どんな結果になるのか、その時にならないとわかりません。つまり、直前で想定と変わることも多々あります。
そうしたとき、一番情報が伝わるのが早いのは音声なのです。
でも、観客の大歓声があり、実況もされていて、そんな中で、フロアにいるディレクターからの「次のスタジオは5分遅れます!」「時間がないのでこのエピソードはなしです!」という音声での情報を、私が“聞き取り”、“理解する”ことは至難の業です。
まず音を聞き取ることに精一杯になってしまい、
「このエピソードが落ちるなら、じゃあせめてこの情報は短く入れよう」
などという判断ができず、最高のパフォーマンスを発揮することが難しくなってしまいます。
そこで、東京パラリンピックでも使っていたシステムを、さらにバージョンアップ。
フロアにいるディレクターの音声を文字化(左)するとともに、局内で開発されたネットワーク”カンペ”ツール(右)も利用。
重要な情報はカンペツールでずっと見られるようにしました。
そのため、私のテーブルの上にはスマホが2台も!

打ち合わせのときも、どうしてもバタバタしていると情報保障(※)は忘れられがちに…。
「聞こえないです!」とか「書いてください」など、以前は遠慮しがちだったお願いも、良い形で放送を出すために積極的に行いました。
だんだんフロアのディレクターも慣れてきて、ジェスチャーや口を大きく動かして教えてくれるようになりました。
※情報保障…障害の有無や内容にかかわらず、実質的に同等の情報が確保されるようにすること。
今回のパリパラリンピックは、何より歓声が大きかったです。
歓声が大きいと、聞こえる人でも会話が難しく…そんなときは、わたしの使っていた文字起こしシステムやカンペツールでみんな会話をしていました(笑)。
わたしにとって使いやすいものが、みんなにとっても役に立つんだなと思いました。
大会終盤では、ありがたいことにわたしが現地で取材した実感を伝える時間をいただきました。
そこにたくさんの想いを込めたので、その内容を引用させてください。
今大会、取材して感じたのは、
“パラリンピックの「スポーツとしての発展」”、
そして歴史が変わる瞬間です。
パラ陸上・走り幅跳びの義足のクラスで今大会4連覇を達成したマルクス・レーム選手は、大会直前のインタビューで「パラリンピックを一歩先に進めたい」と話していました。
「一歩進んだ姿」、その1つが、これまでパラスポーツに取り組んできたたくさんの選手たちのたゆまぬ努力と闘いの歴史が作り上げたハイレベルなパフォーマンスです。
観客は、夢の9メートルジャンプに挑むレーム選手の姿に魅せられ、憧れ、競技を楽しんでいました。
レーム選手の言う“次のステージ”に進みつつあることを実感しました。
そしてもう一つ、「一歩進んだ姿」は会場に集まった観客の声援の中にも感じられました。
私が最初に取材に行った競泳会場での、最も障害の重いクラスS1のレース。1着でフィニッシュした選手はもちろん、大差のついた最後の1人の選手までずっと声援がやまず、フィニッシュしたときには割れんばかりの大歓声と拍手が起きました。
この時の声援は「障害者なのにがんばったね」ではなく、純粋にスポーツとして楽しんでいる「すごい!」という声援だと私は感じました。
フランスパラリンピック委員会会長で、東京大会の陸上・走り幅跳びの銀メダリスト、マリー アメリ・ル フュールさんは言います。
「私たちは4年に1度の存在ではない」と。
パラリンピアンたちは、障害のある人たちは、決して特別な存在ではなく、日常生活で、同じ社会の中に生きています。
今回メダルを取ったパラアスリートたちの中にも、「障害があるから」「危ないから」とスポーツ自体を始められなかったり、可能性を否定されたり。そんな経験がある人が少なくありません。
こうしたパラリンピックの発展が、「障害があるから」とやりたいことができない社会から、だれもがやりたいことをやりたいときにできるようになる、そんな社会の礎になると信じています。
私も、聴覚障害があり人工内耳をつけていますが、障害があってもやりたいことをやっていいんだと発信していきたいです。
パリパラリンピックを経た4年後のロサンゼルス大会で、どんな社会に変わっているのか楽しみです。

障害があるから、障害のある人のことを伝えることだけを仕事にするのではなく、障害があっても、“ひとりの”アナウンサーとして仕事をしたい――。
障害のある人が働いていることが当たり前なんだということを、取材や仕事の幅をひろげながら発信していきたいです。
「聴覚障害のある後藤さんだから伝えられることは何ですか」とよく聞かれます。
当初は「どうしても“障害があること”が先に来てしまうんだな」と困ってしまったこの質問に、いまはこう答えるようにしています。
「障害とともに生きてきたわたしだからこそ、その経験があるからこそ、感じたことを言葉にすることで、結果としてほかの取材者とは言葉や表現が変わることはあるかもしれません」と。
これからも、“わたしだから”何を伝えることができるのか、取材を続けていきたいと思います。

