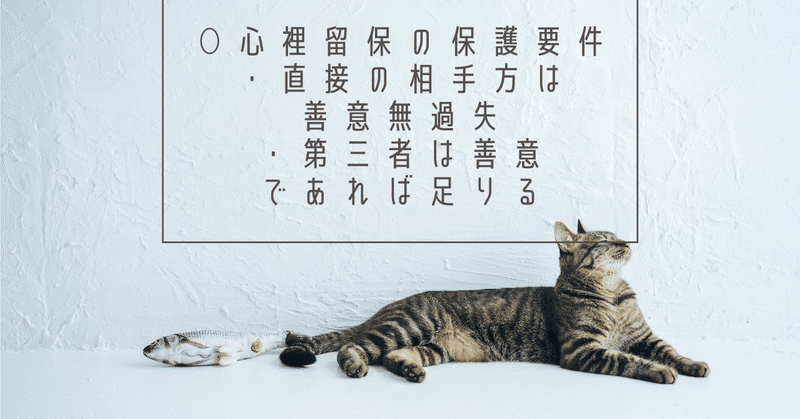#司法書士試験
一般社団法人 財団法人
○社団法人、財団法人共に支配人の選任はできない
○財団法人、期間満了、解散事由での解散は継続できない
300万円未満、300万を回復すれば継続できる
○基金は登記事項でない
○社団法人財団法人のみなし解散は5年
○社団法人公告方法が定款の絶対的記載事項
○ 一般社団法人財団法人共に清算人を選任登記の際は定款必須(清算人会を置けるためその有無の確認)
○役員の欠格の加重要件の会社法関連の
買戻 利息 選択債権 債権者代位 詐害行為など今日の民法22
買戻権・期間最大10年
伸長できない
短縮できる(法律関係安定)
定めがなければ5年となる
(再売買の予約期間はは定めがなければ10年)
・買戻権に劣後する対抗要件を備えた賃借権者は買い戻し権行使があっても1年間引き続き住むことができる
○買い戻し権と再売買の予約の相手方
・買い戻し権の相手方は現在の所有者
(登記が動いてなければ元の所有者)
・再売買の予約は予約の相手方
その他の担保・債権