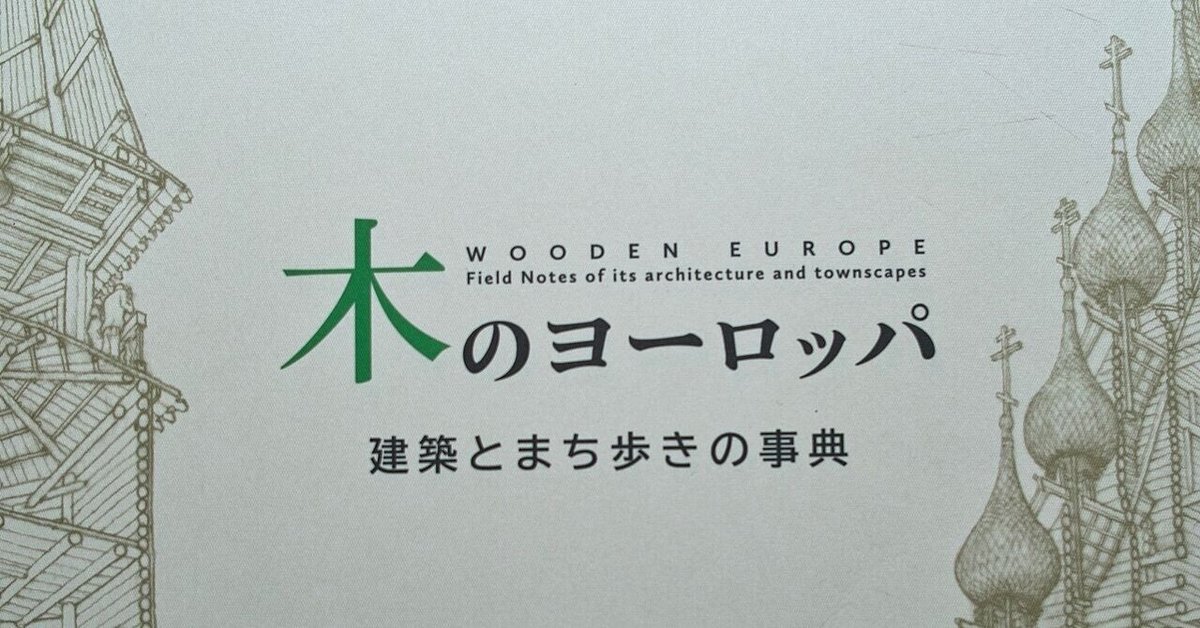
本棚から… 木のヨーロッパ/建築とまち歩きの事典
すみませんでした。二度目の投稿となります。4月13日分は具合が悪くて消してしまいました。あれ、消えちゃったのと驚いた方、ごめんなさい。
まずこの本のタイトルが目を引きます。石畳にゴシック建築がそびえたつ、ヨーロッパといえばこんな風景のはずでしたが、行ったことは無いので、映画や絵画からの思い込みだったのでしょう。目からうろこが落ちるような興味深い本だったので、一部ご紹介いたします。
木のヨーロッパ/建築とまち歩きの事典 太田邦夫著 2015年 彰国社発行
1,まえがき(要約)

ヨーロッパを旅すると、広場や中心街には木造の町屋が残されているのを目にする。近世どころか15-16世紀にまでさかのぼることも少なくない。
数千年前まではヨーロッパも深い森に囲まれた大陸であった。「木のヨーロッパ」を基調文化として、中世まで多様な生活文化を築いてきた。そこに地中海型ともいえる「石のヨーロッパ」を上層文化として取り入れることにより、近世以降のヨーロッパ文明が生まれたとも言える。
日本では文明開化のためヨーロッパの上層文化のみを短絡的に受容してきたが、その基調となっている「木のヨーロッパ」を完全に見過ごしてきた。
「古い家のない町は、思い出のない人間と同じである」というヨーロッパの諺は、彼らの愛着を雄弁に語っている。「木のヨーロッパ」を知ることは、古い建築を年々消し去りつつある日本の町づくりに良い示唆をもたらすだろう。この本が少しでも役立てば幸いである。
2、ヨーロッパの環境

木造と言っても材木の使い方により、工法は大きく言って軸組造、井楼組に分れる。地勢や気候の関係もあり、それらの分布は複雑である。
ヨーロッパの気候や植生、農耕や牧畜の形式、民族や宗教の違いなどを比較することでその伝統的基盤が見えてくる。
気候は北西ヨーロッパでは暖流のせいで温暖であり、降水量も多い。黒海北岸以東は乾燥したステップ気候である。総じて、日本と欧州の年間日射量や降水量はほぼ似たようなものである。
植生であるが、落葉広葉樹林帯、落葉針葉樹林帯、地中海型疎林、常緑落葉広葉樹林が見られる。現在フィンランドとスウェーデンをのぞくと、ヨーロッパの森林率は低く、デンマークやイギリスでは13%にも達しない。(日本は69%)
とはいえ中世以前は中央山地の北側は深い森で覆われ、その豊かな木材でどこでも木造の建物が建てられていた。しかし、人口増から森は開墾され農地や牧場になり、金属治金用の燃料や造船のため良材は真っ先に伐採されていった。ヨーロッパ文明の発達の歴史は、こうした森の破壊によって達成されたといってよい。
土地利用の形態も産業の発達により複雑である。民族的背景である言語をみると多種のインド.ゲルマン語以外の言語の地域もあり多様である。それは建築様式にも影響を与えている。
宗教については、カトリック、プロテスタント、イスラム教まで含まれるので、教会の装飾も多様である。
3、木造建築例
少しですが、本に登場する写真から。

ドイツのマイン川沿いにあるフランケン地方は古い木造の町並みで有名。この広場にそびえるホーエーズ.ハウスは代表的な名建築。

漁民たちがロープや網などを2層以上の高さに収納するため作った木造板張りの網倉。現在この漁網倉庫40棟ほど保存されている。1850年から75年ころには110棟も並んでいた。(右下の人物と比較すると高さが分かる)

ズボイから移築された。内部を隔てるロココ様式の聖障や門構えとともに、ベスキテイ山脈東に住み着いたルテニア人の建築様式を伝える貴重な遺構。
4、野外博物館、民家園など

上の建物は1897年に開設された国立博物館の分館で、広大な敷地にデンマーク中の民家80棟を移築している。民家園では主屋だけでなく穀倉や獣舎などの付帯施設も保存している。
旅行をするなら、ヨーロッパに興った野外博物館や民家村を活用しよう。木造建築が盛んだった国では、貴重な古建築を一か所に集め、保存しながら後世の人たちも往時の建築と風習を体験し学べるようにした。民家園の発祥は1891年ストックフォルム(スェーデン)とされる。
ヨーロッパの野外博物館や民家村の数は100か所以上である。下↓

5、巻末資料

巻末には、事典という名にふさわしい充実した資料集が付いています。
上記の屋根の形から始まり、屋根と壁の仕上げ、構造材の名称、木造軸組、住宅の平面図(農村部)、住宅の平面図(都市部)、インテリア、窓、教会の種類、納屋と穀倉、細部の装飾、大工道具、建築用の樹林、図版の出典説明。
6、感 想
執筆だけで15年もかかったという大作です。ごく一部の紹介でも、長文になるくらい濃い内容です。そして、この本と対比し思い出してみると、日本の古いものは何でも時代遅れで駄目なんだという風潮がかつてありました。あれは誰が何のために言い出したのでしょう?
けれど、日本がお手本としてきたヨーロッパでは、100年以上も前から自国の木造建築を大切に保存し活用してきたのです。国柄や民族性を失くしてしまうこと、近代化といえば聞こえはいいのですが、それは愚かで危ういことではないのだろうか?伝統文化や歴史を雑巾で拭うがごとく消し去るのは、時間軸を無くすことであり人間の足元を不確かにしてしまうのではないのか?蓄積された知恵をゴミのように捨て去るのは、そんなに称賛されることなのだろうか?色々考えてしまいます。
「古い家のない町は、思い出のない人間と同じである」このことわざが心に残ります。

