
ゆっくりゆっくり本を読む#1『私がホームレスだったころ』李玟萱(リー・ウェンシュエン)著 橋本恭子 訳 白水社刊
7月半ば、蟬の声の中で読みはじめた本を、9月になって、金木犀の香りとともに読み終えました。
ライターの青野棗(あおのなつめ)です。
『外国ルーツの人にきく〜食べたら元気になるごはん』という企画に取り組んでいます。
日本で働く外国ルーツの方々に、疲れたとき、落ち込んだときに食べたくなる料理を教えてもらいながら、インタビューするという企画です。
その第2回「乃毓(ナイユー)さんの三杯鶏」で、台湾出身の乃毓さんの記事を書くときに、台湾関係の本を何冊か読みました。
台湾のことは、知っているようで、知らないことばかりでした。
そんな台湾の入門書としてとても良かったのが、
『台湾の歴史と文化〜六つの時代が織りなす「美麗島」』(大東和重 著・中公新書)です。
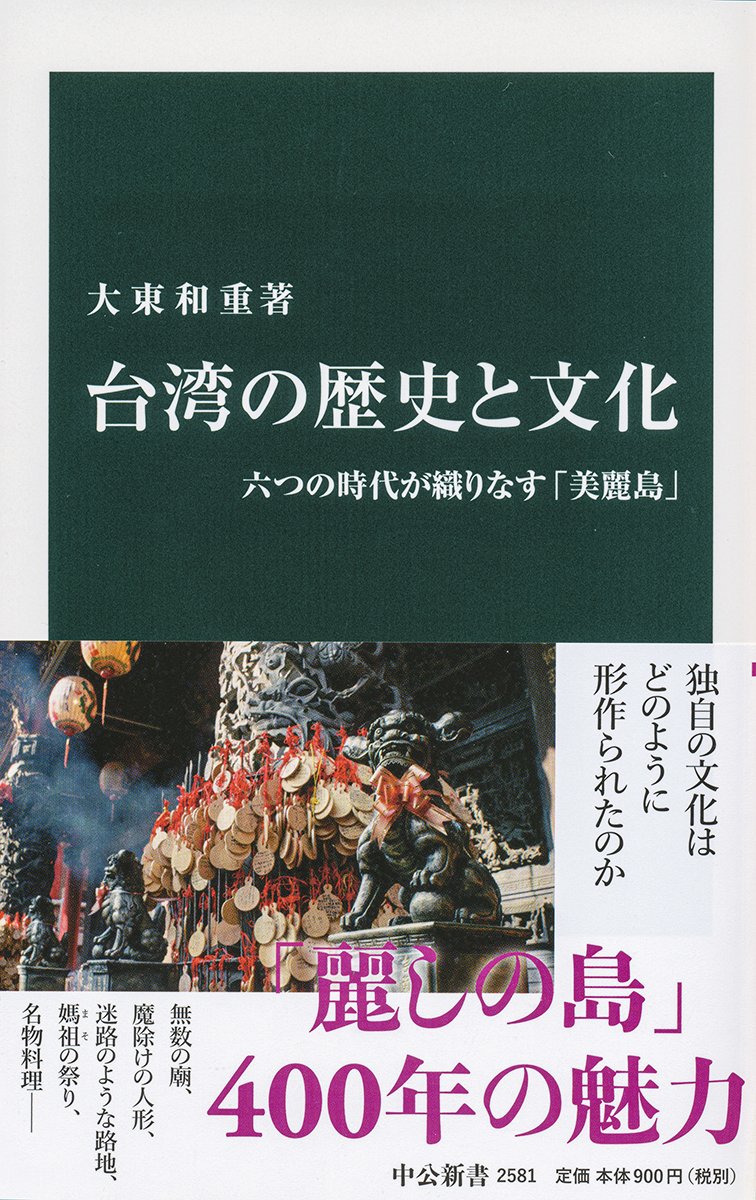
この本の著者、大東和重さんに第2回の記事をお送りしたら、ありがたいことに、丁寧な感想をくださいました。
乃毓さんのことを「他人事と思わずに読みました」とのこと。
大東さんは台湾の大学で教員として働いた経験があって、教え子が日本で働いているそうです。
このコロナ禍で、辛い思いをしている人がいないか、心配されていました。
「台湾における、東南アジアから来た労働者への差別に触れられているところ、記事にしてくださって感謝いたします」
とも書かれていました。
これは第2回後半の記事で、乃毓さんが日本で自分が経験した差別に触れたあと、でも、「台湾にも人種差別はあります」と言われた部分です。
こういう話の流れになったのは、もちろん私の力ではなく、乃毓さんの聡明さゆえです。
大東さんの感想を、乃毓さんに伝えました。
いま暮らしている日本のことも、故郷の台湾のことも、どちらからも少しだけ距離を取って、良いところも悪いところもできるだけ公平に見ようとすること。
これは簡単なようで、なかなかできることではないと思います。
そして大東さんも、そういう視点をお持ちの方のように感じました。
台湾への深い愛を持ちつつも、
「台湾も決してバラ色の世界ではありません」
でも、「台湾の人たちの元気を見習わないと、とも思います」とのこと。
「気軽に行けて、誰かひとり知り合いがいれば、そこからさらに人と知り合えるのが、台湾のいいところです」
だから「コロナが収まったら、ぜひ遊びに行ってほしい」と書いてくださいました。
(そのときは、大東さんの本を持って、台南の街歩きをしたいです!)
さて、その大東さんから、本をいただきました。
『私がホームレスだったころ』(李玟萱 著・台湾芒草心慈善協会 企画・橋本恭子 訳・白水社)という本です。

大東さんの台湾研究のご友人が翻訳されたそうで、
「台湾のいろんな人生模様です」というコメントとともに、送ってくださいました。
台湾でホームレス状態にあった10人、それぞれの方の人生をたどるこまやかなインタビューと、そんな彼、彼女らを支えるソーシャルワーカーやボランティアの人たちのインタビューが載っています。
7月に送っていただいたこの本を、読み終えたら、もう9月になっていました。
私は本をあまり速く読むことができません。
それから常に何冊かを並行して読んでいるので、ずっとこの本だけを読んでいたわけではないのですが、この夏は出かけるときも必ずバッグの中にこの本を入れていて、毎晩眠る前に読むのも、決まってこの本でした。
ひと夏をまるごと、この本と一緒に過ごしたような感じがします。
いろんな人の人生を、少しずつ少しずつ読みました。
『私がホームレスだったころ』は、
「かわいそうな」人が、「がんばって」苦難を乗り越え、読む人に「勇気を与えてくれる」というような話ではありません。
そんなふうに、ざっくりとくくってしまえるような話からは、ずいぶん遠いところにある気がします。
ひとりの人が持っているものと、背負わされているもの。
生まれた境遇や、生まれもった性質や、育った時代の違い。
インタビューを行ったライターの李玟萱(リー・ウェンシュエン)さんは、決してそれらを、わかりやすい色で、雑に塗ることはしません。
繊細な色は、できるだけ繊細なまま。
余計な感情は上乗せしないように。
彼女はそういうことを、厳しく自分に課しているようです。
これも簡単なようで、非常に難しいことだと思います。
この本を読んでいると、登場するひとりひとりの人生が、「他人事」のようには思えなくなってきます。
野良猫の世話をする趙(チャオ)おじさん、教会の伝道師になった阿忠(アチョン)さん、賢い阿明(アミン)さん、ソーシャルワーカーの運生(ユンシュン)さん、ボランティアの梅英(メイイン)姉さん……ひとりひとりが、名前で呼びたい個人として、頭の中に立ちあらわれてくるからです。
「他人事」ではなくなると、無関心ではいられなくなります。
私たちが無関心ではなくなることは、社会が少しでも良い方向に進んでほしいと願うとき、それは小さくても、最初の希望になります。
自分とは違う立場の人のことを、知りたい、理解したいと思うことは、たとえ完全にそうすることは不可能でも、時には嫌な思いをすることがあったとしても、本来はあたたかくて、ゆたかで、あかるいことであるということを、この本は教えてくれているように感じます。
李玟萱さんは「ペンをカメラに見立て、語り手の人生をドキュメンタリー映画のように記録する方法を取った」そうですが、これはなんともセンスの良い映画のようです。
私は中国語の原文は読めませんが、翻訳の橋本恭子さんの仕事がすばらしく、文章に独特のスタイリッシュなリズムがあります。
きっと原文でもそうなのでしょう。
これは李さんが作詞家でもあることに、関係しているかもしれません。
もともとの、中国語での文章のリズムも感じてみたいと思っていたら、YouTubeでオーディオブックの一部を視聴できることがわかりました。
第一部の冒頭に登場する64歳の「王子」の話を、映画監督の黄信堯(ホアン・シンヤオ)さんが、朗読しています。
これは、ぜひ聴いてみてください!
中国語の字幕をつけると、漢字からの類推で、本のどの部分を朗読されているかがなんとなくわかるような気がして、ちょっとうれしくなります。
黄監督の、穏やかでハスキーな声で朗読される、李さんの文章。
ほんとうに素敵です。
「訳者あとがき」によると、この本の企画は最初、17社もの出版社から断られたそうです。
それを志ある編集者、李晏甄(リー・イェンチェン)さんが小さな独立系出版社 ・游撃文化に入社後の初めての仕事として引き受け、それからさらに3年ほどかけて、本のかたちになったそうです。
いつも不思議に思うのですが、本というのは、目に見えるかたちを持って存在しているけれど、その背後の、目には直接見えないものが、実はすごく大きな役割を果たしているのではないでしょうか?
関わった人たちの時間や想いが、しっかりこめられた本。
そんな本は、印刷された文字を脳が意味に変換するということからだけではなくて、その本を持った手からも、ページをめくる指先からも、何かが伝わるような、何かが立ち上がってくるような気がするのです。
「祝福されている本」、と私は勝手にそういう本のことを呼んでいます。
そういう本との出会いはこのうえない喜びで、この本も、私にとってはそんな一冊となりました。
この本は写真も、挿絵も、実に味わい深いです。
機会があったら、ぜひ実際に手に取ってみてください。
* * *
