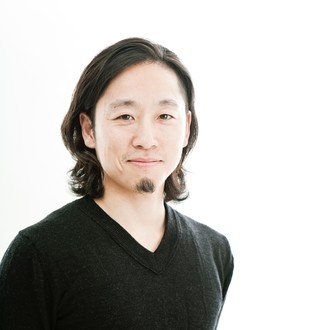【臨床日記】肩甲骨は胸椎とセットで動くということは胸椎の可動性の低下は肩甲骨に影響するということ
肩には「肩甲上腕リズム」(Scapulohumeral Rhythm)という関係性が存在します。
肩甲骨と上腕骨が1:2で動くというものですね。
その他にも「ゼロポジション」や「肩甲骨面」(Sucapula Plane)という面が存在し、肩に負担のない使い方のために必要な知識です。
ここまではスポーツやリハビリテーションの常識です。
肩甲骨は大事だよということですね。
ただし、上記の肩甲骨面の動きのためには、胸椎の可動性が重要というところになると、まだ常識とはいえない部分があります。
運動療法の専門家でも気づいていない人もいます。
肩甲骨-胸郭連動とでも言いましょうか。
肩甲骨には4つの動きがあります。
前方突出(外転)
後退(内転)
上方回旋(挙上)
下方回旋(下制)
これらの動きが組み合わさると、胸郭の動きになります。
胸郭とは、胸骨と肋骨と胸椎ですので、関節としては以下の関節になります。
肩甲胸郭関節
胸肋関節
肋椎関節(肋横突関節、肋骨頭関節)
肋骨の動きに関してはこちらも参照してください。
胸郭に存在するこれらの関節の動きを促すと、肩甲骨の動きが広がり、結果的に肩甲上腕関節への負担が減ります。
スキャプラプレーンは分かっていても、その状態を維持できない理由は、胸郭の可動性にあるということは多々あります。
胸郭の可動性の評価としては、体幹の回旋がおすすめです。
回旋は、椎間関節としては伸展と屈曲の組み合わせです。
そして、この回旋こそが人間特有の動きなのです。
胸郭の動きとしては抗重力である伸展がやはり重要です。
伸展の可動性低下は肩関節の屈曲に影響を与えます。
特に前方突出は前鋸筋で、肩関節の外旋とセットになります。
ここに機能低下が起こるとインピンジメントの原因になります。
また、回旋の低下は後ろの物を取るときにスキャプラプレーンからの逸脱を起こし、上腕二頭筋長頭腱炎につながります。
肩を考える時は、胸郭をセットで考える必要があります。
Scapulohumeral-thorax complexとでも言いましょうか。
SHT-complex。
何か良いですね、横文字(笑)
いいなと思ったら応援しよう!