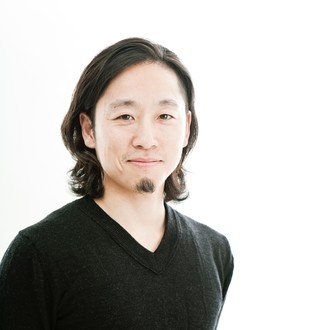【予防運動】臼蓋形成不全に気づいたら注意すべきこと
先日のパーソナルレッスンに臼蓋形成不全から変形性股関節症に進行された方がいらっしゃいました。
臼蓋形成不全とは、股関節の構造が一般の方に比べて浅い状態のことを言います。
変形性股関節症は、関節の変性疾患で概ね中年になってから軟骨の消失、骨の変形などが起こります。
変形性関節症の原因の8割が臼蓋形成不全です。
しかし、痛みが出るまで多くの方は自分では気づきません。
痛みが出た段階ではもう変形性関節症の初期になっています。
進行は早い人では1〜2年です。
痛みの他に可動域制限、脚長差などが起こります。
特に可動域制限は生活に支障が出てきてしまいますので、最終的には人工関節になります。
現在は再生医療もありますが、まだ人工関節ほどの劇的な改善とまでは行っていないと思います。
結局は予防が一番大切です。
臼蓋形成不全の兆候
痛みがないのに外から臼蓋形成不全かどうかを判断することは困難です。
レントゲンですぐ判断はできますが、痛くない人がレントゲンを撮ることはないでしょう。
だだし、臼蓋形成不全の方には、特徴的なサインがあります。
以下の中で当てはまるものが多い方は注意したほうがいいかも知れません。
股関節が外れるような不安定な感じがすることがある。
同じ姿勢を取った後に動き出すと、股関節で音が鳴る。
股関節のハマりが悪く、音を鳴らして整復すると楽になることがある。
特にヨガをしている人は要注意です。
先日いらした方はバレエ、ダンスでした。
これらの体操は関節の可動域を必要以上に増やしてしまいます。
基本的に関節のルーズさはそのまま関節症のリスクになります。
体が柔らかいことはいいことだと思っている方が多いと思いますが、医療的に見るとそれは関節が不安定だということで、危険なサインです。
音が鳴る、外れる感じがするというのは不安定性を示しています。
ヨガやバレエは関節を不安定にしかねないのです。
さらに臼蓋形成不全があるなら、尚更です。
ただでさえ構造的に不安定なのに筋肉を伸ばして、関節にストレスをかけて練習してしまうのです。
正直、臼蓋形成不全の方には避けてほしい体操です。
予防的な視点では、臼蓋形成不全に限らず、骨格的に向いているスポーツや体操、逆に向いていないスポーツや体操がそれぞれにあります。
うちの子どもは四人いますが、それぞれ体の特徴を持っています。
運動神経も然りです。
ですから、それぞれ違うことをしています。
向いている、向いていないがあるのです。
それは好き嫌いという好みではなく、体の傾向なのでどうしようもありません。
そういう意味で、好きだったから体を犠牲にして楽しんだというのが関節症に移行した人の現実です、、、。
人生としては致し方なかったのです。
ただ、もし僕がまだ前述したサインが出ている若い子なら、忠告したでしょうね。
向いていないよと。
ここに前捻角の問題が加わるとさらに関節を壊す習慣になってしまいます、、、。
臼蓋形成不全も骨格の特性です。
この概念がもっと広まれば、予防できる疾患は沢山あります。
もどかしいですが、まだまだ医療者も運動指導者もこの事実を知りません。
予防歯科がこれだけ認知度があるのにもかかわらず、運動器に関する予防運動はまだまだです、、、。
この投稿を読んでる方くらいでしょうね。
臼蓋形成不全の方がすべきこと
自分が臼蓋形成不全かも知れないと思ったら、まずはレントゲンで確認することが必要です。
医療保険は問題がなければ適応されません。
ですから、股関節に違和感があるとか痛みがあるとかが必要です。
気になるだけでは難しいので、何かしらの問題を提示して受診して下さい。
CE角、Sharp角という角度ですぐに測定できます。
臼蓋形成不全の傾向があると分かったら以下のことをして下さい。
過剰に関節の可動性を高めるようなことはしない。
重いものを持ったり、激しいジャンプ動作などは避ける。
脚長差の有無を確認して左右差は補正する。
ジグリング(貧乏ゆすりの様なもの)を行う。
不良姿勢で立つ、歩くことをやめ正しい姿勢と歩き方を習得する。
貧乏ゆすりは面白いですよね。
軟骨再生に効果があるとされています。
近くに以下の専門家がいる場合はぜひ相談して下さい。
予防運動アドバイザー®︎
脚の長さコーディネーター®︎
ファンクショナルローラーピラティス®︎
今、予防運動の仲間が変形性股関節症予防に向かって、HPやコンテンツの開発を頑張っています。
何こちらでも紹介できると思います。
変形性関節症にならなくてもいい時代が来ますように。
予防運動を地道に広めていきます。
いいなと思ったら応援しよう!