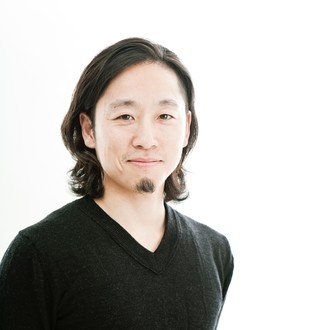安全な筋肉の緩め方〜相反神経抑制とは〜
【筋肉を緩める】
多くの方は、左右開脚したい、前屈で手を床につけたいとか、体の柔軟性に関してそれなりの関心があると思います。開脚の本が100万部を超えるところから、潜在的に柔らかくなりたいと思っている人が多いということでしょう。
まぁ左右開脚できたところで日常生活で役に立つことは殆どありませんけど、、、。Instagramで見せたいということでしょうか、、、。
左右開脚が必要かどうかはさておき、柔軟性がある程度あることは、怪我の予防や血流の改善などいいこともあります。
柔軟性がないとは、筋肉が緊張していることであり、柔軟性があるとは、筋肉が緩んでいるとも言えます。柔軟性を獲得するためには筋肉の緊張を落として緩ませなければなりません。
筋肉を緩める方法には、以下のようにいくつかあります。
・持続的ストレッチ(伸張、自己抑制)
・マッスルリセッティング法(筋肉を短縮させる方法)
・筋肉を温める
・心をリラックスさせる
そして、今回のテーマである相反神経抑制があります。
【相反神経抑制とは?】
相反神経というのは、表裏の筋肉関係を指し、筋緊張が反射で制御されていることです。「抑制」という言葉を使うのは、筋肉の緊張には「興奮」と「抑制」の神経がそれぞれ存在していて、筋肉を緩めるには、その内の抑制神経を用いているからです。
肘を例に挙げると、肘には「曲げる筋肉」と「伸ばす筋肉」があります。屈伸は相反関係にありますから、肘を曲げている時には伸ばす筋肉は緩んでおり、肘を伸ばしている時には曲げる筋肉は緩んでいます。
もし両方が緊張してしまったら、肘は屈伸ができない状態で固まってしまいますね。
少し早く肘を曲げ伸ばしすると分かると思いますが、その屈伸の筋肉の相反関係を意識しては行なっていないですよね。つまり、曲げている時に同時に伸ばす筋肉を緩めようと意識はしていないということです。
曲げれば勝手に伸びる筋肉は緩みます。なぜならそれは反射で制御されているからです。効率的ですね。この反射は曲げる筋肉からの刺激(筋紡錘という受容器)で相反神経にスイッチが入り、相反神経が反対の伸ばす筋肉に指令を出して抑制がかかるという反射です。反射ですから意識は関係ないので、とても早く反応が起こります。
では、肘を実際に使って確認して見ましょう。
①先ずは、自分の腕を触って、二の腕の筋肉の緊張を確認しましょう。硬さを感じましょう。
②次に片脚を持ち上げて、肘を軽く曲げた状態で膝に手を当て、その脚を下に降ろそうと力を入れます。脚は負けずに上げ続けておいて下さい。その時の曲げる筋肉(力こぶの筋肉:上腕二頭筋)の緊張はどうなっていますか?そして反対の筋肉(上腕三頭筋)はどうですか?

③次に、上げていた脚の膝下に手を入れて、脚を持ち上げようとします。脚は今度は下に降ろそうとして下さい。この時の曲げる筋肉(力こぶの筋肉:上腕二頭筋)の緊張はどうですか?そして反対の筋肉(上腕三頭筋)はどうですか?

感じましたか?力の入っている方は固くなって緊張が高く、反対は柔らかくなって緩んでませんでしたか?でも緩めようとは考えなかったはずです。これが相反神経抑制です。
このように相反神経は、面白いことに片方の筋肉を緊張することで、逆にその反対の筋肉を無意識で緩めるという効果があるのです。つまり、、、。
筋肉を緩めたければ鍛えなさい!
ということです。
いいなと思ったら応援しよう!