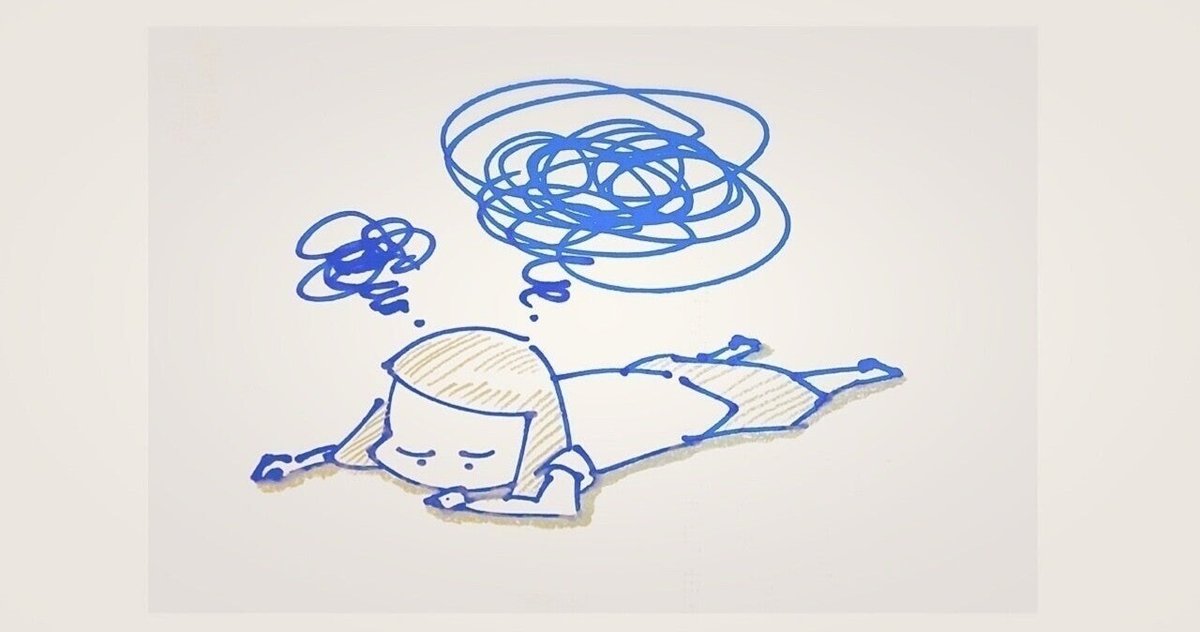
【子育て】小4くらいの女子が一番わけわからんかったのには、わけがあった。
こんにちは ナカちゃんです。
連休中日、カレンダー通りに仕事でした。
5日までに、何とか5冊の教科書を読み終え、マークシートテストまでたどり着きました。
今日は、最後の1冊 『思春期・青年期の心理臨床』に取り掛かり中です。
今、前半を勉強しているのですが、自分の子育てで、どうしてもモヤモヤしていたことが、「そうだったのか。」とスッキリしたので、
今日は、そのことを書こうと思います。
子どものことが、よくわからなくなるのは、中学生の反抗期ではなくて、小学校の3〜4年生くらいからだ、ということ。(特に女子)
娘の子育て中、一番手を焼いたのは、小学校中学年から高学年にかけてでした。
いわゆる「反抗期」は、中学校に入ってからというイメージがあると思いますが、女の子は特に、「荒れる」時期というのが、そこではない気がしていました。
中学校ではそこそこトラブルはありますが、いろいろとこじれるのは、小学校4〜5年生がピークなのではないか、とも。
実際に、自分の子どもが一番大変だったのも、その頃でした。
親にベッタリしたかと思うと、反抗的になり、学校ではうまく行かず、人間関係が拗れる。先生との関係も、うまくいかない。
自分の体型も変わり、生理とかいう厄介で恐ろしいものが始まり、理由もなく太ってしまう。
何をしても鬱々とした感情が消えずに、でも、自分でもどうしたらよいかわからない。
そして、その不安を「言語化できない。」
だから、苦しい。
本人が、「これから、自分はどうなってしまうんだろう?」という強い不安にかられていたことは、後で知りました。
実は、この時期を「前思春期」というらしい。
この時期は、第二次性徴が始まる前、まだ子どもの体のままなのだけれども、心が大きくオトナに向けて変化するのだそうです。女子は3年生位から、男子は4年生か5年生くらいで始まると言われています。
前思春期には、それまで当たり前だと思っていたものが突然にあたりまえでなくなる体験をします。
色々なものに違和感を持ってしまい、「世界に対しても、自分に対しても突然に違和感を持つ」時代であると考えられています。
その意識が行き過ぎると、醜貌恐怖や摂食障害、強迫神経症に繋がりかねないほど、不安定な状況に落ちいってしまうのです。
友達関係も、大きく変わります。排他的で親密な同性の友達が大切になってしまいます。その関係が、彼女(彼)らの「世界のすべて」になってしまうのです。
これらの変化が、子どもに起こっているとき、大人(親)は、どれだけ彼らのことを理解できていただろうか?
「思春期・青年期」の子どもたちが、不安定であることは、広く知られていますが、その前の「前思春期」の子どもたちの心理状況を知っていたら、もっと子どものことを分かってあげられたのかな。。。とも思います。
中学校にいると、12歳から15歳の子どもたちを相手にしているので、それ以前の子どもたちについて知ることがあまりありませんが、自分の子育てで「?」と思っていたことが、役に立つこともあるんだな、と改めて感じています。
「前思春期」を経て、「思春期」、そして「青年期」へと
子どもたちは成長していきます。
彼らの成長を、適切な距離で見守っていくために、
私達大人が、彼らに寄り添うために、学ぶことが必要なのだなあと、
改めて感じた出来事でした。
いいなと思ったら応援しよう!

