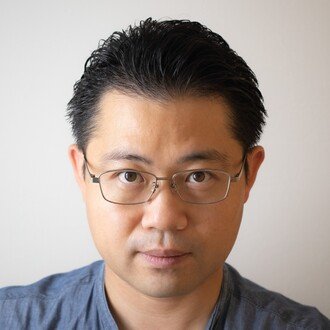東国の櫟【読書感想文】
梅雨入りのニュースとほぼ同時に、頼んでいた書籍が手元に届いた。
…『雨は五分後にやんで』
雨音を聴きながら、本を読む。私はこの静かな時間を、大切な時間として過ごした。そしてその中の一つの歴史小説に目を通す。
歴史小説は時と場所を越えて、人と生をつなぐ。
このオムニバスの最後に収録された小説『東国の櫟』を読み、あらためてそのことを思い知る。『髙島泰』名義で書かれたそのたった20頁の小説には確かに歴史と人物が描かれていて、登場人物である忠宣王(ちゅうせんおう)と李斉賢(りせいけん)の人生を通して見える世界があった。そのことを今回は読書感想文という形でお話ししたいと思う。
この小説の主要な舞台は14世紀の大都(チンギス・カアンが造営した都市で、場所は現在の北京に位置する)である。
そこには蒙古軍によって国土を蹂躙された高麗王の末裔である忠宣王(ちゅうせんおう)が居て、高麗・慶州の生まれであり学問に秀でた李斉賢(りせいけん)を大都に呼び、召し抱えるところから物語は展開される。
二人は学問や詩を通じて年の離れた友人のように時を過ごす。
煌びやかな大都での学究生活を謳歌する李斉賢であったが心の隅では荒れた高麗の地を尻目に恵まれた環境にいる自身の姿をいつしか後ろめたいものとして捉えるようになっていた。
そして、ついには疑念を忠宣王に投げかけるのである。
そこで李斉賢は忠宣王の本心を知る。
忠宣王は支配者の姻戚の身として大都に身を置きつづけることで高麗の地を護っていたのである。いや、そう信じているのである。李斉賢は涙する。
『東国の櫟』
これは身を大都に置きながら、心で高麗を案じる退位した忠宣王とそれを慕う李斉賢の物語である。
そして、二人にとって心の裏舞台は常に高麗なのである。志を共にしている。
それは李斉賢が高麗の開京に戻り、忠宣王と離れて職に就こうが変わることが無い。政略的な流れで忠宣王の身が吐蕃(チベット)に移されようが変わることが無い。
この移ろいが多い世の中で何が変わって何が変わらなかったか。この小説にはそれが描かれている。
あとはあなたの目で確かめてみてほしい。
私が語ったのはあらすじである。
20頁の小説も長い歴史からみればあらすじと言えるかもしれないが、そこには明確な編集があり、血が通っている。
そこには見慣れない言葉も多くあるだろう。
でも、一つ一つ調べればいい。
どうしてその言葉を選ばなければならなかったかがきっと見えてくるだろう。
言葉の意味ばかりではない、少し地図を調べるだけで開京と江華島がどれだけ近いかに驚愕するだろう。
そこには日本海を間に挟み、元寇の脅威を回避できた日本には分からない苦しみが、開京と江華島の距離の短さに顕れている。
重要でなさそうな単語も調べてみればいい。
『海東青』、朝貢の一つとして半島から納められた鷹である。
美しい鷹だ。
これが毎年数千に及ぶ奴隷や、大量の鉱石、農作物と一緒に要求された。
そう、全てが奪われてゆくのである。
調べれば、それらすべての苦しみや悲しみが言葉・文字に圧縮されているのをあなたは感じることができるだろう。
その中で変わらなかったものを見つけてほしい。
それがきっと美しさや希望である。
私はそう思った。
いいなと思ったら応援しよう!