
クラシック音楽の歴史 #001「信仰統一のためのグレゴリオ聖歌」
こんばんは。名古屋クラシック音楽堂(@nagoyaclassicca)です。ずっとやりたかったクラシック音楽の歴史シリーズを今日から始めたいと思います。
そもそも、クラシック音楽とは1550年頃から1900年頃に生まれた音楽のことを指しますが、それ以前のものも、それ以後のものも、同じ流れに属する音楽のことを、あわせてクラシック音楽と呼ばれることが多いです。
今日から始める「クラシック音楽の歴史シリーズ」では、主に西洋音楽史を基盤に今日クラシック音楽と呼ばれる音楽の歴史を順に追っていきたいと思います。
それは、音楽に限らず、美術や文学、哲学、数学、科学、天文学といった学問は、歴史の上に積み重ねられてきた人類の功績といってもいいものだからです。
歴史を知ると、なぜその時代にその文化や風俗が生まれたかが理解できます。特に音楽や美術はその時代時代の情勢に大きく影響を受けています。
とはいえ、クラシック音楽を知るということを「お勉強」としてご提案したいわけではないので、クラシック音楽にまつわる歴史のトピックに「へぇ!」と発見や驚きをもっていただき、クラシック音楽の時間の連続性を楽しんでいただければと思います。
そして毎回、SpotifyやYoutubeの音声や動画も一緒にご紹介しますので、記事を読みながらぜひ音楽もお楽しみください♪
はじまりは、キリスト教布教の最強ツールとなった「信仰統一のためのグレゴリオ聖歌」
第1回目に取り上げるのは「グレゴリオ聖歌」です。今回Spotifyからご紹介するグレゴリオ聖歌のアルバム「Canto Gregoriano」は1993年にリリースされ翌年1月までに25万枚を超える驚異的なヒットを記録しました。
歌うのは、スペインのサント・ドミンゴ・デ・シロス修道院のベネディクト会の修道士。ベネディクト会は、529年にできたカトリック教会最古の修道会です。
キリスト教の新約聖書には最後の晩餐で賛美歌を歌ったことが言及されています。つまりイエス=キリスト存命の時にすでに讃美歌は歌われていたと思われます。
そして、4世紀初頭には教会の毎日の聖務の中で聖歌が歌わていました。ですが、この時代の聖歌は各地固有、つまり国や地域によってバラバラでした。
この聖歌は、そもそも識字率の低い民衆にイエス=キリストの偉業を字が読めなくても理解できるようにし、宗教画と共に信仰への求心材料として生み出されたものです。
590年から604年に在位したローマ教皇グレゴリウス1世によって、バラバラだった聖歌を「グレゴリオ聖歌」として編纂・統一されたと言われています。
これは、聖歌を統一することによって「キリスト教=ローマ教皇」という民衆への教会権力の刷り込みが図られたとされています。
統一された聖歌をヨーロッパ中に均質に普及させるための楽譜の誕生
聖歌は何世紀もの間口伝によって伝えられてきました。しかしひとつの聖歌を当時のヨーロッパ中に伝播されるためには、音楽を正確に伝えるためのツールが必要になります。
それで9世紀に誕生したのが、ネウマ譜。最初は音の高低が現代のような五線譜ではなく、相対的にアクセントやニュアンスを表記するにとどまりましたが、12世紀後半になると4線譜が登場します。
この楽譜の普及とともに、グレゴリオ聖歌は西方キリスト教世界の他の聖歌を完全に凌ぎ、駆逐していきました。
グレゴリオ聖歌は中世西洋音楽およびルネサンス音楽に大きな影響を与えていきます。現代の記譜法はグレゴリオ聖歌のネウマ譜から直接発展したものです。
名古屋クラシック音楽堂はTwitterもやっております。
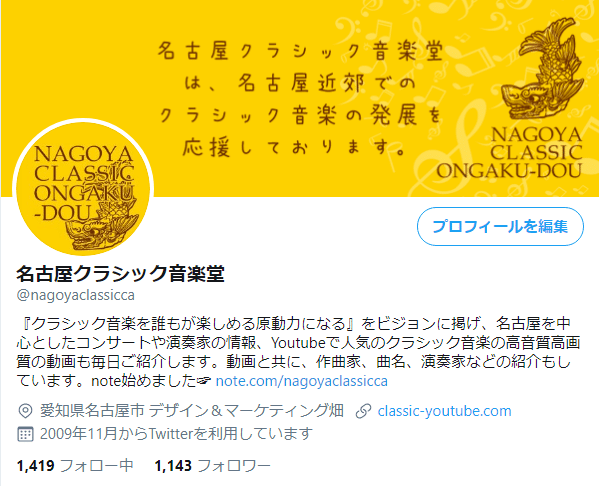
名古屋クラシック音楽堂のTwitterでは、毎日クラシック音楽に関するニュースや、演奏会・ライブ配信などの情報をシェアしています。ぜひフォローお願いします。
