
ゼロからの挑戦、ガチで切り拓く心不全治療の未来
日本人の死因の第二位を占める心疾患。その原因の一つが「心不全」です。心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液が送り出せなくなった状態のことをいいます。高齢化に伴い、年々患者さんが増加しているんだとか…😥。
「心不全の患者さんの数は増えているのに、特効薬がありません。」
そう医療の現場の状況を教えてくれたのは、名古屋大学の吉田 達矢さん(医学系研究科 客員研究者)です。名古屋大学の循環器内科を卒業した今、指導教官だった竹藤 幹人さん(医学系研究科 講師)と共に現在も心不全の基礎研究を進めながら医師として仕事をしています。今回は心不全の制御機構に新しい発見があったとのこと。早速お話を聞いてきました。

写真右上:吉田 達矢さん(医学系研究科 客員研究者)
今回もフロントライン担当の丸山 恵& 坪井 知恵(名大URA)がインタビューしてきました😉。
ポッドキャストでインタビューのダイジェストをお届けしています。ぜひ番組登録いただき、新着をお受け取りください。
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
──心不全っていくつか種類があるのですか?
(吉田さん)そうですね。機能不全が起こっている場所による分類(左心室と右心室)もありますし、最近では心臓の機能による分類(収縮不全と拡張不全)で大きく二つに分類されています。HFrEF(収縮不全)とHEpEF(拡張不全)です。HFrEFは心臓のポンプ機能が落ちてしまう、従来知られている心不全です。HEpEFは心臓のポンプ機能は落ちていない心不全で、実はこの10年くらいで世界的に増えているのですが、従来の心不全の治療薬が効かないので世界的な問題となっています。
──ポンプ機能が落ちていないのに、心不全??
(竹藤さん)心臓を風船に例えると…風船って膨らんで、縮むじゃないですか?縮まなくなってしまうと全身に血が送れなくなるので、それが心臓の機能(ポンプ機能)が落ちているって言われていたのです。それが従来型です。最近だと、逆に、膨らまないってことも心不全の原因だと考えられるようになりました。膨らめないと送り出す量も少なくなってしまいますから。縮むのができないのか、膨らむのができないか、簡単に分けるとその二つに分類できます。

(図は看護roo!「心臓の電気伝導の原理|心臓と心電図の原理」(https://www.kango-roo.com/learning/2165/)より引用)
──なるほど。なぜHEpEF患者さんが増加しているのですか?
(竹藤さん)検査技術が発達し、心臓の拡張を正しく評価できるようになったことが原因の一つかな、と思います。また、食事の欧米化による肥満や高齢化の影響もあると思います。
(吉田さん)しかし、原因は未だ分かっていないので、拡張不全型のHEpEFについて研究を進めました。その中で、ALPK2というプロテインキナーゼの一つが心臓特異的に発現していて、拡張不全を抑える可能性を見出しました。
──アルファキナーゼ❓って初めて聞きました…😮
(竹藤さん)15年前に既に存在自体は明らかになっていましたが、その機能は分かっていませんでした。なので、聞いたことなくても当然かもしれません😉。
竹藤さんはプロテインキナーゼ研究の第一人者です。15年前の留学からプロテインキナーゼ研究に没頭し、約520種類のプロテインキナーゼが発現する臓器を調べてきたんだとか。今回のALPK2もその時に存在は明らかになっていましたが、その機能は分かっていなかったようです。竹藤さんは、世の中に知られていないキナーゼの働きを見出し続けています。
👇👇👇👇👇👇
──ならよかったです🤭。どんな実験でそれが分かったのですか?
(吉田さん)まず、HEpEF(拡張不全)のモデル動物を作り、心臓の細胞だけに特異的にALPK2の発現を無くす(ノックアウト)操作を行いました。その結果、正常な動物に比べて心臓の拡張がより悪化していました。

是非コチラからご覧ください🤗。
──ALPK2がないと拡張できないんですね。でも、ALPK2はどんな働きをしているんですか?
(吉田さん)ALPK2は筋肉が伸びたり縮んだりするのに重要なTPM1というタンパク質を活性化することがわかりました。この活性化が進むことで、心臓がしっかり拡張できるようになる、と考えられます。

──主にALPK2がTPM1を活性化している、と考えてよいのですか?
(吉田さん)厳密に言うと他のキナーゼも関与しているかもしれませんが、よりメインでリン酸化しているのはALPK2なのかな、と思っています。
──大発見ですね!HEpEFの新たな治療法のアプローチにも繋がるのでは?
(竹藤さん)そうですね。しかもこのALPK2は主に心臓で作られているので、ここをターゲットにしても他の臓器には理論上はあまり影響はないのではないか、と思っています。心臓にのみ、効率的に効くような薬の開発に繋がるといいな、と思っています。
──とはいえ、実験では苦労されたことも多いように思いますが…。
(吉田さん)そうですね…😏苦笑
(竹藤さん)吉田先生が入学する前に、私が一人で数年間は準備をしていたのですが…なんていうか、今回はガチの研究だったんですよ。
──ガチ!?
(竹藤さん)成果が見えるかどうかも全く分からなくて、一からの立ち上げだったので、本当にガチの研究だったので、結構辛かったと思いますよ。
(吉田さん)そうですね~。でも、頑張ったから運も味方してくれたと思っています。HEpEFのモデル動物なんて入学する直前で報告された方法でしたし、入学のタイミングに新しい方法論が生み出されたこと自体も、なんだか運命のように今となっては感じています。
──何事もタイミングなんですかね。
(竹藤さん)タイミングもそうですが、一人ではない、ってことです。世界中の人がみんなで解けない謎に向かって行くことで、ほんの少しずつその謎が解けていく。それが時間も空間も越えて繋がっていって、何かを引き合わせていく…そういうところが研究の大事な一つかな、と。
(吉田さん)竹藤先生と出会えていなければ、今の自分もないと思います。竹藤先生のご指導のもと、大きく進められることができましたが、6年間、本当に大変でした🤭。
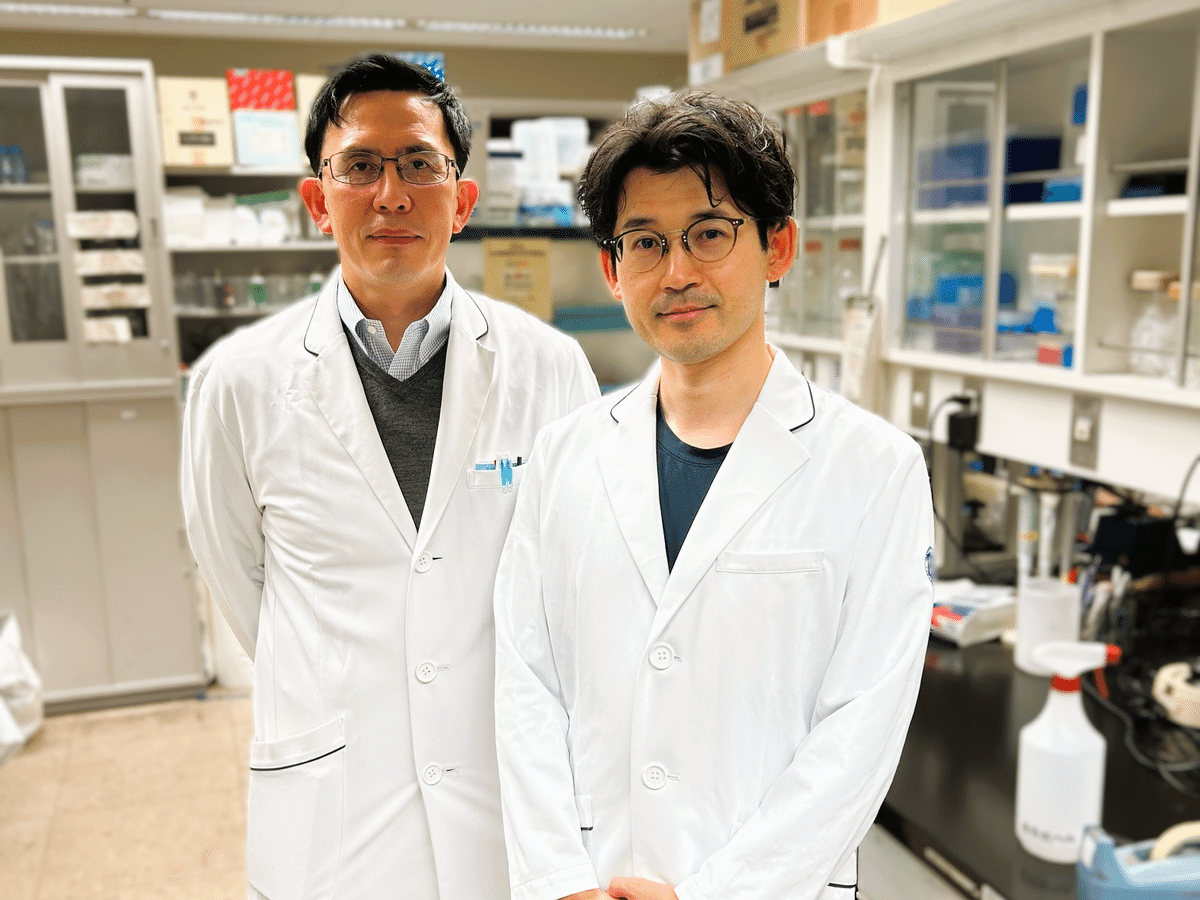
なぜ循環器に進もうと思ったのですか?という問いに、お二人揃って「命に直結する、ダイナミックさに惹かれたから、ですかね。」と。命に直結するダイナミックな研究に、お二人ともスタティックな気持ちで真っすぐ突き進んでいらっしゃる姿に、とても励まされました🥲。
── 特効薬がない、ポンプ機能が落ちていない心不全。今回の研究の成果が、その謎を解くカギとなり、心不全の治療に新たな光となる日は遠くないように思いました。お二人の歩みは時空を超えて、今後何を引き合わせていくのでしょうか…🫀
インタビュー・文:坪井知恵(名古屋大学URA)
◯関連リンク
論文(国際学術誌「The FASEB Journal」誌に掲載、表紙を飾りました。論文タイトル:ALPK2 prevents cardiac diastolic dysfunction in heart failure with preserved ejection fraction
竹藤 幹人さん
