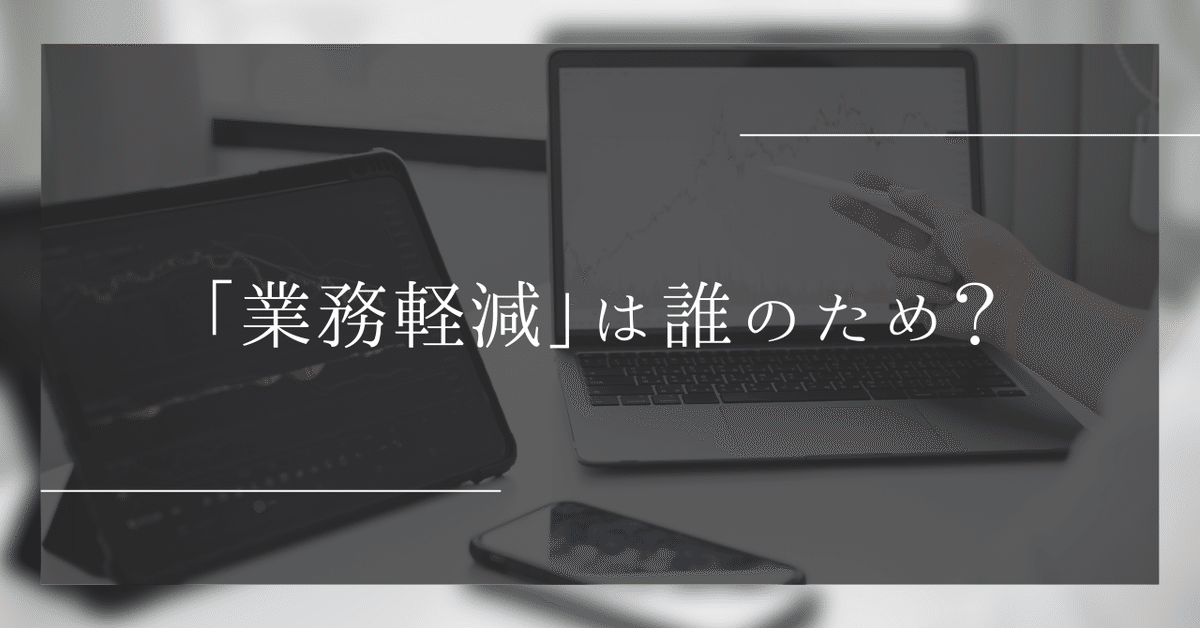
「業務軽減」は誰のため?
先生って大変ですよね。
「先生」=「ブラック」というイメージがついてからもうどれぐらいの月日が経ったのでしょうか。最近ではないはず。
私が教員を目指した時からもそういうイメージでしたし、高校生の時の父は本当に忙しそうでした。
教員の1日に特集して「ブラックさ」加減を伝えているダイジェスト映像。
過労死ラインを大幅に超えて、その命を自ら絶ってしまう悲しきニュース。「定額残業させ放題」という名の「教職調整額」(給特法)。
なかなか進まぬ部活動地域移行。
「成り手不足」が露呈してしまっている教員採用志願者向。
そして、「忙しい」と叫び続けている職員室の先生方。
私の身の回りだけでも、その「ブラックさ」は至る所で耳にしたり、目にします。私自身も定時で帰れたことが年に何回あるのでしょうか。
確かに、教員は所謂「なんでも屋」に成り果て、業務のメインである授業に支障が出るほどの、事務作業、保護者対応、分掌業務、私立なら広報活動、、、。
一般的な企業に勤めたことがないので、比較し難いですが、これほどまでに様々な仕事内容を定時を超えた時間で日々こなしている仕事や働き方は、もはや令和という時代の中では「異常」であることは認識できます。
だからこそ、今は「業務削減」「業務軽減」や「働き方改革」が求められてきている流れとなっています。
昔と対比すれば、この「なんとかしなければ」という気持ちが芽生え始め、何ができるのかを考えようとする姿勢が、公学私学共に見られ始めたのではないでしょうか。
教育現場から聞こえる悲痛な叫びの中の小さな疑問
ただ、そのような状況の中、先生方の悲痛な叫びに少しだけの疑問を抱くことがあります。
「業務削減は誰のため?」
私は、どこかこの「業務軽減」が「教育の本質」と乖離してしまっているのではと危惧しています。
「忙しいから〇〇をやめよう!」
それは、先生の負担を減らすためだけになってませんか?
「今は手一杯だから、〇〇はできない」
本当にやるべきことは、教育的価値があるのもを忙しさを理由に拒絶するのではなく、よりよい教育を取捨選択していくことではないですか?
こんなことを思うことが最近増えたからこそ、私は2つのことを意識し続ける必要があると思っています。
業務軽減=生徒のため
まず1つ。
もうすでに問題提起させていただきましたが、
「業務軽減」=「生徒のため」
にしていかなくてはならない。
ということです。どんなに忙しくても、「学校」は「学校」です。
「学校」という場所は、「教育の本質」である、「生徒と共に未来を考え、社会をよりよいものにしていく持続可能な社会の創り手」を育成していく場にする必要があるのではないでしょうか。
決して、教員だけで完結することなく、生徒がよりその教育ができるように整えていくという、目的・目標を忘れることなく進めていきたいと思うのです。
ただ、やめればいい。なくせばいい。
忙しいから新しいことを増やさない。
そんな単純な形で終わらせたくない。
どんなことだって「教育をする先生」だということを忘れてはならない。
と私は思うのです。
業務軽減=「探究のロールモデル」になるため
そして2つ目。
「探究のロールモデル」になる絶好のチャンスだと思うこと。
前回の記事で、「時間」の儚さについて触れさせていただきました。
同じことが言えますが、「忙しい」「大変」と嘆いているだけになってしまっては意味がないと思います。「時間の流れ」は私たちと一緒に教員のブラックさを嘆いても、愚痴ってもくれません。
話が逸れますが、
なぜ、「総合的な探究の時間」を設定しているのでしょう?
それは、目の前の子どもたちにその「探究心」を持って欲しいからだと思っています。
「探究」は決して、遠い国の「社会問題」や、SDGsを解決するだけではないのです。「探究」とは目の前の状況に対し、批判精神を持ち、課題発見・課題解決をし、よりよい社会を作っていくという、未知なる未来への生き残り戦法です。
そしてそれは、決して子供たちだけの問題ではない。
未来を生きるのは私たち教員としての大人も同じこと。
VUCA時代を生きる子どもたちに求めているのと同時に、教員自身が激しい変化を前向きに捉え、行動を起こし改善しようとすることが必要になる。
子どもたちが、学校が、予測困難な社会の中で生き残り、持続可能なものにしていくのであれば、「教育者」としてのこのスキルを身につけていきたいと思ってます。
教員は「知識」としての「探究」を教えるたけではではく、「業務過多」という学校全体が抱える課題を解決するために、所属している環境をより良くしていくために、行動を示すロールモデルとなれば、子どもたちをも巻き込むよき学習が一緒にできるのではないでしょうか。
「嘆く」のではなく「考える」時間に、教員が、私がしていく。
子どもたちと一緒に「未来」を作る。
たしかに、教員4年目の私ができることは限られています。
できることも立場的に少ないと思います。
だけど、それを嘆くのではなく、私だからこそできることとは何かを考え続けていきたい。その思いで私は「業務軽減」とは何かを見つめなおしてみます。
理想主義者が探究心を持ち続ける
最近、noteで記事を書いているときに少しある不安としては、「そんなの理想論だ」って言われそうなこと。
間違いないです。私はおそらくきっと「理想主義者」なんですよね、、、。まあそうですよね、、、。認めざるを得ません。今までの記事の様子からもそれがお恥ずかしいぐらいに謙虚に出てしまっていまよね。
たしかに、最初にも述べたように、「業務軽減」はそんな簡単に解決できる問題ではないからこそ、これだけ長期間にわたって大きく問題視されています。
学校単体で動くことも制約されていたいり、国がなかなか動かないことも承知です。多方面にわたる原因が複雑に絡み合ったことが、今の教員の業務過多へと結びついてしまった結果だということも認識しています。
だけど、「理想主義者」はその理想の追求を諦めないことが強みです。
そしてそれを「探究心」をもって追い求める。
国が、管理職が、誰かがやってくれるのを待つのではなく、その「理想」や「あるべき姿」を追求するために生徒と同じように「探究心」を磨いて、私という人間に何ができるか、できることが何かを考え続けて、行動し続けて、訴えて続けたい。
「探究心」を持ち続けた者が見つけられる新しい発見が、よりよい教育ができるタネとなるという希望を捨てることなく向き合っていきたいと思います。
子どもたちが強く逞しく「生きる力」を身につけるための教育ができるような場所に、「学校」がなるように。
先生と子どもたちが共に「未来」を明るく語れる場所になるように。
今日も、明日も、これからも、私は学校で「教育」をしていきます。
