
ピアノが弾ける発達障害児に対する、世間の思い違い(ドクターも!)
今回は、ピアノ演奏を習得してきた(この場合は両手奏を指します)
発達障害のある子ども達について、世間の思い違い・・思い込み・・
「それは違うよ!」について2つ、お伝えしたいと思います。

25年近く、自閉症を始めとする様々な症状を持つ子ども達に
ピアノを教えて来ましたが、ショパンのノクターンが弾けるまでになる子、
バイエルをコツコツこなし、ハノンと併行して、ブルグミュラーへ進む子、8分音符が混じった演奏まではできるようになる子・・と、
その進度が、能力や練習量によって変わってくるのは、
ごく当たり前のことです。・・と、私は思っています。

ただ、この子たちは、
発達障害があるにも関わらず、奇跡的にピアノが
弾けるようになったのでしょうか?
それとも
何か特殊な才能が元から備わっていて、それが故に
ピアノ演奏が可能になったのでしょうか?
努力という才能
初対面の人に、私が発達障害のある子ども達に
ピアノを教えていることを話すと、たまに
「あ~あの子たちって、何かすぐにスラスラ弾けるように
なるんでしょ?」と言われることがあります。
おそらく、絶対音感を持っている自閉症の子どものイメージから
不思議な印象を持っているんだと推測します。
確かに、聴覚が優れている子どものピアノ習得は、
そうでない子に比べて早いです。
でも、だからと言って、魔法をかけられたように、
ピアノの前に座ったとたん、スラスラ弾いているわけではありません。
とにかく、よく練習をするのです。
毎日毎日、例外を作らず、365日、決まった時間に練習をしています。
宿題をきちんとこなすことで、一つずつの課題を克服し、
やがて読譜力が上がるに連れて、スラスラ弾けるようになっていきます。
努力して習得していくのは、皆、同じです。
どこから、そして、いつから、こんな思い違いが発生したのでしょう?
そう言っている私も、だいぶ経験を積んだことで
いちいち驚かなくなりましたが、最初の頃は、
自閉症児(その他、様々な障害を持つ子ども達)の言動に、
「うっそーっ!」「なんだってーっ!」
「なんでやねん??」の連続でした。
今でも、たまに、新たな発見があります。
と言うことは、一般の人達は、この仕事をスタートしたばかりの頃の
私と同じなんですね。彼らへの思い違いや思い込み、理解の無さ・・
でもでも、それも仕方のないことなんです。
まだまだ彼らの言動の根拠は、はっきりとした理由が
わかっていないのですから・・
でも、ささやかですが、ピアノに関しては言えること。
弾けるようになる子は、努力家だということです。
定型発達の子と、ここは全く同じと言えます。

継続という才能
ある大学病院のお医者さんに、数名の発達障害の子ども達の
演奏動画を見てもらった時のことです。
その時の動画を一部、貼っておきます。
ぜひ、ご覧になってください。
見終わったあと、私は思い掛けない質問を受けます。
「この子たちは発達障害があるのに、どうしてピアノが弾けるんですか?
僕は子どもの頃に習っていたけど、やめてしまって、
今は全く弾けません。」
・・そうでしょうねぇ~。。
でもドクターは、いたって真面目に質問してくださっているのです。
ここで大切なこと。
発達障害があると、全ての脳力が、定型発達児に比べ
劣っているという思い込み。
もちろん、できないことの方が多いと感じています。
マナーから身に付けないといけない子も多くいるし、
勉強も遅れがちです。
ましてや【習得困難】のイメージが強いピアノ演奏が、
発達障害があるのに弾いてる?弾けてる?弾けるの?
となるのは、全体的な印象から見れは、仕方のないことです。
でも、毎日コツコツと続け続ける恩恵は、
必ず数年後にやって来ます。
そして、年数が経てば経つほど、良い方向への改善が
見られるようになってくるのです。
努力という才能に加え、継続という根気強さが武器になっていくのです。

これから大切になる視点
私は差別はしませんが、区別はします。
定型発達の子ども達に対し、差別にあたるから、と、
我慢をさせたり、ペースダウンさせるようなことは
絶対にしてはいけないと思います。
これからの世の中を、広く支え、リードしていく子ども達に、
「愛」を教え、手を差し延べることを教えることと、
発達障害のある子ども達と、足並みを揃えさせることは、
全く話が別問題です。
私の教室の発表会では、全員が一緒の舞台に立ちます。
そして、全く同じ内容、タイムスケジュールで動きます。
こうすることで、障害のある子ども達は、本来持つ力を
上へ上へと伸ばし、発揮することができるようになります。
定型発達の子たちも、いっしょが当たり前だと思っているので、
何の違和感も互いが抱かずに、同じ時間を共有します。
障害を理解しろ、と言われても、ふだん、身近にいない人たちに
心を馳せることは難しい。
でも、こういった空間が、例えば多くの言葉を必要としない
音楽や絵画などの芸術的分野で、専門家による専門的な視点が、
いわゆる「何もかも同じが良い!」というような、
どちらにも辛い平等ではなく、互いに存在し、同じ目的を
共有できるようなスペースが増えて行けば、もっと皆が
個々の力を発揮できる未来になるのではないか?と考えます。
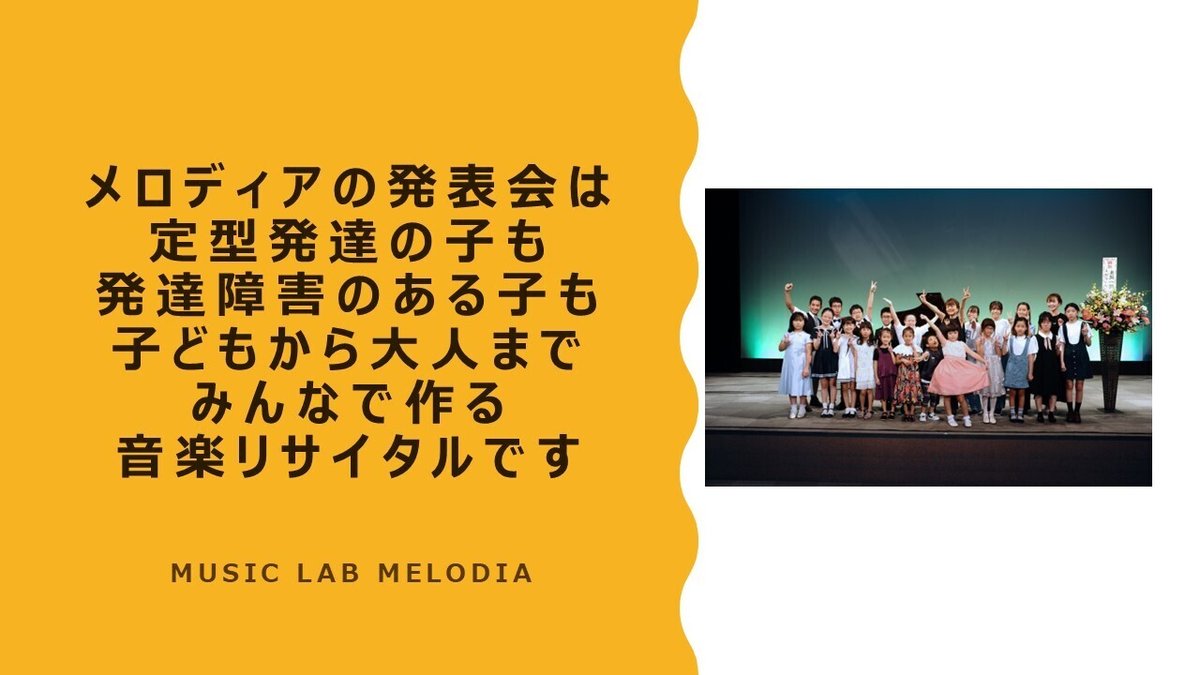
今回の2つの思い違いのような、
「努力と継続が、発達障害のある子ども達の、
成長の大きな要因になっている。
それは、誰にとってもそうであるように。」
というシンプルなことは、実は当たりまえ過ぎて
障害の症状に捉われ過ぎると、見逃されがちになります。
何か特別なことばかり、やらさなればいけないように思う、
「指導者の思い込み」も、一度はずしてみることも大切です。
やれば、その子なりに伸びるんですよ!
この認識がもっと広まれば、もう少し支援の仕方にも変化が出て、
IQが70程度だから、このくらいで上等!で終わらなくなるでしょう。
彼らと関わる専門家の方々は、まず、「努力することと根気」を
身に付けさせるべきだと思うのです。
努力や根気強さを才能と言わないにしても、
特別な教材を使うことに加え、疲れるかも?嫌がるかも?
の配慮を少し減らし、癇癪の上を行く勢いを持ち、
親に悪く思われるから、と遠慮しないで、
とにかく良いと思われることは全て試しながら、
何でも続けさせる工夫をすることが、良い結果をもたらします。
教える側も、工夫という努力と、彼ら以上の根気強さを持って、
これからも取り組んでいきたいと考えています。
****************************
ありがとうございました。
こちらの記事を動画にしたものを貼っておきます。
もし動画の方がご覧になりやすいようでしたら、
どうぞご覧ください。
