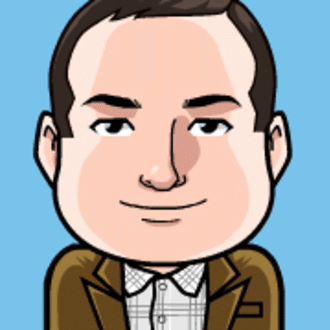邪馬台国の謎 (6)
邪馬台国の謎に関するお話も6回目になりました。
いまだ考察を行なわず、ひたすら論争の経緯を紹介していっている段階なのですが、色々な説に触れると、何だか楽しくなってきて、ついつい、取り上げてしまっております。
でもまあ、色々な説を聴いて、その説の良いところや悪いところを考察するというのも大事かな、と思いますので、今回も、論争の経過や、諸説の紹介をしていきたいと思います。
さて、前回は、戦前の津田事件までお話しました。
皇室の祖先を議論の対象にしかねない邪馬台国論争は、厳しく制限され、下火になっていきます。
再び、邪馬台国論争が巻き起こるようになるのは、戦後しばらくたってからでした。
学術的な論争ではなく、手塚治虫による漫画『火の鳥』や、作家・宮崎康平による九州長編レポート『まぼろしの邪馬台国』、同じく作家・松本清張の『陸行水行』・『古代史疑』・『遊古疑考』といった創作家による古代史ミステリーを題材とした作品の登場が、ブームの火付け役になったのです。
今まで学者の間で論争されていたものが、一般の歴史マニアの俎上に上り、色々な説を唱える人が増えていくようになりました。
学術という点では、かなり問題が多いのですが、素人には素人なりの豊かな発想力があり、奇説・珍説は、読んでいるだけで、なんだか楽しくなってきます。
手塚治虫は、黎明編で、【南方民族漂着説】を採用し、卑弥呼=天照大神として、『火の鳥』を発表しました。
ただ、この時の作品は、雑誌の廃刊で、あえなく中断。
10年の時を経て、リメイクされることになりました。
リメイク版の設定は、その当時、話題になっていた
江上波夫の【騎馬民族征服説】
が採用され、ニニギノミコトが邪馬台国の女王卑弥呼を攻撃するという設定に変わっています。
この辺り、時代の変遷、邪馬台国論争の変遷を感じるところですね。
宮崎康平は、地元島原にこだわり、遺跡を二百か所以上巡り、長崎県雲仙市を邪馬台国に比定しています。

1955(昭和30)年6月28日『別冊文藝春秋』第46号文藝春秋
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seich%C5%8D_Matsumoto_(1955,_46_years_old).jpg?uselang=ja
松本清張自身は、邪馬台国論による比定地を最終的には特定しきっていませんが、基本的には邪馬台国九州説の立場にあったといえます。
戸数・里数・日数の解釈論や、狗奴国、卑弥呼等、作家らしく、様々な点を推論していっています。
やはり、松本清張が引っ張ったことで、邪馬台国論争は大衆化し、面白くなったと言えるのかもしれません。
逆に、何が何やら、多すぎて良く分からん、という状況にもしてくれました。ざっと、俯瞰してみただけでも・・・
邪馬台国畿内説
・大和説
・琵琶湖畔説
・大阪説
・伊勢説
・丹後半島説
邪馬台国九州説
・北部九州広域説
・島原説
・筑紫平野説
・大分説
・宮崎説
・鹿児島説
・熊本説
邪馬台国その他地方説
・阿波説(徳島)
・出雲説(島根)
・吉備説(岡山)
・越後説(新潟)
・千葉説
・福井説
・長野説
・石川説
・静岡説
・沖縄説
邪馬台国外国説
・ジャワ島説
・フィリピン説
・エジプト説
ざっくり紹介しただけで、これだけの異説があるようです。
私自身、全ての説の詳細を理解しているわけではなく、多少、聞きかじっている程度ですが、説得力のあるものから、キワモノにしか見えないものまで、多種多様、玉石混交で、やっぱり苦笑いしつつ、楽しいなあと思えてきます。
特に、特殊な説ほど、細かく聞いてみたいのですが、入手困難なものもありますし、その辺は限界があるだろうな、と思っています。
いいなと思ったら応援しよう!