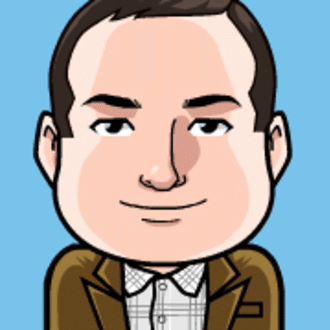邪馬台国の謎 (16)
いよいよ、魏志倭人伝の最終段になります。
正始元年 太守弓遵 遣建中校尉梯儁等 奉詔書印綬詣倭国 拝仮倭王 并齎詔 賜金帛錦罽刀鏡采物 倭王因使上表 答謝恩詔 其四年 倭王復遣使 大夫伊聲耆掖邪拘等八人 上献生口倭錦絳青縑緜衣帛布丹木拊短弓矢 掖邪狗等壱拝率善中郎将印綬 其六年 詔賜倭難升米黄幢 付郡仮授 其八年太守王頎到官 倭女王卑弥呼與狗奴国男王卑弥弓呼素 不和 遣倭載斯烏越等 詣郡 説相攻撃状 遣塞曹掾史張政等 因齎詔書黄幢 拝仮難升米 為檄告喩之 卑弥呼以死 大作冢 徑百余歩 徇葬者奴婢百余人 更立男王 国中不服 更相誅殺 當時殺千余人 復立卑弥呼宗女壹與年十三為王 国中遂定 政等以檄告喩壹與 壹與遣倭大夫率善中郎将掖邪拘等二十人 送政等還 因詣臺 獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔 青大句珠二枚 異文雑錦二十匹
正始元年(240)、(帯方郡の)太守、弓遵は建中校尉の梯儁を倭国へ派遣した。
梯儁は詔書、印綬(=親魏倭王という地位の認証状と印綬)を倭王に授けたのである。
また、詔(=制詔)をもたらし、金、帛、錦、罽、刀、鏡、采物を下賜した。
これを受け、倭王は使者を送って、感謝の意を表した。
(正始)四年(243)、倭王は使者の大夫伊聲耆、掖邪狗等八人を派遣し、奴隷や、倭製の錦、青の縑、綿の着物、帛、丹、短弓、矢を献上した。
掖邪狗等は、皆等しく率善中郎将の官位と印綬を授けられた。
正始八年(247)、(弓遵が戦死したため)王頎が帯方郡太守に着任した。
女王・卑弥呼は、狗奴国の男王・卑弥弓呼と不仲で、倭の載斯烏越等を帯方郡に派遣し、互いに攻撃しあっている状態であることを説明した。
(王頎は)塞曹掾史の張政を派遣した。
詔書、黄幢を、難升米に授け、檄文をつくり、これを告げて諭した。
卑弥呼は死んだ。
冢(墳丘墓)を大きく作った。
直径は百余歩。殉葬者は奴婢、百人余りである。
新たに男王を立てたが、国中が不服で互いに相争うことになった。
千人余りが犠牲になったという。
そこで、卑弥呼の宗女である壱与(台与という説も)、を立てて王とした。年は十三。
すると、国中が治まった。
張政たちは檄をもって壱与に教え諭した。
壱与は倭の大夫で、率善中郎将の掖邪拘等二十人を派遣して、張政等が帰るのを送らせた。
その際、男女の奴隷三十人を献上し、白珠五千、青大句珠二枚、模様の異なる雑錦二十匹を貢いだ。
このくだりでは、邪馬台国や卑弥呼を取り巻く情勢の変化について語られています。
西暦247年に帯方郡太守が王頎に代わったこと。
邪馬台国と狗奴国が交戦状態に入ったこと。
張政が、詔書と黄幢を携えて倭国に赴いたこと。
卑弥呼が死んだこと。(墳丘墓をつくり奴隷100人が殉葬させられたこと)
男の王を立てたら内紛が発生したこと。
卑弥呼の親族から13歳の少女壱与を女王に推戴することで内紛が鎮まったこと。
その後、張政が帰国したこと
という流れです。
邪馬台国と狗奴国が交戦状態に入り一進一退の攻防が繰り広げられたとすれば、狗奴国の力は、邪馬台国連合に匹敵するほど巨大だったと考えるべきなのか?
それとも、連合とはいいつつも、軍事作戦上の連携が機能しておらず、二ヵ国間の戦争として他国が傍観していたのか?
この辺りについては記載がないので良く分かりません。
次に、魏の張政ですが、詔書(文書)と黄幢(皇帝の旗)を携えてやってきた点です。
この辺り、どういう思惑があったのか?
不思議でなりません。
まず、狗奴国と魏は国交を樹立していません。
魏の皇帝の書状や旗など、停戦の役には立つはずがないのです。
それでも大丈夫という考えで来たのなら、慢心ですし、中央の官僚ならともかく前線で実際に戦争経験をしているであろう帯方郡の官僚たちが、
武力なき交渉
の無意味さを理解していないとは考えにくいです。
となると、帯方郡には援軍を派遣する余力がなかった、と考えるべきなのでしょう。
そう考えると、書状や旗は、対狗奴国ではなく、邪馬台国連合の諸国を鼓舞し、戦闘に参加させるためだったと考えればいいのかもしれません。
であれば、狗奴国一国だけで邪馬台国と渡り合えたのも理解しやすいです。
そして、張政が皇帝の名を使い、周辺国にも兵を出させたとすれば、狗奴国を何とか押し戻すことも出来ただろうと考えることが可能です。
そして、唐突過ぎる卑弥呼の死の一文があります。
寿命で死んだのか?
病気で死んだのか?
暗殺されたのか?
戦争で死んだのか?
死因が不明です。(張政らに死因が伝えられなかったのでしょうか? )
ここで、【天岩戸神話】を使い、卑弥呼が日食により殺されたという説が登場してきます。
西暦247年や248年に日本列島近辺で皆既日食があり、日の巫女である卑弥呼が神通力を失ったとして殺されたのだ、という説です。
ここから、皆既日食が視認された地域こそ、邪馬台国である。
という説が登場しました。
で、NASAの日食に関する観測とシミュレーション結果から、導き出されたのは、山陰・北陸・東北ぐらいになります。(248年9月5日)
また273年5月4日にも、日本列島付近で皆既日食が観測されています。
こちらは、北陸から関東方面で観測されています。
日食によって日の巫女が殺されるという説が本当なら、
卑弥呼の死は、248年9月5日以降
壱与の死は、273年5月4日以降
となり、両方の日食が観測された場所。
すなわち、北陸地方が邪馬台国の最有力候補地になります。
ただ。
これはあくまでも、『日食により日の巫女が殺された』という条件が事実である場合のみのお話です。
日食神話というのは、世界中にありますし、日本人の原型を作ったとされる東南アジア等の南方諸国にも、世界が暗闇になった神話はあります。
つまり、日の巫女の死(卑弥呼の死)と再生(壱与の即位)が日食と結びつくかどうかは、「分からない」のです。
ただ、魅力的な仮説ではあります。
実際、越前周辺は、古代でも富裕な土地柄ですし、邪馬台国畿内説の里程計算と考えると、場所的にいっておかしくはないです。
でも、これで決まりだ、という決定打になるものではないといえるでしょう。
私が日食説に疑問を感じるのは、
「そこまで日の巫女を重視するのであれば、なぜ男の王を後継にしたのか? 」
という疑問を解消できないからです。
日の巫女の霊力で邪馬台国連合を繫栄に導くという思想があるのならば、後継者として男子を立てることなく、壱与やその他の巫女を擁立したのではないでしょうか?
女王が共立されていたのは、各国の政治的思惑があり、主導権を奪われたくないという意図があったからです。(これは記述から読み解けます。)
そもそも、倭国大乱の収束は、この理屈で卑弥呼を擁立していたはずです。
さらに、壱与の擁立も男の後継王で生じた内紛を鎮めるためでした。
どちらの擁立にも、「日の巫女の霊力」にすがろうとする人々のお話がないのです。
あくまでも、女性を共立することで、まあ争わないでおいてやろう、という不思議な空気感に包まれているだけなのです。
ですから、日の巫女を擁立しなければならないという何らかの宗教的理由に関する記述や証拠となる考古学的発見がなされなければ、
日食による日の巫女取替説
は、成り立たないように思います。
ただ、日食説は魅力的だなと思ってはおります。
なぜなら、倭国からの使者は、魏が滅び晋王朝が誕生した翌年の266年で途絶えているからです。
日食説で考えると、273年の日食で壱与が殺されたから、と考えることも出来ます。
ただ、再び日の巫女を擁立すれば済むはずですし、その後、晋に朝貢すればいいだけなので、合理性は欠けているとも言えます。
以上で、魏志倭人伝全文の大雑把な翻訳は完了です。
結論としては、
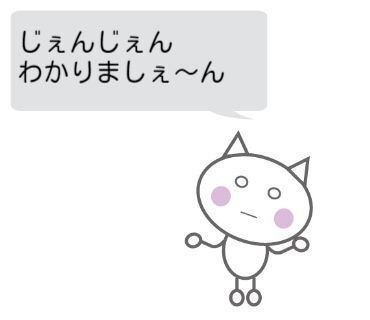
となりますね。はい。
特に、里程、人口、方位が、謎すぎます。
だからこそ、何百年も論争が続いているわけですけれども・・・
邪馬台国論争の中核となる魏志倭人伝の翻訳については、とりあえずはここで切り上げます。(のちのちピンポイントでの翻訳は予定しています)
いいなと思ったら応援しよう!