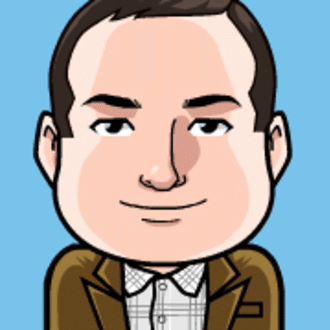邪馬台国の謎(8)
第八回目の今回は、魏志倭人伝を見ていくことにします。
全文は、長すぎるので、分割して翻訳していくことにします。
倭人在帯方東南大海之中 依山島為国邑 旧百余国 漢時有朝見者 今使訳所通三十国 従郡至倭 循海岸水行 歴韓国 乍南乍東 到其北岸狗邪韓国 七千余里
倭人は、帯方郡の東南、大海の中にいる。
山や島で構成された国々で、百か国以上あったらしい。
漢(魏国が滅ぼした先代の国)の時代に、朝廷に貢物を納めに来る者がいたという。
今の時代、使者の往来があるのは、三十か国である。
帯方郡から倭に至るには、(朝鮮半島を)海岸に沿って、船で進み、韓国を通り越して、ある時は南に進み、またある時は東に進んで、(倭の)北岸にあたる狗邪韓国に辿り着かないといけない。
ここまでの距離、実に七千里余りである。
ここで、注目しておきたいのが、【七千余里】という距離表記です。
どこからどこまでの距離が、【七千余里】あるのか?
という点です。
なお、倭の北岸ということで、狗邪韓国を九州北岸とする意見もわずかながら、見られるようです。
色々な意見はあるでしょうが、後段に続く文章を読み進めると、倭という国は海洋国家と考えるのが、適切だろうと思われます。
となると、当時の倭の勢力圏は、朝鮮半島南岸に隣接していたのだろうと思われます。
そのため、【北岸】という表現になったのだろうと考えられます。
帯方郡のどの地点を出発地点としているのか?
狗邪韓国のどの地点を到着地点としているのか?
距離の単位である【里】は、現在の距離で何mになるのか?
そもそも、記載されている【里】は、正しく測定された数字なのか?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Korea_Taihougun.png?uselang=ja
1) 帯方郡のどの地点を出発地点としているのか?
三国志の時代、震旦の東北方付近は、独立王国の様相を呈していました。
後漢末期に頭角を現したのが、公孫度です。
彼は、董卓が朝廷を牛耳った頃に台頭し、遼東太守の地位に就いています。
その後、高句麗や鳥桓を圧迫しました。
その子・公孫康の代には、三韓を圧迫し、倭にも影響力を与えるところまで、勢威を拡大しています。
なお、この時期も震旦の中央政権であった曹操や曹丕に一応は従う格好になっています。
そして、公孫康の時代に楽浪郡の南側から三韓付近にかけて分割設置されたのが、帯方郡とされています。
そのため、楽浪郡が現在の北朝鮮の首都・平壌と考えると、帯方郡はその南に位置していますので、上記の地図の
(a)鳳山郡
(b)安岳郡
(c)ソウル
(d)広州
が、候補地として挙げられているということになります。
個人的には、ソウル近郊を流れる漢江が、かつては、帯水と呼ばれていたことから、漢江=帯方郡中心付近の河川と考えれば、筋が通るのではないかと考えています。
実際問題として、三韓に睨みを利かすには、ソウルの位置取りは平壌との連携性も含め、合理的な地点にあります。
ただ、あくまでも統治面・軍事面での合理性からの比定なので、本当のところまでは、良く分かりません。
2) 狗邪韓国のどの地点を到着地点としているのか?
狗邪が、後の時代に登場する伽耶と類似した発音であるため、朝鮮半島南端中央部付近が、狗邪韓国だろうとされています。
3) 距離の単位である【里】は、現在の距離で何mになるのか?
西暦239年といえば魏の時代ですが、後漢が滅んだのは西暦220年。
しかも、三国分裂の時代ですから、度量衡がどの程度変更され、浸透したのか、定かではありません。
一応、漢の時代は、一尺=23cm : 一歩=六尺 : 一里=三百歩 でした。
となると、一歩=1.38m : 一里=414m と算出されることになります。
つまり、7,000里は2,898kmとなります。
蛇足になりますが、
【寸】は、「人の親指」を基準としています。
親指の幅という場合もあれば、親指の指先から第一関節までの長さとする場合もあります。約3cmになります。
【尺】は、「手を広げた際の親指から中指までの長さ」とされています。
体格とか手の大きさで影響されますが、一尺=23cmというのも納得できる数字かと思います。
【歩】は、左・右と人が歩いた際の歩幅で決まります。
片方の足を踏み出す長さが約70cmと言われておりますので、両足を交互に出すと、1.4mとなり、一尺=六歩という十進法ではない表し方になったのも理解しやすいかと思います。
4) そもそも、記載されている【里】は、正しく測定された数字なのか?
前項の計算から考えると、この距離表記は、異常となります。
7,000里(2,898km)を日本列島で考えると、北海道の宗谷岬から宮古島ぐらいまでを直線で結んだぐらいの長さです。
朝鮮半島の南北全長で840km、東西最長で354kmというのが、現在の測量技術で弾き出されている数字です。
仮に、朝鮮半島を南北に縦断し、南岸を東進したとして、最大距離を足し算したとしても、1,194kmとなり、2倍以上の違いがあります。
こうなると、海岸沿いを徹底的にジグザグに進んで距離を稼ぐしかありません。
つまり、のっけから一里=414mの長さが成り立たないのです。
方位を無視し、海岸伝いに2,900km進むと、ウラジオストクを通り過ぎるぐらいまで進む感じになります。
そうなると、南進ではなく北進になりますし、この後に続く対海国や、一大国の状況とまるで異なる風景になってきます。
この問題への解決策として、いくつかの仮説が立てられています。
水行では、航海技術の不十分さから、距離が不正確になっている。
【短里】で記述されている。
統治地域ではないので、適当に記述している。
司馬懿の功績を称揚するため、露布が用いられている。
追記 ~ 朝に落ち着いた時間を取れなかったので・・・
昼休み前の小康状態を利用して、少々追記をば・・・
1) 水行では、航海技術の不十分さから、距離が不正確になっている。
この後の海を渡る際の距離についても、2~3倍と里程が長く表記されています。
このことから、陸路と異なり、水路ではかなり不正確な距離測定しか出来ないのではないか? と考えることが出来ます。
2) 【短里】で記述されている。
漢帝国が滅んだことから、度量衡の変更が行なわれ、【短里】が定められ、用いられたのではないか? という説もあります。
一里 = 77~85m 程度の仮説が多くなっております。
個人的には、百歩=138mぐらいにした方が、キリが良くていいのになあと思ったりしています。(でも、辻褄は合わなくなるんですよね・・・)
もう一つの考え方として、六尺で一歩なら、六十歩で一里とするのも面白いかな、と思います。そうすると、一里 = 82.8m。
【短里】の数字としては、あり得るのかな、と。
可能性のお話になりますが、収穫量で考えるのもアリかなと思っております。
82.8x82.8=約0.7ヘクタール
現代の小麦収穫量が、1ヘクタール当たり3,000kgあるとされていますので、古代の収穫量を1/3ぐらいにして考えると、1短里四方の土地で、700kgぐらいの収穫量があると推定することが可能です。
人一人の年間消費量を150Kgとすると、4~5人分。
夫婦と子供2~3人を養える広さなのかな、と。
あくまでも、仮定の世界ですが、そういう割り当て方があって、【短里】が定められたのであれば、おもしろいかな、と。
3) 統治地域ではないので、適当に記述している。
これ、意外にそうかも? と思ったりしてしまいます。
しょせんは、蛮族の地。中華から遠く離れた土地のことなので、真剣に方位や里程を調査していなかったというのも、あながち否定できません。
4) 司馬懿の功績を称揚するため、露布が用いられている。
魏王朝滅亡後、司馬懿の孫・司馬炎によって、晋が建国されています。
前王朝時代に書き溜められた歴史を最終的に編纂するのが次の王朝の仕事となっておりますので、次の王朝の先祖を悪く言うわけにはいきません。
司馬懿の徳を強調するとすれば、東夷の中で最果てに位置する倭を、より一層遠くにあるとすることで、あまねく威徳を示したとして称揚されることになるのは確実です。
そういう観点から、実際の距離よりも長く設定されたのではないか、と考えるのも妥当性はあります。
以上のことから、朝の締め言葉
いずれの説も、相応に説得力があるため、現時点では何とも言い難いという感じになります。
につながった次第です。
ということで、次回に続きます。
いいなと思ったら応援しよう!